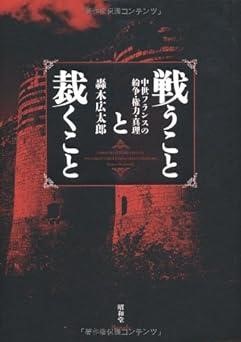学部・大学院 教員詳細
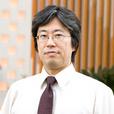
轟木 広太郎(とどろき こうたろう)
- 職名
- 教授
- 担当分野
- ヨーロッパ社会史
- 学位
- 博士(文学)
- 研究キーワード
研究内容
中世のヨーロッパ(とくにフランス)を研究しています。だいたい11~14世紀あたりがメインですが、国家というものがまだカッチリと存在していなかった時代です。近代ヨーロッパの持つ合理性というイメージからはかけ離れた時代ですが、騎士や修道士、王侯や農民・都市民たちによって構成されるこの社会は独自な興味深い論理で動いています。以前は、奇蹟信仰や紛争・紛争解決のルールなどを研究していましたが、最近は魂をどう統治するか、王国をどう統治するか、という点で、どういう試みがなされたかということを調べています。
主な研究
私が研究している分野はヨーロッパ中世史です。とくに、10~14世紀のフランス王国とローマ・カトリック教会関連のことを対象としています。最近は、「人が人を治める(一言でいうと「統治」)というのはヨーロッパの歴史のなかではどういうことだったのか」という、一見分かりづらいテーマを研究しています。「そんなの支配者や奴隷や市民とかの、つまるところ政治の話でしょ」と言われそうですが、じつはちょっと違います。
たとえば、ローマ・カトリック教会が古代の終わり頃に形成されていく過程で、司祭が信徒の魂を天国に導く活動(「司牧」といいます)は、「統治のなかの統治」といわれました。言い換えると、最高形態の統治、もっとも高度な能力と資格を求められる統治ということです。つまり、魂に対する統治というものも存在するのです。人を力で支配して言うことを聞かせるというのではなく、人に献身的に働きかけて目標に導くというのも、「統治」と観念されたわけです。
このようなことは現代社会にも見られます。たとえば、コロナ対策だって、国民の手足を力で抑えつけてワクチンの強制接種が行われたわけではなかったですよね。個人や家族の健康、自分が他人に対して感染を通じて「加害者」あるいは「被害者」となるリスク、ワクチン自体の危険性など多様な要素を勘案しながら、様々な主体(国や県、市町村、職場や学校、家族、個人)が導きあるいは導かれながら、公衆衛生的な「統治」のようなものが行われたのです。もちろん、一部の国で行われたように、集団免疫を獲得するために何も防疫対策をしないというのもひとつの「統治」です。最初に多少の犠牲が出ても、長い目で見れば流行が早めに終息してトータルの被害がもっとも少なくて済む、これを最善の目標と見なしてそこへ国民を導こうとしたのですから。
私が研究している中世のヨーロッパでも、さまざまな形態と目的を備えた「統治」がありました。たとえば、高校世界史に必ず出てくる「贖宥状」もじつは魂の統治のためのひとつの手段でした。これがプロテスタントから批判されたのは、たんにお金で買えるからというのではなく、魂の統治のための手段としてふさわしくないとされたからです。
それから、中世の国王はかつては自分の権利を追求したり、所領を守るために戦争していましたが、14世紀くらいからは、みなにとって価値ある「祖国」(たとえば、フランス王国)を防衛するために(少なくともそう称して)戦争するようになります。これも国民を至上価値に向かって導く一種の「統治」でした。このころのフランス王は、「余が戦争をしている間は、みなの者は自分の戦争を控えよ」というような御触れを出していました。つまり、一方で貴族や騎士たちの戦争の権利を認めてもいるんです。いってみれば、「祖国」という上位の価値ある目標と個々人の権利の間で調整をつけながら統治するのが王様の役割だったわけです。ところでこれ、先ほど触れたコロナ対策で、個々人の健康・生命と国民全体の損失の両方を睨みながら公衆衛生が展開されたのと構図だけは少し似ているとは思いませんか。「統治」は、支配者が一方的に意思を押し付けるのとは少々違うのです。
ここまで書いてきた私の研究紹介は、きっとみなさんが考えるだろう歴史研究とはかなりかけ離れた内容だったと思います。でも、ちょっと見方を変えると、歴史のなかに思いもよらなかった現象が繋がって浮かび上がってくるということを少しは感じ取ってもらえたのではないでしょうか。「こういう歴史学もあるんだな」くらいに受け止めてもらえばと思います。
著書紹介
最後に著書の紹介です。もう10年以上前に出版したもの(轟木広太郎『戦うことと裁くこと―中世フランスの紛争・権力・真理―』昭和堂、2011年)ですが、11、12世紀(イメージとしては騎士や修道士たちの時代)の紛争や裁判、平和や奇蹟信仰などを論じています(現在、次を計画中ですが、先は長そうです)。表紙の写真は、フランス西部アンジェに残された中世の城壁です。