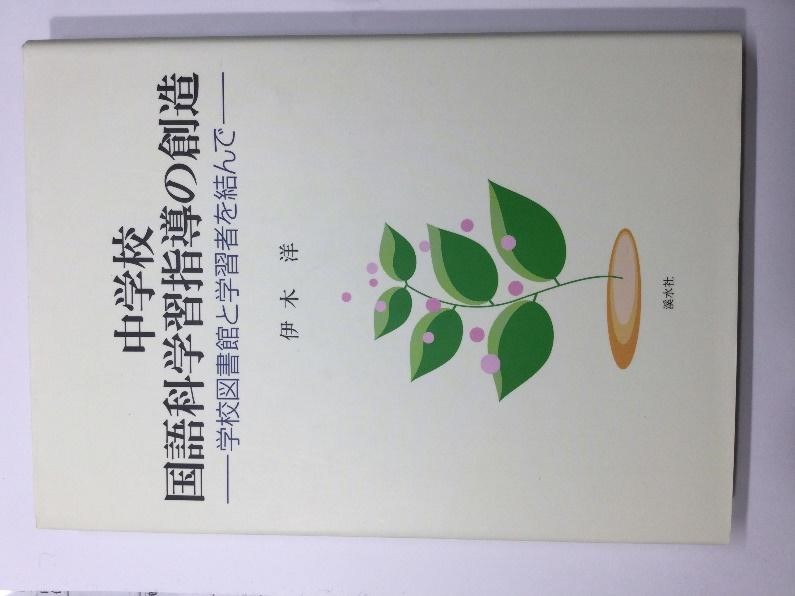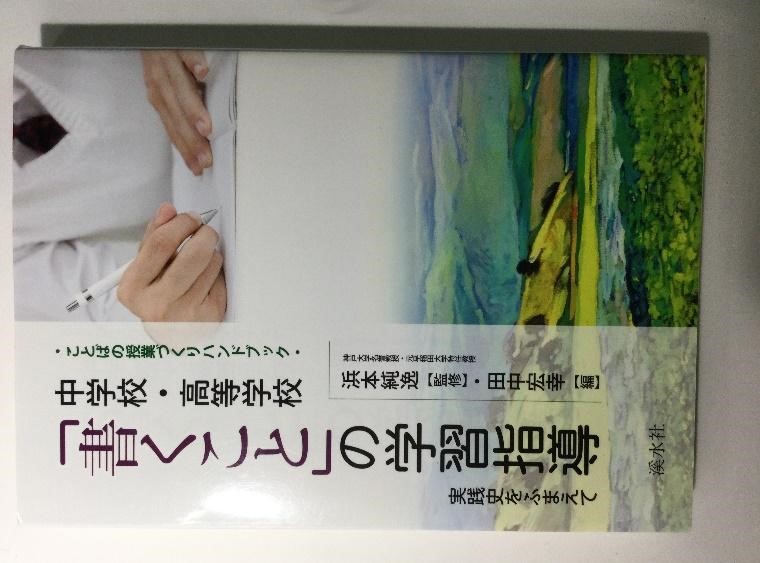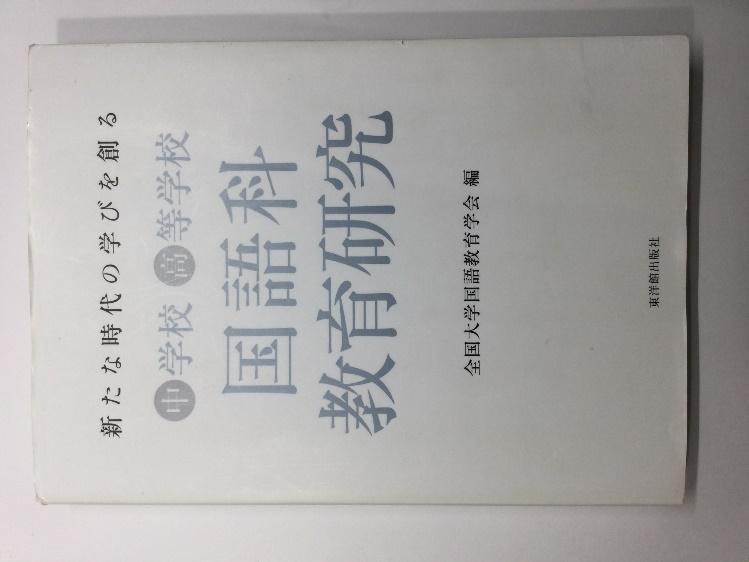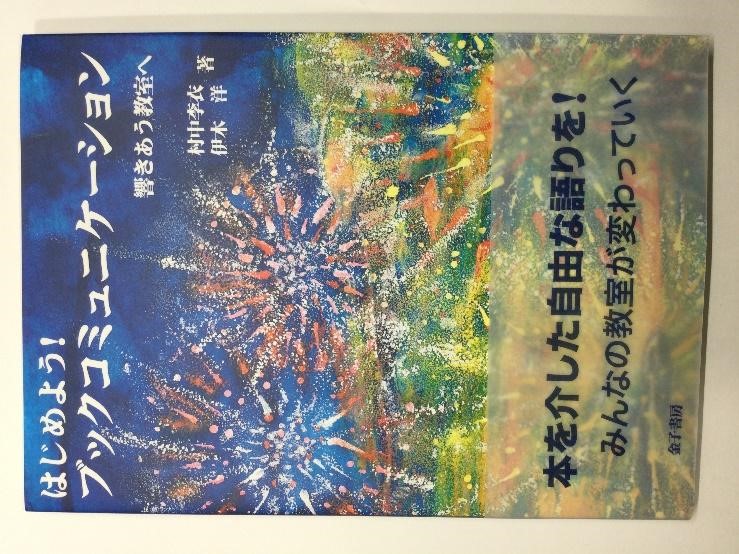学部・大学院 教員詳細

伊木 洋(いぎ ひろし)
- 職名
- 教授
- 担当分野
- 国語科教育学
- 学位
- 博士(教育学)
- 研究キーワード
- 国語単元学習、話すこと・聞くことの学習指導、書くことの学習指導、読むことの学習指導、読書生活指導、伝統的な言語文化の学習指導
研究内容
国語単元学習を中心として、学習者一人一人の主体的な学びを実現する国語科学習指導の実践理論を研究しています。 その一つ、研究論文「1970年代前期における大村はま話しことば学習指導の検討-質疑力指導の形成過程に着目して-」(伊木洋2019『国語科教育第86集』全国大学国語教育学会編集pp.17-25)においては、我が国の中等国語教育において優れた実践を行った大村はまによる二つの実践を、質疑力指導の形成過程に着目して考察しています。その結果、1970年代前期の大村はま話しことば学習指導の特徴として、討議力の育成とともに質疑力の育成が図られており、さらに、質疑力指導の形成過程において、自ら疑問を見出していく量的な指導が重視される段階から、何が問題かを問う質的な指導が重視される段階へと移行していったことを明らかにしています。
国語科学習指導の実践理論を研究
『中学校国語科学習指導の創造-学校図書館と学習者を結んで-』(伊木洋2018溪水社)は、学習者一人一人をすぐれた言語生活者として育成し、社会的存在としてことばを使って幸せに生きる力を育てたいという願いに基づき、国語単元学習の理念を生かして取り組んだ実践をまとめたものです。
『ことばの授業づくりハンドブック中学校高等学校「書くこと」の学習指導-実践史をふえて-』(伊木洋他2016浜本純逸監修・田中宏幸編溪水社)では、「書くこと」の授業実践史をふまえて、実践事例を分析し、そこから「授業づくりのヒント」を引き出しています。
『新たな時代の学びを創る中学校高等学校国語科教育研究』(伊木洋他2019全国大学国語教育学会編東洋館出版社)は、社会生活を送る中で生きて働く国語の力を育てることを目指す中学校・高等学校教員養成におけるテキストとして、これからの時代に生きる子供たちのことばの力を育てるための中等国語科教育の研究・実践の取組を示したものです。
『はじめよう!ブックコミュニケーション響きあう教室へ』(村中李衣・伊木洋2019金子書房)では、一人の人間として本との思い出や本をきっかけにふと考えたこと、気づいたことを自由に語るブックコミュニケーションを、新たな読書活動として提案しています。
実際に国語科の学習指導を実践なさっていらっしゃる先生方と連携し、単元構想の段階から関わり新たな単元を生み出していく実践研究にも取り組んでいます。2022年度は全国高等学校国語教育研究連合会第55回研究大会岡山大会、第44回鳥取県中学校教育研究会国語部会研究大会、2023年度は岡山県高等学校教育研究会国語部会秋季大会の指導助言者として実践研究に取り組んできました。2023年度は岡山県立岡山操山中学校高等学校、岡山県立倉敷南高等学校、岡山県立岡山一宮高等学校、岡山県立邑久高等学校の国語科の実践研究にも指導助言者として関わっています。
現在は、2024年度開催予定の岡山県中学校国語教育研究大会浅口大会の分科会指導助言者として、担当地区の倉敷市の先生方と実践研究を進めています。同様に2024年度開催予定の第45鳥取県中学校教育研究会国語部会研究大会の指導助言者として鳥取市の先生方とも実践研究を進めています。
こうした実践研究に関しては、ノートルダム清心女子大学日本語日本文学会大会や同学会国語教育部会国語教育研究会における研究発表の機会を設け、実践研究を深めています。
▶ 【国語教育】「三時の会」参加者インタビュー動画を公開しました|日本語日本文学科
同学会国語教育部会国語教育研究会における研究発表
山陽新聞社との連携
山陽新聞社読者局共創本部教育サポートセンターとの連携を図り、デジタル情報も含めた新聞活用の教育における新たな方向性を検討しています。