学部・大学院 教員詳細
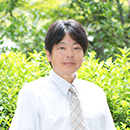
小橋 雅彦(こばし まさひこ)
- 職名
- 教授
- 担当分野
- 英語教育、評価、教材開発、授業研究
- 学位
- 教育学士
- 研究キーワード
- 英語科授業研究、教室内第二言語習得、省察的実践、評価、英語教員養成
研究内容
公立高等学校、国立大附属中・高等学校の実務経験をもとに、英語教育学の中でも「英語指導法」「授業研究」「学習評価」を中心に研究をしています。2020年度より小学校中学年で外国語活動、高学年で外国語科が導入されました。このことは中学校における英語教育の在り方に大きく影響を与えています。また、「話すこと」に「やり取り」の領域が加わり、4技能5領域となりました。こうした現状の中で日本の英語教育のさまざまな課題について、理論と実践を往還しながら研究を進めています。
1 英語科授業研究 コミュニケーションを行う目的や場面、状況
平成29年告示の中学校学習指導要領(外国語)で、「コミュニケーションを行う目的や場面、状況など」を設定し、生徒が理解し、外国語で表現し伝え合う力を育成することが外国語科の目標の一つとされています。外国語について身に付けた知識や技能を活用し、情報を伝えたり考えを伝え合ったりするためには、実際に外国語を使用する必要があります。
一方、「教室」といういわば特殊な環境の下で行われるコミュニケーションは実際のものとは異なり、展開の予測ができるような「場面」や「状況」が設定されるのが一般的です。したがって、実際のコミュニケーションがもっと柔軟であることを踏まえると、教室内で行うコミュニケーションも「実際」という未知の状況にも対応できることを念頭に置かなければなりませんし、設定する「場面」や「状況」もできるだけ現実世界と乖離しないことが求められます。
そのように設定された課題に取組むことによって、学習者は相手のメッセージを理解し自分の考えを何とか伝えようとする気持ちが生まれ、積極的にコミュニケーションを図ろうと努力するようになります。様々な制約がある中で、そのような優れた言語活動を実践されている指導者は多く存在します。そのような実践を可能にしている要素を教師の立場からだけでなく、学習者の立場からも分析し明らかにすることを研究目的の一つにしています。
2 英語科授業研究-単なる言葉の「やり取り」にしない-
英語で「やり取り」を継続するためには、「相づち(リアクション)」が有効な方略として機能します。教科書で、“I see.”(理解している)や“Really?”(驚いている)などの定型表現を学習した後で、日常的な話題についての簡単な「やり取り」をこれらの表現を使い練習をさせます。学習者はこうした表現を使用することで「やり取り」に必要な技能を体験的に学びます。しかしながら、コミュニケーションは技能の育成だけでは成立しないことも学ぶ必要があります。
たとえば、英語でやり取りをする際に、“I see.”や“Really?”を使いながらしきりとうなずいていることがないでしょうか。日本人の「相づち」は「しぐさ」を意味しますので、英語での「やり取り」の際も無意識にうなづいてしまうのです。英語での「やり取り」はまず「相手の目を見ること」が大切で、話が一段落した時に“I see.”などの言葉を返し会話を継続させていくのです。日本人のうなづきも英語での「相づち(リアクション)」も“I’m listening and interested.”というメッセージを伝えているのですが、「相づち」(リアクション)に関するこのような文化の違いを理解させることも指導に加えることが大切です。
「やり取り」の指導においては、相手の言葉にうなずいてリアクションを示すのではなく、言葉で示すことが、単なる言葉の「やり取り」に終わらせないポイントです。
3 英語教員養成
英語教育では様々な課題があります。例えば、小学校と中学校、中学校と高等学校の「接続」に関して、校種ごとの教育目標や発達段階が異なれば「接続」の仕方も質も異なります。指導面だけに焦点化して解決するものではありません。また、教室内での使用言語に関する課題もあります。英語の授業で日本語を使うメリットが十分に認識されていないと、「英語の授業は英語で」という現在の方針が目指す効果を得ることはできません。その他、生徒の振り返りだけでなく教師の振り返りの在り方や、フィードバックの与え方など様々な課題があります。
教職課程で行う講義・演習やゼミの指導においては、常にこうした諸課題と向き合いながら、理論と実践の往還をしつつ、学生のみなさんと共に英語教育の理想を追求しています。


