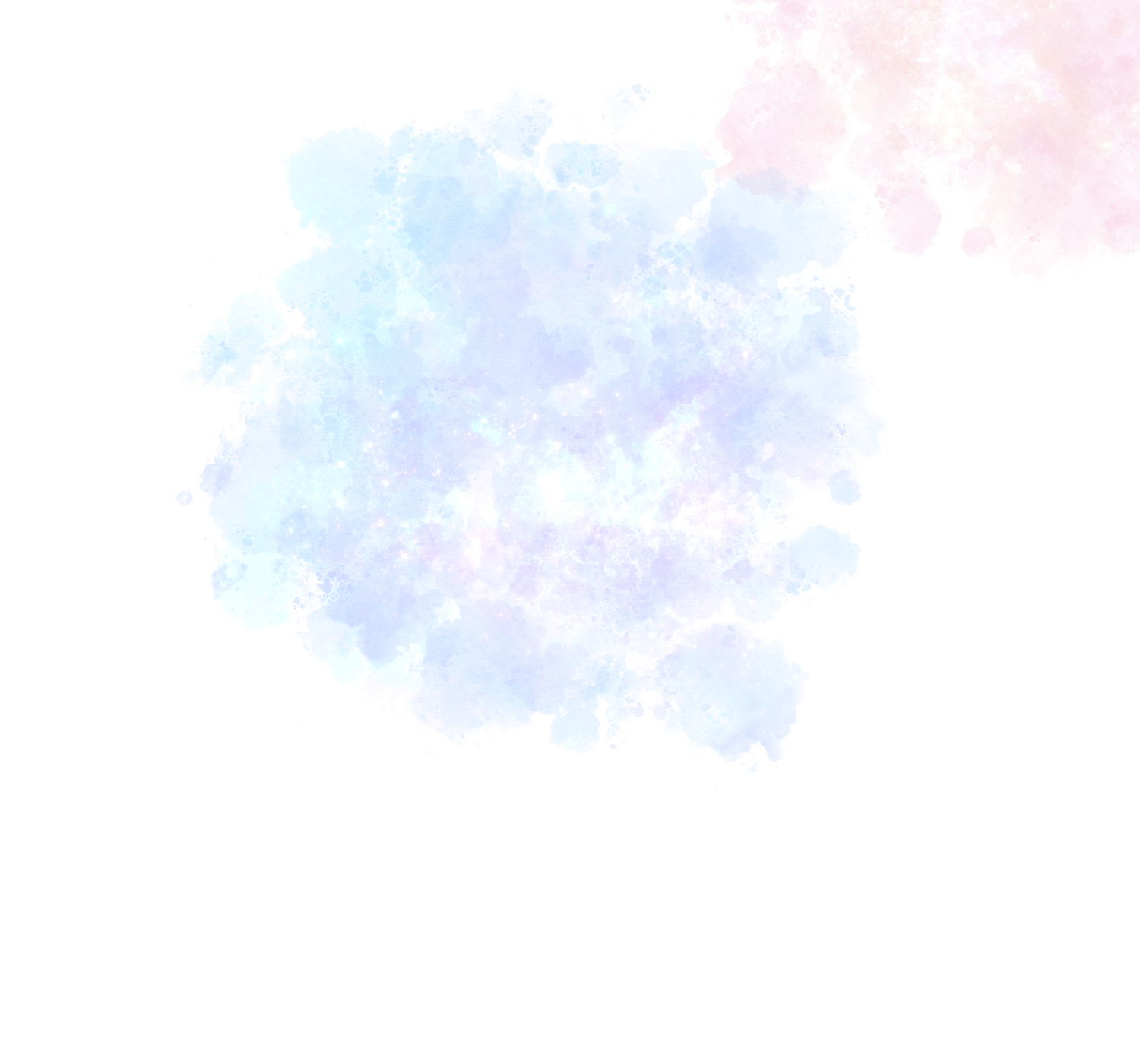【著者紹介】
星野 佳之 (ほしの よしゆき)
日本語学担当
古代語・現代語の意味・文法的分野を研究しています。
特別講演会「日本語教師経験者のライフストーリー」について
ノートルダム清心女子大学の日本語教員養成課程は1997年に開設され、四半世紀余の歴史があります。今年の1月に、本学の卒業生で実際に日本語教師として教壇に立った方々をお招きして講演会を行いました。異なる世代からお招きした方々は、一貫して日本語教員の職を続けている人、結婚してその職を離れた人、転職した人、など、その経歴も様々です。日本語教員としてのキャリアについてはもとより、今の日本社会で女性が生きていくということについてのお話を伺うことにもなりました。参加した在学生に、大きな刺激となったようです。今回はその様子をお知らせします。
 特別講演会「日本語教師経験者のライフストーリー」チラシ
特別講演会「日本語教師経験者のライフストーリー」チラシ
講師を務めてくださったのは次の方々です。藤田朋子さん(第26期英語英文学科卒)、久保望美さん(第51期日本語日本文学科卒)、笹堂果奈さん(第67期日本語日本文学科卒)、そしてコーディネータを務めてくださった青井由佳さん(第40期日本語日本文学科卒)です。青井先生は本学の日本語教員養成課程科目を長年担当してくださっている方で、今回の講演会は先生のご尽力なしには実現しませんでした。
事前に参加受付フォームを通じて寄せられた質問事項に、講師の方々がそれぞれコメントするという形で会は進んでいきました。
「教案は盛り込むより削る。その分学生に話させたい」(藤田)、「漢字がネックなのは漢字圏の中国人留学生も一緒。自国語の用法と違う場合が多くて混乱する」(笹堂)など、実用的で時に意外なアドバイスもあって、現在授業を履修している在学生にとって大いに参考になったのはもちろんです。しかし今回の講演会ではもっともっと本質的なところまで、先生方はお話しくださったと思います。
久保さんは「一族の期待を背負って教室に来ている中国人留学生に接した時、責任の重さを感じるとともに、彼の苦難を自分ではどうにもできない非力さを感じた」と言います。また笹堂さんは同じ教室で学ぶ留学生が「同級生は本国では異なるカーストの出身なので嫌だ」とこぼした時のことを話してくれました。「私たちの社会の尺度で“差別は良くない“と頭ごなしに言うのが正しいかどうか。それでも”この教室では誰もが一人一人に敬意を持って、対等に接する場にしたい”と全体に呼びかけた」そうです。これを受けて藤田さんはこう言います。「対立する国同士の出身学生がいる場合は珍しくない。それでも毎日授業をして、ある時同じことでみんなが笑ったりした時には、世界が一つだと実感する」。逆に言えば、教室は小さいようで世界の縮図なのですね。
こうしたお話を聞いていて強く印象に残ったのは、教え子である留学生への敬意が言葉の端々に表れでていることです。「彼らは働きながら日本語を勉強しているのはすごいこと。“先生だからこちらが上“というだけでは通用しない」「彼らは上達前の日本語には表れない、優れた資質を持っている。特別な存在だと思える」などといった言葉が、ポンポンと飛び出る講演会でした。
その上でやはり日本語教員の経済的な待遇は必ずしも良いとはいえないというところも、正直にお話しくださいました。常勤の職自体が少ないことについて、藤田さんは「自分の場合は子育てと介護があってフルタイムでは日本語教員を務められる状況ではなく、非常勤ゆえに家庭と仕事を両立できた」ということでしたが、全体的に不安定な部分は否めません。久保さんも「非常勤講師での就職に親の理解は得にくかった」とのこと。それでも、コーディネータの青井先生に「やりがいあるよね?」と聞かれると、全員が頷いていました。
みなさんおっしゃることは、二つ。まず「この仕事の需要はあるはず」と言うこと。日本の社会で生活する外国人は確実に増えているのだし、誰もが理解できる「やさしい日本語」が力を発揮する場所は、日本語学校以外にも私たちの社会にいろいろあるはずだと藤田さんは言います。
また、青井先生は「言葉を使うということは生活することそのもの。日本語教師は必ず自らの生活や文化を振り返る経験をする。それは必ず意味があることだ」と言います。
こうして明るいことも大変なことも、大局的な観点から具体的な点まで、惜しみなく語ってくださいました。在学生の「日本語教育」という意義、役割、場についての解像度が幾重にも増したことは間違いありません。また、講師の方々がそれぞれのお力で自分の人生を切り開いてこられたことが強く伺われて、かっこいい先輩がいてくれて心強いなとも思いました。今後もこういう機会を持ちたいと思っています。
 講演会の様子
講演会の様子
・星野佳之准教授(教員紹介)
・星野佳之准教授のブログを読んでみよう!
・日本語日本文学科
・日本語日本文学科(ブログ)
・日文エッセイ
・免許・資格