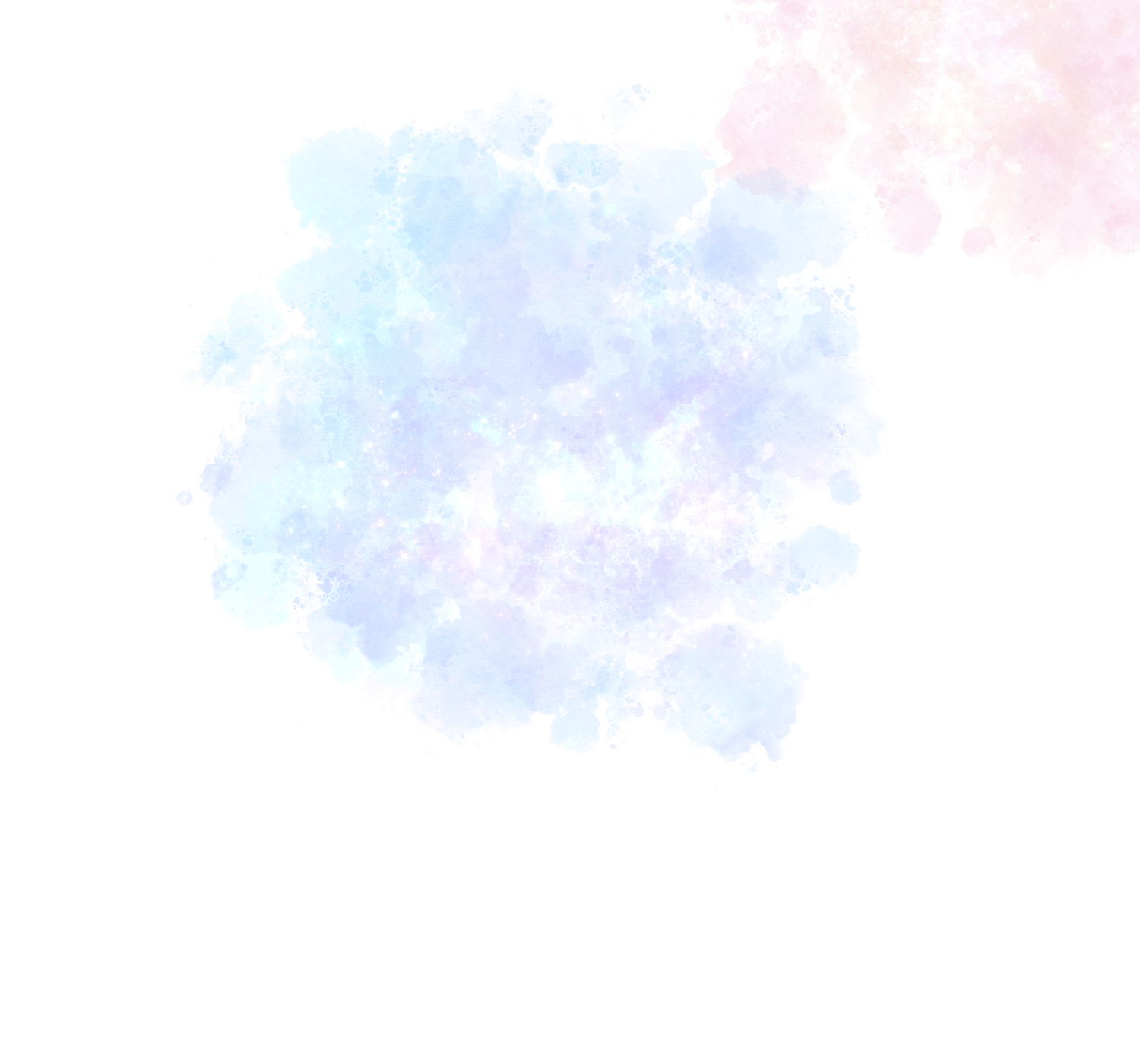【著者紹介】
東城 敏毅 (とうじょう としき)
古典文学(上代)担当
奈良時代の文学、『万葉集』や『古事記』『風土記』について研究をすすめています。
「大きなる石」の記憶
―『播磨国風土記』生石神社を旅して―
奈良時代の715年頃に編纂されたと考えられる『播磨国風土記』(はりまのくにふどき)の印南郡(いなみのこほり)の大国(おほくに)の里(現在の兵庫県加古川市西神吉町大国周辺から高砂市伊保周辺)には、以下の記事が見られる。
(美保)山の西に原有り。名は池の原と曰ふ。原の中に池有り。故、池の原と曰ひき。原の南に作石(つくりいし)有り。形、屋のごとし。長さ二丈、広さ一丈五尺、高さもかくの如し。名号(なづ)けて大石と曰ひき。伝へて曰へらく、「聖徳王(しやうとこのおほきみ)の御世、弓削大連(ゆげのおほむらじ)が造れる石なり」といへり。
このように、『風土記』の記された奈良時代において、すでに正体不明の「大きなる石」の遺構が、この地に存在していたことが記されている。そして、その「大石」には、「聖徳太子の時代に弓削大連が造った石」という伝説が語られていたことが分かるのである。「弓削の大連」とは、物部守屋(もののべのもりや)のことであり、歴史的には、聖徳太子の立太子・摂政の時代より6年も前に蘇我馬子(そがのうまこ)に攻め滅ぼされているために、この伝説には時代的な錯誤も見られる。しかし、この播磨国印南郡には、聖徳太子ゆかりの法隆寺領の土地が多かったことや、聖徳太子が建立した四天王寺(物部守屋邸宅跡)の基礎石に、この周辺の石が使用されていることから、伝説が生まれてくる過程や、伝説の拡がる経緯を実感することもできるのである。
さて、この大石は、現在では、兵庫県高砂市阿弥陀町の生石(おうしこ)神社の御神体である石と伝えられている。横約6.5m、高さ約5.6m、奥行約7.5m、重さ約500tの巨大な石造物であり、「石の宝殿」と呼ばれ、水面に浮かんでいるように見えるところから「浮石」ともいわれている。多くの謎に包まれている「大きなる石」であり、現在みてもその大きさ、形、建てられ方は異常であり、その佇まいには、驚くべきものがある。この一帯は、竜山石(たつやまいし)という、ここでしか採掘されない石の産地であり、大山古墳(伝・仁徳天皇陵)の石棺にもこの竜山石が使用されていると言われている。現在でもこの一帯は石の採掘場としても著名なのであるが、当時から石の流通の拠点として、重要な地であったことが分かるのである。
 生石神社の御神体の「大きなる石」
生石神社の御神体の「大きなる石」
この生石神社に残る「生石神社略記」には、以下の神話が伝えられている。
神代の昔大穴牟遅(おほあなむち)、少毘古那(すくなひこな)の二神が天津神(あまつかみ)の命を受け国土経営のため出雲の国より此の地に座し給ひし時、神相謀り国土を鎮めるに相応しい石の宮殿を造営せんとして一夜の内に工事を進められるも、工事半ばなる時、阿賀(あが)の神一行の反乱を受け、そのため二神は山を下り、数多(あまた)神々を集め、この賊神を鎮圧して平常に還ったのであるが、夜明けとなり此の宮殿を正面に起こすことができなかったのである。時に二神のたまはく、たとえ此の社が未完成なりとも二神の霊はこの石に籠り、永劫に国土を鎮めんと言明せられたのである。
大穴牟遅と少毘古那の二神は、日本神話において、ペアで登場する神々であり、ともに国作りをする神々として語られている。『古事記』においては、神産巣日神(かみむすひのかみ)の子であり、神産巣日神の手の股から抜け出た小さい神として描かれる少毘古那と、大国主神(おほくにぬしのかみ。大穴牟遅の別名)の二神が共同で国を作り堅める神話が記されている。
また、この二神は、『播磨国風土記』では、まったく別様の興味深い神話も残している。神前郡(かむさきのこほり)の堲岡(はにおか)の里(現在の兵庫県神崎郡神河町周辺)の地名起源譚であり、概要を示せば、以下の通り。
大汝命(おほなむちのみこと)と小比古尼命(すくなひこねのみこと)の二柱の神様が、埴(赤土の粘土)の荷物を背負って歩いて行くのと、便意を我慢して歩くのとどちらが遠くまで行けるか、という我慢比べをした。何日か経って我慢しきれなくなった大汝命がとうとうその場で大便をしてしまった。それを見て、小比古尼命も、笑って自分も苦しかったことを告げ、埴を道端に投げ出した。この埴が投げ出された岡を埴岡と言い、また、大汝命の便が、笹の葉にはじかれて飛び散った場所を、波自賀(はじか)と言うようになった。投げ出された埴と便は固まって石に姿を変えた。
この神話は、『古事記』の神話の世界とは全く異なったユーモラスなものであり、この二神の、その土地その土地での受容のあり方が見出されて、大変興味深い。さらに、『万葉集』には、以下の歌も収録されている。
大汝(おほなむち) 少彦名(すくなびこな)の いましけむ 志都(しつ)の石屋は 幾代(いくよ)経にけむ(巻3・355番)
(大国主命や少彦名命が住んでおられた、この志都の岩屋は、神代の昔からいったいどのくらいの年代を経たことであろうか)
この「志都の岩屋」は、現在の注釈書では所在未詳とされており、島根県にあるとする説が多いのであるが、当該歌の作者が「生石村主真人」(おひしのすぐりまひと)であること、一つ前の354番歌には「縄の浦」(兵庫県相生市)が詠まれていることも考えると、当該歌は、生石神社周辺の景を詠んでいるとも考えられるのである。
目の前に存在する見慣れない異様な大きな石に、神話性を感じとり、その石の背後に過去の記憶を甦らせること、また、甦らせなくては安心できない人間の心理を、私たちは、このような伝説や歌から、かいま見ることができる。そしてはるか昔に、人の手によって築かれた痕跡に畏敬を感じることは、奈良時代の人々も、私たちも大差ないことを、実感するのである。
 「大きなる石」の後側
「大きなる石」の後側
 「大きなる石」の上側(遠方が竜山)
「大きなる石」の上側(遠方が竜山)
画像の無断転載を禁じます
・東城敏毅教授(教員紹介)
・東城敏毅教授のブログを読んでみよう!
・日本語日本文学科
・日本語日本文学科(ブログ)
・日文エッセイ