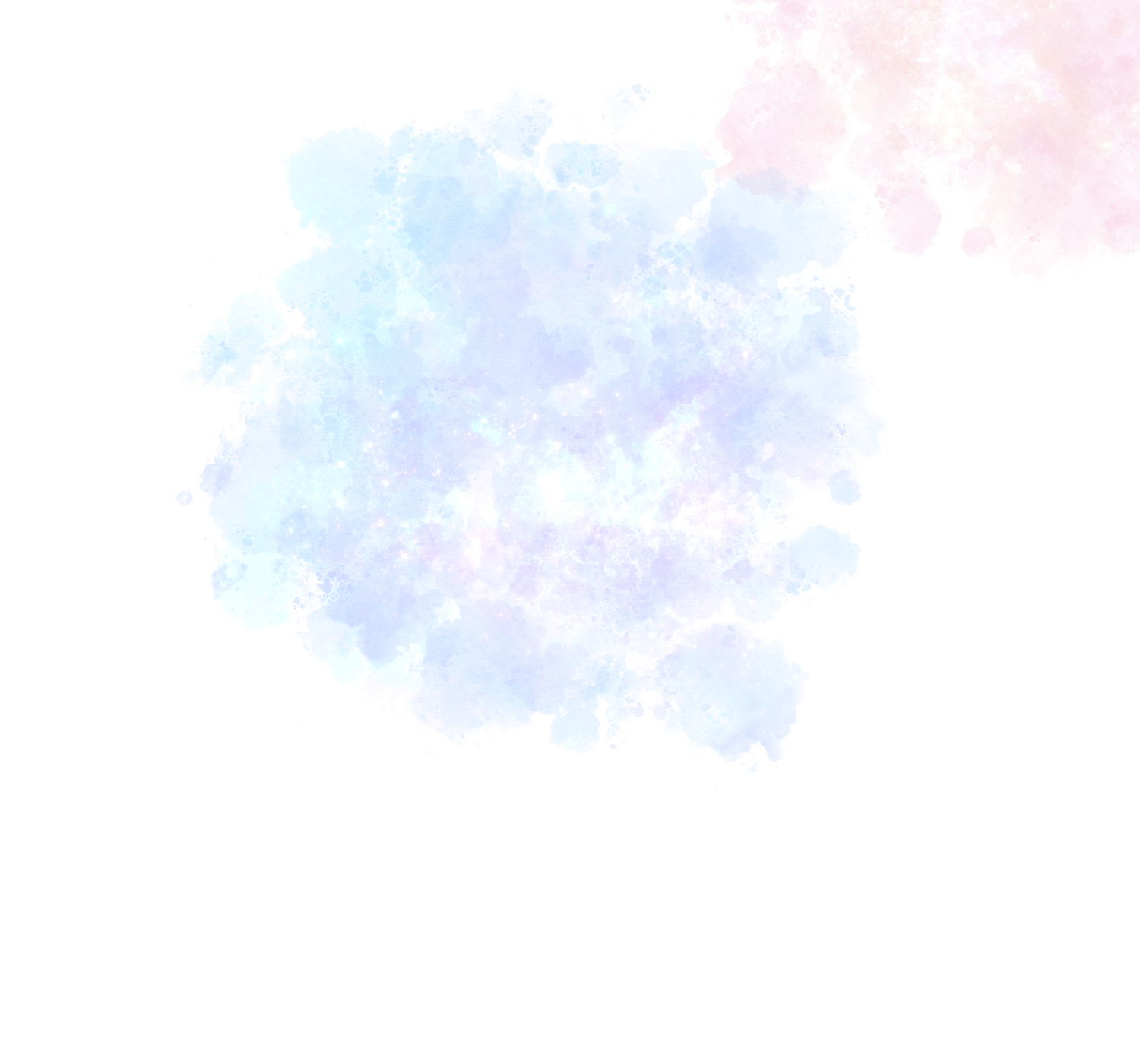本学科の授業科目「文学創作論」では、履修生が1年をかけて作り上げた作品をまとめて、文集を発行しています。
ここでは、第20集『始発点』に掲載の一作を、ご紹介します。
文集は、オープンキャンパスなどでご希望の方にお渡ししております。機会がありましたらぜひお手にとってみてください。
 第20集文集『始発点』の(2022年度)表紙
第20集文集『始発点』の(2022年度)表紙
イニシエーション・テディベア
作・森本 彩乃 (2022年度・2年生)
――まるで、宝石箱だ。
部活帰りに寄ったショッピングモール。その一角で俺ははっと息を呑んだ。フードコートに向かっていたことも、他に友人たちがいたことも何もかも忘れて、俺は一人歩みを止めた。
視線の先は、ゴシック・ロリータファッションのショップ。洋館を彷彿とさせる店内には、所狭しときらびやかな衣装が並んでいた。その中でも一際目を引いたのは、ショーウィンドウの中でマネキンがまとっている衣装だった。絵本から飛び出したような、ふんだんにレースがあしらわれたワンピース。その洗練されたデザインの美しさに、俺は感嘆のため息を漏らした。こころなしか、スポットライトを浴びるマネキンは誇らしげだった。
むさ苦しい男子校ではお目にかかれない、華麗で甘美な空間。少しでも長くそれに浸っていたくて、俺はショップの前で立ち尽くしていた。そんな俺の横をすり抜けて、忙しなく人は行き交う。
どれくらいの間、そうしていたのだろう。
「なーにそんな真剣な顔で見てるんだよ、早く行くぞ」
そう言われながら腕を引かれ、ようやく俺は我に返った。少し先に目をやれば、怪訝そうな顔をして友人たちは俺のことを見ていた。
「あ、わりい。ぼーとしてたわ」
「世界がひっくり返ってもお前には似合わねぇよ」
追いついた俺を、友人たちは面白おかしく茶化す。無邪気に笑う彼らから悪意は感じられず、俺は言い返そうとするのをやめて言葉を飲み込んだ。ほんの数秒前までは惹かれてやまなかったはずのショップが、なんだか見てはいけないもののように感じられて、俺はさっと目を逸らした。
「もしかしてお前、ああいうの好きなん?」
「……はは、んなわけねーじゃん」
友人の言葉に俺は乾いた笑いをこぼし、何事もなかったように振る舞った。ちくりと痛んだ胸には気がつかないふりをした。
深夜のベッドの上、なかなか寝付けずにいると今日の何気ないやりとりが頭をよぎる。傍から見ればなんてことない日常の一コマだが、俺の中ではわだかまりとなって残り続けていた。
「高一にもなって、あんなの好きとかやっぱおかしいよな……」
そう独りごちて、俺は大きくため息をついた。俺、海野藍(うみのあい)は昔から可愛いものが大好きだった。別段女の子になりたいとか、かっこいいものに全く興味がないというわけではなかったが、それ以上にフリフリのレースやキラキラの宝石といった、可愛らしいものの方に惹かれた。
それもあって、小さい頃は女の子と遊ぶことの方が多かった。公園に行っても鬼ごっこではなく、ぬいぐるみを片手におままごとをするのがお決まりだった。小さな手には少し余る、柔らかい毛質のテディベア。それが幼い俺にとっては一番の宝物で、いつも一緒だった。
今でも忘れられない、あれは物心がついた頃だっただろうか。あの日も俺は、いつものようにテディベアを抱いて公園に向かった。しかし、そこには俺を迎え入れる女の子の優しい微笑みは無かった。あったのは拒絶を含んだ冷たい視線だけ。
「アイくん男の子なのに、いつまでも一緒にお人形遊びするの気持ち悪い! あっち行ってよ!」
そう言って、彼女は俺のことを突き飛ばした。この時初めて、男である自分が、可愛らしいものを愛でるのは普通ではないのだと知った。
テディベアは、突き飛ばされた拍子に俺の腕から投げ出され、土の上にくたりと転がった。頭が真っ白になった俺は、土まみれになったそれを拾うと、公園を飛び出した。がむしゃらに走り続けて、ようやく辿り着いたのは町外れのゴミ捨て場。俺は泣きじゃくりながら、そのゴミの山にテディベアを投げ捨てた。――可愛いものを愛でる自分と決別するために。
今となれば、幼さゆえの遠慮のなさからくる言葉だと思えるが、俺の生き方を変えるには充分すぎる言葉だった。それから俺は、周りに言われるがままに生きることを決めた。本当の自分をさらけ出して、うっかり世間一般という枠からはみ出してしまうことが何よりも怖かったから。両親は比較的寛容な方ではあったが、それでもやはり魔法のステッキではなく、ヒーローロボットをねだった時は「やっと男らしくなった」と喜んでいた。
おもむろに体を起こすと、俺は部屋の隅にある姿見の前に立った。鏡の中の自分を忌々しげに見つめれば、真っ先に目に入るのは父親譲りの体格の良さ。今年入部したバスケ部も、好きで始めたわけじゃない。同年代の平均を大幅に超える長身をかわれ、周りに流されるがまま入部しただけだ。癖っ毛を誤魔化すために後ろに撫でつけた髪型や、生まれつきの鋭い目つきも相まって、鏡の中の自分からは威圧感が滲み出ていた。そんな俺に対して、周りは「男らしくてかっこいい」と羨望の眼差しを向けてくれる。でも、俺の心は全く満たされなかった。むしろ虚しくて仕方がなかった。
普通から外れないように、と周りに従うことを選んだのは紛れもない俺自身なのに、ふとした時に「自分は何がしたいのだろう」とわからなくなることが多かった。せめて、顔立ちが名前のように中性的で優しげだったなら、ここまで思い悩むこともなかったのではないかと時折思う。そんなタラレバ話をしたって意味なんてないのに。
「はっ、なにが『アイ』だよ。不釣り合いにも程があるだろ」
俺は自嘲ぎみに笑って鏡を軽く殴った。掻き乱された心に蓋をするように、布団に潜り込もうとした時、枕元のスマートフォンが通知音を鳴らした。
『明日、渡したいものがあるから昼休み教室来て』
メッセージを寄越してきた相手を確認すると、俺は適当にスタンプを送り返した。なんだか今は、打ち返す言葉を考えるのさえも億劫だった。早く寝ないと余計なことをまた考え出してしまいそうで、俺は無理やり目を瞑った。
退屈な午前の授業が終わり、ようやく訪れた昼休み。俺は約束通り隣のクラスへ向かった。ところが、俺のことを呼び出した張本人は見つからず、代わりに同じバスケ部の洋(よう)に声をかけられた。それから暇つぶしに、洋と他愛もない会話をしていた時だった。
「アイ、おまたせ! ちょっと職員室行ってた」
俺の頭ひとつ分くらい低い位置から名前を呼ばれた。そっちに目を向ければ、中学からの仲である桜庭桃李(さくらばとうり)が少し息を弾ませながら立っていた。今年はクラスが離れてしまったが、気心のよく知れた間柄だ。そして、彼こそが昨晩俺を呼び出した張本人である。
「おせーよ、モモ。相変わらずちっさくてお前可愛いなぁ」
俺が頭を軽く叩きながら言うと、桃李――もといモモは頬をふくらませながら睨んできた。モモは、高一にしてはかなり小柄で可愛らしい顔立ちをしていて、皆から「モモ」という愛称で親しまれていた。
モモも俺と同じく可愛いものが好きで、文房具やスケジュール帳もキャラクターものを愛用していた。ただ、俺と決定的に違うのは、それが皆に容認されているということ。同じ男なのに、見た目によってこんなにも扱いに違いがあるのかと正直ショックだった。そして、可愛いものを当然のように持てるモモが内心羨ましくもあった。
「で、俺に渡したいものって何?」
「あーそうそう。ちょっと前にネットで可愛いテディベアのマスコット見つけてさ、ついでにアイのも買ったんだよ。ね、めっちゃ良くね?」
モモは鞄から手のひらサイズのマスコットを取り出すと、そう言いながら笑いかけてきた。柔らかそうな毛質のころっとしたフォルムに、俺はいとも容易く射止められた。「早く俺にくれ」と急く気持ちが込み上がってくるほどだった。モモによって動かされる、少し短めの手足が一層愛くるしさを増している。つややかなビーズの目が光を受けてきらりと光り、俺はまるで見つめられているような錯覚に陥った。
少しして、俺ははっとした。今でも鮮明に浮かぶ、俺にとって一番の宝物だったあのテディベア。大きさこそ違えども、このマスコットは瓜二つだった。懐かしい感覚に胸がじんわりと温かくなり、思わず頬が綻ぶ。「さすがモモだな、ありがとう」そう言おうとして俺は口を開いた。しかし、そばにいた洋の何気ない一言で、俺が言おうとしていた言葉は全て喉の奥に張り付いたままになった。
「モモってばおもしれーな。アイがこんなの持つわけねえじゃん、似合わねえし」
俺は静かに口を閉じた。図星だった。似合わないなんて自分が一番わかっている。俺は何も言い返せず、テディベアを受け取ろうと伸ばしかけた手は宙をさまよったままになった。
「ちょっと、洋。お前なんでそんなこと言うの? アイ、こいつの言うことなんてほっとけばいいからね。……アイ?」
動かなくなった俺を、モモは心配そうな表情を浮かべて見上げてきた。当然その手にはテディベアが握られたままになっていたのだが、俺と違ってモモにはよく似合っていた。じわじわと、どす黒い感情がせり上がってくる。言うなれば、嫉妬だ。
「……なんだよこれ、いらねえよ。罰ゲームかっての」
どうにか絞り出した言葉は、八つ当たりのような酷い暴言だった。大きな目を見開いて、モモは「え」とこぼした。俺はモモの顔が見ていられず、目を伏せた。なんでこんなこと言っちゃったんだろう、俺のためにせっかく買ってくれたのに。きっとモモは、今にも泣きそうな顔をしているだろうな。いや、もしかしたら怒っているかも。
そのまま俺はモモの方を向く勇気が出ず、小さく「ごめん」と言うと教室を飛び出した。後ろから声をかけられた気がするが、振り向かずそのまま自分の教室に戻った。
放課後、俺はちゃんと謝ろうと、モモがまだいるであろう隣の教室の扉の前に立っていた。あとはここを開けて謝罪の言葉を述べるだけ。たったそれだけのことなのに、あと一歩が踏み出せないままでいた。もしかしたらアイツ、部活とか委員会かも知れないし。別に俺たちいつも一緒に帰ってるわけじゃないし。そんな誰にでもない言い訳をすると、俺は踵を返して下駄箱へ向かった。そそくさと靴を履き替えると、逃げるように足早に校舎を後にした。
ところが、歩いているうちに、モモに謝れなかったという後悔が質量を増して押し寄せてくる。もう許してもらえないかもと思うと、今にも胸が押しつぶされそうだった。秋の曇り空も相まって、どんどん重くなっていく足取りのなか、校門を出ようとした時だった。
「アイ、一緒に帰ろうよ」
突然後ろから強く背中を叩かれ、俺は転びそうになった。少し特徴的な高めの声は聞き慣れたもので、振り向かずとも、それが誰のものかすぐにわかってしまう。
「モモ……」
あまりの気まずさに俺は言葉に詰まってしまった。しかし、そんなことは気に留めない、というような快活な声でモモは言い放った。
「これ、忘れ物。悪いけど返品は受け付けてないからね」
振り向こうとしない俺の正面に回り込むと、モモは俺の胸元に何かを押し付けた。咄嗟に受け取ったそれに視線を移すと、そこには昼休み、俺が突き返したテディベアが微笑んでいた。はっとして顔を上げると、柔らかく笑うモモがいた。途端に罪悪感に耐えきれなくなった俺は、勢いよく頭を下げながら言った。
「モモごめん! あんなひどいこと言って。せっかく俺のために買ってくれたのに」
「ぜーんぜん平気。てか、あれは僕もタイミングが悪かったよね。こっちこそ気遣えなくてごめん」
そう言って苦笑するモモを見て、一気に緊張の糸が切れる。先ほどまであんなに重苦しかった空気が嘘のようだ。一言二言交わしてすっかりいつも通りに戻った俺たちは、再び駅までの道のりを歩き出した。しばらくして、並んで歩いていたモモが口を開いた。
「それにしても、アイがあんなこと言うの珍しいよね」
「もうあのことは忘れてくれよ、悪かったって」
「違うよ、アイが何か悩んでるんじゃないかって。じゃないとアイはあんなこと言わないでしょ」
俺の言葉を遮って、モモはきっぱりとそう言った。驚いてモモを見ると、何もかもお見通しといった目で見つめ返された。普段はどこか抜けた天然のくせに、こんな時だけやたら勘がいい。
それからモモは何も言わず、じっと俺が話し出すのを待ってくれていた。しばらくの間沈黙が流れ、ただ俺たちが落ち葉を踏みしめる音だけが響く。ようやく俺は、言い淀みながらも思いを口にすることができた。
「……モモは俺が可愛いもの好きなの知ってるだろ。でもさ、やっぱ俺みたいなのがこういうの持ってたら気持ち悪いのかなって」
そう言って、俺は手の中におさまっているテディベアをじっと見つめた。何度見ても愛らしいそれの、ふっくらとした頬を指先で優しく撫でてやる。
「気持ち悪くなんかない!」
辺りに響くほど大きなモモの声に、思わず俺は顔を上げた。俺たちと同じように、駅に向かっている人たちの視線が降り注ぐ。
「僕は可愛いものを見てる時の、幸せそうなアイの顔が一番好きだよ。それのどこが気持ち悪いの」
そう言い放ったモモの、あまりにまっすぐな目に恥ずかしさがこみあげてくる。ああ、そうだ。モモはいつだってこういう奴だった。俺がモモに嫉妬した本当の理由は、可愛いものが似合うからとかそんなことじゃない。臆病な俺とは違って、堂々とありのままの自分をさらけ出す姿が眩しかったからだ。
「俺、お前がずっと羨ましかったんだ。男が可愛いものを好むなんて普通じゃない、男らしくしてなくちゃだめだって思って俺は生きてきた。それなのに、モモはそんなもの簡単に飛び越えていくからさ」
上手くまとまらない思いを、俺は必死に言葉にして吐き出す。その間、モモは一度も俺の言葉を遮ることなく、黙って耳を傾けてくれた。そんなモモが再び口を開いたのは、改札の少し手前まで来た時だった。突然足を止めたかと思えば、くるりと俺の方に体を向けた。
「アイはアイなんだから、それでいいんじゃないの。普通とか男らしさとかにこだわらなくたってさ。だってそんなの誰かが勝手に決めたものでしょ。――アイ、もういいじゃん。好きなように生きなよ」
そう言ってモモはとん、と俺の胸を叩いた。その瞬間、宝物のテディベアを抱きしめる幼い自分の姿が脳裏をよぎった。あの日捨てたはずの、ありのままの自分が再び息を吹き返したような気がした。
空っぽだった心が満たされていくのがわかる。気がつけば俺の頬には涙が伝っていた。年甲斐もなく泣き出した俺を、モモは優しくなだめてくれた。そして、俺の背中をさすりながら、モモは遠い目をしてぽつりぽつりと話し出した。
「ぶっちゃけ僕だって、皆に『かっこいい』って言われるアイが羨ましいよ。たまには僕も言われてみたいもん。まあ……僕には似合わない言葉だよね。せめて可愛いもの持つの、我慢しなきゃかな」
へらっと笑いながらも、少し声の暗くなったモモに俺は動揺する。モモがこんなことを思っていたなんて全く知らなかった。俺は出かかっていた涙をごしごし拭くと、モモの方に向き直った。照れくさい気持ちをこらえて、率直な思いを伝える。
「俺、お前のこと超かっけーって思ってるけど」
モモがかけてくれた言葉のおかげで俺は救われた。でも、自分の思いを相手にまっすぐに伝えるのが簡単じゃないことを、俺はよく知っている。だからこそ、それを平気でやってのけたモモのことをかっこいいと思った。
「へ……僕がかっこいい?」
「おう、モモは今のままで十分かっこいいぞ」
そう言うと、モモは顔を真っ赤にして俯いた。しばらく「あー」だの「うー」だの言葉になってない声を漏らしていたが、突然誤魔化すように「もうちょいで電車来るよ」と言った。冷静を装ったような声色だったが、その顔はにやけるのを抑えられていなかった。さっきまでの頼もしい姿とのギャップに、俺はつい吹き出す。
モモの言葉どおり、掲示板を見上げれば、それぞれのホームにあと少しで電車がやってくるらしい。現実に引き戻された俺たちは、挨拶もそこそこにホームへ駆け出した。俺の涙はとっくに引っ込んでいた。
「モモ、ありがとな!」
そう俺は声を上げながら、同じくらいに反対側のホームに降り立ったモモに大きく手を振った。
「こっちこそありがとう! アイと話したらおれまでスッキリした!」
俺と同じように、声を上げながら手を振り返してくるモモを見てほっと息を吐く。その時ふと、モモの言葉に俺は違和感を抱いた。なんだろう、と考えようとしたが、直後にやってきた電車の轟音にそんなものはかき消された。
電車に乗り込み、ちょうど空いていた席に俺は腰を下ろした。さっき鞄の中にテディベアを押し込んだのを思い出し、窮屈そうにしていたのをそっと取り出した。改めて見ても、かつて一番の宝物だったあのぬいぐるみによく似ていて、また自分のもとに帰ってきてくれたのではないかと思ってしまう。
「ごめんな、もう二度と捨てたりしないから」
自分にしか聞こえないほどの声で、そっとテディベアに語りかけた。ぬいぐるみを捨てた時の、あの胸の苦しさは今でも忘れられない。ずっと後悔していたことだった。これからは周りがなんと言おうと、俺が大事にしたいと思うものは大事にしよう。そう心に誓った。
しばらく電車に揺られぼんやりしていると、一昨日、ショッピングモールで見たワンピースのことをふと思い出した。あれをこのテディベアに着せることができたら、どんなに可愛いことだろう。そんなことをあれこれ考えているうちに、「俺の手で、このテディベアをもっと可愛くしてやりたい」そんな思いが膨らんだ。フリフリのレースにキラキラのビーズやスパンコール。昔捨てきれなくて、今でも引き出しの奥底で眠っている宝物に思いを馳せる。
ちょうどその時、車内アナウンスは俺が降りる駅の名前を繰り返した。早く帰って作業に取り掛からなくては、と胸が躍る。俺は勢いよく席を立つと、ドアの方へ向かった。
電車がホームに入る時、何気なく目を向けた窓には、自分の姿が反射していた。相変わらず体格はいいし、顔立ちも相まって威圧感は否めない。でもそれが俺だし、可愛いものが好きなのもたしかに俺なのだ。随分シンプルなことだが、ようやく俺は受け入れることができた。ガラスに映った自分の顔は清々しかった。
翌朝、俺は大きなあくびをしながら学校へ向かっていた。ひんやりとした風に吹かれ、幾分か目が冴える。鞄についたテディベアの衣装も、風をはらんでふわりと揺れた。あの時のゴシック・ロリータをイメージした衣装は、俺にとって渾身の一作だ。おかげさまで睡眠不足だし、手は絆創膏だらけになったが、そんなことはどうでもよくなるほど、俺は充足感に包まれていた。
早く誰かに見せたくて、つい急ぎ足になる。そんな俺に「おはよ」と駆け寄ってきたのは洋だった。俺も挨拶を返しつつ振り返ると、彼の顔はわずかに引きつっていた。その視線の先は――テディベア。
「え……お前、そのクマ結局貰ったのかよ。しかも昨日よりグレードアップしてね?」
「おう、俺が服を作ってやったんだ。この方がもっと可愛いだろ」
俺はテディベアを見せつけるように、ぐっと洋との距離を縮めた。俺の好きなものが詰まった、世界で一番可愛い小さな宝石箱だ。
「お、お前一晩でどうしちゃったんだ?」
「どーもしねえよ。てか、俺が好きなもんつけて何が悪いんだよ」
うろたえる洋に、俺はにっと笑って言い返す。こいつに悪気がないのはわかっているが、一方的にとやかく言われるのはもうごめんだ。俺に可愛いものが似合わないのは、俺が一番わかっている。それでも俺は自分が好きなものはちゃんと「好き」と言いたい。男らしさとか普通とか、そんなものはどうだっていい。ただただ俺という一人の人間が、たまたま可愛いものが好きなだけの話だ。
「まあ……言われてみれば、可愛いのか……?」
困惑した表情を浮かべながら、恐る恐るといったふうに洋はテディベアに触れた。ところが案外良い触り心地が気に入ったのか、なかなか手を離そうとしない。どうやら掴みは上々らしい。そんな洋を見て、俺はふっと笑う。その時、聞き慣れた高い声が俺の鼓膜を揺らした。
「おはよー。アイ、洋」
声がした方に顔を向ければ、モモが俺たちに手を振っていた。その鞄には、しっかりとおそろいのテディベアがぶら下がっている。俺と洋が軽く手を上げて応えると、「おれも話に入れてよ」と言いながらモモは間に割り込んできた。まったく、朝から元気な奴だ。無理やり隣におさまったモモは、ちらっと俺の鞄に目をやった。
「テディベア、めっちゃ可愛くなってるじゃん。やっぱりアイにあげて正解だったよ」
そう耳打ちをして、モモは満足げに笑みを浮かべた。俺は込み上がってくる喜びを噛み締めて、「だろ?」とだけ返して口角を上げた。
なんてことない、日常の始まり。でも、俺にとってはほんの少し特別な日。再び俺たちが歩き出せば、それに合わせてテディベアたちも嬉しそうに揺れた。
※作品の無断転載を禁じます。
・日本語日本文学科(学科紹介)
・日本語日本文学科(ブログ)
・文学創作論