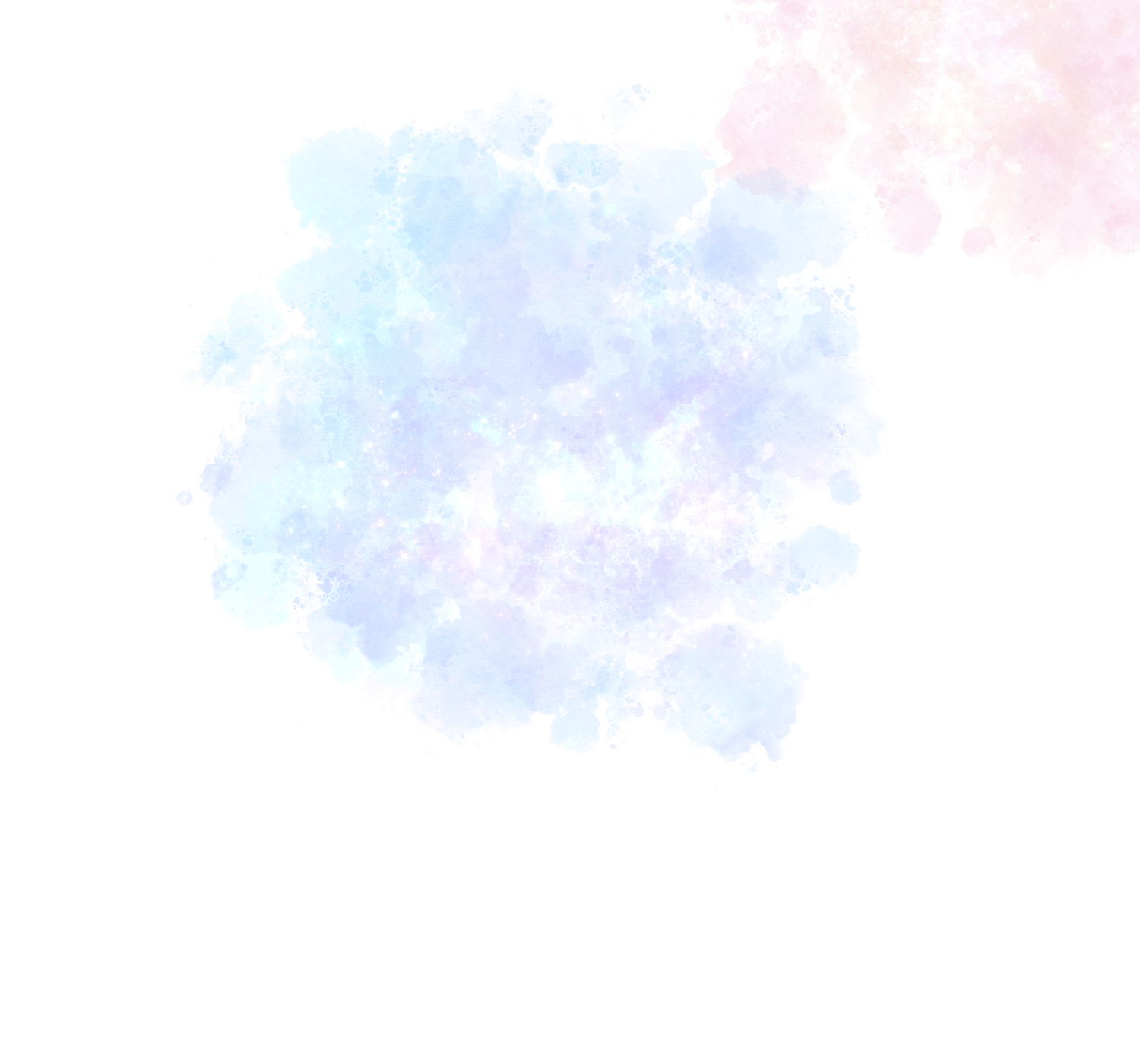本学科の授業科目「文学創作論」では、履修生が1年をかけて作り上げた作品をまとめて、文集を発行しています。
ここでは、第19集『夕映え』に掲載の一作を、ご紹介します。
文集は、オープンキャンパスなどでご希望の方にお渡ししております。機会がありましたらぜひお手にとってみてください。
 第19集文集『夕映え』(2021年度)表紙
第19集文集『夕映え』(2021年度)表紙
意欲と熱
作・高橋 美優
ぽかぽかと暖かい日差しに誘われて、遥(はるか)は一つあくびを漏らす。それが切り替えのスイッチかのように、数時間の批評会の緊張感がドッと抜けていく。その様子を見ていた那奈(なな)がお疲れさま、と笑いながら声をかけた。
目の前に広がったままの冊子は、部員と顧問の努力が詰まっていてそれなりに分厚い。読んで物語の世界を旅するのも、物語をさらに魅力的にするための批評会も、それなりに労力が必要である。遥は、ひと仕事終えたと言わんばかりに大きく伸びをした。
遥は、批評会が得意ではない。他の部員や顧問の作品を読んでもアラなんて見つける前に物語に入り込んでしまうから、感想程度のものしか発言できない。けれど、他の作者が求めているのは改善するためのアイディアなのだ。那奈に返事しながら緊張でにじんだ手汗をスカートでこっそり拭く。
「むずかしいな……」
考えるって、難しい。なんとなくで生きるのはダメなのかな。
ぽつりとこぼれた本音は、誰にも気づかれずになま暖かい教室に溶けていった。本棚に囲まれた部室は少し埃っぽく、舞っている塵が日光でチラチラと輝いている。
「もう四月から高三か。私たちが文芸部引っ張っていかなきゃね」
「実感ないな……」
荷物を片付けながらそう意気込む那奈に対して、遥はひとつ溜息をついた。
「自分の創作で精いっぱいなのに、タメになること言えるかな」
「ね、なかなか難しいよね。ま、がんばろ!」
遥は那奈の言葉にうなずく。那奈は難しいと言うけれど、いつも的確に痛いところを突いてくるじゃないかと密やかにねめつけておいた。
「まあ、まずは自分の創作を頑張りなよ。創作って難しいけど、楽しいからさ。二年の二人にはこれからも頑張ってほしいな」
顧問の中村の低い声が聞こえる。それに合わせて中村の視線が、卓上の冊子から遥と那奈の方へ向いた。遥はドキリとしてつい視線をそらしてしまう。文芸部の活動を大変だなと思うことが多くなったことを悟られたくなかったからだ。
「はーい、がんばります」
中村の話にうなずきながら聞いていた那奈は、笑顔のまま答えた。
「……池田はさ、創作において大事なものって何だと思う?」
「え? 急になんですか?」
「いいから」
自分に話が回ってきたため、遥はおずおずと中村のほうへ視線を向ける。急かされるがまま、遥は少し考える。教室は暖かいはずなのに、緊張感で体が冷えたように感じる。遥の視線は天井、壁の本棚、机の上の冊子と移動して、中村に戻っていく。
「え、えっと……。物語の設定、とかですかね」
「それも大事だね。でも、俺は自分らしさだと思ってる」
「自分らしさですか?」
聞き返す遥と、二人のやりとりを聞いていた那奈を交互に見た中村は一つうなずいた。
「うん、今や小説は星の数ほどあって、全く被りのない完全オリジナリティの作品を作り上げることは不可能だと思うんだ」
確かに、と那奈が呟いた。遥も納得したようにうなずく。
「だから、物語に自分らしさをどれほど詰め込めるかが勝負になってくると思うんだよね」
自分らしさ、その言葉が胸にズンと深く突き刺さる。自分らしさって、何だろう。答えの分からない問いが、頭をよぎる。今まで考えたこともなかったけれど、自分らしさってみんなは自覚してるのかな。ぐるぐる、ぐるぐる。少し考えたところで、遥はまあいいかと考えることを諦めた。
放課後になった途端、教室は一気に騒がしくなる。部活動へ向う者、他の教室へ駄弁りに行く者と、すぐに教室から人が減っていく。ホームルームが終わって、遥はいそいそと帰る準備をしていく。批評会は月に一回であるため、しばらくは部としての活動はない。遥は放課後になった途端に早く帰りたそうに日向(ひなた)に声をかける。中高一貫校に入学してずっと仲が良かった日向と、高校二年生でやっと同じクラスになれたのだ。日向も帰宅してゲームしたいからと二人で即帰宅するのがお約束となっている。
「帰ろ~」
「ごめん、今日バスだから無理だわ」
「バス? 珍しいね、どっか行くの?」
バス停は学校の最寄りの駅と反対方向であるため、帰るときに立ち寄ることは少ない。いつもなら教科書は机の中に残すから日向のカバンはスカスカなのに、今日は何かの教材が詰まっていた。
「うん、ボイトレに通うことにして」
「ボイトレ?」
「うん、ボイストレーニング。声優って初めてやりたいって思ったことだからさ。本気でしてみようと思って」
この前の批評会のときと同じ、ズンとした感覚が蘇る。遥は勝手に、日向のことを周りに流されてなんとなく生きている仲間だと思っていたのに。そんな日向も、いつの間にか自分のやりたいことを見つけて行動している。寒くないはずなのに、鳥肌が立っていく。日向の話を聞いて笑って応援しながら、遥はひっそりと、やっぱり自分はひとりぼっちなんだと考えた。
日向と別れて一人で帰路につく遥は、いつものようにイヤホンを装着して動画を見始めた。いつも通りのことなのに、好きな活動者の動画なのに、なぜかいつものようには楽しめなかった。暖かな日差しが降り注ぐなか、一つ冷たい風が遥の頬を撫でていく。
やりたいことなんて見つからないし、なんとなく適当に生きるのはダメなのかな。自分のこと、進路のこと、やりたいこと……。そんなことを考えたって正解が分からないし、そもそも正解なんてないのかもしれない。この前とは違い、重い刺激は消えることなくズキズキと胸に残る。痛みと連動しているかのように、遥も考えることを諦められなかった。
ぼーっと歩いていると、いつの間にか駅に着いていた。動画の音声に透ける、駅のにぎやかさに寂しさが増して、遥はそっと音量を上げた。
私も、自分らしさを探す努力はした方がいいのかな。探しても、見つからないのかもしれない。自分が理解できないかもしれない。それでも……。そうやって、またぐるぐると考えていく。
このまま帰ってゲームをする、だらけた時間を過ごすのがなんとなく惜しくて、遥は駅の近くの商業施設へ入る。胸の痛みをごまかしたくて、アクセサリーショップやアパレルに軽く立ち寄っていく。きらきらしたアクセサリー。違う。かわいいフリルのついた服。違う。心にぽっかりと空いた寂しさの穴は埋まらない。
なんとなく訪れた書店で、読書でとにかくインプットしようと思いついた。本を読んで、他の人の人生を知ろう。たくさんの生き方を知ろう。目に付いたものや、表紙が気になったもの、好きな作家の文庫本を数冊手にする。新刊コーナーに、有名作家のエッセイ本が並んでいた。星のない夜空のような深い紺に夕暮れのオレンジを数滴たらしたような抽象的な絵画に『熱』と明朝体で書かれたその本は、まるで小説かのような出で立ちであった。近くに積んであったカゴを一つ貰い、文庫本たちをそこへ入れて両手を空ける。立ち読みはあまりしたくないけれど、なぜか気になって仕方がなかった。
――エッセイにはルールなどない。好きなものを書けば良いし、そこに正解も間違いもない。自分の気持ちを発信するツールは無限にあるけれど、いちばん、自分の言葉で読者に届けることが出来るのはエッセイだ。イチゴのおいしさを語ろうが、政治的意見を語ろうが、どれも同じエッセイなのである。エッセイにルールはない。結論を出す必要もない。読者よ、自由であれ。
結論を出す必要がない。自由であれ。遥は、夢中で文字を追った。私は、自分だけ自身のことが理解できず焦っていたのかもしれない。
顔を上げると、レジ横の柱に貼られた大きなポスターが目に入った。
『第十回 学生エッセイ賞 ――自分とは、なんだ?』
自分とは、なんだ。遥の胸がまたズンと重くなる。痛い、苦しい。けれど、悪い痛みではない。これだ。エッセイなら。結論を出さなくてもいいんだ。エッセイなら……、自分らしさが分かる第一歩になりうる。
そうポスターを見つめる遥の目には、熱い意欲が宿っていた。
※作品の無断転載を禁じます。