現代社会学科の卒業論文(卒論)のテーマは、おそらく他のどの学科より多様です。
社会学も歴史学も、政治、経済、文化から国際関係、メディアまで本当に幅広く研究対象にしますし、地理学も幅広い分野ですので、現代社会学科の学生は、かなり自由に幅広く卒論の研究テーマをえらぶことができます。
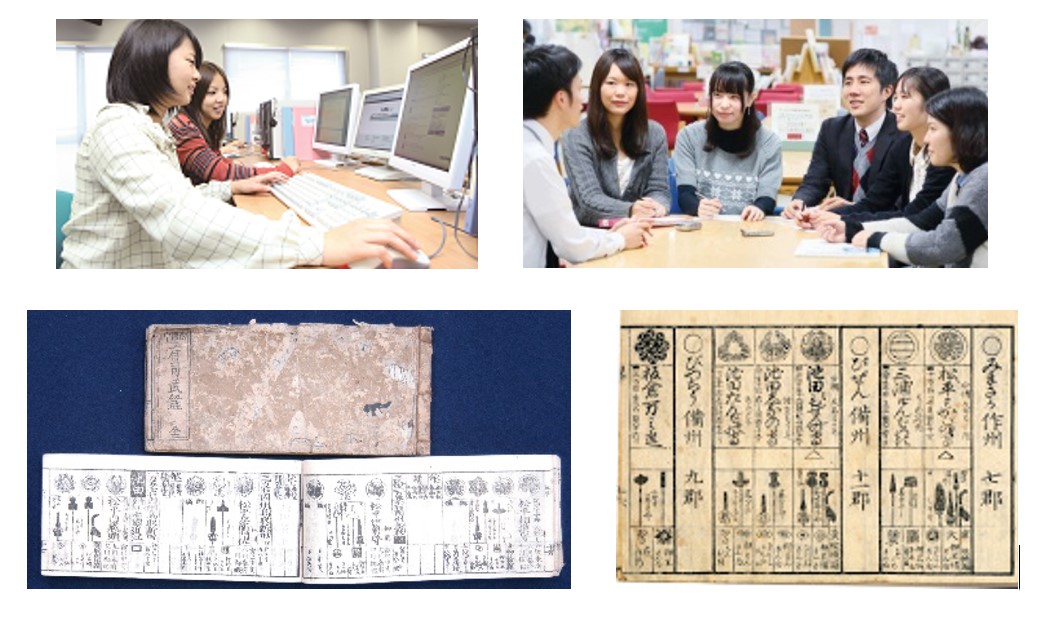
分かりやすく言うと、中学の「地理」・「歴史」・「公民」、高校の「地理」「世界史」「日本史」、「倫理」「政治経済」「現代社会」で学んだ内容であれば、まずすべて卒論のテーマにすることができます。これほど広い学科は他にはないと思います。
日本社会だけでなくアジアやヨーロッパの社会も、また時代も現代だけでなく近代も中世も古代のことも対象になります。社会学は同時代のことであればすべて対象になりますので、今日のTVや新聞で話題になっていることも、ファッションや事件、最先端の話題もすべて研究テーマにすることができます。
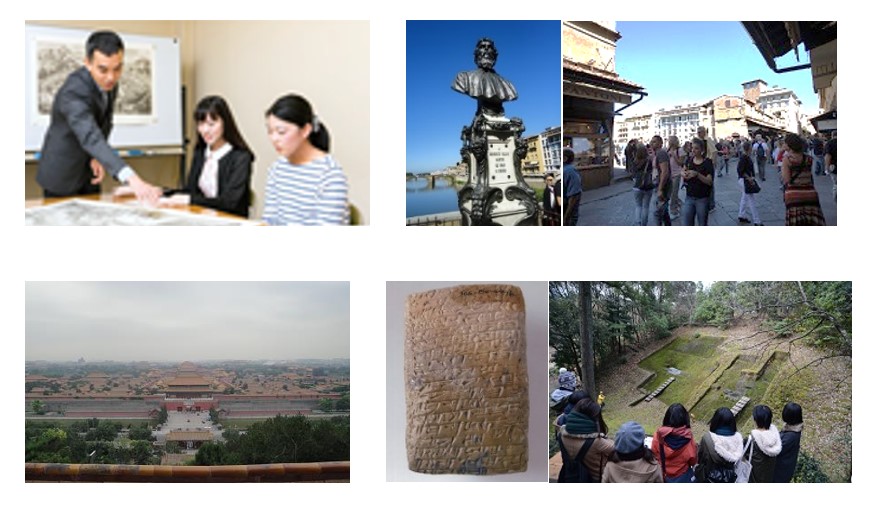
高校の総合型学習で、地域の歴史やSDGsについて調べた人もおられるでしょう。もちろん、それらも現代社会学科では研究テーマになります。実際、環境問題や様々な社会問題を卒論のテーマとして選ぶ学生は多いですし、岡山や瀬戸内海、中四国の歴史をあつかう学生も少なくありません。
では、「なんでもありなんですか?」というと、やはり信頼のおけるデータや史料をしっかり集めたり、客観的な分析を行ったり、という「研究の作法」はしっかりあります。それらは1年生・2年生と順にまなんでいきますので、心配される必要はありません。
実際に、先輩たちの卒業論文のタイトル・サブタイトルをまずはみていただきましょう。
以下は、2021年3月に卒業した現代社会学科学生の卒業論文のタイトル・サブタイトルを、指導教員ごとにまとめたリストです。もっと多様な年もありますので、一つの参考にごらんください。
| ■現代社会学コースの卒業論文 山下美紀ゼミ(家族社会学) 二階堂裕子ゼミ(地域社会学) 濱西栄司ゼミ(社会集団・組織論) 中山ちなみゼミ(社会心理学) 福田雄ゼミ(宗教社会学) 森泰三ゼミ(人文地理学) |
■社会史コースの卒業論文 西尾和美ゼミ(日本社会史) 久野洋ゼミ(日本社会史) 鈴木真ゼミ(アジア社会史) 轟木広太郎ゼミ(ヨーロッパ社会史) 紺谷亮一ゼミ(考古学) 小嶋博巳ゼミ(民俗学) 森泰三ゼミ(人文地理学) |
| 現代若者の人間関係構築過程における選択行動の解明 |
| 愛情と弁当の関連 |
| 現代女性における価値観の世代的差異 |
| アイドルのファン行動と結婚観の関連 |
| 嘲笑されるフェミニスト |
| 日本社会にあり続ける占いの価値―運命による自信の獲得― |
| 恋愛ドラマにみる理想のライフスタイルの変遷―未婚女性の理想の恋愛・結婚― |
| 「女性らしさ」の多様性とその影響 |
| 他者に依存する自己肯定感―容姿と能力を求められる若年女性― |
| 性に関するカミングアウトを余儀なくさせる社会の解明 |
| 障害者を管理する家族―精神障害者家族の役割と機能― |
| 「善良な人」が抱える偏見とその低減の可能性 ―カテゴリー化と性的マイノリティへの偏見に関する活動に着目して― |
| 現代若者の友人関係の形成と展開 |
| 叱らない社会と叱られたい若者たち |
| 障害者アートはいかなる価値をもつか |
| パパは何を買うのか―岡山県のパパ活を事例に― |
| 農福連携における時代的課題 |
| 廃校の利活用をめぐる地域社会学的考察―岡山県真庭市上田地区の「UEDA VILLAGE」を事例として― |
| まちゼミの可能性と課題 |
| セラピードッグとセラピストとのチームがもたらす効果 |
| 現代日本の性教育をめぐる課題と可能性―香川県における取り組み― |
| 1999年東京生まれ岡山育ちの自己エスノグラフィ |
| 子ども食堂におけるボランティアスタッフが得るものとは何か |
| 等身大の吹屋を描き出す |
| 日本の漁村部に嫁いだ中国人女性と地域社会 ―白石島の日中国際結婚を事例に― |
| 迷惑施設としての子ども施設 |
| 多文化主義の教育実践と留学生の配慮と葛藤 ―ヴィクトリア大学附属語学学校を事例に― |
| 被災地支援団体の活動と被災者・地域の受け入れと評価 ―平成30年7月豪雨災害におけるAMDAの活動を事例に― |
| しまなみ海道がもたらす地域の変化と島民の認識 |
| 空港建設と近隣住民の反対理由―岡山空港を事例に― |
| 太陽光発電所建設が生み出す環境問題―足守地域住民の反対活動を事例に― |
| 訪日外国人旅行者急増地域の住民の対応と複雑な思い―瀬戸内国際芸術祭開催地域の宿泊施設を事例に― |
| NPO法人のまちづくり協働事業における役割と関与 ―西川緑道公園とNPO法人タブララサを事例に― |
| 「多様な正社員」制度と正社員転換制度に関する雇用者と労働者の認識の相違 ―A社を事例に― |
| 豊島問題をめぐる住民の反対運動とその継続要因 ―廃棄物対策豊島住民会議中心メンバーへの聞き取り調査をもとに― |
| 小さな世界で自己充足化するファン |
| アイドルを同性間消費する女オタク |
| インフルエンサーの誕生による現代の消費行動 |
| ゲーミフィ社会における内観的な<わたし>―「異世界もの」でシュミレートする人生の選択肢― |
| マクドナルド化するInstagramの自己発信 |
| 有名人化するYouTuberの魅力の構造 |
| マンガの主観的重要度を規定するマンガと現実の関連度 |
| SNS化するクチコミサイトにおける利用者の相互関係 |
| 人と猫が共生できるまちづくりに向けて ―2つの猫島における地域猫活動の現状と課題― |
| LGBT活動の成果と課題 |
| 近代化産業遺産の歩みと展望 ―瀬戸内地域の銅山からの考察― |
| 日韓の美容整形における価値観の考察 |
| 離島における活性化の現状と課題 ―笠岡諸島を事例に― |
| 地方の水族館における集客力とその要因 |
| 全国の防災教育における地域的特徴と課題 |
| 岡山市北区問屋町における再開発とまちづくりの課題と展望 |
| 市民農園による地域活性化の状況 ―牧山クラインガルデンの事例から― |
| 岡山県内における清酒製造業者の現状と課題 ―地域の魅力創出の視点から― |
■社会史コースの卒業論文
| 『今昔物語集』にみえる病と医療について |
| 中世の文学作品にみえる「異形」の形 |
| 『今昔物語集』・『日本霊異記』にみる捨て子 |
| 『今昔物語集』にみえる婚姻のジェンダー非対称―人間の婚姻と異類婚姻譚の比較・考察を通して― |
| 『今昔物語集』にみる地蔵信仰と観音信仰 |
| 説話と民俗にみえる人身御供 |
| 日本統治時代の台湾における皇民化運動―志願兵への影響― |
| 『史記』からみた秦の統治と始皇帝の統一 |
| 興中会・華興会・光復会の結社的性質の相違からみた中国同盟会の分裂 |
| 『貞観政要』からみた唐太宗李世民の実像 |
| 『唐代伝奇』にみえる女性の恋愛 |
| 清朝初期における三藩の処遇問題 |
| 唐代における女性の服飾と日本への影響 |
| 新羅における女王即位の背景 |
| 清末の宮廷内における西太后の権力掌握の過程 |
| 近世・近代フランスの学校と教育 |
| 宮廷モードからコレクションへ―フランス・ファッションの変遷― |
| グリム兄弟の仕事の裏を読む |
| 魔女裁判とその前史 |
| ロシア革命下の社会生活 |
| 古代ローマ社会と奴隷 |
| アベラールとエロイーズ―世俗的愛から導きの絆へ― |
| ナチスに抵抗した人びと |
| 近世・フランス革命期 パリの死刑執行人 |
| 19世紀パリの娼婦 |
| ポリスから警察へ―元密偵刑事ヴィドッグの回想録を中心に― |
| ナチ宣伝相ゲッベルス |
| ユダの福音書の再考察 |
| 縄文時代における青森県のアスファルト利用 |
| 吉備中南部における弥生~古墳時代の集落変化 |
| 日本人西アジア考古学者の研究動向と課題 |
| 西アジア考古学者Kに関する新聞記事とその評価 |
| 児島八十八カ所の構造と展開―新四国霊場間の比較と札所の移動― |
| ひょうげ祭り―高松市香川町の水利とため池築造伝説― |
| 高梁市津川町今津における小祠祭祀 |
| 近代に発生した小信仰集団・泉聖天 |
| 地方の温泉における課題と展望 |
・現代社会学科
・研究分野



