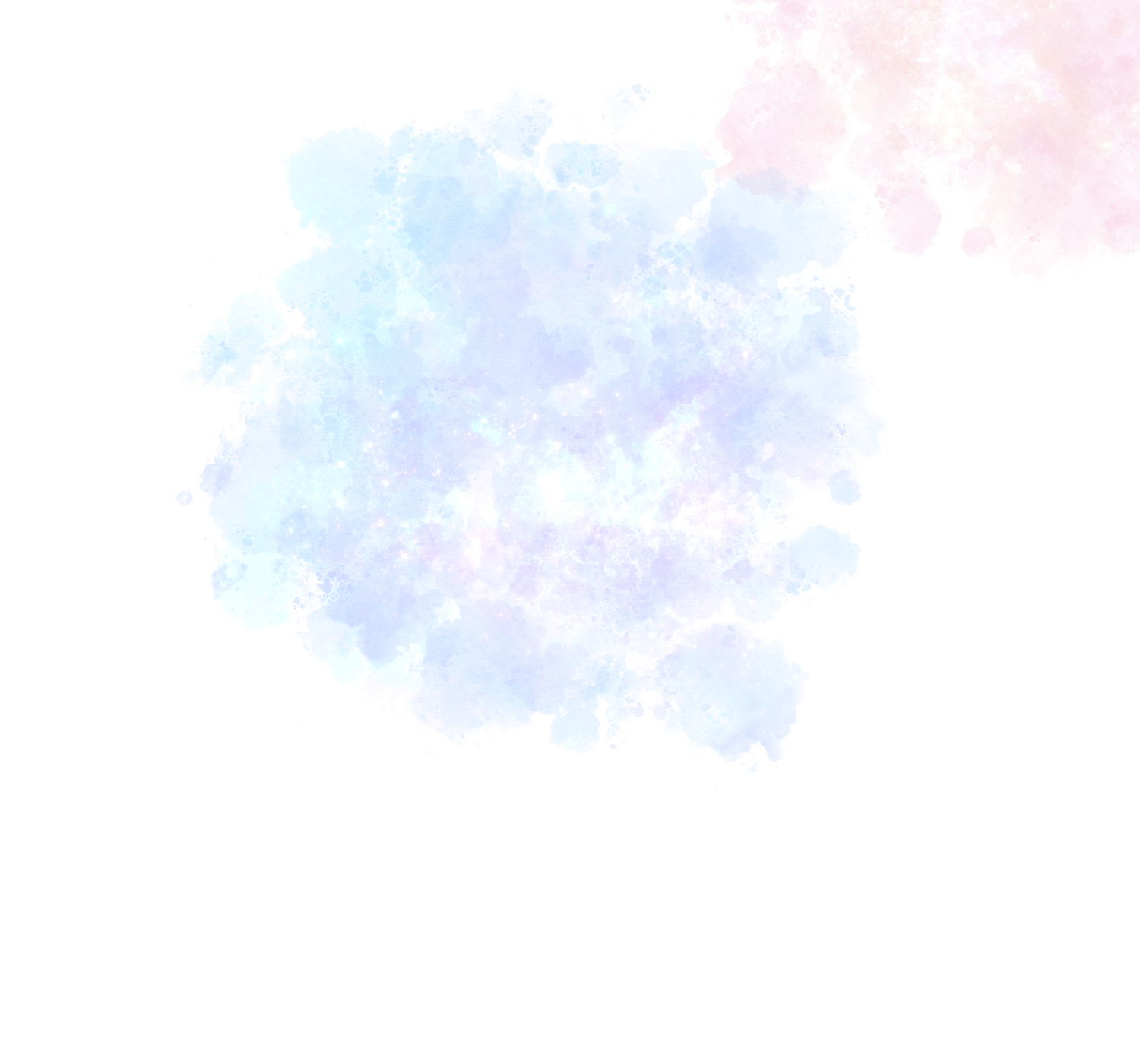本学科の授業科目「文学創作論」では、履修生が1年をかけて作り上げた作品をまとめて、文集を発行しています。
ここでは、第22集『結び』に掲載された一作「バット・ヒューマン」を、ご紹介します。
 第22集文集『結び』(2024年度)の表紙
第22集文集『結び』(2024年度)の表紙
文集は、オープンキャンパスなどでご希望の方にお渡ししております。機会がありましたらぜひお手にとってみてください。
バット・ヒューマン
作・向井地 愛(2024年度・3年生)
自宅から徒歩五分。無人駅の踏切が鳴り始める音が、うっすらと耳に届いて溶け込んだ。アタシは、待ち合わせ相手の家を囲む、高い塀でできた日陰にすっぽりと包まれる中、
「雅(みやび)、出かけるなら麦茶パック買ってきて」
というママからの一言を、眉間をぐりぐりと指圧しては反芻していた。
今日は高二の夏休み最終日。いつもなら三度寝を開始している時間帯だからか、起床時から今に至るまで眠気との闘いは続いている。負けそう。
しかも暑い。この時期は外に出ただけで、汗が生え際から目に向かって流れ落ちてくるから困る。首筋に風が通るだけ、まだマシだと思った方がいいんだろうけど。半袖のスポーツウェアは、既にじっとり汗が染みては乾いてを繰り返している。照り返しの眩しさから目をつむり、汗をグイと手の甲で拭って欠伸をしていると、
「みーちゃん!」
凛とした声が聞こえた。左側をぐるんと向いたアタシは、待ち合わせ相手が顔にかかる髪の毛を耳にかけ直す姿を目に映した。白いブラウスにパステルブルーのロングスカート。夏の入道雲のように真っ白なレースの日傘を手に添えている様は、童話の中のお姫様がふわっと降り立って現れたようだ。
「ほはよぉ、響希(ひびき)ぃ」
欠伸を噛み殺しきれないまま、アタシは三歳年下の幼なじみにだらんと手を振った。
「みーちゃん、待たせちゃってごめんね。今日の服装に合うリボン選んでいたら、時間かかっちゃった」
ふわりと長い髪の毛に包まれた頬は、ほんのりと赤く染まっている。ココア色の眉毛も、みずみずしいさくらんぼのような唇も、全てが響希を引き立てている。目の前でずっと下がりっぱなしの眉毛と、ウロウロと焦点が迷子になった瞳を交互に見て、思わず笑ってしまった。
「普段はアタシが寝坊して、響希をずっと待たせとるじゃん? こんな時もあるんやなぁ」
「いつもはちゃんと準備してるよ。ただ、今日はどうしても迷っちゃって」
アタシは、響希の首元で結ばれた紺色のリボンに視線を向ける。アタシ目線だと、響希が持っているリボンはどれも一緒に見えてしまう。でも、本人にとっては重要事項なんやろうね。
「とりあえず、はよ店行こう……暑いけぇ溶けそうやわ」
アタシは持ってきたお茶のペットボトルを開け、口に運んだ。香ばしい匂いが鼻にグッと入ってくる。よく冷えた麦茶が喉を通っていく感覚に一瞬の幸福感を味わったけど、半袖からはみ出た肌越しに感じる暑さで、秒で現実に戻されてしまう。
「そうだね、行こ行こ! おれ、今いっぱい買いたいものあるんだ」
響希の声と共に、柔らかな風が響希のストレートヘアとスカートを揺らした。
長い髪の毛はウィッグ、小さいけれど角張った手、首元にちらちらと覗かせては上下に動く突起。
響希は、可愛いものが大好きなだけの男の子。
買い物に行くといっても、田舎にはショッピングモールどころか、ちゃんとした雑貨店さえない。かといって、電車に乗って遠出をするのも中高生の身には負担が大きい。仕方なしに、近所の百円ショップに向かった。二階建ての建物の内、二階全面に百円ショップが展開されており、一階部分はスーパーとなっている。
べたついた体にシャツが張り付くのをうっとうしく思いつつ店内に入ると、一気に冷気が肌を直撃した。汗がひいて、むしろ肌寒さを感じる程だ。目の前には、出入り口からすぐのところにエスカレーターと大きな階段がどっしりと構えている。
「みーちゃん、どっちで行く? エレベーターもあるけど、今ご家族が入ったところだから時間かかると思う」
スーパーの一角にあるエレベーターに視線を移すと、響希の言葉通り、ベビーカーを押して入ったご夫婦の顔が小さく見えたと思ったら、丁度扉が閉まったところだった。
アタシは、目の前で規則正しく動くエスカレーターを軽く見上げて、すぐに響希の整った顔の方へ向き直った。
「階段にしない? 最近、暑いし学校ないからって家でゴロゴロしてばっかだったし。せめて今ぐらいは動いとかないと、制服入んなくて明日焦ってるアタシの姿が、容易に想像できるけぇな」
半分ホントで半分ウソな理由を、冗談めかして舌先で滑らせる。
「りょーかい。おれも毎日最低一個はアイス食べてたから、そろそろ引き締めないと!」
幸いにも、響希はアタシの発言を疑うそぶりは見せずに、十分ほっそりとしているお腹の辺りをさすさすと撫でていた。
アタシと響希は、既に少し重たい足を踏み込んで進んでいった。階段はタンタンと軽やかな声で歌っている。エレベーターを待っていた方が早く着いたし楽だったんじゃないかとも一瞬思ったけど、二階にたどり着いた時、
「これでちょっとは、カロリー消費できたかなぁ」
って、買い物カゴを手にしながら朗らかに口元を両手の指で隠す響希を見ていたら、やっぱり階段でよかったのかもってアタシは自分を納得させた。
お店をゆったりと歩き、商品棚をじっくりと見ては、丁寧に商品をカゴに入れていく響希の後ろをついていく。商品を大方選んだところで、響希が最後に向かったのはコスメコーナーだった。アタシは、一昨日からずっと考えていた疑問を、響希に向けてみた。
「なぁ響希。なんで突然、買い物行こーって誘ったん?」
両手にネイルを持って吟味する響希に、アタシは横から声をかけた。響希はアタシに顔を向けて、まばたきをする。響希が目を瞬かせる度に、長くふわっと盛られたまつ毛が呼吸した。
「もうちょっとで秋でしょ、秋と言ったらハロウィンもあるし……だから今のうちに準備しておこうって。あと、みーちゃんは明日から、文化祭準備が始まるから忙しくなるってこの前電話で話してたし、今日しかないって思ったんだ。みーちゃんのクラスは迷路作るんだっけ? 今年も出店や出し物、楽しみだなぁ」
響希は鼻歌交じりに答えを返して、すぐにアタシの顔面に両手を近づける。蛍光ピンクとワインレッドの鮮やかな色が、軽くのけぞったアタシの両目の前でパッと広がった。両手の間から顔を覗かせて、響希は首をこてんと傾けた。
「ねぇ、おれにはこの二つだとどっちがいいかな?」
アタシは響希のセレクトに目を見張った。響希はどっちかと言えば、パステルカラーというか、薄めの柔らかい色を身につけているような印象がある。今日の服装も、淡めの色合いだし。
「なんか、響希ってこの二色選ぶイメージなかったけん新鮮やわ」
響希は薄く色付いた唇を微かに横に広げて、ネイルボトルをぎゅっと握りしめた。
「今年のハロウィンは、いつもとは違うカッコをしたいなって。来年は受験勉強に集中したいし、今回は新しいことに挑戦したいんだ」
なるほどね、とアタシは腑に落ちる。響希がニコニコと見せてくるネイルを改めて見比べてから、アタシはワインレッドの小瓶を指さした。震える指、気づかれないといいけど。
「こっちの方が、落ち着いた色合いだから秋冬通して使えるんじゃない? ハロウィンコスにも映え……そう、だし」
響希は満足そうな表情で頷き、ピンク色のネイルボトルを静かに棚に戻した。勘と理由を間違えなかったことに、肩の力を抜く。
「じゃあ、おれはもう選べたから。みーちゃんは何か買いたいものある?」
響希が取っ手を握り直した買い物カゴには、先程のネイル以外にも、髪飾りやコスメ、工作用リボンが転がっていた。アタシは何かお菓子でも買おっかなって考えてすぐに、考えを打ち消した。
「いや、何もないよ。芯とか消しゴムは買ったばっかだし。もうレジ行こ」
響希が片手でクルッとマルを作ったのを見てから、アタシはレジに向かって歩き始める。響希も後ろに続いて歩いた。
家がお隣さんかつ年も近かった響希とは、アタシが幼稚園児だった時からの付き合いだ。外遊びが好きでしょっちゅう走り回っては叱られていたアタシに対し、響希はおままごとやお絵描きが好きで、よく家で遊びたがっていたことを思い出す。
「雅はお姉ちゃんなんだから、響希君に合わせて遊んでね」
というママの約束を守るため、響希と遊ぶ場所はどちらかの家であることが多かった。おままごとやお絵描きは、外遊びに比べたら好きではなかったけど、響希の楽しそうな姿を見ていると、ついアタシも夢中でやり込んでいた。
あの頃から、響希はお化粧に興味があったり、人形用の洋服を自分で作って着飾ったりしていたっけ。成長した今でも、中身はあんまり変わっていないなあ……。
「みーちゃん、大丈夫?」
いつもと違う落ち着いた声を聞いて、意識がハッキリとしてくる。
響希はとっくにお会計を済ませていて、エコバッグの中に買ったものを納め終えたところだった。自分は、ただ昔のことを思い起こして立ち尽くしていただけ。顔を下から覗き込んでくる響希に、
「ごめん、今日はいつもよりも寝てねぇけん寝不足かもしれん」
って早口で言い訳をし始める。だけど、口を閉じ終える前に、手に柔らかい感触が伝わった。すべっとしていて焼けていない肌は、指先にかけてほんのりと冷えている。
「みーちゃん最近、テスト勉強テスト勉強ってずっと言ってたでしょ? ムリはダメだからね」
色づいた指は、いっそう力を強めた。アタシは感情を顔に出さないようにしたまま、するりと指をほどく。そのまま、両手を合わせてから胸の前で小刻みに動かしておいた。
舌を出してにやつくアタシを見つめていた響希は、宙ぶらりんになった指を口元まで持っていき、膨らました頬の前でメッとポーズをキメてから、ふふっと笑った。
結局、その後は響希が頼まれていたおつかいと麦茶パックのために、一階のスーパーについて行ってから、一緒に帰った。食料品の入った花柄のエコバッグを指に食い込ませながら玄関まで運んで、響希の家を後にした。帰宅後、玄関で一応挨拶はするけど、返事は無い。
ダイニングテーブルに麦茶パックを放り投げ、二階へ駆け上がった勢いで自分の部屋を開ける。体中にぶつかる熱気に倒れてしまいたくなるけど、最後の気力を振り絞ってクーラーのリモコンのボタンに爪をぐいと立てた。
電子音が聞こえた瞬間、アタシはクッションにダイブする。しばらくは立ちたくない。顔を上げたら、笑っているような天井のシミと目が合ったように感じて、すぐに顔を背けた。
視線の先には本棚が見える。目ん玉だけを軽く動かしてみると、今の気力でも読めそうなものが目線と同じ高さに見えた。アタシは床を這いずって目的のものを目指した。
ちっちゃい時から何かと動き回ってばかりだったアタシが、唯一静かにできていたことは読書。絵本や童話、なぞなぞの本を図書館で借りてもらっては、響希と一緒に寝転がって読む時間がたまらなく楽しみだった。分からないところを適当に誤魔化して読み聞かせている時は、自分も一緒に不思議が飛び交う世界へ没入していたものだ。
本棚の前に辿り着き、アタシはギリギリまで腕を伸ばして分厚い本を手に引っかけてから、ごろんと寝転がった。表紙の【イソップ童話集】と記されたエンボス加工を指先でなぞって、ページをめくった。おばあちゃんから誕プレとして幼稚園の頃に貰ったやつ。あちこちが黄ばんでいたりシワが寄っていたりするけど、素朴な絵が踊るのが愛らしくて、今でもアタシのお気に入りだ。
久しぶりの再会に口角を軽く上げて更にページをめくっていると、あるページが目についた。シワやシミが他のページよりも多い。タイトル七文字を見た瞬間に、アタシの胸はズキリと痛んだ。
作品名の欄には、『ずるいコウモリ』の七文字が浮かんでいた。
今日は土曜日、文化祭二日目。ここ数日降っていた雨は無事に止んでおり、今朝からすっきりとした青空が広がっている。学校の至るところでソースやチョコレートのいい匂いがするし、吹奏楽部の演奏や笑い声は校内を賑わせている。
アタシは図書室にいた。クラスの当番が終わった後、逃げるようにクラスから離れて、三階の避難場所に飛び込んだ。文化祭の日でも図書室を開けてくれる司書の方には感謝でしかない。
アタシは、横目で中庭側の窓を見る。出店やパフォーマンス会場には多くの人が密集していて、笑っている顔と賑やかな声でいっぱいだ。目を伏せたアタシは本棚の迷路を闇雲に進み、テキトーに止まったところの本棚からテキトーに一冊取って、近くの椅子にどかっと腰掛けた。古ぼけた本の表紙には、エスカレーターのモノクロ写真がでかでかと載っている。少し酸っぱい臭いが漂う、ずっしりとした本につらつらと記述されていた中身は、エスカレーターの誕生や歴史、社会での活用法とこれから……。表紙からも察せる内容ばかりだった。
エスカレーターの乗り方・降り方のコツなんて、初歩的で幼稚なコーナーなんて、当たり前だけどなかった。
ちっちゃい時、エスカレーターが怖かったことを思い出す。上りはまだ、階段と同じように行けばいいと思えるからマシだった。問題は降りる時だ。行こう、行こうとしても足がすくんでしまう。落ちてしまいそうで、怪我をしてしまいそうで嫌だった。段々と、後ろに列が並び始めて、皆の視線が自分を向いていることが嫌でも分かった。舌打ちの声も聞こえる。誰かと一緒だったら怖くないのに、一人だと何にもできなかった。
普通の人ならできることが、できない。できたって褒められない当たり前のことでも、できない。いくら練習しても、いくら教えられても、できないものはできなかった。
成長した今も同じだ。夏休み前にあったクラスの出し物決めの時、アタシは面白そうだなって思った占いの館に手を挙げようとして、クラスがビミョーな空気になっていることに気づいた。アタシは挙げかけた手を耳に持っていき、髪をかけ直しておいた。
皆が一斉に手を挙げたのは、その後に提示された巨大迷路の方。アタシも堂々と手を挙げておいた。しれっとした顔を作れていたハズだったけど、胸中ではぞわぞわとした気持ちがうごめいていた。その後、清掃時間開始の際に耳にした、
「企画決めの時に空気読めんヤツって何なんやろな」
という発言と笑い声で、自分も該当の「ヤツ」の一歩手前まで来ていたことを背中越しに思い知った。冷や汗ダラダラのまま、清掃場所の女子トイレへと向かったことは、今思い返すのも嫌なぐらいにくっきりと記憶に刻まれている。
白いシャツに一滴の墨が目立つような生き様だ。オシャレに無頓着なところも、普通じゃない言動をしてしまうところも。ちっちゃかった時の方が、言い訳で逃げることができて、無知なまま踊ることができた分、まだ微笑ましかったかな。
あのコウモリだって、寂しかっただけなのだろう。どちらの種族とも友だちでありたかっただけなのだろう。でも、動物も鳥もそんなコウモリを許さなかった。結局、コウモリは陰に追いやられてひとりぼっちになった。現実って非情だ。可哀想なコウモリ、哀れなコウモリ。それって
「みーちゃん、ここにいたんだ」
我に返った。目の前には、カスタード色のワンピースを裾がつかないように手で押さえて、アタシの顔を覗き込む幼なじみがいた。いびつに広がった視界に、響希を映さないために頭を下げる。グレーのスラックスを手で無意味に手繰り寄せた。冷房の風が、額や腕のあちこちにぶつかってきて、寒かった。
「……汗びっしょりだね」
響希はシミひとつない真っ白なハンカチと、淡いブルーの布カバーに包まれたティッシュを取り出し、そっと差し出してくる。アタシは手を動かすこともできずただ、向けられたものをぼんやりと眺めた。お礼を言って受け取ることや遠慮して断ること以前に、猫背のままである姿勢を正すことさえ、今のアタシには厳しすぎた。
響希はアタシの両手にそれぞれを握らせて、近くのスツールに腰かけた。
「夜のうちに雨やんでよかったね。食べ物も美味しかったし、ダンスや劇もスゴかったなぁ」
響希の足元で、何かがガサッと音を立てる。響希が床に置いたエコバッグには、イラスト部の販売している画集やらビンゴ大会の景品である文具セットやらで満杯になっている。
「めっ、ちゃ楽しめてんじゃん」
言い切った瞬間、夏場の外のように視界がグニャグニャと濁ってぼやけた。
「ねぇ、みーちゃん。その本見せて」
顔は下に向けたまま、声がした方向に左手を伸ばす。ふっと手が軽くなってから、パラパラめくる音が聞こえた。
「降りるコツ、わかんなかった」
自分を含めた二人だけにしか伝わらない声量で呟いてから、そびえ立つ本棚の頂をじっと目に焼き付ける。見つめれば見つめる程、天井が自分自身から遠ざかっていくように感じた。
「おれも、長縄入るの苦手だったな。いっつも引っかかってこけてたから恥ずかしかった」
響希の顔を盗み見る。笑って頬を赤らめるお人形さんがそこにはいた。膝の上で手を組み替えた響希は、続けて話す。
「まあ、できないものは仕方ないよね。体育得意な子には理解されないんだろうけど、どれだけ練習しても無理だったから。逆上がりや二重跳びも」
運動が苦手で、日々泣いていた幼い頃の響希が脳裏に浮かんでくる。手にタコができても足にアザを作っても、響希は地面を濡らしては孤独に挑んでいた。どれだけ頑張ってもできないのに、無理に練習する必要なんてあるのかって、アタシは練習を見守る中で思っていた。
「みーちゃん。昔、おれがクラスの子に『オンナ男』ってからかわれて帰ってきた時あったの覚えてる?」
アタシが何か言う前に、響希は目をつむって前かがみになりつつ前後に揺れ始めた。響希が何か昔のことを話す時は、真剣に思い出そうとしてつい、こんなポーズをとっちゃう。幼稚園児の頃から全く変わっていない癖。
「えっとね、たしか……泣きじゃくってるおれの話を聞いて、みーちゃんは言ってくれたんだ。『誰にも迷惑かけてないんやから、響希がやりたいコトやりゃいい。アタシは、響希がずっとオシャレの研究しているのはすごいことやと思う』って。もうずっと前のことだから、ちょっと違うかもだけど」
そこまで言ってから、響希は緩んだ表情を見せる。
「みーちゃんのおかげで、おれはずっと『好き』なものを『好き』なままでいれているよ」
今日の響希は、甘酸っぱいオレンジの唇をしていた。栗みたいな茶色のベレー帽を含めた響希の全身コーデは、モンブランを想像させる色味で美味しそう。お腹がすいていたことを、アタシは今理解した。
「そうだ、みーちゃんちょっと待って!」
響希は膝に置いていたショルダーバッグを探って、取り出したスマホを素早くスワイプしてから、アタシに向けてくる。
画面に映っているのは、シンプルな黒ワンピに網タイツと厚底ローファーを組み合わせた響希の自撮り。深紅のルージュとネイルが、普段よりもずっと響希を大人びて魅せている。ワンピの上に、裾の部分がギザギザした薄手の上着を身につけていることに気づいて、
「コウモリ?」
無意識のうちに声が出ていた。響希は深く頷き、満面の笑みで、
「そう! 今年はドラキュラをテーマにしたんだよ。スタイリッシュさをメインにしたくて、コウモリの羽っぽいケープを買ってみたんだぁ。まだハロウィンは先だけど、待ちきれなくって。試しに着てメイクとネイルも合わせたんだけど、過去イチの出来栄えかも」
と、早口でしゃべり終えてからひと呼吸して、小さくはにかんだ。
「へぇ、そうなんや……。カッケェが、コウモリ」
アタシがわざと明るい声を口から出して、再びまじまじとスマホを見はじめると、
「一匹だから、カッコいいのかもね」
ぽそっと響希がつぶやいた。
「コウモリって何にも混じらずに孤独に飛んでるでしょ、その上皆に嫌われているし。でも、だからカッコいいんじゃないかな」
響希は口元をほころばせて、両手で本を返してくる。秋晴れの空のように澄んだ両目と視線を合わせる。すっと受け取ったら、手が軽く沈んだ。表紙を目に捉える前に、アタシは本棚の隙間へ一冊を静かに納めた。やっと、息を吐けた。
アタシは、変わり者だ。コウモリみたいなヤツなんだ。だけど、それでも『人間』を名乗って生きてみようと思う。エスカレーターが怖いなら、階段でもエレベーターでも使って移動すればいいだけだ。
「今年のパーティーもさ、ハロウィンの週の日曜日にやるん?」
スツールにドカッと腰を下ろして、アタシは響希を見つめる。響希はぱっちりなお目目を瞬かせて、キャラメル色にきらめく両指を口元に添えた。
「もちろん! おれの部屋で、お菓子いっぱい用意して待っとくから」
響希の頬は、熟れたリンゴ色にじゅわっと染まった。白雪姫って、こんなほっぺたをしていたんかな。
「今年は、早めに響希ん家行っていい? お菓子作りとか、メイクしてるとことか見てみたい。ブキッチョじゃけん、何か手伝うとなったら響希の負担増えるかもしれんけど」
伝え終える前に、響希は両手を合わせて何度も首を上下に軽く揺らしていた。アタシは笑い声を抑えきらないまま、くくっていたヘアゴムを外して、髪の毛をわしゃわしゃと崩した。レースのカーテン越しに照らす光が、ぽかぽかと心地よかった。
※作品の無断転載を禁じます。
・日本語日本文学科(学科紹介)
・日本語日本文学科(ブログ)
・文学創作論
・これまでの文学創作論を読もう
・文学創作論 文集紹介(第1~22集(最新)) はこちら