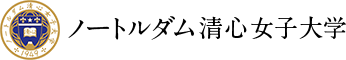2024.03.26
本学科の授業科目「文学創作論」では、履修生が1年をかけて作り上げた作品をまとめて、文集を発行しています。
ここでは、第21集『夕顔』に掲載された一作「思い出玉」を、ご紹介します。
なお、作者・藤澤さくらさんは、「文学創作論」の授業を履修した2023年度中に、童話「ねこのみち」を第39回岡山市文学賞「市民の童話賞」に応募して入選。『おかやま しみんのどうわ 2024』(ふくろう出版)に掲載されました。
ここでは、第21集『夕顔』に掲載された一作「思い出玉」を、ご紹介します。
なお、作者・藤澤さくらさんは、「文学創作論」の授業を履修した2023年度中に、童話「ねこのみち」を第39回岡山市文学賞「市民の童話賞」に応募して入選。『おかやま しみんのどうわ 2024』(ふくろう出版)に掲載されました。

第21集文集『夕顔』の(2023年度)表紙
文集は、オープンキャンパスなどでご希望の方にお渡ししております。機会がありましたらぜひお手にとってみてください。
思い出玉
作・藤澤 さくら(2023年度・3年生)
「それでは始めさせていただきます」
小さな舞台だった。その中心、ぽつんと置かれた座布団の上に、女が座して、ゆっくりと頭を下げた。かたわらで燃える一本の蝋燭が、女の姿と、板張りの床を照らしていた。
これは私が子どもの頃のお話です。当時一番仲の良かった――そうですね、たまちゃんと呼びましょうか。たまちゃんといつものように学校から帰っていると、
「あ、そうだ。手ぇ出して。手のひら上に向けて」
突然こんなことを言われました。私は少し不思議に思いながら、言う通りに手を出しました。するとたまちゃんはスカートのポケットから何かを取り出して、私の手のひらに乗せました。
それは、薄く青みがかった透明の玉でした。見た目はビー玉に似ていました。大きさもちょうどそのくらいです。ですが触り心地は少し柔らかくて、スーパーボールのようでした。
玉はポケットの中でたまちゃんの体温が移ったのかほんのり温かく、湿っていました。それがなんだか生きているみたいで気持ちが悪くて、私はすぐたまちゃんに突き返しました。「ありがと、返すね」
「見た? 見えた?」
たまちゃんは透明の玉をポケットに仕舞いながら、ちょっと照れ臭そうに言ってきました。
「なにが?」
「玉の中にさ、見えたでしょ」
「なんのこと?」
「見えなかった? あたしとあんたがさ」
私には、たまちゃんの話していることがちっとも分かりませんでした。困惑する私の手に、たまちゃんは「じゃあもっかい見てよ」とまた透明の玉を乗せました。
何か特殊な細工がされているのかしら。私は思って、上から覗き込んだり、光にかざしたりしてみるのですけども、玉はただ辺りの景色を透かすばかりです。たまちゃんはうっとりして、まるで遠くのものを見るみたいに玉を見つめています。
「綺麗だよねえ。ほら今、あたしが走ってるよ」
確かに綺麗ですが、たまちゃんが言うようなものは見えません。
「ええ? 何にも見えないよ。ねえこれ何? ビー玉じゃないでしょう、スーパーボールとも違うでしょう。どこで拾ったの」
そう尋ねると、たまちゃんは顔を上げ、
「拾ったんじゃないよ。これ、思い出玉」
と言いました。
「思い出玉」
私は、たまちゃんの言ったことを繰り返しました。それから思い出しました。
今はめっきり見かけませんが、昔は小学校の前にね、何でしょうね露天商といいますか、ひよこやらおもちゃやら飴細工やらを売りに来る人がいたんですよ。若い人には信じられないでしょう。いろいろと大らかな時代だったんですね。
それで、そんな中に混じって、ときどき透明な玉を売りに来るおじさんがいたんです。「思い出玉、一個一〇〇円だよ。大事な思い出を綺麗な玉の中に入れたげるよ」……そうやって、校門から出てきた子どもに声をかけるんです。いかにも怪しげでしょう。ひよこやお菓子なら心惹かれますけども、『思い出玉』なんて聞いたことがありません。適当なことを言ってビー玉を売りつけようとしてるんだ、って誰も相手にしていませんでした。
「え、あれ買ったの!」
駄菓子屋のお菓子が一個一〇円でしょう。一〇〇円もあれば、両手じゃ足りないくらいのお菓子が買えます。私からすれば「あーあ、たまちゃん、馬鹿なことしたなあ」と。自分がだまされて買ったのが口惜しくて、今度は私を「何か見える」って言ってだまして買わそうとしてるんじゃないか。そう思いました。
けれどどうにも、たまちゃんは真剣なのです。
「あたしもね、嘘かと思ったの。嘘かと思ったんだけどね、おじさんが玉を持ってあたしの心臓のところにかざしたら、本当に移ったのよ」
思い出が。
はあ、と私は言いました。にわかには信じられませんが、たまちゃんがあんまり本気な様子なので、私の手のひらに乗ったままの玉をたまちゃんの前に出し、興味本位で「何の思い出を移したの」と聞いてみました。
「なんの思い出ってわけじゃないけど」
たまちゃんはじっと玉を見つめて答えました。
「今はね、ほらあんたとあたしで去年の夏にさ、川に遊びに行ったでしょ。あのときの様子が映ってる。綺麗だよ」
私には相変わらずただの透明な玉にしか見えませんでした。
たまちゃんが『思い出玉』を私に見せた次の日から、クラスの中で『思い出玉』を持つ子が少しずつ増え始めました。玉を持っている子たちは、みんな嬉しそうに玉の中の思い出を見せてくれるのですが、やっぱり私には、ただの透明の玉にしか見えません。私以外の『思い出玉』を持っていない子たちも同じようでした。『思い出玉』を持っている子じゃないと、玉の中の思い出は見ることができないのです。玉を持っている子同士で休み時間に集まって、思い出の見せ合いっこをしていることもありました。
先生たちはね、学業には関係のないことですし、あんまり騒ぐと怒られてましたけど、おもちゃって言うほどのものでもないし、持ってくるなとまでは言いませんでした。まあもともと、学校の前の物売りを放っておくくらいですからね。
「ねー、たまちゃんの『思い出玉』さあ。あたしらの玉より大きいよね?」
休み時間、教室でたまちゃんと話していると、クラスメートの女の子が話しかけてきました。女の子の近くにいた子たちが、「えっ、そうなの?」「見たい見たい」「比べてみようよ」と寄ってきます。たまちゃんは笑顔で「いいよ」とポケットから玉を取り出しました。
一見、大きさは前に見せてもらったときと変わらないように見えました。けれど、他の子たちが持っている玉と比べると、確かにたまちゃんの『思い出玉』の方が少し大きいのです。
「ほんとだ、違うね」
「いいなあ。こっちの方が、思い出が良く見えるね」
「大きいのに移し変えてもらったの?」
口々に言う子どもたちに囲まれて、たまちゃんはにんまりと笑いました。
「ううん、違うよ。あたしもこの間気づいたんだけどね、実はね。『思い出、移れ~』って思いながらさ、こうやってぎゅっ……って握ると、大きくなるの」
そう言ってたまちゃんは、自分の玉を力いっぱい握りました。
私は『思い出玉』なんて端から信じていませんからね。単にそんな気がするだけだろう、もともとたまちゃんの『思い出玉』が大きかっただけだろう、と思ってそれを見ていました。
一〇秒くらいして、たまちゃんが手を開きました。
びっくりしましたよ。
本当に大きくなっているんです。見間違いで済まされないくらいに。
私はぞっとしました。
それから、『思い出玉』を持つ子はどんどん増えました。私と一緒に「やだね、『思い出玉』なんて」と言っていた子までもが、いつの間にか『思い出玉』を手に、うっとりそれを眺めているのです。
『思い出玉』を持つ子供が増えたきっかけは、やっぱりたまちゃんでした。たまちゃんが『思い出玉』を大きくしたのを見て、生き物みたいで面白いと評判になったのです。評判はクラスの外にも広がりつつありました。その昔、アメリカではなんでもない石をペットにするのが流行ったくらいですからね。大きくなる綺麗な玉なんて、そりゃ人気になって当然だったのかもしれません。
「思い出はね、いつか忘れちゃうでしょ。でも『思い出玉』に移しておけば、ずっと綺麗なまま閉じ込めておけるの」
たまちゃんはそう言いました。
私はたとえクラスで持っていないのが私一人になっても、絶対に買わないぞ、と思っていました。それだけでなく、たまちゃんにも捨ててほしいと思っていました。
だって、ただの玉が大きくなるなんてありえないでしょう。気味が悪いですよ。
あの玉は生きてるんだ。最初にたまちゃんに持たされたとき、じっとりして温かかったのも、生きているからなんだ。みんなの思い出を食べて大きくなっているんだ……。
私はたまちゃんに、玉を捨てるようお願いしました。
でもたまちゃんはうんとは言いませんでした。
なにせ、彼女は『思い出玉』ブームの火付け役ですし、それでクラスの人気者になっていましたから。玉を捨てると、そういうものも一緒に捨てることになります。それが嫌だったんじゃないかと、今になって思います。私の心配事が的中するように、たまちゃんの様子は段々とおかしくなっていきました。
それは、ある日の学校帰りのことでした。土手を歩きながら、私はたまちゃんに話しかけます。
「たまちゃん、もうすぐ夏休みだけどさあ」
「んー」
「去年の夏は、川に行ったけどさ」
「んー」
夏休み前には、学校の『思い出玉』ブームも落ち着いてきていて、他のみんなはもう玉のことなんて忘れかけていました。けれど、たまちゃんは、たまちゃんだけは肌身離さず玉を持ち歩き、いつの間にか四六時中『思い出玉』を眺めているようになりました。話しかけても生返事ばかりで、こっちを見ようともしません。
玉は子どもの片手いっぱいの大きさになり、到底ポケットには入らないので、たまちゃんはいつも両手で大事そうに抱えていました。何も知らない人には綺麗な水晶玉に見えたかもしれませんが、私にはでっぷりと肥え太った得体の知れない化物に見えました。
「今度はね、川じゃなくて海行こうよ」
「んー……」
たまちゃんは、うっとりと『思い出玉』の中を見つめています。何が映っているのだろうか? 去年の川遊びの様子? 私は段々腹が立ってきました。
「……いい加減にしてよっ」
私は『思い出玉』を持つたまちゃんの腕を引っ掴みました。
「そんな気持ち悪いもの見てないで、こっちを見なさいよ!」
「きゃあっ」
私はたまちゃんの腕を掴み、身体を引き寄せて、たまちゃんから『思い出玉』を奪おうと手を伸ばしました。
「ねえっ、それよこして!」
私はたまちゃんから『思い出玉』を引き剥がそうとしました。たまちゃんは掴まれていない方の腕を振って嫌がります。
「やだ、いやだっ」
たまちゃんは必死に『思い出玉』を守りながら、私の足を強く蹴りました。バランスを崩した私は地面に転げ、私が掴んでいたたまちゃんもつられて転げました。
「やめてっ、いやだっ」
「よこしなさいってばっ!」
泥と汗と涙でぐちゃぐちゃになりながら、私は玉を奪おうと、たまちゃんは玉を守ろうと、動物の喧嘩みたいに暴れ回り、もつれるように土手の斜面を転がり落ちました。草の青臭い匂いがしました。
「何が嫌なのよ、何が嫌なのよ! そんなかに入れちゃった思い出の何が大事なのよ、今目の前にいる私よりも、そんなガラクタの、どこがいいっていうの! ええっ! 言ってみなさいよ!」
私はたまちゃんの胸倉を掴んで馬乗りになり、たまちゃんの身体を草地に押し付けて、叫びました。
たまちゃんは嫌だ嫌だと声を上げて泣くだけで、私の言ったことには答えません。それがなおのこと腹立たしく、私はお腹の辺りに、ドロドロぐつぐつ、溶岩みたいなものが湧き起こるような気がしました。
私はたまちゃんの頬をぶって、ひるんだ彼女の手から『思い出玉』を奪い取りました。玉はやはりぬるく湿っており、とくとくと脈打っているような気さえしました。
私は、よろめきながら立ち上がりました。
「返してえ、返してよお」
たまちゃんはわんわん泣いて、返して返してと私の足にすがります。私はそれを見るとむかむかして、もう我慢なりませんでした。
「こんなものっ!」
私は思いっきり腕を振り上げて、河川敷の、草のないところを狙って玉を叩きつけました。
玉は重く硬い音を立てて壊れ、その欠片が辺りに飛び散りました。すると、玉の残骸からいくつもの、うっとりするほど綺麗な、白く輝く塊が出てきました。塊は欠片から離れ、一つになりながら天に昇っていきます。
私はなんだか、それを逃してはいけないような気がして、目いっぱい手を伸ばして捕まえようとしました。しかし塊は指をすり抜けていってしまいます。私はすっかり頭が冷えて、泣きそうになって、たまちゃんの方を振り返りました。
たまちゃんはぽかんと口を開け、よだれを垂らして天に昇るそれを見つめていました。
「……皆さん怖いものがお好きでここに集まっているんでしょう」
女は静かに言った。
「見たいと思いませんか。『思い出玉』を」
ごくり、と誰かが息を呑む。
「これが『思い出玉』でございます」
いつの間にか女の手には、大きな透明の玉があった。女は蝋燭の前に玉をかざした。薄暗い会場内の、舞台の中心で、玉は光を受けてきらきらと煌めいている。
「勿論、信じるかどうかは皆さま次第。私の話はこれで終わりにございます」
女は薄く笑みを浮かべ、ふっ、と一息で蝋燭を吹き消した。
がちゃん。
重く硬い音が、小さな会場中に響いた。
思い出玉
作・藤澤 さくら(2023年度・3年生)
「それでは始めさせていただきます」
小さな舞台だった。その中心、ぽつんと置かれた座布団の上に、女が座して、ゆっくりと頭を下げた。かたわらで燃える一本の蝋燭が、女の姿と、板張りの床を照らしていた。
これは私が子どもの頃のお話です。当時一番仲の良かった――そうですね、たまちゃんと呼びましょうか。たまちゃんといつものように学校から帰っていると、
「あ、そうだ。手ぇ出して。手のひら上に向けて」
突然こんなことを言われました。私は少し不思議に思いながら、言う通りに手を出しました。するとたまちゃんはスカートのポケットから何かを取り出して、私の手のひらに乗せました。
それは、薄く青みがかった透明の玉でした。見た目はビー玉に似ていました。大きさもちょうどそのくらいです。ですが触り心地は少し柔らかくて、スーパーボールのようでした。
玉はポケットの中でたまちゃんの体温が移ったのかほんのり温かく、湿っていました。それがなんだか生きているみたいで気持ちが悪くて、私はすぐたまちゃんに突き返しました。「ありがと、返すね」
「見た? 見えた?」
たまちゃんは透明の玉をポケットに仕舞いながら、ちょっと照れ臭そうに言ってきました。
「なにが?」
「玉の中にさ、見えたでしょ」
「なんのこと?」
「見えなかった? あたしとあんたがさ」
私には、たまちゃんの話していることがちっとも分かりませんでした。困惑する私の手に、たまちゃんは「じゃあもっかい見てよ」とまた透明の玉を乗せました。
何か特殊な細工がされているのかしら。私は思って、上から覗き込んだり、光にかざしたりしてみるのですけども、玉はただ辺りの景色を透かすばかりです。たまちゃんはうっとりして、まるで遠くのものを見るみたいに玉を見つめています。
「綺麗だよねえ。ほら今、あたしが走ってるよ」
確かに綺麗ですが、たまちゃんが言うようなものは見えません。
「ええ? 何にも見えないよ。ねえこれ何? ビー玉じゃないでしょう、スーパーボールとも違うでしょう。どこで拾ったの」
そう尋ねると、たまちゃんは顔を上げ、
「拾ったんじゃないよ。これ、思い出玉」
と言いました。
「思い出玉」
私は、たまちゃんの言ったことを繰り返しました。それから思い出しました。
今はめっきり見かけませんが、昔は小学校の前にね、何でしょうね露天商といいますか、ひよこやらおもちゃやら飴細工やらを売りに来る人がいたんですよ。若い人には信じられないでしょう。いろいろと大らかな時代だったんですね。
それで、そんな中に混じって、ときどき透明な玉を売りに来るおじさんがいたんです。「思い出玉、一個一〇〇円だよ。大事な思い出を綺麗な玉の中に入れたげるよ」……そうやって、校門から出てきた子どもに声をかけるんです。いかにも怪しげでしょう。ひよこやお菓子なら心惹かれますけども、『思い出玉』なんて聞いたことがありません。適当なことを言ってビー玉を売りつけようとしてるんだ、って誰も相手にしていませんでした。
「え、あれ買ったの!」
駄菓子屋のお菓子が一個一〇円でしょう。一〇〇円もあれば、両手じゃ足りないくらいのお菓子が買えます。私からすれば「あーあ、たまちゃん、馬鹿なことしたなあ」と。自分がだまされて買ったのが口惜しくて、今度は私を「何か見える」って言ってだまして買わそうとしてるんじゃないか。そう思いました。
けれどどうにも、たまちゃんは真剣なのです。
「あたしもね、嘘かと思ったの。嘘かと思ったんだけどね、おじさんが玉を持ってあたしの心臓のところにかざしたら、本当に移ったのよ」
思い出が。
はあ、と私は言いました。にわかには信じられませんが、たまちゃんがあんまり本気な様子なので、私の手のひらに乗ったままの玉をたまちゃんの前に出し、興味本位で「何の思い出を移したの」と聞いてみました。
「なんの思い出ってわけじゃないけど」
たまちゃんはじっと玉を見つめて答えました。
「今はね、ほらあんたとあたしで去年の夏にさ、川に遊びに行ったでしょ。あのときの様子が映ってる。綺麗だよ」
私には相変わらずただの透明な玉にしか見えませんでした。
たまちゃんが『思い出玉』を私に見せた次の日から、クラスの中で『思い出玉』を持つ子が少しずつ増え始めました。玉を持っている子たちは、みんな嬉しそうに玉の中の思い出を見せてくれるのですが、やっぱり私には、ただの透明の玉にしか見えません。私以外の『思い出玉』を持っていない子たちも同じようでした。『思い出玉』を持っている子じゃないと、玉の中の思い出は見ることができないのです。玉を持っている子同士で休み時間に集まって、思い出の見せ合いっこをしていることもありました。
先生たちはね、学業には関係のないことですし、あんまり騒ぐと怒られてましたけど、おもちゃって言うほどのものでもないし、持ってくるなとまでは言いませんでした。まあもともと、学校の前の物売りを放っておくくらいですからね。
「ねー、たまちゃんの『思い出玉』さあ。あたしらの玉より大きいよね?」
休み時間、教室でたまちゃんと話していると、クラスメートの女の子が話しかけてきました。女の子の近くにいた子たちが、「えっ、そうなの?」「見たい見たい」「比べてみようよ」と寄ってきます。たまちゃんは笑顔で「いいよ」とポケットから玉を取り出しました。
一見、大きさは前に見せてもらったときと変わらないように見えました。けれど、他の子たちが持っている玉と比べると、確かにたまちゃんの『思い出玉』の方が少し大きいのです。
「ほんとだ、違うね」
「いいなあ。こっちの方が、思い出が良く見えるね」
「大きいのに移し変えてもらったの?」
口々に言う子どもたちに囲まれて、たまちゃんはにんまりと笑いました。
「ううん、違うよ。あたしもこの間気づいたんだけどね、実はね。『思い出、移れ~』って思いながらさ、こうやってぎゅっ……って握ると、大きくなるの」
そう言ってたまちゃんは、自分の玉を力いっぱい握りました。
私は『思い出玉』なんて端から信じていませんからね。単にそんな気がするだけだろう、もともとたまちゃんの『思い出玉』が大きかっただけだろう、と思ってそれを見ていました。
一〇秒くらいして、たまちゃんが手を開きました。
びっくりしましたよ。
本当に大きくなっているんです。見間違いで済まされないくらいに。
私はぞっとしました。
それから、『思い出玉』を持つ子はどんどん増えました。私と一緒に「やだね、『思い出玉』なんて」と言っていた子までもが、いつの間にか『思い出玉』を手に、うっとりそれを眺めているのです。
『思い出玉』を持つ子供が増えたきっかけは、やっぱりたまちゃんでした。たまちゃんが『思い出玉』を大きくしたのを見て、生き物みたいで面白いと評判になったのです。評判はクラスの外にも広がりつつありました。その昔、アメリカではなんでもない石をペットにするのが流行ったくらいですからね。大きくなる綺麗な玉なんて、そりゃ人気になって当然だったのかもしれません。
「思い出はね、いつか忘れちゃうでしょ。でも『思い出玉』に移しておけば、ずっと綺麗なまま閉じ込めておけるの」
たまちゃんはそう言いました。
私はたとえクラスで持っていないのが私一人になっても、絶対に買わないぞ、と思っていました。それだけでなく、たまちゃんにも捨ててほしいと思っていました。
だって、ただの玉が大きくなるなんてありえないでしょう。気味が悪いですよ。
あの玉は生きてるんだ。最初にたまちゃんに持たされたとき、じっとりして温かかったのも、生きているからなんだ。みんなの思い出を食べて大きくなっているんだ……。
私はたまちゃんに、玉を捨てるようお願いしました。
でもたまちゃんはうんとは言いませんでした。
なにせ、彼女は『思い出玉』ブームの火付け役ですし、それでクラスの人気者になっていましたから。玉を捨てると、そういうものも一緒に捨てることになります。それが嫌だったんじゃないかと、今になって思います。私の心配事が的中するように、たまちゃんの様子は段々とおかしくなっていきました。
それは、ある日の学校帰りのことでした。土手を歩きながら、私はたまちゃんに話しかけます。
「たまちゃん、もうすぐ夏休みだけどさあ」
「んー」
「去年の夏は、川に行ったけどさ」
「んー」
夏休み前には、学校の『思い出玉』ブームも落ち着いてきていて、他のみんなはもう玉のことなんて忘れかけていました。けれど、たまちゃんは、たまちゃんだけは肌身離さず玉を持ち歩き、いつの間にか四六時中『思い出玉』を眺めているようになりました。話しかけても生返事ばかりで、こっちを見ようともしません。
玉は子どもの片手いっぱいの大きさになり、到底ポケットには入らないので、たまちゃんはいつも両手で大事そうに抱えていました。何も知らない人には綺麗な水晶玉に見えたかもしれませんが、私にはでっぷりと肥え太った得体の知れない化物に見えました。
「今度はね、川じゃなくて海行こうよ」
「んー……」
たまちゃんは、うっとりと『思い出玉』の中を見つめています。何が映っているのだろうか? 去年の川遊びの様子? 私は段々腹が立ってきました。
「……いい加減にしてよっ」
私は『思い出玉』を持つたまちゃんの腕を引っ掴みました。
「そんな気持ち悪いもの見てないで、こっちを見なさいよ!」
「きゃあっ」
私はたまちゃんの腕を掴み、身体を引き寄せて、たまちゃんから『思い出玉』を奪おうと手を伸ばしました。
「ねえっ、それよこして!」
私はたまちゃんから『思い出玉』を引き剥がそうとしました。たまちゃんは掴まれていない方の腕を振って嫌がります。
「やだ、いやだっ」
たまちゃんは必死に『思い出玉』を守りながら、私の足を強く蹴りました。バランスを崩した私は地面に転げ、私が掴んでいたたまちゃんもつられて転げました。
「やめてっ、いやだっ」
「よこしなさいってばっ!」
泥と汗と涙でぐちゃぐちゃになりながら、私は玉を奪おうと、たまちゃんは玉を守ろうと、動物の喧嘩みたいに暴れ回り、もつれるように土手の斜面を転がり落ちました。草の青臭い匂いがしました。
「何が嫌なのよ、何が嫌なのよ! そんなかに入れちゃった思い出の何が大事なのよ、今目の前にいる私よりも、そんなガラクタの、どこがいいっていうの! ええっ! 言ってみなさいよ!」
私はたまちゃんの胸倉を掴んで馬乗りになり、たまちゃんの身体を草地に押し付けて、叫びました。
たまちゃんは嫌だ嫌だと声を上げて泣くだけで、私の言ったことには答えません。それがなおのこと腹立たしく、私はお腹の辺りに、ドロドロぐつぐつ、溶岩みたいなものが湧き起こるような気がしました。
私はたまちゃんの頬をぶって、ひるんだ彼女の手から『思い出玉』を奪い取りました。玉はやはりぬるく湿っており、とくとくと脈打っているような気さえしました。
私は、よろめきながら立ち上がりました。
「返してえ、返してよお」
たまちゃんはわんわん泣いて、返して返してと私の足にすがります。私はそれを見るとむかむかして、もう我慢なりませんでした。
「こんなものっ!」
私は思いっきり腕を振り上げて、河川敷の、草のないところを狙って玉を叩きつけました。
玉は重く硬い音を立てて壊れ、その欠片が辺りに飛び散りました。すると、玉の残骸からいくつもの、うっとりするほど綺麗な、白く輝く塊が出てきました。塊は欠片から離れ、一つになりながら天に昇っていきます。
私はなんだか、それを逃してはいけないような気がして、目いっぱい手を伸ばして捕まえようとしました。しかし塊は指をすり抜けていってしまいます。私はすっかり頭が冷えて、泣きそうになって、たまちゃんの方を振り返りました。
たまちゃんはぽかんと口を開け、よだれを垂らして天に昇るそれを見つめていました。
「……皆さん怖いものがお好きでここに集まっているんでしょう」
女は静かに言った。
「見たいと思いませんか。『思い出玉』を」
ごくり、と誰かが息を呑む。
「これが『思い出玉』でございます」
いつの間にか女の手には、大きな透明の玉があった。女は蝋燭の前に玉をかざした。薄暗い会場内の、舞台の中心で、玉は光を受けてきらきらと煌めいている。
「勿論、信じるかどうかは皆さま次第。私の話はこれで終わりにございます」
女は薄く笑みを浮かべ、ふっ、と一息で蝋燭を吹き消した。
がちゃん。
重く硬い音が、小さな会場中に響いた。