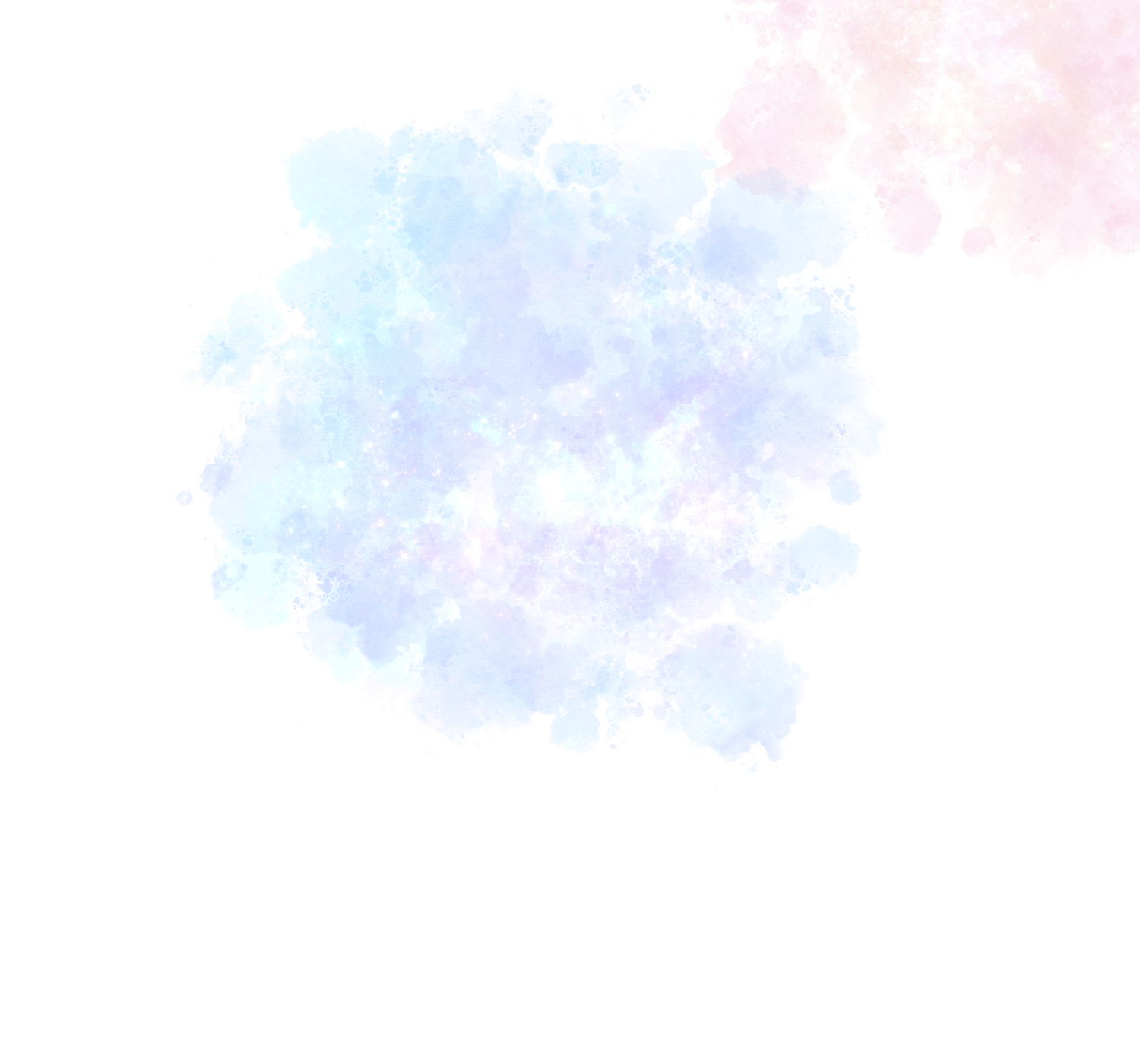長原 しのぶ(ながはら しのぶ)
近現代文学担当
太宰治や遠藤周作を含めた近代と現代の作家を対象にしたキリスト教と
文学、戦争と文学、漫画・映画・アニメと文学などを研究テーマとする。
小説を読むとき、少し違う角度から切り込んでみるのも面白いものです。〈王道〉ではなく〈横道〉から。回り道かもしれませんが、見えなかったことが見えてくる場合もあります。例えば太宰治の「水仙」(『改造』1942・5)注1です。
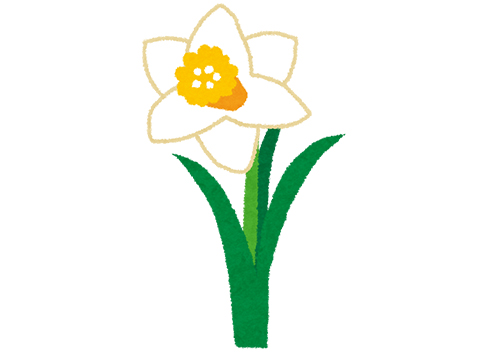
太宰治の小説「水仙」の最初と最後には、菊池寛の小説「忠直卿行状記」(『中央公論』1918・9)が登場し、「水仙」の主要人物である草田静子と小説家の僕が、「忠直卿行状記」の忠直卿とその家来に重ねられています。そのため、「忠直卿行状記」を介した読み方は〈王道〉の一つです。また、「水仙」には僕から読者に向けての挑戦的な謎が提示されています。唯一残された草田静子の描いた絵を僕が引き裂いてしまう場面です。「バケツに投げ入れられた二十本程の水仙の絵」を僕は「つまらない絵」だと言って「ビリビリと引き裂き」ます。その後、次のように語ります。
僕はその絵を、さらにこまかに引き裂いて、ストーヴにくべた。僕には、絵がわかるつもりだ。草田氏にさへ、教へる事が出来るくらゐに、わかるつもりだ。水仙の絵は、断じて、つまらない絵ではなかつた。見事だつた。なぜそれを僕が引き裂いたのか。それは読者の推量にまかせる。
「つまらない」どころか実は「見事」だと評価を一変させること、しかもその絵を完全に消滅させること、謎です。「まかせ」られたからには解き明かしたくなります。作品研究においても、「静子の絵を一つ残らず葬ることで静子を〈芸術家〉〈天才〉として確定した」注2や「「僕」は絵を引き裂くことで、草田静子の絵が「この世」に評価されることを拒絶した」注3など、多くの考察がなされています。このように、敢えて語らない僕の行為の理由と意味、さらには題名にも繋がる「水仙」の象徴性などを考えるのも〈王道〉でしょう。もちろん〈王道〉は作品全体を読み解く重要な視点となります。
さて、ここで〈横道〉から入ってみます。私が「水仙」の中で注目する場面は、僕が「眉間をざくりと割られる程の大恥辱」と記憶する草田家での食事シーンです。流行作家として名の知れ始めた僕は内心「いい気」になり、上流家庭である草田家のお正月の招待を受けます。そこで出された蜆汁を僕はおいしくいただきます。
せつせと貝の肉を箸でほじくり出して食べてゐたら、
「あら、」夫人は小さい驚きの声を挙げた。「そんなもの食べて、なんともありません?」無心の質問である。
思はず箸とおわんを取り落しさうだつた。この貝は、食べるものではなかつたのだ。蜆汁は、ただその汁だけを飲むものらしい。貝は、ダシだ。貧しい者にとつては、この貝の肉だつてなかなかおいしいものだが、上流の人たちは、この肉を、たいへん汚いものとして捨てるのだ。なるほど、蜆の肉は、お臍みたいで醜悪だ。
ここでの僕と草田静子のやり取りは、「冷酷な「夫人」像を形象化するために「僕」の狼狽ぶりを対比的に強調」し、「「僕」は自らの隠しきれぬ卑しさを見抜かれてしまう」注4というように、上流階級にある草田静子と「極貧に近いその日暮し」の僕の対立構造を鮮明にします。その結果、僕の中の「ひがみ根性」と敵意は増幅し、絵を見て欲しいという草田静子の願いを拒絶するのです。
もう一歩踏み込んでみましょう。食事が人物造形に結びつくパターンは他の太宰作品にも確認できます。「水仙」と同じく上流家庭を描く「斜陽」(『新潮』1947・7~10)のかず子は、最後の貴族と評する母のスープの飲み方を自分には真似のできない独特なものと述べ、母の高貴さを強調します。また、「男女同権」(『改造』1946・12)注5の老詩人である「私」は、講演中に次のような女性とのやり取りを語り、虐げられてきた男性の権利回復を主張します。
(・・・)いもの天ぷらを頬張つたら、私の女が、お前、百姓の子だね、と冷く言ひます。ぎよつとして、あわてて精進揚げを呑みくだし、うむ、と首肯くと、その女は、連れの職工のおいらんのはうを向いて小声で、育ちの悪い男は、ものを食べさせてみるとよくわかるんだよ、ちよつちよつと舌打ちをしながら食べるんだよ、と全くなんの表情も無く、お天気の事でも言つてゐるみたいに澄まして言ふのでございます。
「いもの天ぷら」の食べ方を「女」に指摘されることで、「私」は卑屈さと女性への憎悪を深く抱え込みます。「冷く」「表情も無く」「澄まして」いる上から目線の「女」の残忍さが余計に「私」の自尊心を傷つけるのです。しかし、ここで注意すべきは、「女」のあまりにもひどいと思われる態度は全て「私」による解釈である点です。問題は「女」にあるのではなく、そのように見る「私」側にあるといえます。そうすると、「私」の傷は自傷行為と言えるかもしれません。
「男女同権」と同じく、「水仙」も僕によって語られる物語です。「斜陽」の例のように上流階級ならではの食事作法があるとすれば、草田静子には蜆汁の「貝の肉」を食べる習慣はなかったのでしょう。僕に対して「驚きの声」を発したのは、(大袈裟に言えば)食文化の違いからだといえます。それを「上流の人たちは、この肉を、たいへん汚いものとして捨てるのだ。なるほど、蜆の肉は、お臍みたいで醜悪だ。」と、言われてもいない言葉を連ねて過剰に解釈し、「大恥辱」だと傷つく僕。その傷は実は自分で作ったものなのです。僕の内面には卑屈や「ひがみ」では片づけられない、「ひとに侮辱をされはせぬかと、散りかけてゐる枯葉のやうに絶えずぷるぷる命を賭けて緊張してゐる」と分析する深い闇が見え隠れします。そして、僕が「緊張」の先に見据える「ひと」には、草田静子を代表とする他者だけではなく、自分自身の姿も含むと考えられるのです。
敵は草田静子ではなく自分自身。このような僕のあり方に着目して「水仙」全体を読み直してみると、〈王道〉からたどり着く結末にも別の色合いが見出せるかもしれません。小説の面白さが広がります。
最後に、蜆汁の「貝の肉」を食べるか食べないかと問われれば、私は食べる派です。そして、誰かから「え? 食べるの?」と言われても「食べます」とおいしくいただきます。

注
1.「水仙」の本文引用は全て『太宰治全集6』(1998・9 筑摩書房)に拠る。旧漢字は新漢字に改めた。
2.滝口明祥「読者からの手紙/作者からの手紙―太宰治『水仙』を中心に―」(『学習院大学国語国文会誌』第五十号 2007・3)
3.勝田真由子「国策と文学者―太宰治「水仙」試論―」(『国文論叢』第四十二号 神戸大学文学部国語国文学会 2010・3)
4.舘下徹志「太宰治『水仙』論―〈徳〉の不在証明―」(『釧路工業高等専門学校「紀要」』第43号 2009・12)
5.『太宰治全集9』(1998・12 筑摩書房)に拠る。旧漢字は新漢字に改めた。
・長原しのぶ教授(教員紹介)
・日本語日本文学科
・日本語日本文学科(ブログ)
・日文エッセイ