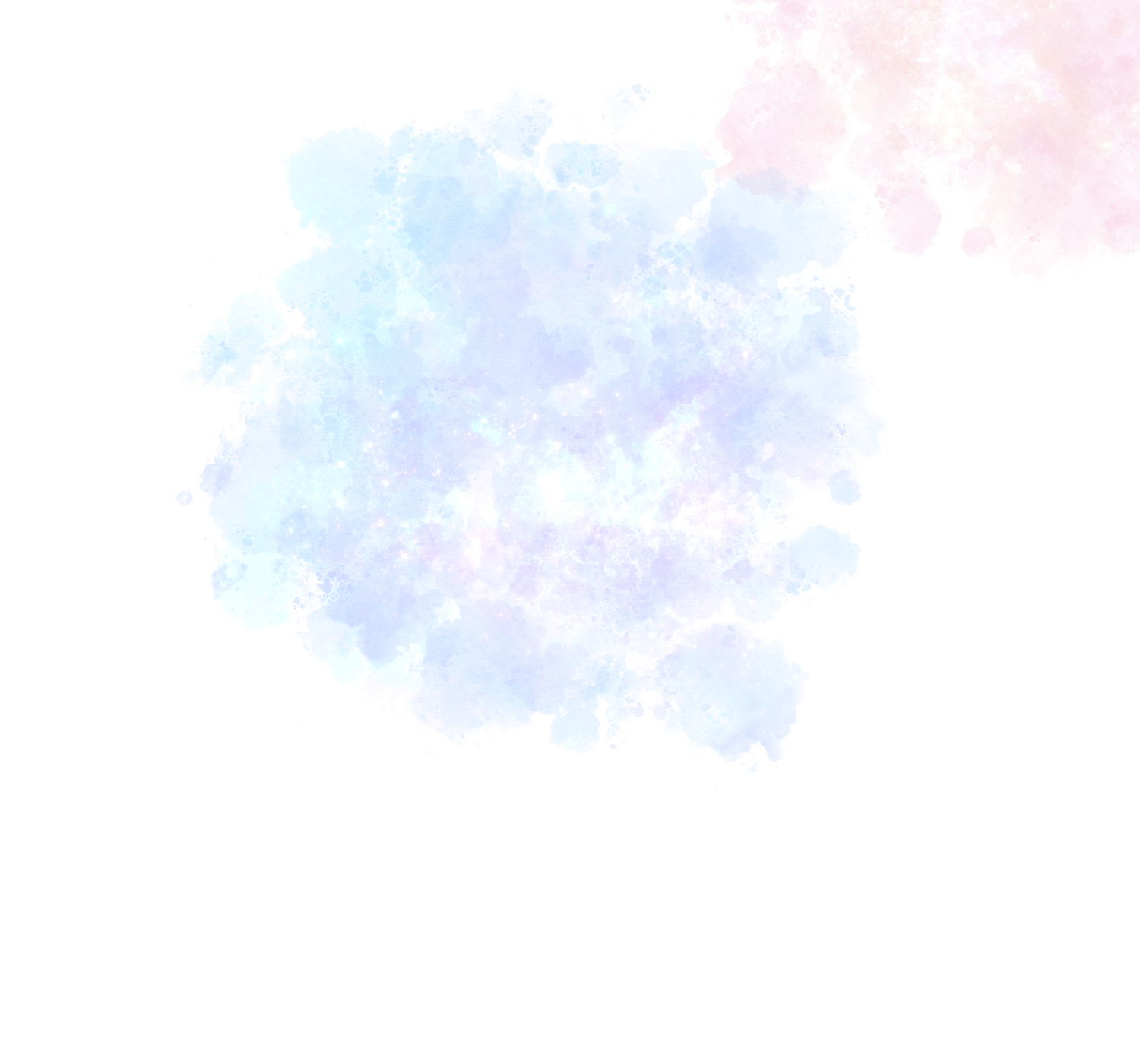【著者紹介】
東城 敏毅(とうじょう としき)
古典文学(上代)担当
奈良時代の文学、『万葉集』『古事記』について研究をすすめています。
古典文学(上代)担当
奈良時代の文学、『万葉集』『古事記』について研究をすすめています。
天平時代のパンデミック―『万葉集』の遣新羅歌群―
1.新型コロナウイルス感染症との戦いの中で
私たちは、新型コロナウイルス感染症が世界中にはびこり、日本においても緊急事態宣言が三度も発令され、外出の自粛が求められるという、予想だにしなかった事態を経験した。現代というこの時代に、このような事態を経験するとは誰もが想像していなかったことだと思われるし、また未知の感染症の怖さを身に染みて実感しているところである。本エッセイでは、新型コロナウイルスとの戦いが一年を過ぎたこの時だからこそ、万葉びとと感染症との戦いと、その渦中の万葉歌に焦点をあてて、奈良時代のパンデミックについて考えてみたい。
2.天平時代における天然痘の大流行
天平9(737年)年、藤原四兄弟があいついで亡くなるという事件が起こる。4月には藤原房前(ふささき)が57歳で、7月には武智麻呂(むちまろ)が58歳、麻呂が47歳で、8月には宇合(うまかい)が44歳で亡くなったのである。この四兄弟の他に、多くの高官がなくなり、新元号「令和」のもととなった「梅花の宴」(天平2年)にも参加していた太宰府の小野朝臣老(おゆ)や、天智天皇の皇女でもある水主親王(みぬしのひめみこ)も世を去っているのである。
奈良時代に大きな権力を手にし、その政治の中枢にあった四兄弟らが命を落としたことは、「長屋王の祟りである」等の、様々なデマが流れるもとともなるが、実はこの天平9年には、天然痘の大流行があったのである。いわゆる天平時代のパンデミックであった。『続日本紀』は以下のように記す。
①この年の春、疫瘡(えきさう)大いに起こる。初め筑紫(つくし)より来たりて夏を経て秋にわたる。公卿(くぎゃう)以下、天下の百姓、あひ継ぎて没死(し)すること、あげて計(かぞ)ふべからず。近き代よりこの方、これ有らず。 (天平9年12月27日条)
②遣新羅使(けんしらぎし)大判官(だいはんぐわん)従六位上、壬生使主宇太麻呂(みぶのおみうだまろ)、少判官(せうはんぐわん)正七位上、大蔵忌寸麻呂(おほくらいみきまろ)ら京に入る。大使従五位下、阿部朝臣継麻呂(あへのあそんつぎまろ)、津嶋に泊りて卒(しゅつ)しぬ。副使従六位下、大伴宿弥三中、病に染みて京に入ること得ず。 (天平9年1月26日条)
③太宰の管内の諸国、疱瘡時行(はや)りて百姓多く死ぬ。詔(みことのり)して、幣(みてぐら)を部内の諸社に奉りて祈(の)み祷(いの)らしめたまふ。また、貧疫(ひんえき)の家を振恤(しんじゅつ)し、併せて湯薬を給ひて療(いや)さしむ。 (天平9年4月19日条)
①は、天平9年の1年間を回顧し、天然痘の蔓延した状況を概観する。その流行のきっかけが、②の「遣新羅遣」(けんしらぎし)という、新羅に派遣される使節団であったことが分かる。これは、天平8年に新羅に向かった使節であるが、帰国後、大使が対馬で亡くなり、その後副使も感染している。これが天平9年1月のことである。その後、③の4月には、諸外国との玄関口である大宰府において、天然痘の流行を見、多くの民衆が亡くなっていることが分かる。この病はどうやら国外からもたらされた可能性が考えられる。そして、それと同時に、貧しい人々に薬を施す等の政策を迅速に実施していることも見て取れるのである。
また、天平9年6月には、司法・行政・立法を司る国家最高機関である「太政官」(だいじょうかん)が、太政官符を発令し、東海・東山・北陸・山陰・南海の五街道の諸国司に、疫病の治療法と禁ずべき食物についての七か条を命令する。その指示は、「併発する症状は四種類あり、咳。或は嘔吐。或は吐血。或は鼻血である。このうち合併症よりも下痢の治療に最も急がねばならない」「粥、おもゆなどは、温冷にかかわらず食べさせなさい。ただし、鮮魚や肉や生野菜は食べさせないように」などと非常に具体的である(『類聚符宣抄』〔るいじゅうふせんしょう〕第三「疾疫」〔天平9年6月26日付〕)。
3.「遣新羅使歌」における痕跡
この天平8年の遣新羅使は、実は、『万葉集』巻15に145首の「遣新羅使歌」(3578番歌~3722番歌)を残した使節である。「遣新羅使歌」は、多分に物語的要素をも含みつつ、奈良時代の瀬戸内海航路を現代に伝える稀有な歌群である。例えば、航海のはじまりは以下のように詠まれる(下線部は地名)。
朝開き 漕ぎ出て来れば 武庫の浦の 潮干(しほひ)の潟に 鶴(たづ)が声すも (巻15・3695)
我妹子(わぎもこ)が 形見に見むを 印南都麻(いなみつま) 白波高み よそにかも見む (3696)
ぬばたまの 夜は明けぬらし 玉の浦に あさりする鶴 鳴き渡るなり (3698)
月読の 光りを清み 神島(かみしま)の 磯みの浦ゆ 船出す我れは (3699)
武庫の浦(摂津)→ 印南都麻(播磨) → 玉の浦(備中) → 神島(備後)と、現在の大阪から兵庫、岡山、広島へと沿岸沿いを船で旅する当時の使節団の航路が見出される。それと同時に、まさしくこの遣新羅使こそが、天然痘を日本にもたらした使節であることが、以下のような歌からも分かる。
壹岐嶋(いきのしま)に至りて、雪連宅満(ゆきのむらじやかまろ)のたちまちに鬼病に遇ひて死去(まか)りし時に作る歌一首
天皇(すめろき)の 遠の朝廷(みかど)と 韓国(からくに)に 渡る我が背は 家人の 斎ひ待たねか 正身(ただみ)かも 過(あやま)ちしけむ 秋去らば 帰りまさむと たらちねの 母に申して 時も過ぎ 月も経ぬれば 今日か来む 明日かも来むと 家人は 待ち恋ふらむに 遠の国 いまだも着かず 大和をも 遠く離(さか)りて 岩が根の 荒き島根に 宿りする君 (3688)
当該歌の「鬼病」という言葉は、当時の人々の、未知の病に対する恐怖を端的に示しているだろう。しかし、ここで重要なのは、「鬼病」と記されてはいるが、奈良時代においても、すぐに感染症対策がたてられ、感染症が広がる兆候があると都を封鎖、また太政官が、各国の国司に、その治療法を指示し、かつ貧の家庭に薬を届けるよう、迅速に指示していることである。当時の最先端の医学の知識に基づいて、未知の感染症に立ち向かっている奈良時代の人々の姿は、「長屋王の祟り」というデマが拡散することも含めて、まさしく令和の日本人の姿とも重なる。それとともに、奈良時代の行動力の速さは、現代への警鐘ともなるだろう。

遣新羅使の寄港地「玉の浦」(現在の岡山県倉敷市玉島)
(円通寺より撮影 撮影:東城敏毅)
(円通寺より撮影 撮影:東城敏毅)
・東城敏毅教授(教員紹介)
・日本語日本文学科(学科紹介)
・日本語日本文学科(ブログ)