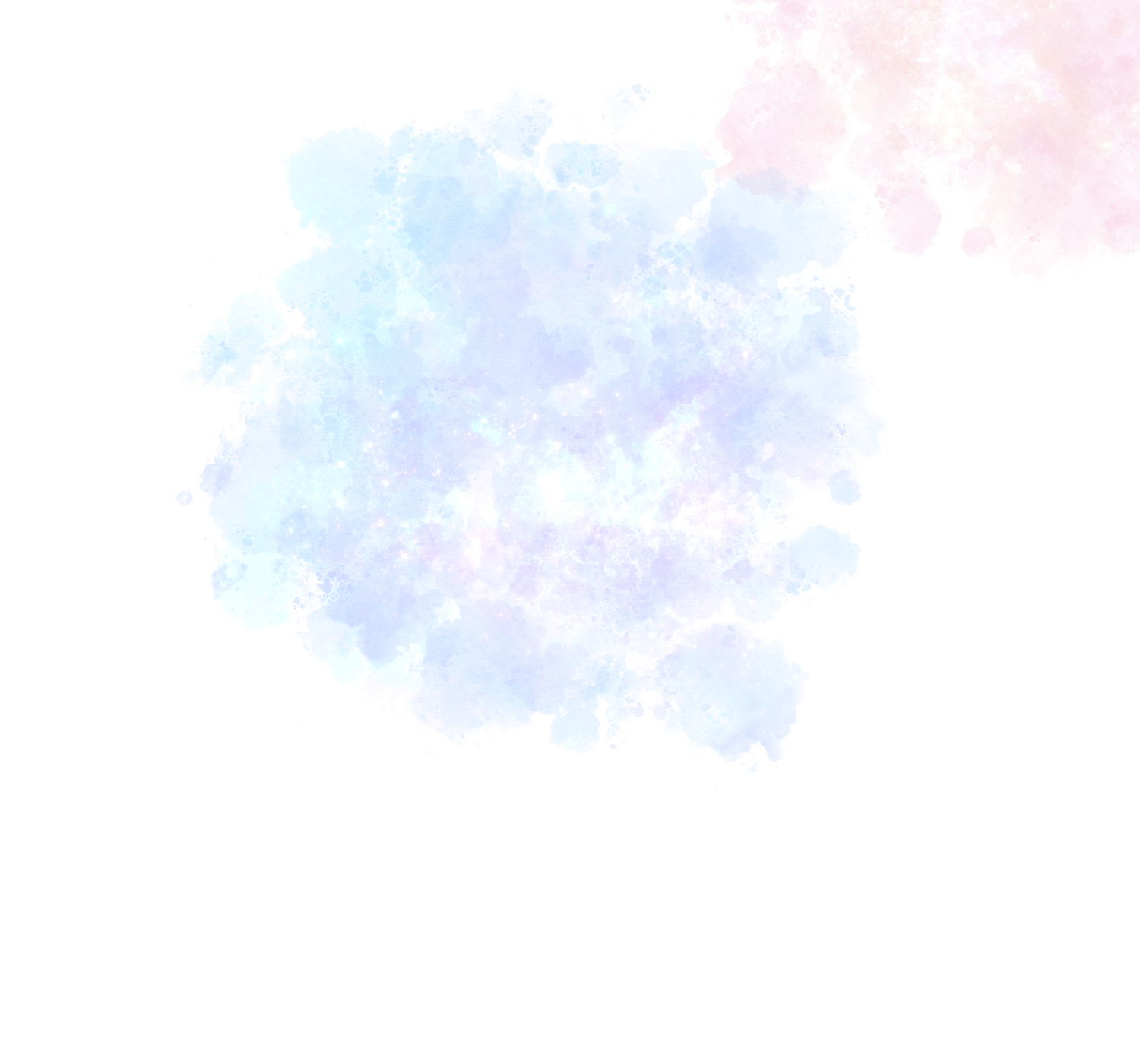本学科の授業科目「文学創作論」では、履修生が1年をかけて作り上げた作品をまとめて、文集を発行しています。
ここでは、第17集『トライアングル』に掲載の一作を、ご紹介します。
文集は、オープンキャンパスなどでご希望の方にお渡ししております。機会がありましたらぜひお手にとってみてください。
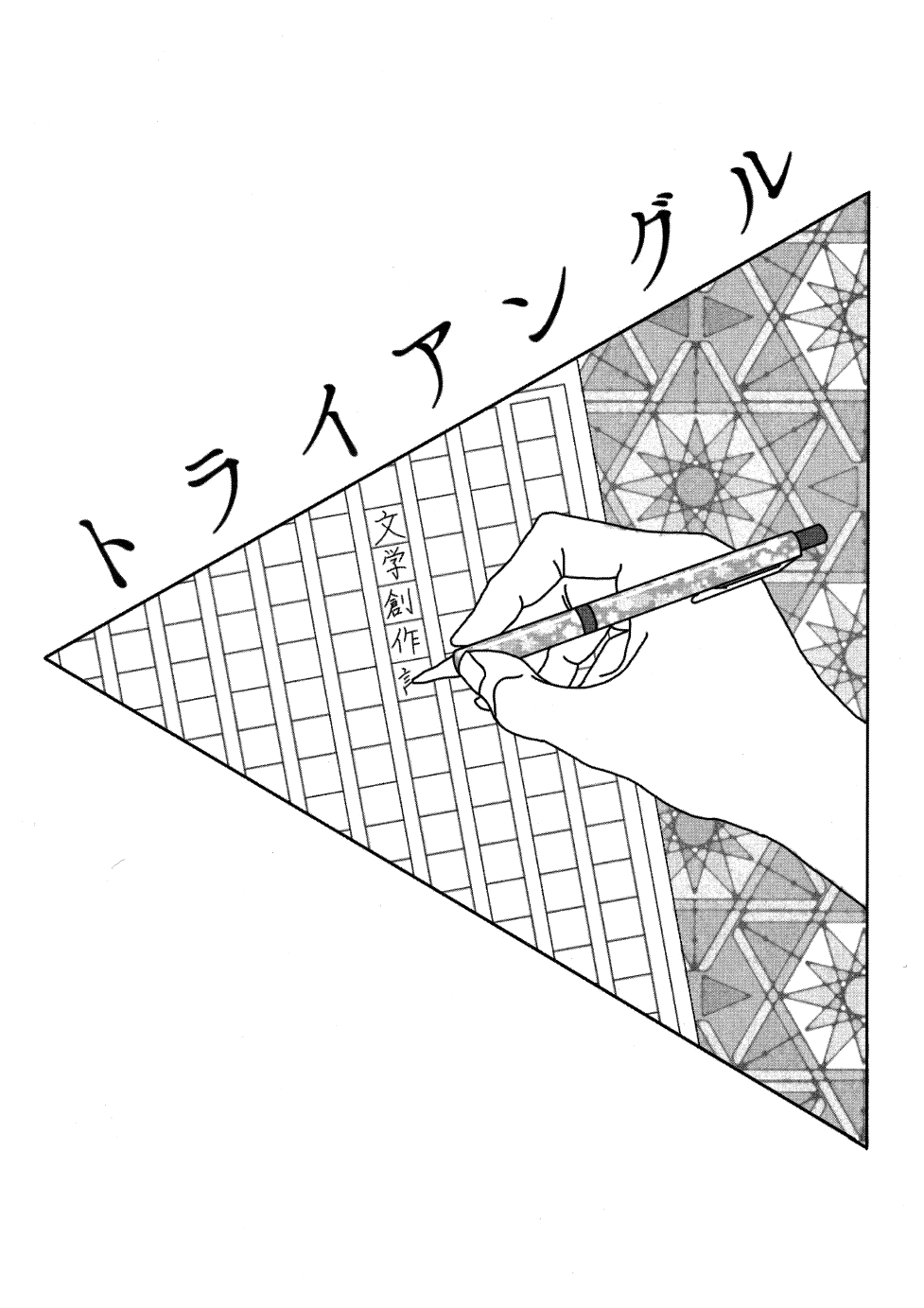 第17集文集『トライアングル』(2019年度)表紙
第17集文集『トライアングル』(2019年度)表紙
嘘のような夢の話
作・廣瀬 季里
表に出ると、紫色の道が目に入ってきた。昨日食べたヨーグルトに比べれば、まだ青臭さが足りないようだ。顔を上げると、青すぎる青空が頭上を覆っていた。じっと見上げていると目がちかちかと痛くなってきた。目を背けると、ついさっきまで紫色だった道路が灰色の芝生に成り代わっていた。向かいの家の玄関先に目をやり、芝生の境界線を確認する。ここまで綺麗に植えるのはさぞ大変な作業だったろう。名も無き庭師に敬意を示そう。
敬礼をしようと右腕を上げると、腕はボロボロと崩れ落ちた。腕の欠片が粉となって目に入った。痛い。最悪だ。多分これは夢なんだろうけど、仕方がない。芝生に落ちた「腕だったもの」を踏みつけ、靴底ですり潰すように足を動かす。
早く潰してしまわないと学校に遅刻してしまう。急がなければ。焦りに身を任せ、足元に落ちている薬指が粉になるまで踏み潰す。次に雨が降るのはいつだろうか。そんなことを考えながら人差し指に右足を乗せる。身体から離れた手がこんなにもろいだなんて知らなかった。今度クラスメイトにも教えてあげよう。右足に全体重をかけると、人差し指が落雁のように崩れた感触が伝わってきた。足を上げ、指が跡形も無くなったことを確認する。少し残しておいてもよかったかもしれない。惜しいことをした。
足を下ろし顔を上げると、私は学校の玄関に立っていた。天井には箱の形をした大きな水の塊が張り付いている。凍らないままその場に留まるそれは、静かに波打っていた。今日もまたあの中に飛び込もう。授業で疲れた頭をリフレッシュするにはもってこいだ。靴箱には上履きと、キャラメルの箱くらいの大きさの水の塊と、昨日捨てたはずのごみが入っている。また追いかけてきたのか。あと何度捨てに行かなければならないのだろうか。いい加減、鬱陶しい。他のクラスメイトの靴箱には日本製の槍が刺さって、黒い柄が垂直に飛び出している。どうやら皆は先に来ているらしい。引き戸を開けると、教室には先生やクラスメイトが待ち構えていた。
「なんであんな事をしたの」
「あれは何」
「どういうつもり」
「今日はちゃんと持ってきたの」
何を言っているんだろう。何を聞かれているのだろう。理解をしようとする前に先生やクラスメイトが自分を囲み、答えようのない質問をぶつける。何かいる物なんてあったかな。これは、私が悪いのだろうか。必死に思い出そうとするが、腕が崩れたあの瞬間の映像しか思い浮かばなかった。気がつくと、教室が赤くなっていた。対照的に、皆は真っ黒な影になっていく。
「ピニャータ」
誰かがそう呟いた。他のクラスメイトも続けて、
「ピニャータ」
「ピニャータ」
と唱え始めた。それは罵倒か、それとも私の名前なのか。分からない。ピニャータって何だっけ。唇を噛むのをやめ、疑問をクラスメイトにぶつける。
「ピ、ピニャータって何」
思いの外大きな声が発せられ、教室に響く。それでもクラスメイトの声は止まなかった。
「ピニャータ」
「ピニャータ」
「ピニャータ」
これは、私が悪いのだろうな。
「……タ、あんた、起きなさい」
母親の声が聞こえると、赤と黒が視界から消えた。
目の前には白い枕と、そして少し離れた場所に壁があった。壁にはブレザーとスカートが掛かっている。半年前に入学した高校の制服だ。
「ちょっと、実(まこと)」
私は、自分が王見実(おうみまこと)であること、そして目の前に広がる空間が自室であることを思い出した。一階にいる母に聞こえる程度の声を何とか絞り出して返事をする。こうして一日が始まる。これが最近のルーティン。
教室はざわついていたが、私に詰め寄る人はいなかった。
「おはよう。まことちゃん」
机に突っ伏していると、クラスメイトの茉莉が小さな声で話しかけてきた。返事をしようとしたが、あくびの混ざった唸り声を上げるので精一杯だった。
「その様子だと、また悪い夢を見たの?」
茉莉は心配そうな声でそっと訊ねた。
「そう。そうなんだよ。まただよ」
「もうこれで一週間連続で悪夢を見てることになるね」
「うん。今日なんて五限目に英語の小テストもあるのにさ。もう寝るのが嫌になってくるよ。こうなったら一生起きていようかな、なんて」
「ダメだよ、ちゃんと寝なくちゃ。そうだ、今日は良いもの持ってきたのよ」
「良いもの?」
「うん。まだ完成してないから、放課後には仕上げて渡すね」
その時チャイムが鳴り、誰かが「先生が来たぞー」と叫んだ。教室のあちこちで固まっておしゃべりをしていたクラスメイト達は各々の席に座った。茉莉も「じゃあ、またね」とだけ言い残し、自分の席に戻っていった。間もなく先生が教室に入り、朝の会が始まる。
「良いもの」。「未完成」。何だろう。また何かを作っているのだろうか。先生が進路について何か話している間、以前茉莉がくれた誕生日プレゼントを思い出す。
丁度おでんの餅巾着と同じくらいの大きさの布製の袋。ピンク色のリボンが結ばれたそれは、持ってみるとかしゃかしゃと音がした。それに顔に近づけてみると、微かに花の匂いがした。確か「サシェ」という名前だっけ。あれが茉莉の手作りだと知った時は本当に驚いた。
私はあの袋の匂いを鮮明に思い出した。その時先生の話も終わり、皆は一限目の授業の準備を始めている。とりあえず、茉莉が何を準備したのか、また放課後にでも聞こう。
放課後。茉莉の元へ行こうと席を立つと、担任の先生が「王見、ちょっと」と声を掛けてきた。小さく手招きする様子を見るに、また例の話だろう。溜め息を吐きそうになるのをぐっとこらえ、先生のいる教室の隅に行く。
「王見。もう、分かるよな」
ジャージ姿の先生は腕を組み、私を見下ろした。
「そりゃ何度もこうして呼び出されていますからね」
「そうか。ならよかった」
先生は引きつった笑顔を見せ、一枚の紙を目の前に突き出した。右上にはクラス名と自分の名前が書いてある。その下にある三つの太めの枠には、何も書かれていない。というより、書きようが無かったのだ。
「いいか、王見。こういうのはな、ちゃんと書くべき場所に書くべき事柄を書いて、そうして先生に出して初めて『提出した』って言えるんだ。つまり王見はまだ未提出なんだよ」
「ですから、親が共働きで、どう書けばいいのかまだ聞けてないんですってば」
「これは進路希望であって、参観日の出欠席じゃないんだ。ちゃんと自分で考えて書きなさい。もう高校生になって半年経つんだから、せめて自分のやりたい事くらいはちゃんと考えとけよ」
先生が目の前でプリントをひらひらと揺らす。しぶしぶプリントを受け取ると、先生は小走りで職員室へ帰っていた。先生の足音が聞こえなくなるのを確認し、手に持っていたプリントを二つに折る。進路なんて正直どうでもいい。やりたいことなんて特にない。そもそも考えるのも、それを行動に移すのも面倒くさい。いっそ誰かが私の生き方を決めてくれたらいいのに。そうすれば、どうやって動こうかとか、どんなことを考えようかとか、そんなこと考えなくて済むから。
大きめの溜め息を吐き、茉莉の席へ向かう。茉莉は自分の席でマスコットを作っていた。裁縫道具を机に広げ、素早く、そして細かく手を動かしている。前々から思っていたが、茉莉は手先が器用だな。しっかりしていて気くばりもできるし、茉莉となら話していても疲れない。そうだ。茉莉に進路を決めてもらうのもありかもしれない。
近くで見ると、茉莉が小さなクッションのような物を作っているのが見えた。白い布と黒い布の境目には、紐でできた輪っかが埋め込まれている。
「これって、お守りか何か?」
「そうだよ。ベッドの柱に掛けてね」
「ベッドか……うちベッドじゃなくて敷布団使ってるから、枕元に置いておくよ」
「分かった。じゃあお守りを置くための座布団も作らなきゃね」
茉莉は赤い糸を取り出し、それを針に通そうとした。茉莉なら本当に作りかねない。流石にそこまでしてもらうのは悪いので、糸を切ってしまう前に茉莉を止める。
「お守りだけでいいよ。下にはハンカチでも敷いておくから」
「あれ、そうなの。じゃあこれで完成よ」
茉莉は私の手にマスコットを乗せた。見た目の割にずっしりと重いそれは、白黒の象のような見た目をしている。けど象にしては耳が小さいし鼻も短い。デフォルメされているからだろうか。
「……なんで匂いを嗅いでるの?」
「え、いや、なんとなく」
匂いが全くしないことを確認し、マスコットを顔から遠ざける。
「でも、いいの? こんなに手の込んだ物もらっちゃって。何かお礼しないと」
「お礼は別にいいよ。それより、ゆっくり眠れるようになったら、ちゃんと進路考えようね」
茉莉は私の足元に目を向ける。見ると、さっき渡されたプリントが床に落ちていた。私自身落としたことにすら気付かなかったのに、やっぱり茉莉はよく見ているな。プリントを拾い上げて立ち上がると、茉莉はもう裁縫道具を全て片付け終わっていた。
夜になり、部屋に布団を敷いた。枕元には清潔な今治産のタオルを敷き、その上に例のマスコットを寝かせる。何故タオルを今治産にしたかというと、質の良いタオルの方がよりご利益がありそうだったから。要するに気休めだ。枕元にタオルとマスコットがあること、そして目覚まし時計がきちんと動いていることを確認し、部屋の電気を消す。
「今夜こそ悪夢を見ませんように」
目をつぶり、なるべく余計な事を考えないようにしながら呼吸を落ち着かせていく。やがてまぶたが重くなっていった。
気がつくと目の前には、学校のグラウンド程の広さの血の池が広がっていた。
「また悪夢か!」
自分の叫び声で目が覚めた。目の前には見慣れた天井がある。でも目をつぶると、煮えたぎる血の池が頭に浮かぶ。まばたきをしてみると、血の池が目の前に何度も浮かんでは消えた。鬱陶しい。
「ひいっ」
頭の上で知らない声がした。体が勝手に飛び上がり、部屋の電気を点ける。枕元には例のマスコットがタオルの上で横たわっている。視線を移すと、窓の前に大きな男がへたり込んでいた。その男はトンボのように大きな目でこちらを凝視していた。
部屋の外に出て、誰かを呼ぼう。そう思いつきドアノブに手を掛ける。しかし、何故だろう。人はあまりに衝撃的な場面に出くわすと、かえって冷静になってしまうようだ。ドアノブを握る手の力を抜き、振り返った。私は悠長に一息吐き、その人間を観察することにした。
その男の顔にはパソコンのマウス位の大きさの目と、おはじき一粒程の小さい鼻、そして引きつった薄い唇が付いていた。体はどこに内臓をしまっているのか見当もつかない程細長く、男物のリクルートスーツを身に着けていた。この男の外見を一言で言い表すなら「現実離れ」だ。こんな男が自室に突然現れたのだから、悲鳴の一つでも上げるべきなのかもしれない。しかし、その男が埃の付いていない黒い靴下を履き、外履き用と思われる革靴を片手に持っているのを見ると、その男には悪意が無いように感じられた。
「あの、どうかされたんですか」
相変わらず何かに怯えている様子の男に歩み寄る。気を緩めたら吸い込まれてしまいそうな男の目を見つめながら歩み寄る。途中、つま先が枕元のマスコットに当たった。蹴られたマスコットはかしゃ、と音を立てて男の側に落ちた。
「わあああああああ」
男は飛び上がり、その華奢な身体に不釣り合いな大声を上げた。
「きゃあああ」
自分もまた、普段は絶対出さないような高い声で叫んでしまった。
男はマスコットの横をすり抜けて勢いよく私の腕にしがみついた。しかし、あまり強い力は込められていなかったのか、男の手は簡単に振りほどけた。
「もしかして、あれが恐いんですか」
部屋の端に転がったマスコットを指差す。男はこくこくと小さく、でも勢いよく何度も頷いた。
マスコットを拾い、勉強机の引き出しにしまう。ついでに椅子の上のクッションを取り、男の前に置く。男は眼だけを動かしてクッションをちらりと見、次にこちらに顔を向けた。
「使っていいですよ。あとマスコットも片付けましたから」
男はクッションを引き寄せ、その上に正座した。私は足元にあった枕の上に腰を下ろした。
「あ」
男ははっと息を呑んだ。しかし、私と目が合うと、すぐに目を逸らした。少し気にはなったが、気を取り直して話し始めた。
「それで、今日はどうされたんですか」
今日は、というのはおかしかったな。言い終えてそう思った。間違いなく今日初めて会ったこの男は、懐から名刺を取り出した。
「いやはや。失礼いたしました。私、こういう者です」
差し出された名刺を受け取り、まず男の名前を見る。
「とり、ゆめ、さん」
「『鳥夢』と書いて『とむ』と読みます。以後お見知りおきを」
「はあ、とむさん」
続けて肩書きを見る。しかし、本来会社名や役職が記載されているべき箇所は全て黒いマジックペンで塗りつぶされていた。照明の光を当てると、インクの下に微かに「夢」という文字が見えた。
「あの、ここは……」
「はい、本日はその件について謝罪をしに参りました」
「しゃざい」
見覚えの無い男から告げられた、身に覚えのない言葉を繰り返す。
会ったことも無い人に謝られるようなことをされた覚えはない。首を傾げたが、男はお構いなしに話を続けた。
「はい。この度は王見実様の快適な睡眠を妨害してしまったことを深く反省し、お詫び申し上げます」
「かいてきなすいみんをぼうがい」
復唱しながら、名刺に書かれた「夢」の字を思い出す。
「まさか」
「はい、そのまさかでございます。実様の見られていた悪夢は、全てこの私が原因でお見せしてしまったものでございます。大変申し訳ありません。今回の不祥事について詳しく説明いたします」
こちらが驚く暇もなく、目の前にパンフレットが広げられた。
「そもそも夢とは、人々が個人の記憶や精神世界を材料として作り上げる無意識の世界を指します。これらは全て無意識のうちに作られ、人々は無意識のうちにそれらの夢を体験させられます。これらは全て無意識のうちに行われるため、自分の求める内容の夢を見られるとは限りません。それどころか、世の中には悪夢に悩まされる方や、そもそも夢を作ることが困難な方もいます。そのような方々は、穏やかで安眠しやすい夢、いわゆる良い夢を見たいと日々願っていらっしゃいます」
鳥夢はパンフレットに描かれた図を指し示しながら説明を続ける。パンフレットは店や施設に置かれていても違和感がない位クオリティが高く、いわゆる「手作り感」の全く無いものだった。私はパンフレットが開かれた時から鳥夢の話を全て聞き流していたが、鳥夢はそれに気付かないまま説明を続ける。
「私はそのような方々をターゲットとした、良い夢を提供するサービスを考えました。それは、特に見たい夢があるわけでもない、そもそも夢自体必要ないと考えている方の作られた夢を引き取り、良い夢を求める人々にそれらを提供する方法です。早速被験者を決め、試験的な活動を始めました。その際被験者に選ばれたのが、実様。あなたでございます」
鳥夢は右手で私を指した。途中から何を言われているのか分からなかった。というより、分からなくなった。分かったことといえば、鳥夢は自分のやろうとした事のためにわざわざ会社を立ち上げたということだ。会社って、そんなに簡単に作れるものなのだろうか。そもそも自ら会社を立ち上げるという発想すらなかった。先程見せられたパンフレットや名刺を思い出す。あれらも全部自分で作ったのだろうか。自分のやりたい事のためにここまで手の込んだ物を自分で用意するなんて、大変じゃなかったのだろうか。色々と考えてみたが、それよりも今は早く眠りたい。あくびを堪えていると、それに気付いたのか、鳥夢は少し早口で言った。
「しかしこの計画には大きな見落としがありました。通常、人間は見る夢が無ければ何も感じないまま眠り続けます。しかし無理矢理夢を採取された人間は悪夢を見てしまうのです。私はその法則性に気付かないまま試験運用を行ってしまい、その結果、実様に悪夢を見せてしまいました。ご迷惑をお掛けしてしまったことを深く反省し、お詫び申し上げます」
鳥夢はクッションから下り、床の上で私に向かって土下座をした。深く頭を下げ小さく縮こまった鳥夢は、もともと異常に体が細いためか、跳び箱の一段目と同じくらいの大きさになってしまった。
「それで、悪夢を見なくて済むようにしてもらえるんですか」
「ええもちろん。そうさせて頂きます」
鳥夢は土下座の姿勢を崩さないまま言った。社会人になったら、自分も土下座をしなければいけない日が来るのだろうか。いまいち想像できないな。でもとにかく、安眠は約束されたようだ。
「ならよかった。では寝ますので、早速お願いします」
鳥夢は顔を上げ、ぎょっとした顔でこちらを見下ろした。布団に入り、上を向いて寝転がる私は、その顔を見上げていた。それにしてもこの人、本当に背が高いな。
「え、もうご就寝なさるのですか」
「はい。明日も学校があるので。もう寝ても大丈夫ですか」
鳥夢は眉間に指を当ててしばらく黙った。何の遠慮もなくあくびをしていると、鳥夢は、
「は、はあ。かしこまりました。では」
と言い、胸ポケットから小さなリングノートとペンを取り出した。
「これは実様の夢日記でございます」
鳥夢はリングノートを私の目の前に提示した。
「夢日記についての説明や扱い方等についてメモを書いておきますから、目が覚めたらまた読んでおいて下さい」
鳥夢はノートの表紙の裏にペンで何かを書き始めた。途中こちらをちらちらと見ながら、素早くペンを走らせた。
「このノートを所持して頂ければ、ひとまず他人に無理矢理夢を見させられることは無くなりますので。では、こちらに置いておきますね」
鳥夢はノートを枕元にそっと置いた。
「寝る前に、鍵、お願いします」
いつの間にか窓の外に出ていた鳥夢は、ベランダから飛び降りた。ゆっくりと起き上がり、窓に歩み寄る。鳥夢はグライダーのように夜空を滑空していた。それを見届け、窓の鍵を閉めた。
鍵はカチャンと音を立て、気がつくと私は布団の中にいた。
電気は消えていたが、窓から日の光が入り込んでいたので部屋の中は明るかった。目覚まし時計を止めようと頭の上を探ると、ボコボコとした感触があった。寝転がったまま体を回転させて枕元を見ると、折り畳まれたタオルの上に小さなリングノートが乗せられていた。私が触っていたのはそのリングの部分らしい。置いた覚えのないノートを持つと、昨晩の出来事が思い出された。起き上がり、勉強机の引き出しを開ける。予想通り、茉莉の作ったマスコットはその中にあった。振り返ると、布団の上にはクッションが投げ出されていた。
昨晩の出来事は夢ではなかったのだ。
今日も教室は赤くない。けれどいつもより明るい気がする。
久々に教室をゆっくりと眺めていると、教室に入ってきた茉莉と目が合った。
「おはよ、茉莉」
「おはよう、まことちゃん。今日は元気そうだね」
「うん。茉莉のお守りが効いたよ。今夜からはゆっくり眠れそう。ありがとう」
昨晩の出来事を話そうかとも思ったが、あまりに非現実的な、そして当事者である自分でも理解しきれていないほど情報量の多い話をしても、かえって茉莉を混乱させてしまいそうだったのでやめた。
「そうだ、今お守り持ってる?」
「うん。あるよ。ほらこれ」
「ちょっと貸してね」
茉莉はマスコットを受け取ると、おもむろにリッパーを取り出し、マスコットのお腹を切り開いた。
「茉莉、何してるの」
「確認だよ。机の上借りるね」
茉莉は小刻みにマスコットを揺らした。すると、机の上に赤や、緑、青の半透明の小さな石がバラバラと落ちてきた。
「何これ、こんなの入れてたの」
「そう。家にパワーストーンが余ってたから適当に詰めておいたの」
茉莉は机の上にできたパワーストーンの山を丁寧に広げながら言った。パワーストーンが「余る」家とは一体どんな家なんだろうか。
茉莉はその石の中から、小さな赤い石を一つ摘んで手の平に乗せた。
「ほら見て。これだけヒビが入ってるでしょ」
その石を受け取り、教室の蛍光灯に透かしてみる。茉莉の言う通り、よく見ると石には細い線が一本通っていた。
「昨日この石が身代わりになってくれたから、まことちゃんは悪夢を見なくて済んだんだね。だからこの石にはヒビが入ってるの」
「パワーストーンってそういうものだっけ」
「さあ」
「『さあ』って」
「正直私もよく分からないんだよね。でもまあ、これがあれば悪夢を見なくて済むんじゃないかな。バクの力もあるし」
「バク?」
聞き慣れない単語を聞き返すと、茉莉は目を見開いてこちらを見た。
「まことちゃん、もしかしてバク知らないの?」
「うん。そんなに有名なものなの?」
「有名ってわけではないと思うけど、悪夢を食べてくれる動物ってよく言われているから、てっきりまことちゃんなら知ってると思ってた」
「悪夢を食べる……」
昨日の出来事を思い出した。鳥夢がこのマスコットを異常に怖がっていたのも、バクという動物のせいだったのだろうか。
茉莉は裁縫道具を取り出し、マスコットのお腹を素早く縫い合わせていた。
「それがバク?」
「そうだよ。このお守りはね、バクをイメージして作ったの」
「そうだったんだ。ただの鼻の短い白黒の象だと思ってた」
正直に言うと、茉莉は比較的大きな、それでも耳当たりの柔らかい声で笑った。笑いながらも針を動かし続けていた。いつか手を刺してしまうのではないかと心配になったが、茉莉は怪我一つすることなく作業を終えた。
「はい、おまたせ。一応持っておきなね。多分また守ってくれるから」
茉莉の手際の良さに見入っているうちにマスコットは元の姿に戻っていた。再び茉莉に手渡されたそれは、やはりずしりと重かった。
「また石入れたの」
マスコットを裏返してみると、お腹の縫い目も元通りになっている。
「もちろん。また枕元に置いておいてね。あ、やっぱり座布団も作ろうか」
おもむろに赤いちりめんの端切れを取り出した茉莉を止めていると予鈴が時間を告げ、茉莉の手も止まった。
その日の晩、枕元には夢日記を置き、その上にマスコットを寝かせた。悪夢の原因がいなくなった今、これらはただの気休めに過ぎない。リングノートを置いた時、昨日の鳥夢の話が頭に浮かんだ。自分のやりたい事のためにわざわざ会社を作り、そしてわざわざ自分の不始末を謝りに来た鳥夢。鳥夢の夢はわざわざ会社を立ち上げないと叶えられない夢だったのだろうか。分からない。分からないけど、鳥夢が自分のやりたい仕事をはっきりと思い浮かべていることだけは分かる。そんなことを考えながら、暗い部屋の中で目を閉じた。
気がつくと教室の壁が一面だけ無くなり、そこに海が広がっていた。その反対側で、巨大イカが教卓を呑み込まんとしている今、皆は各々私服を着て海で水浴びをしていた。
「待って。なんで教室に海があるの。ていうか色々とおかしいでしょ」
思わずそう言うと、体から何かが抜けていくような感覚がした。腕を動かし、足踏みをする。反復横跳びをしながら、自分が自由に動けること、そしてつい先程まで自由に動けていなかったことに気付いた。
改めて辺りを見回す。いつも自分が通っている教室に似ているが、その中には何故か広大に広がる海と砂浜、普段あまり見ない私服姿のクラスメイト、そして全く見覚えのない巨大なイカがいた。これらを認識し、今自分が夢の中にいることを確認できた。
「嘘でしょ。もう悪夢は現れないんじゃなかったの」
とにかくここから逃げよう。少しでも速く走ろうと手に力を入れると、両手に何かを持っていることに気付いた。見ると、右手にはバクのマスコット、そして左手には、昨日渡されたノートが握られていた。
ふと顔を上げると、イカの巨大な足がこちらに迫ってきていた。
「うわっ」
咄嗟に右手で顔を庇う。その瞬間、右手が光り、バチッと静電気のような音がしたかと思うと、イカの足が一本無くなっていた。改めて右手を見ると、やはりバクのマスコットが握られていた。
「もしかして、食べたの?」
問いかけてみても、当然マスコットは何も答えなかった。ひとまずこの状況を切り抜けるために、昨日の出来事をなるべく詳しく思い出す。鳥夢が言っていたこと。夢のビジネス、ノート、夢日記。
「そうだ」
鳥夢が書いていたメモ。あれに何かが書いてあるかも。ノートを開くと、表紙の裏にボールペンでメモが書かれていた。横に数行箇条書きで走り書きされている文章を読み上げる。
「これは個人の夢を記録・管理するためのもの。見た夢の内容が記録され、書き込んだ事柄は夢に表れる」
ページをめくると、「通学路」や「水」、「ピニャータ」などの文字がちらちらと見えた。もう一度表紙の裏を見る。
「ページを破ると、そのページに書かれた夢は取り除かれる。ただしこれを行うと悪夢を見てしまう」
これは昨日鳥夢が言っていた気がする。聞き流してはいたが、何故か思い出すことができた。
「夢の内容を予め決めることはできないが、現実世界での行いが夢に反映されることはある」
その文の下には「(例)枕を踏む=悪夢」とだけ書かれていた。
枕。これもすぐに思い出された。昨日、鳥夢をクッションに座らせ、そして私は足元にあったクッション、ではなく、枕の上に腰を下ろした。そういえば、あの時鳥夢が顔をしかめていた気がする。
「じゃあこの悪夢って、私が原因なの?」
震えた声に振り返る人はおらず、やがてクラスメイトの声は悲鳴となって耳に刺さった。思わず耳を塞ぐ。耳に手も当てず、ただひたすら叫び続けるクラスメイトを見て、私は悟った。
私はこの夢の中で、自分の思うように動くことができるのではないか。今耳を塞いでいる手も、そして足だって、私の思うままに動くのだから。もう一度ノートに目を移す。
「夢日記を持っていれば、夢の中で自由に動き回れる」
そして、先程読んだ一文を読み上げる。
「書き込んだ事柄は、夢に現れる」
「書き込んだ」ということは、ペンがいるのだろうか。この仕組みを使えば、もしかしたら悪夢を良い夢に変えることができるのではないだろうか。自然と口角が上がる。
今まで夢の叶え方なんて知らなかった。それに、三年後のこととか、それより先のことなんてどうせ考えても分からない。だから考えようともしなかった。でも今の私は、今目の前に広がる夢の世界や、たった一晩の安眠を思うままにできる力を持っている。面倒だなんて思わない。むしろ、久しく感じていなかった何か、あえて言葉にするなら「楽しそう」という気持ちが芽生えているのを感じた。
「今なら、何でもしてみたい」
普段は引き戸であるはずの教室のドアに駆け寄り、ドアノブを回す。
誰もいない廊下を、しっかりと踏みしめながら駆けた。
※作品の無断転載を禁じます。
・日本語日本文学科(学科紹介)
・日本語日本文学科(ブログ)