日本語日本文学科 リレーエッセイ
【第52回】 2008年2月1日
「膝に塩を置く」:対照言語行動学の集まり
著者紹介
氏家 洋子(うじいえ ようこ)
日本語学・日本語教員養成課程担当
ことばが私たちの精神活動や社会・文化とどう関係し合うかについて考えています。
ここのところ、言葉については言語記号化された世界に限定して考察されてきた。だが、それでは捉えきれないものが多く、むしろ、捉えきれないものの中にコミュニケーションの実態がある。この辺を意識することで視界に変化が起きる。2000年前後のことだったが、対照言語行動学研究会というものを学会で知り合った仲間と立ち上げることになった。言語行動として捉えることで人間の精神活動そのものに迫る。
日本語の場合なら日本語を知ることで、それを作り、使い、あるいは継承してきた先人の精神文化(物質文明との対比で)を知る。異言語文化に通じる普遍性と、各言語世界にあるとされる特殊性とを、言語行動を対照させるという手法で、それぞれ浮き彫りにしようという狙いである。
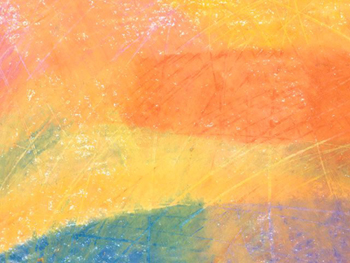
日本語文化の中でも方言と共通語、古語と現代語の世界の各対照もある。また、いわゆる「差別語」に関して、障害を持つ方の考えを聞くことで、「健常者」の思い込みを明らかにする。これは事実、研究会活動の中で証明することのできた大きな収穫の一つである。さらに、日本文化という、日本語でコミュニケーションを取ってきた集団にも下位の文化があり、異言語集団内の類似した下位文化のメンバーとのほうが話が早いということもある。いずれにしても同類の中にいるだけでは得られない目を貪欲に持つことで、自己を、また、それは自他をということにもなるが、客観視する目を持ちたい。
研究会の参加呼びかけに2年余りの年月を掛けた。国内外での学会・研究会への参加時に呼びかけたところ、海外の言語行動や日本語学の研究者も熱心で、2003年に第1回の会合を開くことができた。以来、毎年1回、計5回の会合を都内で開いてきた。世話役(委員会)の一員のハンガリーの方は、日本に数年在住後でも、研究会の委員になったのはこの会だけだと感想を洩らした。講師やコメンテイターとしてはハンガリー、チェコ、中国の朝鮮族、エジプトの方々の参加を得た。
この間、日常の業務遂行に伴うストレスや体調不良の長期化などで、継続の断念を考えたこともある。しかし、会合で心に大きな何かを得た時、続けて来てよかったと改めて思う。先日の会合ではこんなことを知った。アラビア語文化には「膝に塩を置いている」という慣用表現があり、他者につっかかる人、攻撃的な人、ひねくれた人、を指すという。慣用表現だから、その文化の中で生活者に意識され、複数者の意識に同時に上るようになったことで、コミュニケーション上の必要が生じ、形成されたものであろう。人間関係の悩みは万国共通、普遍的な課題かと思うが、この形容をなし得た時、この文化圏の人々はどんな思いだったか。異文化の人間としてこれを知った私はなぜか心癒される思いをした。今までのこの関連の苦しみのもとが視覚的な形に置き換えられたということによるらしい。抽象的な表現に包まれた物体の展開図を示された感じ、あるいは、ブラックボックスの中味を一部知り得た感じと言えばよいのか。何とも不思議な心的経験である。
ところで、イスラム文化圏で日本製缶詰が当初売れなかった理由が太陽のマークにあったということは鈴木孝夫氏の紹介するところだが、塩はアラビア語文化でどんな意味を持つのか。この文化圏からの研究会への参加者5名中の唯一の女性からお七夜が彼の文化にもあり、その際に塩を撒いて悪魔を追い払う風習があるとの情報が得られた。生存に不可欠の物だが、塩はどうやらここでは塩辛いものとして嫌われるのか。とすれば、膝に塩を置くとはいつでも人に憎まれ口を浴びせたり、攻撃したりする準備ができているということになる。塩を集めて膝に置くに至るまでには当人が塩投げ行動を幼時から身近なものとし、投げつけられてきた経験もあるというような水面下の積み重ねが想像される。それが意識的になされたものではないために、当人は膝に塩を置いて準備していること、それを投げつけていることに気付いていないと推測される。
それが解決の難しい点か。
そんなことを考えていたところ、トルコに長い、現代社会学科の紺谷亮一さん(考古学)にこの点についてお尋ねする機会があり、トルコにも同様の慣用表現があることを知った。トルコ語のトゥズ・アットゥという表現で、直訳では「塩を投げる」(過去形)だが、「縁を切る」、「相手を嫌う」、「裏切る」の意で使われるとのこと。アラビア語文化からこの表現が同じイスラム文化圏のトルコに入ったのか、トルコ語の表現がアラビア語文化に入ったのかは定かでない。が、この地で塩と言えば岩塩を砕いた物だという。
日本語では「塩を撒く」として穢れを清める意の慣用表現が作り出された。こちらは海水から精製した結晶。彼の地の塩は岩塩、当然、痛い。所変われば、である。アラビア語文化での慣用表現の研究はまだ緒に着いたばかりだという。だが、人を不快にさせる行動を物を使って示した表現の存在が異文化の人間にもたらしたものは大きい。もともと寄り合うことの不得手な人間ながら研究会を発足させてきたが、未知の文化の考え方を知ることで心癒されるとは発足時には予期し得なかったことである。
・日本語日本文学科
・日本語日本文学科(ブログ)



