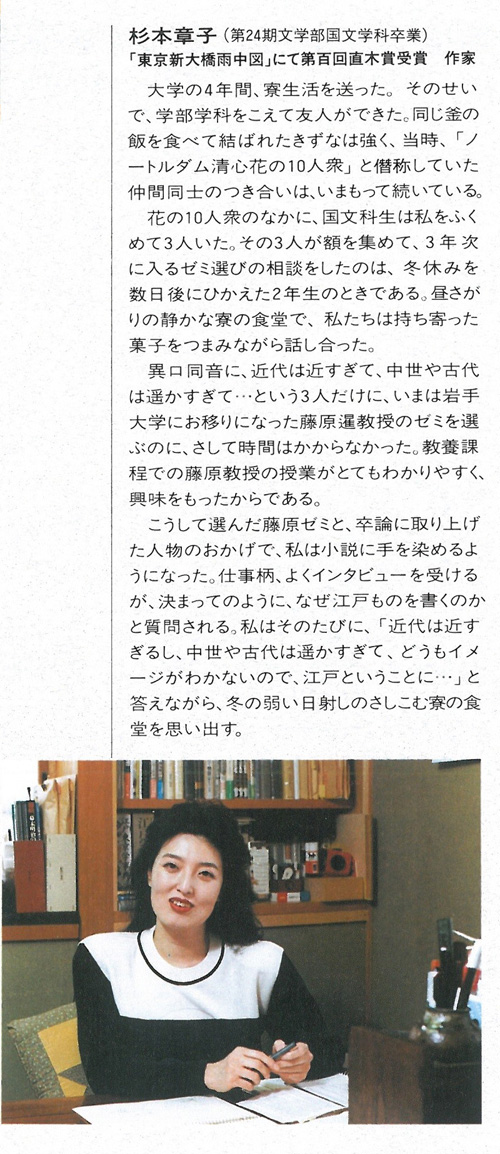このたび2015年12月4日、天に召されました作家・杉本章子さんの永遠の平安を心よりお祈りいたします。
1988年に第100回直木賞を受賞した小説家である杉本章子さんは、ノートルダム清心女子大学日本語日本文学科(当時の名称は国文学科)の卒業生です。
杉本章子さんが作家としてデビューを果たしたのは1980年で、『男の軌跡』で第4回歴史文学賞の佳作に入選したことがきっかけとなっています。これは、本学科での卒業論文(幕末期の儒学者・戯作者である寺門静軒についての研究)がもとになっており、そのことを、「受賞者が語る直木賞受賞までの軌跡」を語る自伝エッセイで、「曲がり角の男」(「オール読物」1989年3月)と題した小説のような文章で自ら次のように表現しています。
卒論も提出したことだし......と心おきなく遊んだ冬休みはあっという間に終わり、帰寮して三日後には、卒論の指導教授であったF教授の面接が待っていた。(中略)
「読ませてもらった」
「......はい」
「まあ、よくできていると思う。ただし、小説としては、ね」(中略)
それから、三年後。
私はひょんなことから小説を書いてみようと思い立ち、この面接のときのF教授の言葉を支えにして、寺門静軒を小説に書いた。
このように、本学での学びと卒業論文が、杉本章子さんにとって「いま歩んでいる道の出発点だった」とされています。
さらに、この自伝エッセイでは、福岡県出身の杉本章子さんが、岡山県岡山市にあるノートルダム清心女子大学に進学した理由や大学生活の様子についても、記しておられます。
まず進学については、杉本章子さんが、1歳3ヵ月で小児麻痺に罹ったことで両脚を松葉杖で支えて移動する生活となったため、高等学校までの12年間、通学に親の手を煩わせ続けたことから、大学で親元を離れて自立したいという思いが芽生えたこと、また高等学校がミッション系だったことから、本学を選んだということです。
そのような進学後の大学生活については、本学に当時あった寮に入り、学科を越えた友人とともに楽しく充実した寮生活を送っている様子が活き活きと描かれています。
先の卒論の指導教授F先生とは、藤原暹先生ですが、杉本章子さんの卒論に至るまでのゼミの様子や、松葉杖をつきながら学内を廻られていた学びの日々の姿が、下記の描写から目に見えるようです。
ゼミの教室は、図書館の三階にある。エレベーターがないので階段を使うほかなく、これが足のわるい私にはこたえるのだ。毎週、階段を登るたびにダイエットを誓うのだが、続いたためしがない。
杉本章子さんが、このように逆境にもあえて挑戦する思いで、自立心を養おうと自らの才能を開いていく大学生活を本学で送り、そうした授業や卒論ゼミの学びのなかで、夢中になれる近世の世界や人物と出会って、かけがえのない個性を活かして分け入ることのできる世界を_みながら小説を書くという、ご自身ならではの生き方をスタートされたということに、深い感慨を抱かずにはいられません。
杉本章子さんは、2002年に本学での鼎談「杉本章子 その創作の原点」のために本学にお越し下さり、藤原先生とも談話いただきましたが、その後のお招きも叶わず、62歳というお歳での逝去は惜しまれてなりません。
せめて、直木賞受賞作家・杉本章子さんの本学での足どりを辿り、残された作品を読むことで、そのお心を皆さまとともに偲びたいと思います。