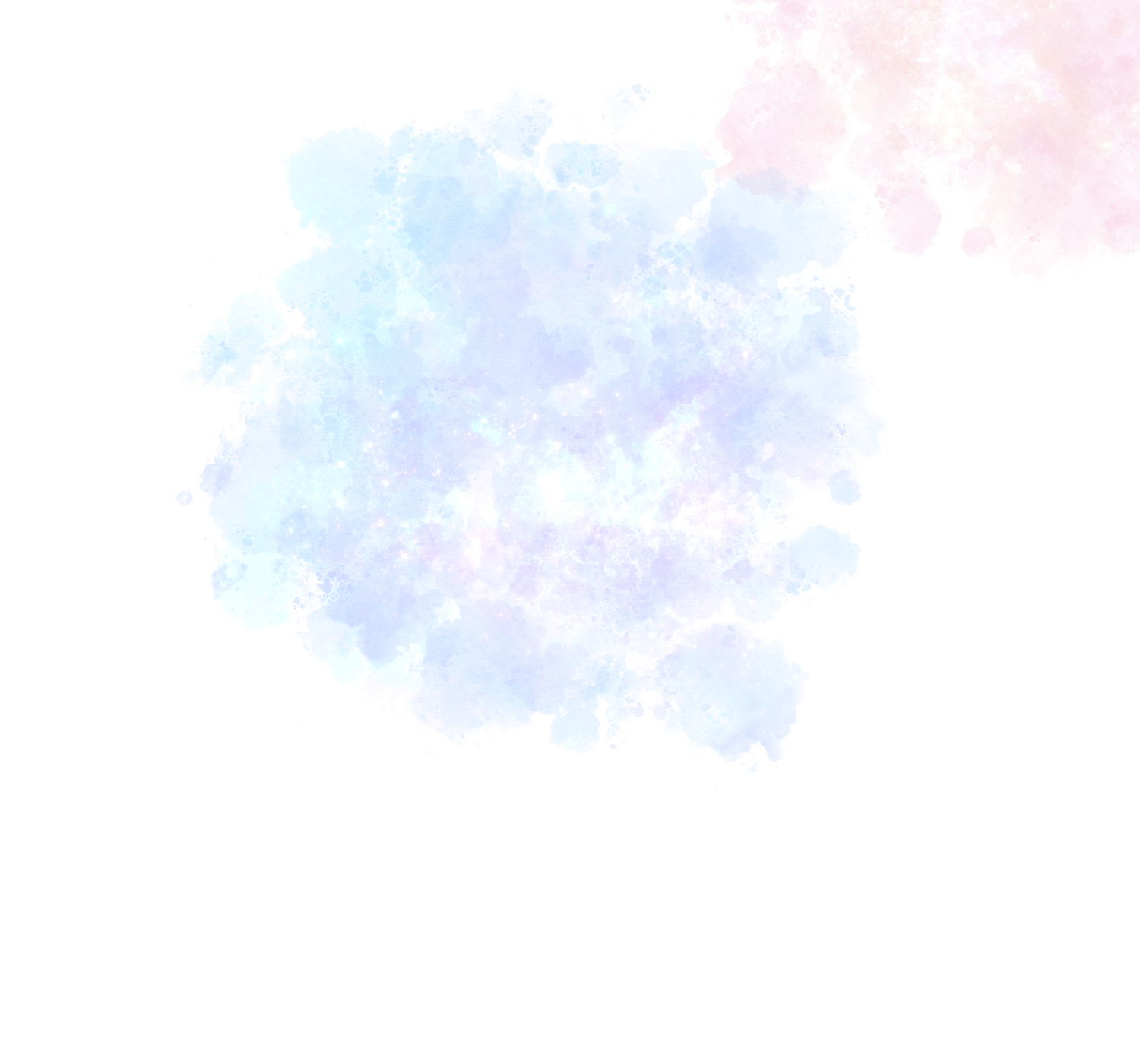本学科の授業科目「文学創作論」では、履修生が1年をかけて作り上げた作品をまとめて、文集を発
行しています。
ここでは、第14集『BRIGHT』(2016年度)より、1作品をご紹介します。
狐はゆりかごの中で嗤う
作・則武はるな
とある昔の話。徳川が日の本を治めていた頃のこと。下総国に井岡屋という米問屋があった。初めは小さな店だったが、だんだんと繁盛し、立派な大店になった。井岡屋の初代大旦那の世茂吉は、店の繁盛祈願のために、井岡屋の近くに昔からあった小さな祠に手を合わせに行っていた。その祠には稲美様と呼ばれる稲の神が祀られていた。稲美様は狐の姿をしていて、人の前に姿を現した年は豊作になると言われていた。世茂吉は稲美様に、稲がよく実り、米がよく売れるようにと祈った。そのかわり、毎日祠の前に握り飯と油揚げを供えると約束した。滝のような雨が降る日も、冷たい風が吹く日も休まず手を合わせ、供え物をし続けたおかげか、井岡屋は大繁盛し、裕福になった。仕事が増えるにつれ、丁稚や手代も増え、世茂吉は一心不乱に働いた。あまりの忙しさに、稲美様への毎日の供え物も忘れてしまうほどだった。初代大旦那の世茂吉は、その生涯を井岡屋に捧げ、七十八でこの世を去った。
井岡屋を継いだ世茂吉の長男・左之次郎は、父の葬式が終わってすぐ、店を大きく建て替えた。建て替えの際、米蔵を増やすために周りの土地を買って新地にすることにした。新地にする土地には、父・世茂吉が繁盛祈願をしていた稲美様の祠がある場所も入っていた。しかし左之次郎は、古い祠でもう誰も参ってもいないからお狐さんもとうの昔に立ち去ってしまっただろうと、ろくに御祓いもせずに取り壊してしまった。いちいち神官を呼んで御祓いをさせるのが面倒だったというのが左之次郎の本音であった。しかし、稲美様の祠を取り壊して再び商売を始めてひと月が経った頃、井岡屋に異変が起こり始めた。
初めに怪異に気が付いたのは、水汲みをしていた丁稚だった。夜中、翌朝使うための水を汲みに井戸へ向かったところ、井戸の上で何やらちかちか光るものが目についた。青い光で、ふわふわと宙を漂っていた。よく目を凝らして見ると、それは蒼い火の玉で、闇夜を舞う狐火であった。丁稚は恐ろしくなり、番頭にそのことを話したが、番頭は寝ぼけていたのだろうと、その時は軽くあしらった。しかし、日が経つにつれ井岡屋を襲う異変はひどくなった。井岡屋の屋敷の中で狐火を見たという者が増え、屋敷が獣臭いという者まで出るようになった。そのうち店で働く者たち、それも女ばかりが次々と病に倒れ、店が上手く回らなくなった。幾日かして治る者もいれば、そのまま調子が良くならないで仕事を辞めていく者もいた。女だけがかかる流行り病ではないかと疑われたが、井岡屋以外のところでは病が流行っている様子はなく、何の変わりもなかった。働く者が減っていく中でも、不思議と病にかからない男たちは倒れた女たちのぶんまで必死に働いた。そのおかげで井岡屋は何とか成り立っていたが、ある日、左之次郎の妻の鹿江が急にひきつけを起こして倒れた。今まで女の手代たちが病に苦しめられてきたのを見ていた左之次郎はすぐに町の薬師を呼びつけ、鹿江を診てもらった。しかし、どの薬師に診せても病のもとは分からず、高い薬を飲ませても良くはならなかった。そうしているうちに鹿江の病状は悪くなり、遂に正気を失ってしまった。左之次郎には娘が二人と息子が一人いた。息子の世次郎には何事もなかったが、娘二人は母に続くようにして気が狂ってしまい、床に臥せった。
家族三人が倒れてようやく、左之次郎は異変の原因が米蔵を建てたときに取り壊した祠のせいだと確信した。左之次郎は昔から近所に住んでいた老人のもとを訪れ、祠に祀られていた狐神・稲美様について詳しいことを聞かせてもらった。狐神というものは、きちんと祀れば商売繁盛や家内安全を成就させてくれるが、粗末に扱えば恐ろしい祟り神になってしまう。また女に憑くことが多く、女ばかりが体調を崩したのは間違いなく稲美様の仕業だと老人は言った。左之次郎の妻や娘たちは稲美様の祟りをその身に直に受け、狐憑きになってしまったのだ。祟り神となった狐は腹に宿った子を喰うこともあるという。左之次郎は己が犯した罪の大きさに身を震わせた。すぐに番頭や手代と寄り合って、この怪異を止める策をいろいろと講じた。だが、祠を壊してしまった後ではどうすることもできなかった。
そうして、左之次郎一家は狐憑きの一家と噂されるようになり、井岡屋も少しずつ傾いていった。
一方、上総国の小さな町に、織物の仕立てや修繕を生業とする嶋田屋という織物屋があった。さほど大きくはないが、丁寧な仕事が評判であった。嶋田屋にはお夏という一人娘がいた。家の仕事をよく手伝い、客に対する愛想も良く、町一番の器量良しと言われていた。働き者で気立ての良いお夏を嫁に欲しがる男は数多いた。しかし、お夏はどの男の求婚にも首を縦に振らなかった。お夏には、幼い頃から夫婦になる約束をした男がいた。名を伊三郎といい、桶屋の一人息子だった。決して裕福ではなかったが優しく気の良い男であった。お夏と伊三郎はとても仲が良く、お互いがお互い以外の人と結ばれることなど考えられなかった。両親たちも二人が結ばれることを望んでいた。
「伊三郎さん。私、誰よりもあなたのことを想っているわ」
「俺もだよ、お夏。必ず夫婦になろう」
二人はそう言い合って、幸せな日々を送っていた。
しかし、ある日お夏のもとにひとつの縁談話が舞い込んできた。お夏は両親に詳しい話を聞く前から首を横に振った。
「ととさん、かかさん。お二人も知っているでしょう。私、伊三郎さん以外の方と一緒になるつもりはありません」
そういって固く断った。しかし、父と母は難しい顔をした。
縁談の相手は、下総国にある米問屋の井岡屋の世次郎だった。お夏の父と世次郎の父は遠い親戚で、お夏も幾度か世次郎と顔を合わせたことがあった。世次郎は端正な顔立ちだが、高飛車で横柄な質の男だった。お夏は態度の大きい世次郎が苦手だった。
「ととさんもかかさんも、伊三郎さんと夫婦になることを喜んでくれたじゃありませんか。なぜ断ってくれないの」
お夏がそう尋ねると、父は険しい顔をしながら口を開いた。
父が営む嶋田屋は、父の代で始めた店だった。店を始める際、足りなかった資金を親戚である井岡屋の左之次郎から借りたらしい。その時、店を構える土地の見定めや御役所への届け出についても随分力を貸してもらったという。
「左之次郎殿から借りた金はすでに全てお返ししたが......そのほかにもいろいろとしてもらった恩があってな」
その恩返しに、お夏を世次郎に嫁がせろというのだ。この縁談を断れば、父が立場をなくすことは考えなくとも分かった。自分たちを脅すような左之次郎のやり口に、お夏は憤った。
「そんな卑怯なやり方しかできないような家には、嫁ぎたくありません」
そう叫び、両親が止めるのも聞かずに家を飛び出した。
逃げるように走り出たお夏は、真っ先に伊三郎のもとへ行った。お夏は伊三郎に縁談の事を話した。
「私、あなた以外の人の妻になるなんていや。でも、ととさんやかかさんが嶋田屋を取り上げられるのも耐えられない......」
袖を濡らすお夏を、伊三郎は優しく抱き締めた。
「お夏、泣くんじゃない。俺が左之次郎様と世次郎様のところへ行って、縁談を取り下げてもらうように話してくる。お前は俺の嫁だ。誰にもやりゃあしない」
伊三郎はお夏の両親と話をつけ、旅支度をすると早速井岡屋のある下総へ向かうことになった。出立の朝、お夏は伊三郎を見送りに出た。
「伊三郎さん、どうか無事に帰ってきて」
「なに、話をしてくるだけさ。心配しなくとも、話がついたら飛んで帰ってくる」
お夏の心配を軽く笑い飛ばすと、伊三郎は下総へ向けて旅立った。下総と上総は隣地なので、行って帰ってくるまでに日はかからないはずだった。お夏は伊三郎が帰ってくるのを、まだかまだかと首を長くして待った。しかし、幾日経っても伊三郎は帰ってこなかった。
伊三郎が出立してから十数日経ったある日、お夏のもとに伊三郎の友人の飛脚が転がり込んできた。下総と上総の境の辺りで、伊三郎の骸が見つかった。骸の背中には刀傷があり、どうやら辻斬りにあったらしいと、飛脚は真っ青な顔で告げた。お夏は、その場に立ち尽くし、一寸も動けなかった。伊三郎が死んだ。殺された。あまりに酷な報せに、泣くこともできなかった。
母に介抱されながら、お夏は全てを悟った。伊三郎は辻斬りなどにあったのではない。左之次郎と世次郎に殺されたのだと。嫁を寄越さなければ店を潰すと脅してくるような親子だ。自分たちの邪魔になるものなら容赦なく始末しかねない。
「どうして......帰ってくるって、約束したじゃない。飛んで、帰ってくるって......!」
伊三郎の死に、お夏は生きる気力を失ってしまった。何をしても何も感じなかった。何を食べても味がしなかった。伊三郎のいない世に生きていても、死んでいるのと同じだった。
生きる骸となってしまったお夏は、入水や毒で自決することも考えた。しかし、それは出来なかった。世次郎と結ばれたくないために自決したと知れれば、父と母は死ぬより酷な目に遭うかもしれない。左之次郎は御役所の上役と繋がりがあるため、嶋田屋をお取り潰しにすることなど容易い。娘を失ったうえ、嶋田屋まで取り上げられたら、両親には何も残らない。伊三郎がいない今、お夏に出来ることは両親が今まで通りに暮らしていけるように、井岡屋に嫁ぐことだけだった。
お夏は、白無垢を着て化粧をして、井岡屋が用意した輿に乗って嫁いでいった。家を出る前、目を腫らす両親に言った。
「この白無垢は、死装束です。この化粧は、死化粧です。ととさん、かかさん、お夏は死んだものと思ってください」
それだけを告げ、お夏は輿に乗った。両親と別れる時さえ涙を見せなかったお夏は、井岡屋に向かう輿の中で、一人ひっそりと泣いた。
こうして、お夏は井岡屋に嫁いだ。井岡屋に着くと、左之次郎が満面の笑みで出迎えた。世次郎もお夏が嫁いできたことをそれなりに喜んでいるようだった。しかしお夏にとっては二人とも伊三郎の仇でしかない。どんなに優遇されようと、地獄に来たことには変わりなかった。左之次郎と世次郎の曇り一つない笑みを見て、お夏は死んだ気で生きて行くことを決心した。両親のため、嶋田屋のために、全てを外面では受け入れ、伊三郎のもとへ行けるその日を待とうと。
嫁いでから数日後、お夏は井岡屋の異様な雰囲気に気が付いた。お夏は、嫁いでから一度も世次郎の母の鹿江に会っていなかった。病で床に臥せっているとは聞いていたが、婚姻の儀の時さえ姿を見せなかった。鹿江だけでなく、世次郎の妹二人も部屋に籠ったまま出てこない。井岡屋の手代たちもどこか気のない顔をしており、お夏の身の回りの世話をする女中も常に顔が白かった。誰もが人形のような顔をしていた。まるで皆が何かに取り憑かれたようだった。
ある日、お夏が鹿江の薬を買いに出て屋敷に帰ると、庭に見慣れない女が立っているのを見つけた。一緒に出掛けていた女中に聞くと、世次郎の妹の一人だと言った。たまに体の調子が良い時に庭に出て散歩をするのだという。庭の真ん中に立つ義妹を見て、お夏は久しく感じていなかった恐れに身を震わせた。妹は着流しではあったがきちんと身なりを整え、髪も綺麗に纏めていた。ふと見ただけなら、病弱な美しい女だった。しかし、ぼんやりと空を見つめる二つの眼がどことなく異様であった。見つめているようで、見つめていない。虚ろな眼だった。口は筋が切れたように細く開いたままで、そこから魂が抜けているのではないかと思われる出で立ちだった。
お夏が目を逸らせずに見ていると、妹は急にくるりと振り向いた。
「あ......」
思わずお夏が声をもらすと、妹は暫くじっと見つめてきた。そうして、にたりと笑った。
「おんや。兄様のお嫁さんかあ。こりゃ酔狂な、酔狂な」
琴の弦を引っ掻いたような声で妹は言った。お夏は妹の尋常でない様に唇を真一文字に結び、何も言えなかった。
「義姉様、知ってるかい。兄様にはねえ、前にお嫁がいたんだよお」
妹は楽しそうに、歌うように言った。お夏の背後で女中が悲鳴をあげるようにして妹を諌めた。しかし妹は構わず続けた。
「けどねぇ、腹にできたやや子と一緒に死んじまった。狐が腹の子を喰ったって言って腹を掻っ捌いて死になさった。狐が憑いたんだよ、狐が。それからだぁれも嫁に来なくなったんだ。でも義姉様が来てくれた。義姉様、優しいね、優しいねぇ」
そう言ってケタケタと笑った。お夏はその場に立ち尽くした。首を振って狂ったように笑う妹を見つめる事しかできなかった。「狐が腹の子喰った、喰ったった」と歌う妹は、女中に連れていかれた。
その日、お夏は自分が仕方なく迎えられた嫁なのだと初めて気が付いた。しかし、人形のように心を殺したお夏には、自分が妥協の末の嫁であることさえもどうでもよかった。ただ、狐の話だけが妙に頭の隅に残った。
そうこうして過ごすうちに、お夏は懐妊した。その身に世次郎の子を宿した。子が出来たと知って左之次郎も世次郎も手を打って喜んだ。手代たちもその時ばかりは笑みを見せて祝った。鹿江や義妹たちは懐妊の報せをやっても顔を見せなかったが、お夏にとってそんなことはどうでもよかった。世次郎の子を宿してしまった。伊三郎以外の男の子どもを孕んでしまった。愛しい人を無残な姿で道端に転がした男の子どもが、今、己の腹の中で生まれる時を待っている。身の毛のよだつことだった。
「いやよ......あの男の子どもを産み落とすなんて。鬼の子......この子は鬼の子よ!」
それまで何があっても拒まずただただ受け入れてきたお夏は、己の血を分けたはずの子どもだけ、受け入れられなかった。腹に宿ったと気付いて始めて、そのおぞましさを身に感じた。
「伊三郎さん、どうしてあなたの子じゃないの......。私は、あなたとがよかったのに。あなたが、よかったのに......」
膨らんだ腹を抱え、お夏は呻いた。腹の中の子が憎い。愛しい人は斬り殺されたのに、この悪鬼は人の血を啜り、日に日に大きく肥えていく。そうしてのうのうと生まれてこようとしている。身も震えるような事実に、お夏は耐えられなかった。
お夏は、腹の悪鬼がこの世に出てくる前に、水子にしてしまうことにした。鹿江の病に効く薬を買いに行くふりをして、子を流す毒を手に入れた。そしてある日の夜。誰もが寝静まった頃を見計らって、お夏は屋敷の庭に出た。子流しの毒を、大切な宝のように握り締めて。闇のような空に、蒼い月がぽっかり浮かんでいた。お夏は血が流れた時のために、井戸の近くで毒を含もうと決めていた。井戸のすぐ脇に正座をして、月を眺めた。月はどこまでも丸かった。
「伊三郎さん、ごめんなさい」
そう呟き、口に毒を含んだ。毒はひどく苦かった。
その時、お夏ははっと目を見開いた。
腹が、動いた。どくっと、脈打った。腹の中の子が、腹を蹴った。
お夏は口の中の毒を吐き出した。一緒に胃袋の中のものも吐いた。
生きている。お夏は思った。この子は生きようとしている。どうしようもなく、ただ、生まれたがっている。憎しみと呪いの悪鬼としてではなく、ただの人の子として。私の子として。
「ああ――......」
命を与えてくれるはずの母に、命を奪われそうになっていようとも。生きたいと、叫んでいる。
「あぁああ――っ」
お夏は泣き崩れた。腹の中にいるのは悪鬼などではなく、間違いなく己の子だった。そして、愛しい人を奪った世次郎の子であった。この世で最も愛しく、この世で最もおぞましかった。
お夏は地に伏して泣き喚いた。すると、どこからか高い声が聞こえた。獣の鳴き声のように聞こえた。お夏は額に土をつけたまま顔をゆっくり上げた。月の光を受けて、何かが座っていた。よくよく見ると、それは赤い眼の白狐だった。静かに座り、お夏を見据えていた。血のように真っ赤な眼に見つめられ、お夏は地に這ったまま動けなかった。
「娘よ。お前の苦しみ、よく分かるぞ」
白狐は赤い舌を覗かせて言った。お夏は声を出せなかった。ただ座っているだけの狐に恐れをなした。
「為すすべなく奪われること。これほど酷なことはあるまいて」
ひたひたと、足音もなく白狐が歩み寄ってくる。お夏の額に汗の玉が噴き出した。
「願いを叶えてやったというに、嗚呼、人の子は愚かなものよ」
白狐は嘆きの声をもらしながら、その口の端を吊り上げた。口の端に何かがぶら下がっているのが見えた。
「お前も苦しかろう。辛かろう。鬼の子を孕んで。その悪鬼、儂が祓ってやろう」
「や......めて......」
お夏は声を絞り出した。両腕で腹を抱きすくめた。
「この子は、私の......生きようと......」
「懲りずに穢れた種を撒きおって。案ずるな、娘よ。喰らってやろう。恐れることはない」
歪んだ白狐の口から赤い汁が零れた。その端に紐のようなものが垂れていた。
「やめて......!」
「もう苦しむこともない」
ぼたりと土の上に落ちる。
「よこせ」
臍の緒だった。
「やめてええぇえ!」
血に塗れた口が大きく開かれた。
「狐が腹の子喰った、喰ったった」
お夏は気を失ってしまった。最後に聞こえたのは、いつか聞いた歌声だった。
お夏が目を覚ますと、そこはいつもの寝床だった。左之次郎と世次郎と女中とが、お夏の顔を覗きこんでいた。お夏が目を覚ましたことに、皆大層喜んだ。女中に話を聞くと、朝水を汲みに行った丁稚が井戸の前で倒れているお夏を見つけたのだという。男たちを叩き起こして急いで床に運んだらしい。世次郎に「一体何があったんだ」としつこく尋ねられたが、お夏は白狐のことを話さなかった。ただ心の隅で、鹿江や義妹たちが表へ出てこられないのも、井岡屋に嫁が来なかったのも、あの白狐のせいなのだろうと思った。
気持ちが落ち着き部屋に一人になって初めて、お夏は恐る恐る腹を撫でてみた。すると、手のひらに僅かな動きを感じた。ぽこっぽこっと、小さな足が腹を蹴っていた。その小さな命の動きに、涙が一筋流れた。暖かく冷たい涙が、頬を滑った。嬉しかったのでも、辛かったのでもなく。ただ、涙が流れた。
「ごめんなさい......」
一人呟くお夏は、他の誰でもなく、遠い日に旅立った愛しい人を思い出していた。優しい笑みを遺していった人を想った。そうして、腹を撫でながら、無性に握り飯と油揚げが食べたいと思った。
それから暫く経って、お夏の腹が大きくなりもうすぐ子が生まれるという頃。お夏は死んだ。正気を失い、そのまま死んでしまった。それまでよく食べよく眠り、腹の子を労わって過ごしていたが、臨月に入ったすぐ後、急に気を狂わせてしまった。「腹の子が入れ替わってしまった」と喚いて暴れまわった。女中たちはお夏を薬師に診せるように世次郎に言ったが、世次郎は「薬師に診せても無駄だ」とだけ言い、のたうち回るお夏を部屋に閉じ込めてしまった。閉じ込められたお夏は、昼も夜も髪を振り乱して叫び喚いた。その声は近所の家にまで響き、獣の鳴き声のようだったという。しかしその悲鳴も長くは続かず、ある日鳴き声はぱったりと止んだ。女中たちが襖の隙間から部屋を覗くと、お夏は布団の上に力なく転がって息を引き取っていた。女中たちはお夏の死に袖を濡らした。だが、お夏の死に顔は、気を狂わせて死んだとは思われないほど穏やかだったという。その白い首には、不思議なことに、男の手で絞められたような跡があった。娘の死を知ったお夏の両親は、「きっと苦しむお夏を伊三郎が救ってくれたのだ」
と言って泣いた。
お夏を閉じ込めて女中たちに任せっきりにしていた世次郎は、お夏の死に様を見て、これでは腹の子は生きてはなかろうと嘆いた。そうしてお夏の亡骸を葬ろうとした時、信じられないことが起きた。死装束を着せられ、いよいよ棺の中に入れようと体を抱き上げたとたん、お夏の股座から何かが滑り落ちた。女中が布団の上に落ちたものを恐る恐る見ると、それは赤子だった。赤子の骸が出てきたと思った女中たちは恐怖のあまり喚き散らした。しかし、騒ぎを聞いてやってきた世次郎が抱き上げると、赤子は息を吹き返したように大きな産声をあげた。女中や手代たちは骸からひとりでに生まれた赤子を気味悪がった。しかし世次郎と左之次郎は赤子が男の子だと分かると、お夏が最後に遺した宝だと言って自分たちの手で育てることにした。
骸から生まれた男の子は秋之助と名付けられ、大事に育てられた。秋之助は欲しいものはどんなものでも与えられ、すくすく大きくなった。好き嫌いもなく何でもよく食べた。しかしその中でも好んで食べたのは握り飯と油揚げだったという。秋之助は何不自由なく健やかに育ったが、いつもぼんやりとしていて、表情の薄い子どもだった。いつになっても世次郎と左之次郎に懐くことはなく、いつも母・お夏の墓の前に座り込んでいた。遊ぶわけでもなく、ただ墓標を眺めていた。そんな秋之助を、世次郎も左之次郎も気味悪がるようになった。
秋之助が生まれてから九年経ったある日、世次郎は棚に閉まっておいた小さな箱がなくなっていることに気が付いた。秋之助とお夏を繋いでいた臍の緒が入った箱だった。世次郎は秋之助の仕業だと勘付いた。秋之助はお夏の墓の前にいた。その手にはやはり箱が握られていた。世次郎が怒鳴りつけると、秋之助はぱっと振り向いた。その顔を見て、世次郎は悲鳴を上げて腰を抜かした。振り向いた秋之助の口は血で真っ赤に濡れ、その端には臍の緒をぶら下げていたという。腰を抜かして恐怖に震える世次郎を見下ろして、秋之助はにんまり笑った。そしてくるりと踵を返すと山に駆けて行った。獣のように山に入っていった秋之助は、二度と井岡屋に戻ってこなかったという。
その数年後、もともと傾いていた井岡屋は遂に潰れてしまった。借金で首が回らなくなった左之次郎一家は、みんな首を掻っ切って自決した。その首の切り傷は、まるで獣に喰い千切られたようだったという話である。
※ 作品の無断転載を禁じます。