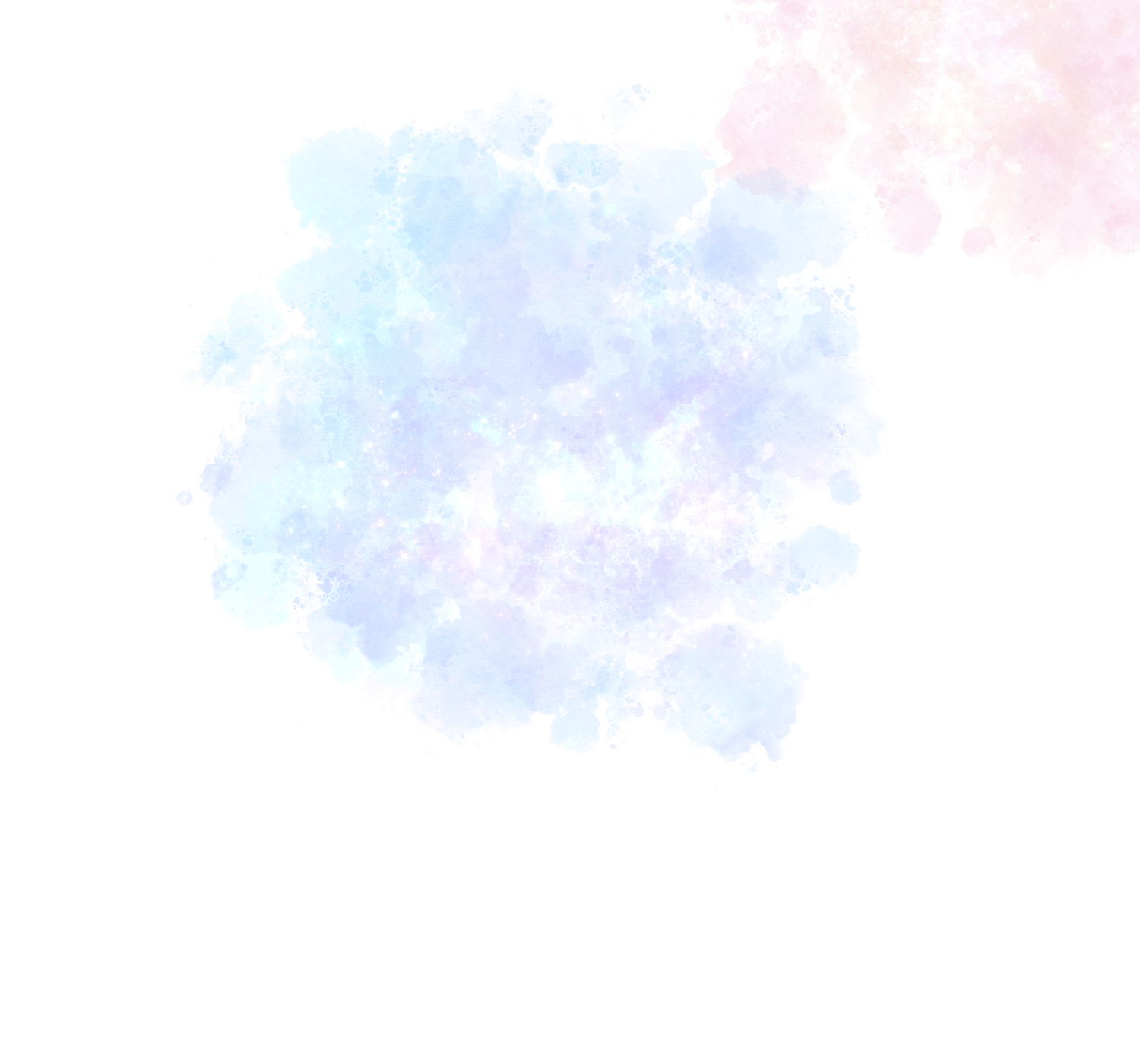【著者紹介】
東城 敏毅
古典文学(上代)担当
古代和歌、特に『万葉集』について、研究を進めています。
「令和」の万葉集―天平時代の「梅花の宴」―
1. 「令和」の出典
万葉歌人、大伴旅人(おほとものたびと)は、神亀5年(728年)頃、大宰帥(だざいのそち:大宰府の長官)として妻の大伴郎女(おほとものいらつめ)、息子の大伴家持(おほとものやかもち)らを伴って太宰府に赴任する。60歳を過ぎてからの九州下向であった。赴任後間もなく妻を亡くし、旅人は多くの「亡妻挽歌」を『万葉集』に残すのであるが、大宰府では山上憶良・満誓(まんぜい)らとの交流を通じて、いわゆる「筑紫歌壇」(つくしかだん)と呼ばれる、日本和歌史上、画期的な一時代を形成するのである。天平2年(730年)には、新元号「令和」の出典ともなった「梅花の宴」を大宰府の旅人宅において催した。
『万葉集』には「梅花の歌三十二首併せて序」として掲載され(巻5・815~846)、その序文の冒頭は以下のように記されている。
天平二年正月十三日に帥老(そちらう:旅人)の宅(いへ)にあつまりて宴会をのべたり。時に初春の令月にして気淑(よ)く風和(やわら)ぐ(初春の正月の佳い月で、気は清く澄みわたり、風も穏やかである)。(略)
メディアでも多く取り上げられた「令和」の出典であるが、この箇所は、以下の漢籍を背景に持つ。
・是に於て仲春令月、時和し気清し。(張衡「帰田賦」『文選』)
・是の日や天朗らかに気清く、恵風和暢(のびやか)なり。(王羲之「蘭亭序」)
特に、書聖とも称された王羲之(おうぎし)の「蘭亭序」(らんていじょ)は、「梅花の歌」の序文に多くの典拠を与えている。このように、漢籍で描かれる幻想的で理想的な世界を、都から遠く離れた大宰府において再現すること、ここに「筑紫歌壇」の画期的な達成があった。しかし、本エッセイで考えてみたいのは、「筑紫歌壇」の中心的人物でもあり、「梅花の宴」にも参加した山上憶良の「梅花の歌」である。
 大宰府政庁跡(撮影:花谷美紅 東城ゼミ4年生)
大宰府政庁跡(撮影:花谷美紅 東城ゼミ4年生)
2.憶良の「ひとり見つつや春日暮らさむ」
「梅花の宴」は大宰府の首席次官の以下の一首をもって幕を開く。
・正月(むつき)立ち春の来たらばかくしこそ梅を招(を)きつつ楽しき終へめ(巻5・815)
(正月になり春がやってきたなら、毎年このように梅の花を迎えて、楽しみの限りを尽くそう!)
このように宴の楽しみを前面に出す歌々の中で、山上憶良は、以下のような「梅花の歌」を詠む。
・春さればまづ咲くやどの梅の花ひとり見つつや春日暮らさむ (巻5・818)
この一首は、宴の歌として非常に違和感がある。なぜ憶良は多くの官人が楽しく集う「梅花の宴」の場で、このように「ひとり見つつや」と詠んだのであろうか? この「ひとり」とはどのような意味なのであろうか?
そこで、『万葉集』全体を概観した場合、「ひとり」は以下のような歌に多く見られることに気が付く。
・流らふる妻吹く風の寒き夜に我が背の君はひとりか寝らむ (巻1・59)
(絶え間なく横なぐりに吹きつける風の寒い今宵、いとしいあの方は、ひとりさびしく寝ていること
であろうか)
・うつせみの世やも二行(ふたゆ)く何すとか妹に逢はずて我がひとり寝む (巻4・733)
(このうつし世がもう一度繰り返されるなんてことがあるものか。かけがえのないこの夜を、あな
たに逢わぬまま、ただ一人どうして寝ることができましょう)
つまり、『万葉集』における「ひとり」は、夫婦や恋人を意識する言葉であり、愛する人(妹・君)が傍にいないことを嘆く歌に詠み込まれる言葉なのである。以上のことから、憶良の歌は、以下のように解すべきである。
春になると真っ先に咲く庭前の白い梅の花、この貴高い花は、私の愛するあの人にぜひとも見せたい花ではあるが、それもかなわず、ただ一人見ながら春の日を暮らすことであろうか。
では、なぜ、憶良はこのような歌を「梅花の宴」で詠んだのであろうか?
 山上憶良歌碑(太宰府市役所前)(撮影:東城敏毅)
山上憶良歌碑(太宰府市役所前)(撮影:東城敏毅)
3.「梅花の宴」における旅人と憶良の心の共鳴
実は、憶良は白い梅園を前にして、旅人の心境に立って、「思う人の歌」を詠じたのではないだろうか。旅人は、大宰府において、ともに伴ってきた最愛の妻を亡くした。その旅人の悲しみ、妻を想う心情を歌に託したのが、憶良歌ではなかっただろうか。
漢籍の世界を、都から遠い筑紫の場においても官人たちは共有した。ただし、単に漢籍の輸入、漢籍の応用としてみるだけではこの宴の意味は失われる。旅人が大宰府において妻を亡くした悲しみを、憶良はそれとなく歌に詠み込み、旅人の心に寄り添った。そして、それは、宴に参加している官人たちにも共有できた心境であったはずである。このような心と心との共鳴、これこそが、「筑紫歌壇」の重要な意味であると考えられるのである。
旅人は、大宰府で妻を亡くした際、
・世の中は空しきものと知る時しいよよますます悲しかりけり (巻5・793)
と絶唱し、また大宰府から都に帰還する際にも妻を想う歌を多くしたためた。
・鞆(とも)の浦の磯(いそ)のむろの木見むごとに相見し妹は忘らえめやも (巻3・447)
都に戻り、かつての家に戻ってからも、妻への思いは続く。
・人もなき空しき家は草枕旅にまさりて苦しかりけり (巻3・451)
・我妹子(わぎもこ)が植ゑし梅の木見るごとに心咽(むせ)せつつ涙し流る (巻3・453)
(いとしいあの子が植えた梅の木、その木を見るたびに、胸がつまって、とどめなく涙が流れることよ)
奈良の故郷において妻が植え、そして愛しんだ「梅の木」、その「梅の木」を、妻を亡くした旅人が、大宰府の「梅花の宴」において思い出さなかったはずはないだろう。
憶良は、その旅人の心にそっと寄り添ったのである。
 太宰府天満宮の飛梅(撮影:花谷美紅 東城ゼミ4年生)
太宰府天満宮の飛梅(撮影:花谷美紅 東城ゼミ4年生)
画像の無断転載を禁じます。