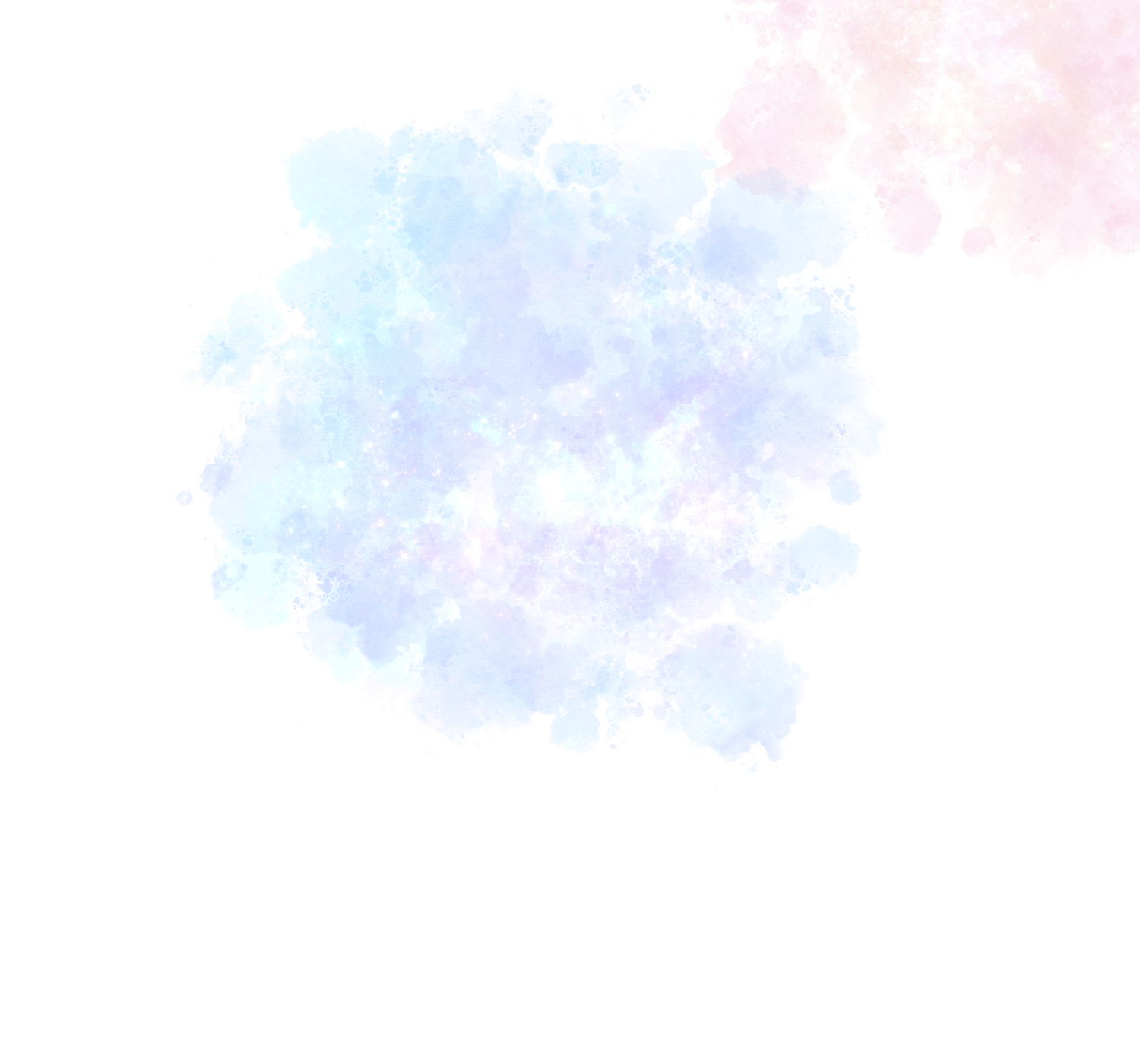本学科の授業科目「文学創作論」では、履修生が1年をかけて作り上げた作品をまとめて、文集を発
行しています。
ここでは、第12集『こころ』(2014年度)より、1作品をご紹介します。
文集は、オープンキャンパスなどでご希望の方にお頒ちしております。機会がありましたらぜひお手
にとってみてください。
夢のくりーむぱん
作・橋目あかり
「ごめん、今日、くりーむぱん売り切れなんだ」
ふいに背後からかけられた優しい声。意識がぐんっと現実に引き戻される。振り向くと、真っ白なコック服が目に映った。目線を上に向けると、人の良さそうな茶色い瞳。なんだ、びっくりした......。声の主が見知った顔であると分かって、私はほっと息をついた。
「優介、驚かさないでよ」
驚いた顔のまま見上げると、声の主は申し訳なさそうに頭をかいた。私より二十センチは高い位置で、茶色い髪がふわふわ揺れる。
「ごめんごめん。あまりにも長い時間立ってるから。声かけた方がいいかなぁって」
長い時間? 不思議に思って店内にある時計を見ると、ここに来てから十五分が経っていた。少なくとも十分はこの場所に立っていたことになる。今は人が少ないから、幸いにも邪魔になっていたということはなさそうだ。それにしても、十分間もひとつのトレーの前から動かないなんて......、我ながらちょっと怖い。
「さっき十個まとめて欲しいっていう人が来てね。歩美ちゃん来るって分かってたら、僕、取っておいたんだけど......」
なぜか優介が悲しそうな顔をする。優介の落ち込んだ顔はちょっと子犬に似ている。この顔を見ると、私の方が慰めなきゃという衝動に駆られるのだ。私は急いでぶんぶんと首を振った。
優介は、ここ【ベーカリーまき】の店主、牧さんのひとり息子だ。将来、自分のパン屋を持つことが夢らしい。専門学校でパン作りの勉強をしながら、休みの日はここでパンを作るお手伝いをしている。私が生まれて十四年、まきが生まれて二十年。親の代からこの店にお世話になっている私にとって、優介は幼馴染みたいな存在だ。胸に付けた名札の「修行中!」という可愛い文字が目に入って、思わず顔がほころんだ。
「代わりにこの『スペシャルイチゴデニッシュ』はどう? 今日から発売の期間限定品! しかも、今なら作り立てだよ」
お詫びに、そう言って優介が指さす先には「ただいま出来立て!」という札の後ろで、きれいに整列したイチゴデニッシュ。赤いイチゴジャムがきらきら光って、宝石みたいだ。漂うバターとイチゴの香りに刺激されたのか、私のお腹は容赦なく音を鳴らした。
「......いただきます」
「オッケー。ここで食べていくでしょ?」
お腹の音は聞こえなかったのか、それとも聞かなかったことにしてくれたのか。無言でうなずく私を見て、慣れた手つきでトレーにデニッシュを乗せてくれた。
ゆっくりしていってね、と店の奥に戻っていく優介を見送って、私はさっきまで自分が凝視していた方向へと視線を戻す。何も乗っていないトレーの前に、札が二つ立っている。「まき特製! 幸せのくりーむぱん」「本日は完売しました」
見慣れない二つ目の札。幸せのくりーむぱんは、私がこの店に来た時に、必ず買っているパンだ。私が世界で一番好きなパンでもある。まき一押しのパンだけど、その分たくさん作っていて、売り切れというのは今までに見たことがなかった。「完売」の文字、いつもと違う空っぽのトレーに自然と目がいく。だんだんと心がざわめくのが分かった。胸を支配する焦燥感。心がいきなりからっぽになった、みたいな。この感じ、覚えがある。私はさっきまでいた学校での出来事を思い出していた。
「今回の作文のテーマは『将来の夢』です」
始まりはこの一言。やっと授業が終わった後のホームルームの時間だった。それまで、隣同士で話す女子やちょっかいを掛け合う男子の声で騒がしかった教室が担任の一言でしん、と静まった。
「君達も来年から三年生ですからね。自分の将来について、しっかり考えてみてください。期限は一週間。ちなみに、発表もしてもらいますよ~」
間延びした担任の声。「発表」という言葉に、「え~」とか「期限早いよ」とかあちこちで非難の声が上がっている。かくゆう私も、心の中で「また作文か」と文句を言った。
うちのクラスの担任は、「作文課題の好きな先生」として校内でも名が通っている。文句を言われることには慣れているのか、涼しい顔で「頑張ってくださいね~」とスルーしていた。
ホームルームが終わった後、教室はさっき出た課題の話で持ち切りだ。いつも以上にがやがやしている。
将来の夢だって。お前決まってんの? 実は俺......、大富豪になりたくて! ギャハハハハ。教室の後ろで、お茶らける男子。
由紀は保母さんになりたいんだよね? うん! 愛は警察官だっけ? 隣の席に集まって、真面目に話し合う女子。
作文の話題が満ちる教室と同じように、私の頭も作文課題のことでいっぱいだった。私は、将来の夢が決まっていない。
将来について、まったく考えていないわけじゃない。進学したい高校は決まっているし、そこに受かるための勉強だって、それなりにしている。でも、将来の「夢」となると話は別だ。そんな先の話、正直まだ想像できない。希望の高校は、どんなものになりたくなっても大丈夫なように、公立高校の普通科。
教室の声を拾いながら、何を書こうか、考えをめぐらせる。頭の中には隣で話している女子の会話が残っていた。
でも、私はそこまで焦っているわけじゃなかった。将来の夢なんて、今はなくても大丈夫。慌てる必要なんてない。心の奥深くに居座る安心感。これにはちゃんと理由があった。
突然、後ろから肩を叩かれる。顔を見なくても誰か分かった。
振り向くと、不安そうに私を見つめる二つの瞳。長い前髪がうつむき気味の顔の角度と相まって、瞳を隠してしまいそうだ。
「歩美ちゃん、まだ帰らないの?」
風に消えそうな小さな声。彼女の登場に心の奥にある安心感は、少しずつ顔を出す。
隣のクラスの幼馴染、木山沙織。彼女が私の安心感の理由だ。
「また作文かぁ。本田先生も好きだねぇ」
学校からの帰り道、坂道に映る二つの影が揺れている。のんびりとした沙織の声が二人だけの世界に響く。私から、作文課題のことを聞いた沙織の影は、さっきからせわしなく右手で長い髪の毛をふにふにといじっていた。これは小さいころからの沙織の癖だ。集中している時や考え事をしている時によく見る気がする。いったい何を考えているのか、小石を蹴り進めながら、ぼんやりと考えた。
沙織とは、幼稚園に入る前からの付き合いだ。母親が高校時代からの友達で、家も隣同士の私たちは、お互いに家族同然の存在として育ってきた。優しくて友達思いののんびり屋。良いところがいっぱいある沙織だけど、彼女には驚くほど決断力がない。学校、洋服、通学鞄、さらにはカフェで頼む飲み物まで!
沙織は常に私の後を追ってきた。隣を見ると、常に私の少し後ろを歩く沙織が目に入る。小学校の時、後ろを歩くことを禁止したのに、とうとう私より前に出ることができなくて大泣きした沙織の顔を思い出した。
「テーマは将来の夢、だって。沙織だったらなんて書く?」
ちょっと意地悪な質問。沙織から将来の話なんて聞いたことがない。クラスの女子の話を聞いて、やっぱり少し焦っていたのかも。
そんなの、まだ、わかんないよ、そんな沙織の答えを聞いて、早く安心感を確かなものにしたかった。
私もだよ、ねぇ、これから一緒に考えようよ、そう言って、いつもみたいにどちらかの部屋で夜までおしゃべりするつもりだった。
視線を向けると、沙織の顔が真横にある。
「私は、飼育員って書くよ」
一瞬の沈黙。向かい合った私たちの間を、冷たい風が通り抜けた。
え、なに、飼育員って、沙織が? 頭に波打つ衝撃に言葉がなかなか出てこない。
「......え、なんで」
やっとのことでひねり出した言葉がこれだ。沙織はたどたどしく、でも、私の目をしっかり捉えて話し出した。
「私、昔から、動物が好きだったから。好きなことなら、頑張れるって、思ったから」
ひゅうっ。風が、心を通り抜けた。沙織が動物好きなのは知っていた。でも、飼育員になりたいなんて、初めて聞いた。なんで話してくれなかったんだろう。風に吹かれた心は、温度をなくしていく。私は耐え切れなくなって下を向いた。
「歩美ちゃん」
でも、沙織の言葉ですぐに上を向く。この時見た沙織の瞳はまっすぐで、私の知っている沙織じゃないみたいだった。
「歩美ちゃんは、なんて書くの?」
答えられなかった。沙織に、置いて行かれた気がした。
あの後、今日はどっちの家で話そうか、といつものように切り出す沙織に今日はごめん、とだけ告げて、私はすぐにまきに向かった。無性にここのくりーむぱんが食べたかった。いつもの時間、いつもの席で、牧さんと優介の会話を聞きながら。
会計を済ませて、店の奥にあるカフェスペースに向かう。今日はいつもより人が少ない。窓から射す夕日を受けたテーブルが寂しそうだ。
私はいつも自分が来た時に座る一番窓際の席に座った。夕暮時のこの席は、差し込んだ夕日が体に降り注いで暖かい気持ちにさせてくれる。私のパワースポットだ。ふぅっと息を吐いて店内を見渡す。
トレーに乗った個性的なパン達は、そのほとんどが食べたことのあるものばかりだった。
店の奥から、牧さんのどっしりとした低い声が聞こえる。牧さんは幸せのくりーむぱんをはじめ、こんなに可愛くて美味しいパンを作ってるとは思えないほどの強面だ。本人には絶対言えないけど。昔かたぎで頑固者の牧さんと、ふんわり、マイペースな優介。全然似てないのに不思議と仲が良い二人の会話は、いつも私の心を癒してくれる。
いつもの時間、いつもの店内、いつもの会話。でも......。
私は手元に視線を移した。お皿の上には、夕日に照らされてオレンジ色になったスペシャルイチゴデニッシュ。一番の目的だったくりーむぱんは、目の前にない。何だかくりーむぱんにまで置いて行かれた気がして、悲しくなった。鼻の奥がつんとする。
泣き出してしまう前に、私は急いでイチゴデニッシュを口に運んだ。
サクッ。デニッシュが軽い音を立てる。生クリームの甘さとイチゴの酸っぱさが口の中で絡み合う。食べた後、爽やかな酸味が駆け抜けた。美味しい。素直にそう思った。
でも、やっぱり「くりーむぱん」じゃない。イチゴデニッシュは美味しかったけど、胸のざわめきは治まらなかった。
今日は、もう帰ろう。テーブルの脇に置いてある【パンノート】に手を伸ばす。
パンノートは、牧さんがお客さんの声を聞くために店内に置いている、ここのパンの感想を自由に書いていいノートだ。私はこの店でパンを食べた時には、必ずこのノートに感想を書くようにしている。最後の書き込みは二日前の私。その下に、今日のイチゴデニッシュの感想を書き連ねた。
「デニッシュのサクサク感がとても美味しかった。生クリームが少し多い。イチゴと同じくらいがいいかも」
書いていると沙織の顔が頭に浮かんだ。相変わらずざわざわと騒がしい頭の中で、細い、でも、しっかりと耳に残ったあの声がこだまする。
『動物が、好きだから。好きなことなら、頑張れるって思ったから』
好きなこと、好きなもの。静かに目を閉じて、考えを巡らせた。
まず、私はパンが好きだ。パンばかり食べる私を見て、親にパン屋になればと言われたこともあったけど、私が好きなのはパンを食べることだ。作ることじゃない。
次に好きなこと。それは、文を書くことだった。ゆっくりと開いた目が、自然とパンノートを捉えていた。私は自分の感じたことを文章で人に伝えることが好きなのだ。雑誌の編集者や広告のキャッチコピーライターになって、もっとたくさんの人たちにこのパンの美味しさを伝えられたら、と思ったことは何度もある。でも、これまでに書いた弁論文や読書感想文はことごとく落選。賞を取ったのは、クラスでも文を書くのが上手いと評判の子ばかりだ。私には才能がないんだと、それを夢にする勇気はなかった。
頭の中に漂う原稿用紙。もし、将来の夢が決まってないのが私だけだったら、どうしよう? 一度浮かんだ考えは、なかなか頭から離れない。私を置いて周りがどんどん変わっていく気がした。
「歩美ちゃん?」
突然の声に驚いて、勢いよく顔を上げた。柔らかい茶色の瞳と目が合う。
「優介」
「また、驚かせちゃったね。ごめん、ちょっと頼みたいことがあって」
そう言って照れくさそうにはにかむ優介は、きれいなドーム型のパンが乗ったお皿を持っていた。
「......クリームパン?」
「当たり! さすが歩美ちゃん、よく分かったね!」
優介は嬉しそうに指を鳴らした。持っているクリームパンは幸せのくりーむぱんじゃない。平たくて軽いのが特徴のくりーむぱんに比べて、このクリームパンはまん丸のドーム型。てっぺんに乗せられたアーモンドスライスもくりーむぱんにはない特徴だ。
優介は、なぜか軽く深呼吸をして、ぽつりぽつりと話し出した。
「実は、僕、来月からフランスに、パンの勉強をしに行くことが決まってるんだ」
ひゅうっ。また心に風が吹く。優介も、私から離れて行ってしまうのか。
おめでとう、と言うべきところで声が出ず、そのまま俯いてしまった。優介は気にならなかったのか、話を続ける。
「でね、向こうに行く前に、自分のオリジナルパンをひとつ作ろうって思って、最近練習してたんだけど......。今日完成したのが、このクリームパンなんだ」
そう言ってお皿を私に近付けた。小麦の良い香りがする。優介はコホン、と小さく咳払いをした。
「歩美ちゃんには、良かったら、このパンの名前を考えてもらいたいんだよ!」
後半は一気に言い切った。いつもと違う真剣な眼差しが、がっしりと私の瞳を捉えている。
「わ、私が? 牧さんの方が適任なんじゃ」
「僕は、歩美ちゃんにお願いしたいんだよ」
これまた言い切った。優介の初めてのオリジナルパンに名前を付けるなんて、と気が引けたが、まだ私から離れない二つの熱い瞳に押されて覚悟を決めた。
「食べてもいいの?」
頷く優介から、パンを受け取る。ずしっ。想像したより五倍は重い。いったい何グラムのクリームが入ってるんだとドキドキした。
小麦の香りを堪能しつつ、ゆっくりとパンを口に運ぶ。
ぱくっ。ふわっ。ぶわあっ。
ふんわり柔らかい生地を破ると、中から一気にクリームが溢れ出す。口の中に納まりきらない量のクリーム。私は夢中で格闘した。
隣から優介の視線を感じる。緊張しているのか、私の隣に座って、手をギュウッと膝の上で握りしめていた。
もぐもぐ。ごくん。やっとのことでパンとの格闘を終えた。幸せのくりーむぱんに比べて、クリームが多くて、甘ったるい。でも、その多過ぎるクリームの量は、パンを持った瞬間に、このパンの中にはどんなものが詰まっているんだろう、と最高にわくわくさせてくれる。ふわふわの生地の中からクリームが溢れ出る瞬間、口いっぱいに広がるバニラビーンズの甘さに、思わずにんまり笑顔になる。
「夢の、くりーむぱん」
「......え?」
無意識にこぼした言葉を優介が拾い上げた。「えっと、パンを食べた瞬間が、夢がいっぱい詰まった宝箱を開ける瞬間みたいだなって思ったから......。だめ、かな?」
あごに手を当てて、じっくりと考え込む優介。言った瞬間から、顔が熱くてたまらない。やっぱり牧さんに頼むべきだったんだ。
「......いい」
ぼそりと呟いたその言葉に、今度は私が首を傾げた。優介はいつの間にか立ち上がって、興奮している。
「いい! すごく良いよ! 僕の『夢』が詰まったパンっていうのとも掛かってて最高! やっぱり歩美ちゃんに頼んで良かったなぁ」
「えっ」
僕の「夢」が詰まったって部分も気になるけど、もっと気になったのはその後だ。やっぱりって......。
「僕、一時期パン作りが全然上手くならなくて落ち込んでたんだ。好きだからって始めた道だけど、才能無いからもう辞めようって、本気で考えてた」
私の胸の音は、優介の言葉に合わせてどんどん大きくなっていく。
「でも、そんな時パンノートの歩美ちゃんの書き込みを見たんだ。僕の担当したパンについて、すごく細かく書いてくれてた、良い点も悪い点も。僕、最後に書いてあった『次が楽しみ』って言葉がすごく嬉しかった。君にもっと美味しいパン食べさせてあげようって、元気が出たよ。それから、こう思うようになったんだ」
ゆっくりと言葉を繋ぐ優介。その目はまっすぐ前を見据えていた。
「好きなら、才能なんか気にせずに、とにかくがむしゃらに頑張ってみようってね。それで、もし僕のオリジナルのパンができたら、絶対歩美ちゃんに命名をお願いしようって決めてたんだ」
話し終えてこっちを向いた優介の笑顔は、なんだかいつもより大人びていて、私の知っている優介じゃなかった。でも、胸のざわめきはもう起こらない。全然知らなかった。私の言葉で笑顔になる人がいるなんて。
頭に浮かび上がるのは、沙織の言葉と優介の笑顔。
『好きなことなら頑張れる』
原稿用紙の入った鞄にそっと手を置いた。思い描く、パンノートをモデルにした雑誌。それを作る私。笑顔になる人々。もう、大丈夫。そう心の中で呟いて、私の未来に夢を馳せる。進んでいく世界に不安じゃなく、希望を抱きながら。
※ 作品の無断転載を禁じます。