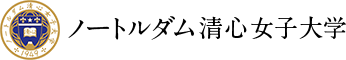2012.04.12
本学科の授業科目「文学創作論」では、履修生が1年をかけて作り上げた作品をまとめて、文集を発
行しています。
ここでは、第9集『六花集』(2011年度)より、1作品をご紹介します。
文集は、オープンキャンパスなどでご希望の方にお頒ちしております。機会がありましたらぜひお手
にとってみてください。
孤独なクラウニー
作・柆田とも子
行しています。
ここでは、第9集『六花集』(2011年度)より、1作品をご紹介します。
文集は、オープンキャンパスなどでご希望の方にお頒ちしております。機会がありましたらぜひお手
にとってみてください。
孤独なクラウニー
作・柆田とも子
私、岸本佐奈が初めて彼に会ったのは、コンビニでバイトをしていたとき。九月下旬から始めたバイトだから、まだ働き出して二週間しか経っていない十月最初の水曜日のことだった。私の通っている水沢高校の制服を着た男子軍団――名前は分からないけど、同じ一年だっていうのが、中にいた目立つ系のやつ二人で分かった――が店に入ってきて、私はちょっとげんなりしていた。多分、七、八人で来ていたと思う。二つあるレジのむこうとこっちとに、半々に分かれて並ばれて、私はなるべく目を合わさないように接客していた。前三人をやりすごし、やっと最後だと思って、「いらっしゃいませー」って無機質に応対したら、「あれ?」って。本当に不思議そうだったその声に思わず顔を上げたら、ばっちり目が合ってしまって、焦った。むこうも焦ったらしい、切れ長の目ではにかんだように笑って、あわててカウンターにお金を置いた。私の手の中で宙ぶらりんになっていた紅茶のペットボトルをひょいとつかみ、「ありがと」って、仲間の待っている外へ、走っていった。
集団の中で、ただ一人だけお礼を言ってくれた彼のことを、私はそれまで知らなかった。初めて会った日から五日経った月曜日の昼休みに、高校の二階の廊下で、私は彼とすれちがった。一対一で、ではない。
私は一人で、むこうは四人グループでやってきて、そのとき仲間の一人に彼が「アサクラ」って呼ばれているのを聞いた。私は、図書室へ本を返し、三階の一年四組の教室へ戻るところだったのを、一階の下駄箱まで駆けおりた。一年一組から六組までの下駄箱を全部回って、アサクラ姓を探す。幸い、アサクラくんは一人しかいなくて、一年六組で、朝倉佑樹だった。佑樹の佑と、佐奈の佐は似ていた。右と左で、となりどうしだと思った。ただそれだけのことなのに、前よりもっと、朝倉くんへと心が動いた。
とどめは、ギターまで弾けてしまう朝倉くんを見たときだ。十月二十四日、土曜日。高校入学して初めて迎えた文化祭の軽音部のステージで、仲間と一緒にのびのびと、ときおり、切れ長の目をくしゃっと笑わせながら演奏している朝倉くんは、かっこよかった。演奏している曲は、私の知らない曲だった。でも、朝倉くんがコピーバンドを組んでいるようなバンドの音楽、もしくはオリジナルの音楽だと思えば、自然と体はリズムにのって、心が跳ねた。
一バンドの持ち時間は準備、片づけを含めて十五分と短い。あっというまに三曲が終わり、朝倉くんたちは舞台袖にひっこんでしまった。まだまだ、朝倉くんの演奏を聞いていたい。じゃあ、もっと聞いているために、私は何をすればいい? 本人に告白する勇気も自信も、今の私にはない。問いかける胸の内に、軽音部に入ってしまえばいいという考えが浮かんだ。人前に出るのは苦手なのに。ピアノのレッスンすら、まともに練習しなかったから先生に怒られて、嫌になって、結局、小学三年生から二年足らずでやめちゃったくせに。こんな私が、軽音部へ入る? どう考えたってありえない。ありえないけど。こんなことを本気で考えだすほどに、私は朝倉くんが好きなんだなということだけは、痛いほど分かった。
季節は十一月を迎え、寒さもいよいよ本格的になってきた。十一月最初の水曜日の放課後、他のクラスより少し長めの帰りのホームルームが終わってすぐ、私は廊下に出た。廊下といっても室内じゃなくて、ベランダみたいな廊下だ。我が一年四組の教室があるのは三階。朝からお天気のよかった今日は、期待通り、マーマレードみたいな夕焼けに会えた。廊下の手すりに頬杖をつき、目を閉じる。バイトに行くまでのしばらくの間、オレンジ色の優しい光を感じて、充電。背後を行く騒がしい声も足音も気にならなくなったとこで、そっと目を開けたら、眼下の、昇降口出てすぐのところに朝倉くんが立っていた。意識がとたんに、りんとする。
ズボンが腰まで下がってるやつとか、けたけた笑いで、髪の毛ワックスで固まってるようなやつとかに囲まれている中で、朝倉くんは一人、しゅっとしていた。落ち着いた面差しに、深緑のマフラーがよく似合う。制服も変に着崩していない。髪の毛だって、そこまで手を入れた様子もなく、風まかせだった。でもそのいでたちが派手な周囲から浮くこともなく、調和している。外見だけじゃない。輪の中心で楽しそうにしているところを見れば、あれは一目置かれているってやつだ。違うのに、浮かないこと。それができない不器用な私は、ごくごく自然に周囲となじんでいる朝倉くんを、ずるいと思う。そして、やっぱり好きだな、と思う。
「ちょっとちょっと、お嬢さん。だれを見てんの?」
ひょいっと、となりにみっこ、ことクラスメイトの瀬戸美智子がやってきた。みっことは、高校に入学してから知り合った仲だ。彼女には、私が朝倉くんに初めて会ったころくらいに、美術部の一つ年上の彼氏ができた。曰く、文化祭でやる展示の準備や運営を、一緒にがんばったことで仲が深まり、つきあうことになったんだとか。打ち明けられたときは正直、おいてけぼりにされたショックで心が痛かったけど、祝福しないわけにもいかない。たわいもない話をしたり、昼休みに一緒にお弁当を食べたりしてくれるのは、クラスにみっこ一人だけだから。邪険になんて、できるはずがない。嘘をつくのもおかしいから、私は黙って、朝倉くんを指さした。
「へーえ?」
「ほんとに分かってる?」
「もち。佐奈の好みは、バックビーの在原さん。ソースより、きりっとしたしょうゆ。あの集団の中で条件を満たしてるのは、緑のマフラーの彼。当たり?」
バックビーというのは、バックビートメイジャーズというアーティストの略称で、みっこと私の好きなバンドだ。在原というのは、そのバックビーのギターボーカルのこと。そこまで好みのタイプを明言した覚えはないから、恐れ入るしかない。ちらっと八重歯をのぞかせて、みっこは笑った。
「当たりだ」
「いじわる」
「あはは、佐奈、かわいい! ・・・・・・で。どーなんだい」
「なにが」
「告白よ、告白」
「しないよ。てか、できない」
「えー、なんでよ。佐奈、見せてくれたじゃん。こないだの体育祭のリレーで、ゆうゆうとしたゴボウ抜き。元陸上部のあの勢いで、ほれっ」
背中をぽんぽん叩いてくるみっこに、私は、ちろっと目を向けた。
「も、いいよ。やめよう、この話。走るのと恋愛は、違うって」
「違わないって! あんな感じの勢いで行けばいいよ、恋愛も。佐奈ならできる。うん」
言い切ったみっこの横顔に、かわいいえくぼが浮かんでいる。しらけてしまった私は、反射的に腕時計を見た。十六時四十五分。バイトは十七時から。駐輪場まで行かなきゃいけないことや、信号にかかってしまうことを考えると、あと十五分は、ちょっときつい。下を見ると、朝倉くんたちも、もういなくなっていた。
集団の中で、ただ一人だけお礼を言ってくれた彼のことを、私はそれまで知らなかった。初めて会った日から五日経った月曜日の昼休みに、高校の二階の廊下で、私は彼とすれちがった。一対一で、ではない。
私は一人で、むこうは四人グループでやってきて、そのとき仲間の一人に彼が「アサクラ」って呼ばれているのを聞いた。私は、図書室へ本を返し、三階の一年四組の教室へ戻るところだったのを、一階の下駄箱まで駆けおりた。一年一組から六組までの下駄箱を全部回って、アサクラ姓を探す。幸い、アサクラくんは一人しかいなくて、一年六組で、朝倉佑樹だった。佑樹の佑と、佐奈の佐は似ていた。右と左で、となりどうしだと思った。ただそれだけのことなのに、前よりもっと、朝倉くんへと心が動いた。
とどめは、ギターまで弾けてしまう朝倉くんを見たときだ。十月二十四日、土曜日。高校入学して初めて迎えた文化祭の軽音部のステージで、仲間と一緒にのびのびと、ときおり、切れ長の目をくしゃっと笑わせながら演奏している朝倉くんは、かっこよかった。演奏している曲は、私の知らない曲だった。でも、朝倉くんがコピーバンドを組んでいるようなバンドの音楽、もしくはオリジナルの音楽だと思えば、自然と体はリズムにのって、心が跳ねた。
一バンドの持ち時間は準備、片づけを含めて十五分と短い。あっというまに三曲が終わり、朝倉くんたちは舞台袖にひっこんでしまった。まだまだ、朝倉くんの演奏を聞いていたい。じゃあ、もっと聞いているために、私は何をすればいい? 本人に告白する勇気も自信も、今の私にはない。問いかける胸の内に、軽音部に入ってしまえばいいという考えが浮かんだ。人前に出るのは苦手なのに。ピアノのレッスンすら、まともに練習しなかったから先生に怒られて、嫌になって、結局、小学三年生から二年足らずでやめちゃったくせに。こんな私が、軽音部へ入る? どう考えたってありえない。ありえないけど。こんなことを本気で考えだすほどに、私は朝倉くんが好きなんだなということだけは、痛いほど分かった。
季節は十一月を迎え、寒さもいよいよ本格的になってきた。十一月最初の水曜日の放課後、他のクラスより少し長めの帰りのホームルームが終わってすぐ、私は廊下に出た。廊下といっても室内じゃなくて、ベランダみたいな廊下だ。我が一年四組の教室があるのは三階。朝からお天気のよかった今日は、期待通り、マーマレードみたいな夕焼けに会えた。廊下の手すりに頬杖をつき、目を閉じる。バイトに行くまでのしばらくの間、オレンジ色の優しい光を感じて、充電。背後を行く騒がしい声も足音も気にならなくなったとこで、そっと目を開けたら、眼下の、昇降口出てすぐのところに朝倉くんが立っていた。意識がとたんに、りんとする。
ズボンが腰まで下がってるやつとか、けたけた笑いで、髪の毛ワックスで固まってるようなやつとかに囲まれている中で、朝倉くんは一人、しゅっとしていた。落ち着いた面差しに、深緑のマフラーがよく似合う。制服も変に着崩していない。髪の毛だって、そこまで手を入れた様子もなく、風まかせだった。でもそのいでたちが派手な周囲から浮くこともなく、調和している。外見だけじゃない。輪の中心で楽しそうにしているところを見れば、あれは一目置かれているってやつだ。違うのに、浮かないこと。それができない不器用な私は、ごくごく自然に周囲となじんでいる朝倉くんを、ずるいと思う。そして、やっぱり好きだな、と思う。
「ちょっとちょっと、お嬢さん。だれを見てんの?」
ひょいっと、となりにみっこ、ことクラスメイトの瀬戸美智子がやってきた。みっことは、高校に入学してから知り合った仲だ。彼女には、私が朝倉くんに初めて会ったころくらいに、美術部の一つ年上の彼氏ができた。曰く、文化祭でやる展示の準備や運営を、一緒にがんばったことで仲が深まり、つきあうことになったんだとか。打ち明けられたときは正直、おいてけぼりにされたショックで心が痛かったけど、祝福しないわけにもいかない。たわいもない話をしたり、昼休みに一緒にお弁当を食べたりしてくれるのは、クラスにみっこ一人だけだから。邪険になんて、できるはずがない。嘘をつくのもおかしいから、私は黙って、朝倉くんを指さした。
「へーえ?」
「ほんとに分かってる?」
「もち。佐奈の好みは、バックビーの在原さん。ソースより、きりっとしたしょうゆ。あの集団の中で条件を満たしてるのは、緑のマフラーの彼。当たり?」
バックビーというのは、バックビートメイジャーズというアーティストの略称で、みっこと私の好きなバンドだ。在原というのは、そのバックビーのギターボーカルのこと。そこまで好みのタイプを明言した覚えはないから、恐れ入るしかない。ちらっと八重歯をのぞかせて、みっこは笑った。
「当たりだ」
「いじわる」
「あはは、佐奈、かわいい! ・・・・・・で。どーなんだい」
「なにが」
「告白よ、告白」
「しないよ。てか、できない」
「えー、なんでよ。佐奈、見せてくれたじゃん。こないだの体育祭のリレーで、ゆうゆうとしたゴボウ抜き。元陸上部のあの勢いで、ほれっ」
背中をぽんぽん叩いてくるみっこに、私は、ちろっと目を向けた。
「も、いいよ。やめよう、この話。走るのと恋愛は、違うって」
「違わないって! あんな感じの勢いで行けばいいよ、恋愛も。佐奈ならできる。うん」
言い切ったみっこの横顔に、かわいいえくぼが浮かんでいる。しらけてしまった私は、反射的に腕時計を見た。十六時四十五分。バイトは十七時から。駐輪場まで行かなきゃいけないことや、信号にかかってしまうことを考えると、あと十五分は、ちょっときつい。下を見ると、朝倉くんたちも、もういなくなっていた。
「・・・・・・じゃ、私、そろそろバイトだから。行くね」
「あ、そっか、今日水曜! がんばってね」
「ありがと。じゃあ、また明日」
「バイ」
みっこがひらっと手をふったのが視界のすみに見え、私が階段を下りようと背を向けたとき、「ミチ
コ~、ちょっといい?」って、教室の中から、クラスメイトがみっこを呼んでいる声が聞こえた。「うん」ってのんびり答えたみっこを、みっこと呼ぶ人は私の他にはいない。ミチコになったみっこは、私の手の届かないところに行ってしまうような気がしている。みっこのクラスでの立ち位置は特殊だ。なんというか、はみだしていても端正だ。
私が彼女と最初に会ったのは、今年の四月のこと。始まりは、一冊の音楽雑誌だった。その表紙がバックビーだったっていうのもある。でも、なにより私が惹かれたのは、入学して最初のホームルームが終わってすぐ、それを開いていた彼女が堂々としていたことだ。思わず声をかけたら、彼女もバックビーが好きだと分かり、盛りあがった。以来、学校でのお弁当やらトイレやら、日常のことを共にする仲良しになった。みっこは、つるまない。私も、つるまない。でも私には、クラスのみんなとの間に、透明だけど堅固な壁ができている。みっこは、みんなに一目置かれている。みっこはどうして私みたいな本当のはみだしものと、一緒にいてくれるんだろう。そのあたりをみっこから聞きだす勇気が、私にはなかった。
たいていの人は、日々の学校生活の中に、ごくごく自然に、自分の本質を示していくことができる。でも、私はそうじゃない。臆病なせいで、本質が表われるどころか、すり減って、埋もれていっているように感じる。いまいち、自分を生かしきれていないようで嫌だけど、集団に染まってしまうのも嫌だ。みんなとは、住む世界が違うんだから仕方ないって思うことにしている。
階段を駆けおり、渡り廊下を抜け、下駄箱で靴をはきかえる。杏色のマフラーをくるくると巻き、かばんを持ち、駐輪場に走る。赤信号にひっかからなかったおかげで、バイトの開始時刻にぎりぎり間に合った。自転車を停め、店に飛び込むと、無機質なドアチャイムと明るいあいさつに迎えられた。
「いらっしゃいませこんにちはー」
「おつかれさまです」
「あー、岸本さん。おつかれ」
レジの点検をしていた千葉さんが笑った。彼は、毎週水曜日と木曜日の十七時から一緒に働く相方だ。両日とも二十時までの私と違い、フリーターの千葉さんは、水曜の今日は二十四時までがんばっているらしい。
学生やサラリーマンの帰宅時間に当たる、十八時から十九時の時間帯は忙しい。さっきも、水沢高校の男子生徒の集団が来て、ひとしきり騒いでやっと帰ってくれた。朝倉くんは、あの日以来、来ていない。私のシフトの時間に来ていないだけかもしれないのに、あわてたように走っていった背中を思い出しては、幸せな空想にひたっていた。
「あー。暇だ」
店内を見て回っていた千葉さんが、本当に暇そうにカウンターに帰ってきた。時刻は、十九時二十三分。
こうやって手隙になると、千葉さんは決まってぼやきだす。忙しいときの敏腕な風貌とは、別人みたいにだらっとして見えた。
「暇、ですか」
「うん。だって俺、これからあとまだ四時間半くらい、耐えなきゃいけないし」
「耐える」
「うん。客、あんま来なくなるから」
レジ背面の煙草の棚にもたれ、腕組みをした千葉さんが笑う。下になっている左手の薬指に、指輪の跡が浮いて、残っていた。
「耐え、ますね。はい」
「えー、なに、その間。一瞬一瞬に新しい発見とかしてるわけ?」
「いや、そういうわけでもないですけど。でも、暇って幸せだと思います」
「ひゃー! なんだ、それ」
千葉さんはけらけらと笑った。私は何がおかしいのか分からなかった。
「岸本さんさぁ」
「はい?」
「何歳だっけ?」
「十六です」
「十六ってことは、高一だろ? まだ若いんだからさ、もっとシンプルに行こうよ」
「若いって・・・・・・千葉さんこそ、まだ十九歳ですよね?」
「もうすぐハタチ。・・・・・・だめだ。なんか最近、いろいろと老いてきてるもん、俺」
「老いって! なんですかそれ」
とりとめのない会話は、ピークを外れてやってきたお客さんの波に飲まれ、中断した。老いって、なんだろう。不思議だけど深い感じがして、私は千葉さんという人がよく分からなくなった。
「じゃ、お先に失礼します。おつかれさまです」
「うん。おつかれ」
二十時を迎えて帰ることになった私に、二十四時までがんばる千葉さんが、口角のきゅっと上がった健康的な笑顔を見せた。やっぱり、千葉さんの雰囲気と、老いという言葉はどうしても結びつかなかった。
家に帰り、お風呂でひとしきり、バックビーの『孤独なクラウニー』を歌った。お風呂から出て、ドライヤーに紛れてまだ歌っていたら、洗面所の鏡が曇った。髪は乾いたということにして、ドライヤーのスイッチを切る。歌いながら、私は曇った鏡に絵を描いた。『孤独なクラウニー』に出てくる人も、最終列車に揺られながら、曇った車窓に絵を描いていく。歌の内容を要約すると、こうなる。曲の中に出てくる「私」が列車の窓に刻みつけるように描く絵はすべて、「私」自身のゆがみから来る「痛み」を投影したものだ。描くにつれ、「私」の「痛み」はどんどん大きくなっていく。「痛み」が肥大すればするほど、それを描く「私」の心もどんどん、くすんでいく。そろそろ終着駅に着くというところで、「私」が一番最初に、遠慮がちに描いた小さなピエロが動き出し、大声で泣き叫ぶ。ピエロにつられ、じわじわと糸をひいて泣き出した、たくさんの大きな「痛み」を、「私」は拭ってみる。そこには他でもない、惚けた泣き顔の「私」が映っていて、なんだ、ピエロは自分だったのかと、「私」は妙に納得してしまう。そして、そんな滑稽な自分の姿がおかしくて、最終的には笑ってしまう。
洗面所の鏡に描いた泣き顔のピエロを拭えば、そこには笑顔の私がいた。ゆがむことなしに生きるなんて不可能だ。だから、ゆがんで自分を痛めた自分を笑ってやれ。ゆがんだ自分を認めて、強くあれ。『孤独なクラウニー』には、「一人でも幸せな君であるように」という歌詞がある。これは、孤独にも種類があるんだということを教えてくれている。「一人でも」のニュアンスを変えれば、みんなの幸せを願うっていう意味にもとれるから、深い。歌って、お腹も心も温かくなった私は、二階の自室に上がった。ずいぶんご無沙汰していたキーボードのスイッチを入れる。バックビーのピアノのスコアをひっぱり出してきて、『孤独なクラウニー』の譜面とにらめっこをする。キーボードとは、こうやってちょくちょく、思い出したように向かい合っては格闘してきた。でも、すぐに面倒になるから、練習が三日と続いたためしがない。このスコアを買ったのは、中学に入ってすぐのころだったというのに、未だに一曲も弾けないのは、全部自分のせいだった。当たり前だけど、譜を読むのも運指も、たどたどしすぎて嫌になる。でも、ステージの上で楽しそうだった朝倉くんを思うと、背筋が伸びる。見えない努力を彼はしている。私は『孤独なクラウニー』を手が痛くなるまで練習した。おかげで、全部で十ページある楽譜の一ページ目だけは、まだ少しつっかえるけど、弾けるようになった。ピアノの練習を面倒に思って、さっぱりやらなかった幼いころにくらべれば、今の私は少しだけ、前に進んでいる。午前三時四十六分。疲れた体に心は満ち足りていた。夢に泣き虫ピエロが出てきそうだと思ったら、それだけで笑えて、なかなか寝つけなかった。
次の週の水曜日は、学校に遅刻してしまった。一時間目は、大嫌いな数学の授業だ。教室の後ろのドアから、目立たないようこっそり入ったけど、数学劣等生の私を、数学教師の金子先生が見逃すはずがない。授業中、先生に何かと質問をされ、恥をかかないようにするので私は精一杯だった。私の斜め前の席に座るみっこは、午前の授業中、ずっと熱心にノートをとっているなと思ったら、大作ができたって、昼休みに『孤独なクラウニー』を題材にしたイラストを見せてくれた。「クラウニー 君に王冠を 猫背なフリしたまっすぐな道化」という歌詞の横へ、列車の窓に右手と額をもたせかけ、泣きながら口許はほほえんでいる王子様みたいな人の絵が描いてあるんだけど、朝倉くんに似てる。「いる!」って言ったら、「孤独な朝クラウニー」って、にやにやしながら渡されて、つき返した。当然怒る気になんてなれない。
「孤独な朝クラウニー」の件で盛りあがりかけた放課後、みっこは彼氏に呼ばれて帰っていった。その後一人でぼんやり、教室前の手すりに頬杖をついて夕焼けを見ていたら、バイトも十分遅刻してしまった。
遅刻のツケが回ってきませんようにと願ったけど、しつこいクレーマーがやってきた。彼女は綺麗な人なのに、必ずといっていいほど、眉間にしわを寄せている。
「ねえ、どういうこと?」
本日二度目の来店。つかつかとヒールの音高くやってきた彼女は、さっき買って帰った一リットルパック
のりんごジュースをどん、とカウンターに置いて、言った。
「外出先で飲もうと思ったのよ。そしたらストローが無かった。どーやって飲めっていうの?」
「す、すみません! 外で飲むって思わなくて」
「はぁ? こっちのせいだって言うの? いい加減にしてよ!」
「すみませんっ、あの、以後気をつけます」
おどおどした私に、いらついたクレーマーが手をあげかけたとき、後ろでドリンクの発注をしていた千葉さんが飛んできて、助けてくれた。ようやく、バックルームから店長が飛び出してきたときには、事態はあらかた片づいていた。まだぷりぷりしてはいたけれど、クレーマーはようやく、ヒールの音を響かせながらひきあげていってくれた。やっぱり、こういうことがあると、落ちこむし、疲れる。列が乱れ、スカスカになっていた棚のおにぎりを整頓しながら溜め息をついたら、千葉さんに肩をぽんと叩かれた。
「あのクレーマー、頭おかしいから。気にしないほうがいいよ」
「あ、はい。ほんと、ありがとうございます」
「いえいえ。なんか言われても、基本笑顔で謝っときゃいいよ。事を荒立てないようにするのが、一番大事」
「はい、次から気をつけます。ほんとに、ありがとうございました」
お礼を言いながら、私は思い返していた。あのあくどいクレーマーが、千葉さんの笑顔に思わず、ふりあげていた手をひっこめたことを。
バイトが終わり、家に戻り、ゆっくりとお風呂につかりながら、私はひとしきり歌った。歌えば、その日あった嫌なことを忘れられる。今日なら、クレーマーのことや、放課後の別れ際に、みっこときまずい感じになってしまったこと、などなどを洗い流すように歌おう。私が歌うのが好きな理由は、もう一つある。大嫌いだったピアノの先生が、唯一、私をほめてくれた言葉が心に残っているからだ。「ピアノを弾いているときよりも歌っているときのほうが楽しそうね」という先生の言葉を、身勝手だって分かっているけど、信じていたい。
二階の自室に上がる。明日の授業の予習もそこそこに、キーボードの練習に移る。つっかえるところをしつこいくらい繰り返して、『孤独なクラウニー』の十ページ中、三ページ目の上から三段目まで、なんとかものにした。よし、今日はこのくらいにしておこう。キーボードのスイッチを切り、部屋の電気も切る。布団をかぶって、真っ暗な部屋の中、さらに真っ暗な空間を作る。プレーヤーを操作したら、画面にほわんと青い明かりが灯って、水底にいるような気分になる。午前二時五十七分。気づいたら、バックビーのアルバムを二枚、聞き終わっていた。暗闇で耳を傾けた音楽は、昼間に聞く音楽より、澄んで聞こえた。
次の週の火曜日。うっかり爆睡してしまった数学の後の昼休み、私はみっこから「後で職員室に来るようにって金子先生が言ってたよ」という衝撃的な事実を聞いた。呼び出しに、心当たりがありすぎて怖い。お弁当を食べ終え、みっこと一緒に教室を出る。みっこは校舎北棟の彼氏のもとへ。私は南棟の金子先生のもとへ。行き先の落差に苦笑しながら、私はみっこと別れた。南棟への渡り廊下にさしかかったところで顔を上げたら、この寒い中、そこでお昼ご飯を食べているつわものたちがいた。見覚えのある、ワックスで凝った作りを保っている頭たちの中に、朝倉くんの風まかせの頭がある。私は、朝倉くんの前を通ろうかどうしようか迷った。でも、ここまで来て遠回りをすれば、職員室へ乗り込んでやろうと決めた覚悟が揺らいでしまう。なるべく足早に、集団の前を通り過ぎることにした。うつむいた視界の端で朝倉くんが、ひょいと頭を下げてくれた、気がした。ふり返ろうとしたら、いきなり、わってハジけた仲間のお調子者の声が聞こえて、私は思わず逃げてしまった。南棟の入り口に駆け込んで、そっとふり返る。
だれもこっちを見ていない。よかった。でも、淡く期待もしていたから、本当は少し複雑だ。車座の中でみんなと同じようにあぐらをかいて、当の朝倉くんは、仲間と楽しそうに笑っていた。かと思えば、後ろの手すりにふいっともたれ、にぎやかなその他はどこ吹く風といった具合に、パックの牛乳をすすっていたりする。会話に参加している時間より、そうしている時間のほうが長い。「孤独な朝クラウニー」って言い得て妙だ。後でみっこに報告しよう。私は、うれしさに思わずほころぶ口許を引きしめた。一つ深呼吸をして、職員室の重い戸を、がらっと開ける。
金子先生には、授業態度も成績も残念すぎる! と、罰としてプリント三枚を渡された。でも、大丈夫、大丈夫。一人でも端正な、あの横顔を思い出せ。おかげで、ふわふわと教室に戻ってきた幸せそうなみっこを見たとき、ひがむことなく、笑って「おかえり」って言えた。
木曜日。先週の木曜日は十分遅刻、昨日のバイトも開始時刻ぎりぎりで入ったから、今日は余裕を持って早めに学校を出た。心に余裕があれば、表情も自然と柔らかくなるものなのかもしれない。「いい顔でがんばってるなあ」って常連のおじいちゃんが初めてほめてくれた。切手一枚レジに通しただけなのに、「ありがとう」ってほほえんでくれたお姉さんの笑顔には、ほっこりさせられた。いいことが続いたから、気を引きしめよう。十九時三十一分。ちょっと手隙になって、栄養ドリンクの補充をしていたら、ドアチャイムが鳴った。視界のすみに緑色が揺れる。まさか、と横目を使ったら、朝倉くんだった。ギターを背負い、深緑のマフラーを巻いて、何かをコピーしている。これから練習だろうか。制服のままってことは、もう家に帰るところなのかも。スタジオも、家も、この近く? ドリンクの補充をしながら、あまりにも朝倉くんについて知らないことが多いのに、苦笑する。
補充より、コピーのほうが早く終わった。朝倉くんがこっちに来る。
当然、横顔の私には気がつかず、ドアチャイムと共に出ていく。私は反射的に立ち上がった。コピー機に走り寄り、ふたを開けると、案の定忘れ物だ。しかも、『オールトの雲』。バックビーの最新アルバムに入っている曲のスコアだった。
「千葉さん、すみません、ちょっと忘れ物届けてきます!」
返答も聞かずに、私は外へ飛び出した。コンビニの真昼のような明るさに感謝。夜闇の中、自転車のサドルにまたがって、今にも帰ってしまいそうな朝倉くんの後ろ姿に、叫ぶ。
「あの!」
朝倉くんがふりむいた。スコアをふってみせると、「あ!」って感じに表情が動いた。自転車を降りて、引き返してくる。私も走っていって、駐車場の中ほどで落ち合う。
「うーわ、ごめんなさい。ありがとうございます」
「いえ、間に合ってよかったです。バックビー、好きなんですか?」
「え? ああ、はい。今度友達とコピーバンド組むんで・・・・・・あの」
朝倉くんは困ったように笑った。受け取ったスコアで顔を隠すようにして少し考え込んで、また笑う。
「えーっと、ごめん。同じ高校、だよね? すごい失礼で申し訳ない、顔分かるけど、名前が」
「岸本です。一年四組の、岸本佐奈」
「きしもと、さん。・・・・・・あっ。一年六組の、朝倉佑樹です」
「う、うんっ。よろしく」
「こちらこそ。よろしく」
朝倉くんの名前は、もう知っている。でも、直々に名乗ってくれたことで彼の存在感が、私の中でもっと確かなものになった。こうして近くで見ると、朝倉くんは私より、頭二つ分くらい背が高かった。
「あ、そっか、今日水曜! がんばってね」
「ありがと。じゃあ、また明日」
「バイ」
みっこがひらっと手をふったのが視界のすみに見え、私が階段を下りようと背を向けたとき、「ミチ
コ~、ちょっといい?」って、教室の中から、クラスメイトがみっこを呼んでいる声が聞こえた。「うん」ってのんびり答えたみっこを、みっこと呼ぶ人は私の他にはいない。ミチコになったみっこは、私の手の届かないところに行ってしまうような気がしている。みっこのクラスでの立ち位置は特殊だ。なんというか、はみだしていても端正だ。
私が彼女と最初に会ったのは、今年の四月のこと。始まりは、一冊の音楽雑誌だった。その表紙がバックビーだったっていうのもある。でも、なにより私が惹かれたのは、入学して最初のホームルームが終わってすぐ、それを開いていた彼女が堂々としていたことだ。思わず声をかけたら、彼女もバックビーが好きだと分かり、盛りあがった。以来、学校でのお弁当やらトイレやら、日常のことを共にする仲良しになった。みっこは、つるまない。私も、つるまない。でも私には、クラスのみんなとの間に、透明だけど堅固な壁ができている。みっこは、みんなに一目置かれている。みっこはどうして私みたいな本当のはみだしものと、一緒にいてくれるんだろう。そのあたりをみっこから聞きだす勇気が、私にはなかった。
たいていの人は、日々の学校生活の中に、ごくごく自然に、自分の本質を示していくことができる。でも、私はそうじゃない。臆病なせいで、本質が表われるどころか、すり減って、埋もれていっているように感じる。いまいち、自分を生かしきれていないようで嫌だけど、集団に染まってしまうのも嫌だ。みんなとは、住む世界が違うんだから仕方ないって思うことにしている。
階段を駆けおり、渡り廊下を抜け、下駄箱で靴をはきかえる。杏色のマフラーをくるくると巻き、かばんを持ち、駐輪場に走る。赤信号にひっかからなかったおかげで、バイトの開始時刻にぎりぎり間に合った。自転車を停め、店に飛び込むと、無機質なドアチャイムと明るいあいさつに迎えられた。
「いらっしゃいませこんにちはー」
「おつかれさまです」
「あー、岸本さん。おつかれ」
レジの点検をしていた千葉さんが笑った。彼は、毎週水曜日と木曜日の十七時から一緒に働く相方だ。両日とも二十時までの私と違い、フリーターの千葉さんは、水曜の今日は二十四時までがんばっているらしい。
学生やサラリーマンの帰宅時間に当たる、十八時から十九時の時間帯は忙しい。さっきも、水沢高校の男子生徒の集団が来て、ひとしきり騒いでやっと帰ってくれた。朝倉くんは、あの日以来、来ていない。私のシフトの時間に来ていないだけかもしれないのに、あわてたように走っていった背中を思い出しては、幸せな空想にひたっていた。
「あー。暇だ」
店内を見て回っていた千葉さんが、本当に暇そうにカウンターに帰ってきた。時刻は、十九時二十三分。
こうやって手隙になると、千葉さんは決まってぼやきだす。忙しいときの敏腕な風貌とは、別人みたいにだらっとして見えた。
「暇、ですか」
「うん。だって俺、これからあとまだ四時間半くらい、耐えなきゃいけないし」
「耐える」
「うん。客、あんま来なくなるから」
レジ背面の煙草の棚にもたれ、腕組みをした千葉さんが笑う。下になっている左手の薬指に、指輪の跡が浮いて、残っていた。
「耐え、ますね。はい」
「えー、なに、その間。一瞬一瞬に新しい発見とかしてるわけ?」
「いや、そういうわけでもないですけど。でも、暇って幸せだと思います」
「ひゃー! なんだ、それ」
千葉さんはけらけらと笑った。私は何がおかしいのか分からなかった。
「岸本さんさぁ」
「はい?」
「何歳だっけ?」
「十六です」
「十六ってことは、高一だろ? まだ若いんだからさ、もっとシンプルに行こうよ」
「若いって・・・・・・千葉さんこそ、まだ十九歳ですよね?」
「もうすぐハタチ。・・・・・・だめだ。なんか最近、いろいろと老いてきてるもん、俺」
「老いって! なんですかそれ」
とりとめのない会話は、ピークを外れてやってきたお客さんの波に飲まれ、中断した。老いって、なんだろう。不思議だけど深い感じがして、私は千葉さんという人がよく分からなくなった。
「じゃ、お先に失礼します。おつかれさまです」
「うん。おつかれ」
二十時を迎えて帰ることになった私に、二十四時までがんばる千葉さんが、口角のきゅっと上がった健康的な笑顔を見せた。やっぱり、千葉さんの雰囲気と、老いという言葉はどうしても結びつかなかった。
家に帰り、お風呂でひとしきり、バックビーの『孤独なクラウニー』を歌った。お風呂から出て、ドライヤーに紛れてまだ歌っていたら、洗面所の鏡が曇った。髪は乾いたということにして、ドライヤーのスイッチを切る。歌いながら、私は曇った鏡に絵を描いた。『孤独なクラウニー』に出てくる人も、最終列車に揺られながら、曇った車窓に絵を描いていく。歌の内容を要約すると、こうなる。曲の中に出てくる「私」が列車の窓に刻みつけるように描く絵はすべて、「私」自身のゆがみから来る「痛み」を投影したものだ。描くにつれ、「私」の「痛み」はどんどん大きくなっていく。「痛み」が肥大すればするほど、それを描く「私」の心もどんどん、くすんでいく。そろそろ終着駅に着くというところで、「私」が一番最初に、遠慮がちに描いた小さなピエロが動き出し、大声で泣き叫ぶ。ピエロにつられ、じわじわと糸をひいて泣き出した、たくさんの大きな「痛み」を、「私」は拭ってみる。そこには他でもない、惚けた泣き顔の「私」が映っていて、なんだ、ピエロは自分だったのかと、「私」は妙に納得してしまう。そして、そんな滑稽な自分の姿がおかしくて、最終的には笑ってしまう。
洗面所の鏡に描いた泣き顔のピエロを拭えば、そこには笑顔の私がいた。ゆがむことなしに生きるなんて不可能だ。だから、ゆがんで自分を痛めた自分を笑ってやれ。ゆがんだ自分を認めて、強くあれ。『孤独なクラウニー』には、「一人でも幸せな君であるように」という歌詞がある。これは、孤独にも種類があるんだということを教えてくれている。「一人でも」のニュアンスを変えれば、みんなの幸せを願うっていう意味にもとれるから、深い。歌って、お腹も心も温かくなった私は、二階の自室に上がった。ずいぶんご無沙汰していたキーボードのスイッチを入れる。バックビーのピアノのスコアをひっぱり出してきて、『孤独なクラウニー』の譜面とにらめっこをする。キーボードとは、こうやってちょくちょく、思い出したように向かい合っては格闘してきた。でも、すぐに面倒になるから、練習が三日と続いたためしがない。このスコアを買ったのは、中学に入ってすぐのころだったというのに、未だに一曲も弾けないのは、全部自分のせいだった。当たり前だけど、譜を読むのも運指も、たどたどしすぎて嫌になる。でも、ステージの上で楽しそうだった朝倉くんを思うと、背筋が伸びる。見えない努力を彼はしている。私は『孤独なクラウニー』を手が痛くなるまで練習した。おかげで、全部で十ページある楽譜の一ページ目だけは、まだ少しつっかえるけど、弾けるようになった。ピアノの練習を面倒に思って、さっぱりやらなかった幼いころにくらべれば、今の私は少しだけ、前に進んでいる。午前三時四十六分。疲れた体に心は満ち足りていた。夢に泣き虫ピエロが出てきそうだと思ったら、それだけで笑えて、なかなか寝つけなかった。
次の週の水曜日は、学校に遅刻してしまった。一時間目は、大嫌いな数学の授業だ。教室の後ろのドアから、目立たないようこっそり入ったけど、数学劣等生の私を、数学教師の金子先生が見逃すはずがない。授業中、先生に何かと質問をされ、恥をかかないようにするので私は精一杯だった。私の斜め前の席に座るみっこは、午前の授業中、ずっと熱心にノートをとっているなと思ったら、大作ができたって、昼休みに『孤独なクラウニー』を題材にしたイラストを見せてくれた。「クラウニー 君に王冠を 猫背なフリしたまっすぐな道化」という歌詞の横へ、列車の窓に右手と額をもたせかけ、泣きながら口許はほほえんでいる王子様みたいな人の絵が描いてあるんだけど、朝倉くんに似てる。「いる!」って言ったら、「孤独な朝クラウニー」って、にやにやしながら渡されて、つき返した。当然怒る気になんてなれない。
「孤独な朝クラウニー」の件で盛りあがりかけた放課後、みっこは彼氏に呼ばれて帰っていった。その後一人でぼんやり、教室前の手すりに頬杖をついて夕焼けを見ていたら、バイトも十分遅刻してしまった。
遅刻のツケが回ってきませんようにと願ったけど、しつこいクレーマーがやってきた。彼女は綺麗な人なのに、必ずといっていいほど、眉間にしわを寄せている。
「ねえ、どういうこと?」
本日二度目の来店。つかつかとヒールの音高くやってきた彼女は、さっき買って帰った一リットルパック
のりんごジュースをどん、とカウンターに置いて、言った。
「外出先で飲もうと思ったのよ。そしたらストローが無かった。どーやって飲めっていうの?」
「す、すみません! 外で飲むって思わなくて」
「はぁ? こっちのせいだって言うの? いい加減にしてよ!」
「すみませんっ、あの、以後気をつけます」
おどおどした私に、いらついたクレーマーが手をあげかけたとき、後ろでドリンクの発注をしていた千葉さんが飛んできて、助けてくれた。ようやく、バックルームから店長が飛び出してきたときには、事態はあらかた片づいていた。まだぷりぷりしてはいたけれど、クレーマーはようやく、ヒールの音を響かせながらひきあげていってくれた。やっぱり、こういうことがあると、落ちこむし、疲れる。列が乱れ、スカスカになっていた棚のおにぎりを整頓しながら溜め息をついたら、千葉さんに肩をぽんと叩かれた。
「あのクレーマー、頭おかしいから。気にしないほうがいいよ」
「あ、はい。ほんと、ありがとうございます」
「いえいえ。なんか言われても、基本笑顔で謝っときゃいいよ。事を荒立てないようにするのが、一番大事」
「はい、次から気をつけます。ほんとに、ありがとうございました」
お礼を言いながら、私は思い返していた。あのあくどいクレーマーが、千葉さんの笑顔に思わず、ふりあげていた手をひっこめたことを。
バイトが終わり、家に戻り、ゆっくりとお風呂につかりながら、私はひとしきり歌った。歌えば、その日あった嫌なことを忘れられる。今日なら、クレーマーのことや、放課後の別れ際に、みっこときまずい感じになってしまったこと、などなどを洗い流すように歌おう。私が歌うのが好きな理由は、もう一つある。大嫌いだったピアノの先生が、唯一、私をほめてくれた言葉が心に残っているからだ。「ピアノを弾いているときよりも歌っているときのほうが楽しそうね」という先生の言葉を、身勝手だって分かっているけど、信じていたい。
二階の自室に上がる。明日の授業の予習もそこそこに、キーボードの練習に移る。つっかえるところをしつこいくらい繰り返して、『孤独なクラウニー』の十ページ中、三ページ目の上から三段目まで、なんとかものにした。よし、今日はこのくらいにしておこう。キーボードのスイッチを切り、部屋の電気も切る。布団をかぶって、真っ暗な部屋の中、さらに真っ暗な空間を作る。プレーヤーを操作したら、画面にほわんと青い明かりが灯って、水底にいるような気分になる。午前二時五十七分。気づいたら、バックビーのアルバムを二枚、聞き終わっていた。暗闇で耳を傾けた音楽は、昼間に聞く音楽より、澄んで聞こえた。
次の週の火曜日。うっかり爆睡してしまった数学の後の昼休み、私はみっこから「後で職員室に来るようにって金子先生が言ってたよ」という衝撃的な事実を聞いた。呼び出しに、心当たりがありすぎて怖い。お弁当を食べ終え、みっこと一緒に教室を出る。みっこは校舎北棟の彼氏のもとへ。私は南棟の金子先生のもとへ。行き先の落差に苦笑しながら、私はみっこと別れた。南棟への渡り廊下にさしかかったところで顔を上げたら、この寒い中、そこでお昼ご飯を食べているつわものたちがいた。見覚えのある、ワックスで凝った作りを保っている頭たちの中に、朝倉くんの風まかせの頭がある。私は、朝倉くんの前を通ろうかどうしようか迷った。でも、ここまで来て遠回りをすれば、職員室へ乗り込んでやろうと決めた覚悟が揺らいでしまう。なるべく足早に、集団の前を通り過ぎることにした。うつむいた視界の端で朝倉くんが、ひょいと頭を下げてくれた、気がした。ふり返ろうとしたら、いきなり、わってハジけた仲間のお調子者の声が聞こえて、私は思わず逃げてしまった。南棟の入り口に駆け込んで、そっとふり返る。
だれもこっちを見ていない。よかった。でも、淡く期待もしていたから、本当は少し複雑だ。車座の中でみんなと同じようにあぐらをかいて、当の朝倉くんは、仲間と楽しそうに笑っていた。かと思えば、後ろの手すりにふいっともたれ、にぎやかなその他はどこ吹く風といった具合に、パックの牛乳をすすっていたりする。会話に参加している時間より、そうしている時間のほうが長い。「孤独な朝クラウニー」って言い得て妙だ。後でみっこに報告しよう。私は、うれしさに思わずほころぶ口許を引きしめた。一つ深呼吸をして、職員室の重い戸を、がらっと開ける。
金子先生には、授業態度も成績も残念すぎる! と、罰としてプリント三枚を渡された。でも、大丈夫、大丈夫。一人でも端正な、あの横顔を思い出せ。おかげで、ふわふわと教室に戻ってきた幸せそうなみっこを見たとき、ひがむことなく、笑って「おかえり」って言えた。
木曜日。先週の木曜日は十分遅刻、昨日のバイトも開始時刻ぎりぎりで入ったから、今日は余裕を持って早めに学校を出た。心に余裕があれば、表情も自然と柔らかくなるものなのかもしれない。「いい顔でがんばってるなあ」って常連のおじいちゃんが初めてほめてくれた。切手一枚レジに通しただけなのに、「ありがとう」ってほほえんでくれたお姉さんの笑顔には、ほっこりさせられた。いいことが続いたから、気を引きしめよう。十九時三十一分。ちょっと手隙になって、栄養ドリンクの補充をしていたら、ドアチャイムが鳴った。視界のすみに緑色が揺れる。まさか、と横目を使ったら、朝倉くんだった。ギターを背負い、深緑のマフラーを巻いて、何かをコピーしている。これから練習だろうか。制服のままってことは、もう家に帰るところなのかも。スタジオも、家も、この近く? ドリンクの補充をしながら、あまりにも朝倉くんについて知らないことが多いのに、苦笑する。
補充より、コピーのほうが早く終わった。朝倉くんがこっちに来る。
当然、横顔の私には気がつかず、ドアチャイムと共に出ていく。私は反射的に立ち上がった。コピー機に走り寄り、ふたを開けると、案の定忘れ物だ。しかも、『オールトの雲』。バックビーの最新アルバムに入っている曲のスコアだった。
「千葉さん、すみません、ちょっと忘れ物届けてきます!」
返答も聞かずに、私は外へ飛び出した。コンビニの真昼のような明るさに感謝。夜闇の中、自転車のサドルにまたがって、今にも帰ってしまいそうな朝倉くんの後ろ姿に、叫ぶ。
「あの!」
朝倉くんがふりむいた。スコアをふってみせると、「あ!」って感じに表情が動いた。自転車を降りて、引き返してくる。私も走っていって、駐車場の中ほどで落ち合う。
「うーわ、ごめんなさい。ありがとうございます」
「いえ、間に合ってよかったです。バックビー、好きなんですか?」
「え? ああ、はい。今度友達とコピーバンド組むんで・・・・・・あの」
朝倉くんは困ったように笑った。受け取ったスコアで顔を隠すようにして少し考え込んで、また笑う。
「えーっと、ごめん。同じ高校、だよね? すごい失礼で申し訳ない、顔分かるけど、名前が」
「岸本です。一年四組の、岸本佐奈」
「きしもと、さん。・・・・・・あっ。一年六組の、朝倉佑樹です」
「う、うんっ。よろしく」
「こちらこそ。よろしく」
朝倉くんの名前は、もう知っている。でも、直々に名乗ってくれたことで彼の存在感が、私の中でもっと確かなものになった。こうして近くで見ると、朝倉くんは私より、頭二つ分くらい背が高かった。
「文化祭、見ました」
「えっ」
朝倉くんの切れ長の目が丸くなる。しまった、唐突だったと私はあわてた。
「あー、あの、ごめん! いきなり」
「え? あ、いや。・・・・・・そっか、だからか」
目じりにふっと、しわを刻んで、朝倉くんは笑った。スコアを自転車のかごに入れ、ひょいと、頭を下げる。
「じゃ、ライヴ見にきてくれたことも含めて、ありがと! ごめん、バイト中に」
「いや、全然! いいよ」
「じゃあ、また」
じゃあ、また。ただそれだけなのに光る言葉を反芻しながら、店内に戻る。時計を見ると、あともう十分ほどで二十時だった。栄養ドリンクの残りを補充しながら、頭の中で音楽を流す。ながらやりは得意じゃないけど、音楽なら邪魔にならない。色とりどりのドリンクが、さくさくと棚に収まっていく。
「それ、バックビーだっけ?」
「え? あ!」
耳が頬が、じわっと熱くなる。私はいつのまにか歌っていた。千葉さんが、カウンターから面白そうにこっちを見ている。
「へへ、そうです。『孤独なクラウニー』」
「へえ? なんか、意外」
「意外?」
「うん。もっとかわいい曲、聞いてるイメージだった。・・・・・・にしても」
千葉さんは、にやっとする。
「びっくりしたぁ、いきなりいなくなるし、歌いだすんだもん。なんかあった?」
「いえ。つい、気持ちが高ぶって・・・・・・心が勝手に歌いだしたって感じです」
妙な沈黙が落ちた。無機質なドアチャイムが、間抜けに鳴った。折しも入店してきたおじさんは、カウンターに半ば伏せって笑いをこらえている店員と、真っ赤な顔でドリンクの空き箱をつぶしている店員を見て、「若いっていいね」という謎のコメントを残し、トイレへ入っていった。今日は木曜だから、千葉さんもバイトは二十時で終わりだ。私は店を出てからも千葉さんにからかわれた。ちょっとしつこいので、
「じゃあ、また」と、とっておきの言葉で一方的に切りあげる。千葉さんは笑いを引きずりながらも、少し驚いたような顔をして「おつかれ」と言った。
朝倉くんのスコア事件から一週間経った次の木曜日。バイト先で再び、事件が起きた。
「おい、なにをチンタラやっとるんだ!」
本来なら手隙になるはずの十九時半過ぎ。レジ待ちの長い列の後ろから、怒鳴り声が飛んだ。見ると、杖をつき、浅黒い顔をしたおじいさんが、こちらをにらんでいる。私はとにかく、目の前のお客さんを順番に冷静に、できるだけ早くさばこうと努めた。おじいさんの番になる。彼は杖をつきながらやってきて、カウンターに商品を放った。雑な所作には不釣り合いなプリンが二つ、無造作に転がる。
「大変おまたせいたしました。誠に申し訳ございません」
私は頭を下げ、商品をレジに通そうとして、中身がぐちゃぐちゃになっていることに気づいた。
「あの、新しい商品と、お取替えしますね」
言ったら、溜め息をつかれた。おじいさんは低い声で、言った。
「店長呼んでこい」
「えっ」
「いいから、早く店長を呼んでこい! 聞こえんのか、責任者を呼んでこいと言っとるんだ!」
わめき散らされ、気が動転した。店長は今日、明日が早朝出勤だということで十九時にもう引きあげてしまっている。私はあわててバックルームに行き、店長に連絡を入れた。急いで店内に出たら、あいかわらずメチャメチャなことをしつこくわめくおじいさんに、フロアに出た千葉さんが頭を下げてくれていた。
逆側のレジに並ぶお客さんを待たせるわけにもいかない。むこうの様子をうかがいながら、レジをしていたら、千葉さんの頭が、くらっと傾いだのが見えた。苦しげに咳く声もする。やってきたお客さんに謝り、私はカウンターから飛び出そうとした。折しも、駆けこんできた店長とぶつかりそうになり、あわてて踏みとどまる。店長は、いつもバックルームにこもってばかりいる店長とは、別人みたいに毅然としていた。こういった非常時に備えて、平常時は力を温存しているのかもしれない。いつになく頼もしい店長に業を煮やし、おじいさんは「警察呼べ!」という狂った言葉を吐き捨てて、やっと、引きあげていってくれた。
千葉さんは、おじいさんに杖の先で、みぞおちを突かれてしまったらしい。「平気、平気」と笑っていたけれど、バックルームの椅子に座り込んでしまっている様子を見ると、五割は絶対、空元気だ。先に帰ってしまうのは気がひけたから、私は千葉さんの復活を待ってから帰ることに決めた。
二十時二十七分。わりとすぐ復活した千葉さんに拍子抜けしながら、私は彼の後について店を出た。雨が降っていた。私は傘もカッパも忘れたので、店へ買いに戻ることにした。
「すみません。じゃ、ここで」
「待った」
腕をつかまれた。ふりかえると、千葉さんがほほえんで言った。
「送ってくよ」
「え?」
「雨。岸本さん、自転車でしょ」
「そうですけど。でも」
「家、どこだっけ」
有無を言わせない雰囲気に気圧される。少し首を傾けて笑う千葉さんに向かって、知らず、私は口を開いていた。
「みなとまち市の、沖浦ってとこ、ですけど」
「あー、そこ、知り合いいるから知ってる。乗って」
「え。いや、あの」
「お嬢さん、ちょっと。すみませんねぇ」
ふりむくと、背中の曲がったおばあさんが、店から出ていきたそうに、こっちを見ている。
「ほら、寒いし。行こ」
千葉さんは、出入口をふさいでいた私の手を引いた。薬指に残っていた、指輪の跡が頭をよぎる。雨はまだ、制服の肩に沈むほどではない。引き返せ。駐車場のすみに停めてあるセダンの横まで連れていかれたら、もう、後戻りはできないような気分になった。後部座席に乗り込んだ私に、千葉さんが助手席を勧める。まさか、自分に限ってそんなことはない。そう、しっかり言い聞かせて、私は助手席へと移動した。
車が走り出してすぐ、フロントガラスを打つ滴が大きくなり、あっというまにどしゃぶりになった。自転車で帰っていたら、いまごろ高校の前くらいでひどいことになっていただろう。私はやっぱり、千葉さんには感謝するべきだと思い直した。
「びっくりしたね」
効きのいい暖房に、曇った窓ガラス。泣き虫ピエロの絵が描けそうだと出しかけた指を、あわててひっこめる。
「あ、はい。ほんと、今日はありがとうございました。あげくの果てにこんな、送ってもらったりして」
「いやいや、いいよ。でも、岸本さん、意外と落ち着いてたね。もっと取り乱すかと思ってた」
「えー、そうですか? めっちゃテンパってましたけど」
「いやいや、最初に比べると成長した。前の岸本さんだったら多分、おじいさんもっと怒らせてたと思う」
「あはは、前の岸本さんって! 二か月でそんな、変われますかね」
目に見えるような成長を、こんな短期間で、自分が遂げたとは思わない。この二か月で変化があったとすれば、朝倉くんのことだけだ。朝倉くんのことを知っているはずがないのに、千葉さんに見透かされたような気がして、落ち着かないような、くすぐったいような妙な気分になった。赤信号で、車が停まる。前の車のテールランプが、雨に滲んでいる。座席にぼんやりもたれていたら、いきなり膝の上の右手を、きゅっと握られた。
「あ、あの?」
「指長いし、華奢だなあ。ピアノとか弾けそう」
「へっ?」
また、なんでそんな話題を。私の右手をそのまま離そうともせず、片手でハンドルあやつりながら、千葉さんはぺらぺらとしゃべる。
「歌も歌うでしょ? バンドとか組まないの?」
「いやいやいや、あの、え?」
「部活は? やってないんだっけ?」
「やって、ないです。中学の頃は陸上部で、音楽とは全然関係なかったし。ピアノだって、あっさりやめちゃったこと、後悔してるし」
「後悔! なんかすっごい思い入れがありそうだけど」
いまや私の右手は、私の膝の横で、千葉さんの左手にがんじがらめにされている。核心を突かれたような思いに、不覚にもカラダが熱い。しかも、ちょっとまんざらでもないと思っているこの胸の高鳴りは、変だ。
降ろしてもらうはずだった駅の駐車場などとうに過ぎて、ここは多分、駅の西に当たる公園の駐車場だ。
車が停まった。曇って、雨の打ちつける窓ガラスのむこう、街灯の黄色い光が輪郭をちらつかせている。
千葉さんが壊れた。私の肩に腕を回してきた。あごの下に、のどもとに手が伸びてくる。爪が、指先が、ブラウスのえりにかかる。肩にかけられた温かい重みに負けそうになって、叫ぶ。
「ちょ、ちょっと待ってください!」
耳元での悲鳴に、千葉さんが少したじろいだ。隙を見てふりほどいたら、視線がぶつかった。
「岸本さん・・・・・・」
はっとしたような千葉さんの顔にすぐ、悪い笑みが浮かぶ。
「泣いてんの?」
「泣いてないっ。帰りますっ」
「は? どーやって帰んの、外、雨」
「さわんなよっ」
私は逆上した。腕にすがってきた千葉さんの手首に思いっきり、爪を立てる。
「いっ・・・・・・」
ひるんだ千葉さんの手を、私は力まかせに押し返した。普段のバイトでの、ぼんやりとした私からは想像もつかなかったんだろう。雷に撃たれたみたいな顔をして、千葉さんがゆっくりと、身をひいた。雨音が、途切れることなく続く。突然、ふいっと、千葉さんは前を向いた。手首をさすっている。少し血が滲んでいるのが見えて、私は、はっと我に返った。
「あのっ」
「なんで?」
「はい?」
調子外れの声を上げたら、千葉さんは口許を尖らせて、笑った。
「すっごい、抵抗。俺、今結構、傷ついたんだけど」
「そ、それは、すみません! でも」
「なに」
「彼女、いますよね」
車体を打つ雨音が強くなる。暗がりのむこうで千葉さんが、空気の抜けたように苦笑する。
「知ってたか」
「知ってます。むりやり引き抜いたような、指輪の跡を知ってます」
「うわー、マジか! 怖いな」
うめくように笑いながら、千葉さんは窓ガラスにもたれた。私は、車内の生ぬるさと冬の雨の外気に曇る、窓ガラス越しの闇を見る。みぞおちよりもずっと深い場所にある、千葉さんの「痛み」を思う。
「・・・・・・で? これ以後は?」
「これ以後、って。繰り返すんですか?」
「繰り返す、というか、繰り返してきた。うん」
ほほえみながら、平然と言ってきた。やばい。この人、怖い。でも。
ハンドルの下、指輪の跡を押さえるように、ぎゅっとこすった仕草を、私は見た。この人、怖いけど。孤独だ。
「あの!」
前を向いていた千葉さんが、ゆっくりとこっちを見る。
「彼女さんと、なにかありました?」
「はあ? なにその質問、斬新!」
千葉さんはけらけらと笑い、のち、表情を改める。
「なんもないよ」
「そう、ですか」
雨の音にまじって、私にはひずんだ「痛み」が聴こえる。『孤独なクラウニー』が聴こえる。きっと最初は、気にもならなかったような小さなゆがみだ。中学のころ、雨に流れたグラウンドに競技用のトラックを引くのを頼まれて、失敗したことを思い出す。
「・・・・・・引き始め、ですよね」
「は? なに、いきなり」
千葉さんの口許がまた尖ってきた。次に彼が壊れたときこそ、私は私でなくなる。カラダの熱さと裏腹に、私の心が、りんと冴えていく。
「いえ。きっと、これくらい、いいじゃんって感じで、どんどん進んじゃって、できあがった姿にびっくりして悲しくなるけど、笑うしかないんですよね。おかしいことやっておかしいって、思わないというか思えないんだろうなあって、思います。私、なんかそういうの分かるんです。千葉さんのそういうところ、おかしいけどたくましくって、いいと思います、多分! てか、こういう変な状況になったのって、もとはといえばなんにも考えずに、車に乗っちゃった私のせいです。ほんと、ぼんやりしてて、うかつでした。だから・・・・・・傷つけちゃってほんと、ごめんなさい!」
雨の音が強くなって、また、遠くなった。千葉さんは、聞いていないんじゃないかってくらい静かに聞いていて、笑い出した。最初は、こらえるように。最後には笑いすぎて、咳が出るほどに。
「あ、あの。大丈夫ですか」
「大丈夫じゃ、ない・・・・・・あのさぁ、それ、なぐさめてんの? 俺のこと」
「いや、別にそういうつもりじゃ」
「別にって! しかもいいと思うって言った後、多分って言った! ・・・・・・岸本さん、すげえ」
千葉さんは、また、笑い出した。騒がしく笑っているけれど、そのたくましさのために、千葉さんは悩むことになるんだということが、私には分かる。千葉さんのたくましさは、ゆがみから来る「痛み」だ。引き始めにほんの少しゆがんでしまったトラックの白線を、私は直さなかった。何だこのくらいと、放ったまま進めていった。最初の小さなゆがみのために、その後のゆがみがどんどん大きくなっていく。最後にはもう、何の競技にも使えないぐらい、いびつな形ができあがる。集団の中でどうしても浮いてしまう自分のことを、間違いだけど、間違いじゃないと思っている私には、千葉さんが繰り返してしまう「痛み」が、理解できるような気がした。笑いの余波に咳払いをして、千葉さんは言う。
「おかしいけどたくましい、ねえ。岸本さんさぁ、一体いつも何を考えてんの」
「特に、そんな。大したことは考えてません」
「えっ」
朝倉くんの切れ長の目が丸くなる。しまった、唐突だったと私はあわてた。
「あー、あの、ごめん! いきなり」
「え? あ、いや。・・・・・・そっか、だからか」
目じりにふっと、しわを刻んで、朝倉くんは笑った。スコアを自転車のかごに入れ、ひょいと、頭を下げる。
「じゃ、ライヴ見にきてくれたことも含めて、ありがと! ごめん、バイト中に」
「いや、全然! いいよ」
「じゃあ、また」
じゃあ、また。ただそれだけなのに光る言葉を反芻しながら、店内に戻る。時計を見ると、あともう十分ほどで二十時だった。栄養ドリンクの残りを補充しながら、頭の中で音楽を流す。ながらやりは得意じゃないけど、音楽なら邪魔にならない。色とりどりのドリンクが、さくさくと棚に収まっていく。
「それ、バックビーだっけ?」
「え? あ!」
耳が頬が、じわっと熱くなる。私はいつのまにか歌っていた。千葉さんが、カウンターから面白そうにこっちを見ている。
「へへ、そうです。『孤独なクラウニー』」
「へえ? なんか、意外」
「意外?」
「うん。もっとかわいい曲、聞いてるイメージだった。・・・・・・にしても」
千葉さんは、にやっとする。
「びっくりしたぁ、いきなりいなくなるし、歌いだすんだもん。なんかあった?」
「いえ。つい、気持ちが高ぶって・・・・・・心が勝手に歌いだしたって感じです」
妙な沈黙が落ちた。無機質なドアチャイムが、間抜けに鳴った。折しも入店してきたおじさんは、カウンターに半ば伏せって笑いをこらえている店員と、真っ赤な顔でドリンクの空き箱をつぶしている店員を見て、「若いっていいね」という謎のコメントを残し、トイレへ入っていった。今日は木曜だから、千葉さんもバイトは二十時で終わりだ。私は店を出てからも千葉さんにからかわれた。ちょっとしつこいので、
「じゃあ、また」と、とっておきの言葉で一方的に切りあげる。千葉さんは笑いを引きずりながらも、少し驚いたような顔をして「おつかれ」と言った。
朝倉くんのスコア事件から一週間経った次の木曜日。バイト先で再び、事件が起きた。
「おい、なにをチンタラやっとるんだ!」
本来なら手隙になるはずの十九時半過ぎ。レジ待ちの長い列の後ろから、怒鳴り声が飛んだ。見ると、杖をつき、浅黒い顔をしたおじいさんが、こちらをにらんでいる。私はとにかく、目の前のお客さんを順番に冷静に、できるだけ早くさばこうと努めた。おじいさんの番になる。彼は杖をつきながらやってきて、カウンターに商品を放った。雑な所作には不釣り合いなプリンが二つ、無造作に転がる。
「大変おまたせいたしました。誠に申し訳ございません」
私は頭を下げ、商品をレジに通そうとして、中身がぐちゃぐちゃになっていることに気づいた。
「あの、新しい商品と、お取替えしますね」
言ったら、溜め息をつかれた。おじいさんは低い声で、言った。
「店長呼んでこい」
「えっ」
「いいから、早く店長を呼んでこい! 聞こえんのか、責任者を呼んでこいと言っとるんだ!」
わめき散らされ、気が動転した。店長は今日、明日が早朝出勤だということで十九時にもう引きあげてしまっている。私はあわててバックルームに行き、店長に連絡を入れた。急いで店内に出たら、あいかわらずメチャメチャなことをしつこくわめくおじいさんに、フロアに出た千葉さんが頭を下げてくれていた。
逆側のレジに並ぶお客さんを待たせるわけにもいかない。むこうの様子をうかがいながら、レジをしていたら、千葉さんの頭が、くらっと傾いだのが見えた。苦しげに咳く声もする。やってきたお客さんに謝り、私はカウンターから飛び出そうとした。折しも、駆けこんできた店長とぶつかりそうになり、あわてて踏みとどまる。店長は、いつもバックルームにこもってばかりいる店長とは、別人みたいに毅然としていた。こういった非常時に備えて、平常時は力を温存しているのかもしれない。いつになく頼もしい店長に業を煮やし、おじいさんは「警察呼べ!」という狂った言葉を吐き捨てて、やっと、引きあげていってくれた。
千葉さんは、おじいさんに杖の先で、みぞおちを突かれてしまったらしい。「平気、平気」と笑っていたけれど、バックルームの椅子に座り込んでしまっている様子を見ると、五割は絶対、空元気だ。先に帰ってしまうのは気がひけたから、私は千葉さんの復活を待ってから帰ることに決めた。
二十時二十七分。わりとすぐ復活した千葉さんに拍子抜けしながら、私は彼の後について店を出た。雨が降っていた。私は傘もカッパも忘れたので、店へ買いに戻ることにした。
「すみません。じゃ、ここで」
「待った」
腕をつかまれた。ふりかえると、千葉さんがほほえんで言った。
「送ってくよ」
「え?」
「雨。岸本さん、自転車でしょ」
「そうですけど。でも」
「家、どこだっけ」
有無を言わせない雰囲気に気圧される。少し首を傾けて笑う千葉さんに向かって、知らず、私は口を開いていた。
「みなとまち市の、沖浦ってとこ、ですけど」
「あー、そこ、知り合いいるから知ってる。乗って」
「え。いや、あの」
「お嬢さん、ちょっと。すみませんねぇ」
ふりむくと、背中の曲がったおばあさんが、店から出ていきたそうに、こっちを見ている。
「ほら、寒いし。行こ」
千葉さんは、出入口をふさいでいた私の手を引いた。薬指に残っていた、指輪の跡が頭をよぎる。雨はまだ、制服の肩に沈むほどではない。引き返せ。駐車場のすみに停めてあるセダンの横まで連れていかれたら、もう、後戻りはできないような気分になった。後部座席に乗り込んだ私に、千葉さんが助手席を勧める。まさか、自分に限ってそんなことはない。そう、しっかり言い聞かせて、私は助手席へと移動した。
車が走り出してすぐ、フロントガラスを打つ滴が大きくなり、あっというまにどしゃぶりになった。自転車で帰っていたら、いまごろ高校の前くらいでひどいことになっていただろう。私はやっぱり、千葉さんには感謝するべきだと思い直した。
「びっくりしたね」
効きのいい暖房に、曇った窓ガラス。泣き虫ピエロの絵が描けそうだと出しかけた指を、あわててひっこめる。
「あ、はい。ほんと、今日はありがとうございました。あげくの果てにこんな、送ってもらったりして」
「いやいや、いいよ。でも、岸本さん、意外と落ち着いてたね。もっと取り乱すかと思ってた」
「えー、そうですか? めっちゃテンパってましたけど」
「いやいや、最初に比べると成長した。前の岸本さんだったら多分、おじいさんもっと怒らせてたと思う」
「あはは、前の岸本さんって! 二か月でそんな、変われますかね」
目に見えるような成長を、こんな短期間で、自分が遂げたとは思わない。この二か月で変化があったとすれば、朝倉くんのことだけだ。朝倉くんのことを知っているはずがないのに、千葉さんに見透かされたような気がして、落ち着かないような、くすぐったいような妙な気分になった。赤信号で、車が停まる。前の車のテールランプが、雨に滲んでいる。座席にぼんやりもたれていたら、いきなり膝の上の右手を、きゅっと握られた。
「あ、あの?」
「指長いし、華奢だなあ。ピアノとか弾けそう」
「へっ?」
また、なんでそんな話題を。私の右手をそのまま離そうともせず、片手でハンドルあやつりながら、千葉さんはぺらぺらとしゃべる。
「歌も歌うでしょ? バンドとか組まないの?」
「いやいやいや、あの、え?」
「部活は? やってないんだっけ?」
「やって、ないです。中学の頃は陸上部で、音楽とは全然関係なかったし。ピアノだって、あっさりやめちゃったこと、後悔してるし」
「後悔! なんかすっごい思い入れがありそうだけど」
いまや私の右手は、私の膝の横で、千葉さんの左手にがんじがらめにされている。核心を突かれたような思いに、不覚にもカラダが熱い。しかも、ちょっとまんざらでもないと思っているこの胸の高鳴りは、変だ。
降ろしてもらうはずだった駅の駐車場などとうに過ぎて、ここは多分、駅の西に当たる公園の駐車場だ。
車が停まった。曇って、雨の打ちつける窓ガラスのむこう、街灯の黄色い光が輪郭をちらつかせている。
千葉さんが壊れた。私の肩に腕を回してきた。あごの下に、のどもとに手が伸びてくる。爪が、指先が、ブラウスのえりにかかる。肩にかけられた温かい重みに負けそうになって、叫ぶ。
「ちょ、ちょっと待ってください!」
耳元での悲鳴に、千葉さんが少したじろいだ。隙を見てふりほどいたら、視線がぶつかった。
「岸本さん・・・・・・」
はっとしたような千葉さんの顔にすぐ、悪い笑みが浮かぶ。
「泣いてんの?」
「泣いてないっ。帰りますっ」
「は? どーやって帰んの、外、雨」
「さわんなよっ」
私は逆上した。腕にすがってきた千葉さんの手首に思いっきり、爪を立てる。
「いっ・・・・・・」
ひるんだ千葉さんの手を、私は力まかせに押し返した。普段のバイトでの、ぼんやりとした私からは想像もつかなかったんだろう。雷に撃たれたみたいな顔をして、千葉さんがゆっくりと、身をひいた。雨音が、途切れることなく続く。突然、ふいっと、千葉さんは前を向いた。手首をさすっている。少し血が滲んでいるのが見えて、私は、はっと我に返った。
「あのっ」
「なんで?」
「はい?」
調子外れの声を上げたら、千葉さんは口許を尖らせて、笑った。
「すっごい、抵抗。俺、今結構、傷ついたんだけど」
「そ、それは、すみません! でも」
「なに」
「彼女、いますよね」
車体を打つ雨音が強くなる。暗がりのむこうで千葉さんが、空気の抜けたように苦笑する。
「知ってたか」
「知ってます。むりやり引き抜いたような、指輪の跡を知ってます」
「うわー、マジか! 怖いな」
うめくように笑いながら、千葉さんは窓ガラスにもたれた。私は、車内の生ぬるさと冬の雨の外気に曇る、窓ガラス越しの闇を見る。みぞおちよりもずっと深い場所にある、千葉さんの「痛み」を思う。
「・・・・・・で? これ以後は?」
「これ以後、って。繰り返すんですか?」
「繰り返す、というか、繰り返してきた。うん」
ほほえみながら、平然と言ってきた。やばい。この人、怖い。でも。
ハンドルの下、指輪の跡を押さえるように、ぎゅっとこすった仕草を、私は見た。この人、怖いけど。孤独だ。
「あの!」
前を向いていた千葉さんが、ゆっくりとこっちを見る。
「彼女さんと、なにかありました?」
「はあ? なにその質問、斬新!」
千葉さんはけらけらと笑い、のち、表情を改める。
「なんもないよ」
「そう、ですか」
雨の音にまじって、私にはひずんだ「痛み」が聴こえる。『孤独なクラウニー』が聴こえる。きっと最初は、気にもならなかったような小さなゆがみだ。中学のころ、雨に流れたグラウンドに競技用のトラックを引くのを頼まれて、失敗したことを思い出す。
「・・・・・・引き始め、ですよね」
「は? なに、いきなり」
千葉さんの口許がまた尖ってきた。次に彼が壊れたときこそ、私は私でなくなる。カラダの熱さと裏腹に、私の心が、りんと冴えていく。
「いえ。きっと、これくらい、いいじゃんって感じで、どんどん進んじゃって、できあがった姿にびっくりして悲しくなるけど、笑うしかないんですよね。おかしいことやっておかしいって、思わないというか思えないんだろうなあって、思います。私、なんかそういうの分かるんです。千葉さんのそういうところ、おかしいけどたくましくって、いいと思います、多分! てか、こういう変な状況になったのって、もとはといえばなんにも考えずに、車に乗っちゃった私のせいです。ほんと、ぼんやりしてて、うかつでした。だから・・・・・・傷つけちゃってほんと、ごめんなさい!」
雨の音が強くなって、また、遠くなった。千葉さんは、聞いていないんじゃないかってくらい静かに聞いていて、笑い出した。最初は、こらえるように。最後には笑いすぎて、咳が出るほどに。
「あ、あの。大丈夫ですか」
「大丈夫じゃ、ない・・・・・・あのさぁ、それ、なぐさめてんの? 俺のこと」
「いや、別にそういうつもりじゃ」
「別にって! しかもいいと思うって言った後、多分って言った! ・・・・・・岸本さん、すげえ」
千葉さんは、また、笑い出した。騒がしく笑っているけれど、そのたくましさのために、千葉さんは悩むことになるんだということが、私には分かる。千葉さんのたくましさは、ゆがみから来る「痛み」だ。引き始めにほんの少しゆがんでしまったトラックの白線を、私は直さなかった。何だこのくらいと、放ったまま進めていった。最初の小さなゆがみのために、その後のゆがみがどんどん大きくなっていく。最後にはもう、何の競技にも使えないぐらい、いびつな形ができあがる。集団の中でどうしても浮いてしまう自分のことを、間違いだけど、間違いじゃないと思っている私には、千葉さんが繰り返してしまう「痛み」が、理解できるような気がした。笑いの余波に咳払いをして、千葉さんは言う。
「おかしいけどたくましい、ねえ。岸本さんさぁ、一体いつも何を考えてんの」
「特に、そんな。大したことは考えてません」
「いや、考えてる。どっからそんな、たくましいとか、悲しいけど笑うしかないとか、面白いこと言えるんだって思うもん」
「面白い?」
ほめられているんだか、けなされているんだか、よく分からないその言葉。だけど、妙に私にしっくりくる言葉を、心の中で何度も反芻してみる。面白いといえば、千葉さんにもそういう言葉があったことを私は思い出した。
「千葉さんも、前に言ってました」
「前に? なにを」
「老いてきたってやつです。深いなあと思いました」
「ああ、あれか。ちょっと疲れたってことを、岸本流で言ってみた。本でも書けば?」
「本?」
「うん。『岸本流・言葉の極意』って」
「・・・・・・千葉さんも、面白いですね」
「うーわ」
千葉さんは笑った。雨はいつしか止んでいた。エンジンがかかる。知らず、冷えていた腕に、暖房の風が当たる。ぐいんと後ろに持っていかれるくらい急転回した車が、駐車場を出る。
また、どこかに連れていかれるんじゃないかと、曇る窓をこすって外を見ていた。見慣れた景色が続いていた。ブレザーのポケットで携帯がふるえる。二十一時五十四分。お母さんが心配するのも無理はない。
どう返信しようか少し迷って、「バイト先に困った人が来て、その対応で遅くなった。もうすぐ帰る」って送った。あながち嘘じゃないから、笑えた。
「・・・・・・佐奈って呼んだら、怒る?」
「はい」
携帯の画面から目を離し、しっかりとうなずく。千葉さんが苦笑する。
「なんで」
「佐奈って呼んでほしい人が、他にいるからです」
「うわ」
走行中だというのに千葉さんがこっちを見た。私があわてた。
「ごめん、っと、ごめん。・・・・・・でもさぁ」
「はい」
「それ、ここで言う?」
「言っちゃいました。てか、自分でもびっくりしました。千葉さんのおかげです」
「・・・・・・ははっ。だめだ」
ハンドルにかぶさるようにして、千葉さんは言った。
「負けた」
腕のすきまから見えた横顔は、へにゃっとしていた。でも、今までで一番、本当に笑っていると思った。
翌週の水曜日。十二月に入って最初のバイトで、当然だけど、千葉さんと顔を合わすことになった。千葉さんは指輪をはめていた。お互いに何もなかったような顔で、普通に会話をし、淡々と業務をこなし、二十時がやってきた。水曜日の今日は、千葉さんは二十四時までがんばる日だ。
「おつかれさまです」
「おつかれー」
「あの」
「ん?」
帰り際に、千葉さんに渡そうと考えているものがあった。カウンターに置かれた、リボンのかかった小さい袋を見て、千葉さんは笑う。
「なに、これ」
「お礼です。いろいろ、お世話になったので」
「お礼。岸本流の?」
「はい」
しっかりとうなずく。千葉さんはおかしそうに、また笑う。
「いいのに」
「いや、そんな大したものじゃないし」
「毒とか入ってない?」
「失礼な! ただのクッキーです」
「ははは、冗談だって!」
遊ばれて、頭にくるも憎めない。クッキーの袋をひょいとつかんで、
千葉さんは笑った。子供みたいに、屈託がなかった。
「ありがと。こっそり食うよ」
「こっそり・・・・・・あ、そっか! 彼女が見る前に消費してくださいね」
「そーする」
「約束ですよ! おつかれさまです」
「うん、おつかれ。がんばれよ」
出ていきかけて、ぐるんとふりむいた。指輪のはまった左手をひらひらさせながら、やつは笑っていた。つられて笑ってしまいながら、私は軽く、千葉さんにお辞儀を返した。外に出る。星空の下、自転車を走らせていたら、『孤独なクラウニー』を歌いたくなった。初めは、小さな声で。だんだんと、大きな声で。明日、学校でみっこにいっぱい打ち明けよう。明日のバイトで千葉さんに、私の決意を聞いてもらおう。そして明後日、軽音部に見学に行こう。私は私を、もう一度私らしく、始めていけばいいんだ。
※作品の無断転載を禁じます。
「面白い?」
ほめられているんだか、けなされているんだか、よく分からないその言葉。だけど、妙に私にしっくりくる言葉を、心の中で何度も反芻してみる。面白いといえば、千葉さんにもそういう言葉があったことを私は思い出した。
「千葉さんも、前に言ってました」
「前に? なにを」
「老いてきたってやつです。深いなあと思いました」
「ああ、あれか。ちょっと疲れたってことを、岸本流で言ってみた。本でも書けば?」
「本?」
「うん。『岸本流・言葉の極意』って」
「・・・・・・千葉さんも、面白いですね」
「うーわ」
千葉さんは笑った。雨はいつしか止んでいた。エンジンがかかる。知らず、冷えていた腕に、暖房の風が当たる。ぐいんと後ろに持っていかれるくらい急転回した車が、駐車場を出る。
また、どこかに連れていかれるんじゃないかと、曇る窓をこすって外を見ていた。見慣れた景色が続いていた。ブレザーのポケットで携帯がふるえる。二十一時五十四分。お母さんが心配するのも無理はない。
どう返信しようか少し迷って、「バイト先に困った人が来て、その対応で遅くなった。もうすぐ帰る」って送った。あながち嘘じゃないから、笑えた。
「・・・・・・佐奈って呼んだら、怒る?」
「はい」
携帯の画面から目を離し、しっかりとうなずく。千葉さんが苦笑する。
「なんで」
「佐奈って呼んでほしい人が、他にいるからです」
「うわ」
走行中だというのに千葉さんがこっちを見た。私があわてた。
「ごめん、っと、ごめん。・・・・・・でもさぁ」
「はい」
「それ、ここで言う?」
「言っちゃいました。てか、自分でもびっくりしました。千葉さんのおかげです」
「・・・・・・ははっ。だめだ」
ハンドルにかぶさるようにして、千葉さんは言った。
「負けた」
腕のすきまから見えた横顔は、へにゃっとしていた。でも、今までで一番、本当に笑っていると思った。
翌週の水曜日。十二月に入って最初のバイトで、当然だけど、千葉さんと顔を合わすことになった。千葉さんは指輪をはめていた。お互いに何もなかったような顔で、普通に会話をし、淡々と業務をこなし、二十時がやってきた。水曜日の今日は、千葉さんは二十四時までがんばる日だ。
「おつかれさまです」
「おつかれー」
「あの」
「ん?」
帰り際に、千葉さんに渡そうと考えているものがあった。カウンターに置かれた、リボンのかかった小さい袋を見て、千葉さんは笑う。
「なに、これ」
「お礼です。いろいろ、お世話になったので」
「お礼。岸本流の?」
「はい」
しっかりとうなずく。千葉さんはおかしそうに、また笑う。
「いいのに」
「いや、そんな大したものじゃないし」
「毒とか入ってない?」
「失礼な! ただのクッキーです」
「ははは、冗談だって!」
遊ばれて、頭にくるも憎めない。クッキーの袋をひょいとつかんで、
千葉さんは笑った。子供みたいに、屈託がなかった。
「ありがと。こっそり食うよ」
「こっそり・・・・・・あ、そっか! 彼女が見る前に消費してくださいね」
「そーする」
「約束ですよ! おつかれさまです」
「うん、おつかれ。がんばれよ」
出ていきかけて、ぐるんとふりむいた。指輪のはまった左手をひらひらさせながら、やつは笑っていた。つられて笑ってしまいながら、私は軽く、千葉さんにお辞儀を返した。外に出る。星空の下、自転車を走らせていたら、『孤独なクラウニー』を歌いたくなった。初めは、小さな声で。だんだんと、大きな声で。明日、学校でみっこにいっぱい打ち明けよう。明日のバイトで千葉さんに、私の決意を聞いてもらおう。そして明後日、軽音部に見学に行こう。私は私を、もう一度私らしく、始めていけばいいんだ。
※作品の無断転載を禁じます。