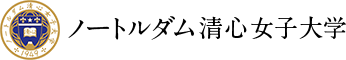2012.04.12
本学科の授業科目「文学創作論」では、履修生が1年をかけて作り上げた作品をまとめて、文集を発
行しています。
ここでは、第8集『四重奏』(2010年度)より、1作品をご紹介します。
文集は、オープンキャンパスなどでご希望の方にお頒ちしております。機会がありましたらぜひお手に
とってみてください。
凱旋行進
作・荒島由貴
行しています。
ここでは、第8集『四重奏』(2010年度)より、1作品をご紹介します。
文集は、オープンキャンパスなどでご希望の方にお頒ちしております。機会がありましたらぜひお手に
とってみてください。
凱旋行進
作・荒島由貴
私、井上瀬莉華(せりか)は頭を働かせ、考え事をしながら歩いていた。キャラクターを考えて欲しい、と頼まれていたから、そのことを考えていたのだ。大体、もう出来上がっているのだが、考えていると尾ひれ背びれがついて、頼まれてもいないことまで考えてしまう。
その時、私ははたと立ち止まった。同じ高校の理沙が、短いスカートの下に短パンを穿いた格好で、犬の散歩をしている。手にはケータイを持って、メールをしているようだった。
私は、学校では彼女と同じような短いスカートで通している。理沙は、学校では一番の友達だ。彼女がメールを打っている相手は私かもしれない。しかし、理沙は夢にも思わないだろう。友達の瀬莉華が、わざわざ制服をぬいでジャージに着替え、顔が見えないようにマフラーを巻いて、帽子まで被って、こそこそとマンガを描きに行こうとしているだなんて。
私は今、忍者みたいだ。毎回、芳香(ほうか)の家に行くたびに誰かに見咎められやしまいかと警戒している。忍者と私に共通していることは、見つかっちゃいけないような秘密を抱えているということ。理沙が行き過ぎても、私はしばらく動かなかった。
理沙は、中学生のころ、私と芳香の家の間くらいの所に引っ越してきた。私と芳香はそれより前から親友だったけれども、理沙が越してきたころには、私は忍者になっていた。だから理沙は、自分が芳香をバカにしているように、私も芳香をバカにしていると思っている。
マンガを描くなんて、ダサい。芳香なんてオタクだ。キモい。そういわれ始めた時から、私は芳香から離れだした。あれは、中学に入るか、入らないかくらいのころだったか。同じように見られて、みんなにバカにされるのが嫌だった。そう思いはじめたら、芳香自身についても友達づきあいするに値しない子のように思えた。
結局、学校では、私と芳香は無視しあうようになった。芳香も、その点で言えば空気を読んでくれていたのだろう。けれど、不思議なことにマンガを描きにいくことだけは、今の今まで続いている。こんな忍者まがいのことをしてでも、芳香の家に行かない、という選択肢は考えられなかった。これはとても、不思議なことだ。
芳香の家は武家屋敷みたいな豪華な家だ。今は普通の家庭なのだが、昔はかなりのお金持ちだったらしい。特に凄いのは玄関で、人の出入りする場所のはずなのに、何となく、人を拒むような雰囲気があった。
そのせいなのか、それとも幼い頃からこの家に出入りしているせいか、私はいつも勝手口からあがっていた。勝手口から入るとすぐに台所だ。私は「おじゃまします」も言わないで上がりこんだ。台所と繋がっているリビングでは、芳香のお母さんがコタツに入って寝ている。私が犯罪者だったらどうするつもりだろう、と思うけれども、私だと分かって寝ている気もする。
私はこの家の人のような顔をして奥へ進み、芳香の部屋のドアをあけた。ストーブのせいで澱んだ空気と、インクの臭いがぶわっと外まで流れ出る。芳香は、勉強机に座って、天上を眺めていた。
芳香は華奢で小さな女の子だ。顔立ちは可愛いのだが、唇を尖らせる変な癖があるので可愛いことはあまり知られていない。今も、尖らせた唇と鼻の間に鉛筆を挟んでいる。彼女の手元には、絵の描かれた紙があった。たぶん、あれは学校でもらったプリントの裏紙だ。
私は何も言わず、部屋の中心に置かれた座机に向かった。勉強机が芳香、この机が私の場所と決まっている。私の場所には、所々背景が描かれていない原稿が置かれていた。この背景を埋め尽くしていくのが、私の仕事というわけだ。
道具は自分の道具がある。それらを広げて、白いところに鉛筆で書かれた指示通りの背景を描く。私は、人物は描けないが、風景は芳香より上手に描けた。
「森」と描かれたところには、すでにがらくた王がいる。芳香が中学生のころから描いている『がらくたマーチ』という物語の悪役で、かつてライバルだったアンドロイドから剥ぎ取った機械の顔を、仮面として自分がつけている、という奇怪な男だ。仮面は目元だけ覆っていて、口元は見えている。不思議なもので、口元しか見えないのに、この男は魅力的に思われた。
私はこのがらくた王が、芳香のキャラクターのなかで一番好きだった。戦争が終わって捨てられた兵器を率いて人間に復讐するという恐ろしいやつなのだが、私はただの悪役ではないと確信している。きっと、この人のバックグラウンドには深い謎があるのだ。ただ、芳香はいくら聞いてもその謎を教えてくれなかった。
しばらく黙って森を描いていると、芳香が立ち上がって、私の机の向こう側に座った。その手には、さっきの裏紙が握られている。
「がらくた王四天王、四人目考えてきてくれた?」
紙には、三つの絵が描かれていた。がらくた王は兵器の王様なので、その四天王も戦車にアンドロイド、ハッキング用プログラムということになっている。私は、曖昧な笑みを浮かべ、首を振った。
「あんたが考えなさいよ。私、そういうの考えられないわ」
芳香は私が背景を描いていた原稿に目を落とした。芳香は人の目を見て話さない。相手の反応を見ないで、自分の言いたいことだけを言う。
「考えられないって、そんなことないでしょ。昔は色々、物語を考えてたじゃん」
「小学生のころでしょ? 大昔のことだわ」
芳香は、唇をとがらせた。どう見たって何か言いたげだったが、何も言わなかった。芳香は破天荒に見られがちだが、意外と気を遣っている。人の目を見ないのも、人の反応を見れば気が引けるからだろう。
「大体、一人だけ他の人が考えたキャラクターが混じっていたら、おかしく思われるんじゃない。どうするの、私がマンガを描いてるってバレたら」
芳香は泣き出しそうな人のように眉をしかめたまま、立ち上がって、勉強机に戻った。私は、机の上に残されていた三人だけの四天王の絵を机の下におろした。
一箇所、背景を埋め終えると次の背景も「森」だった。単純作業を続けていると、段々疲れてくる。芳香のわずかな友達の目にしか触れないマンガなのに、どうして芳香は、こんなに労力をかけるのだろう。あんたはプロじゃないんだよ、と言いたくなる。
それにしたって、空気が悪い。気づけば、二三度、瞬間的に意識がなくなる。要するにこれは眠いんだ、と気づいたときには、私は眠っていた。
夕日を浴びて、長い影を伸ばすビル群。そこに人は一人もいない。きちんと背筋を伸ばして建っているように見えるビルも、よく見ればどれも窓ガラスが吹っ飛んでいて、中にあったものは吹き出された後である。そのとき中にいたはずの人はどうなったのか、それはよく分からないが、今ここに人は私一人っきりだということはよく分かる。
断言していい。私は夢を見ている。なぜなら、この、荒廃したビル群は『がらくたマーチ』の背景なのだ。よく、枕の下に絵を敷いて寝るとその夢を見ると言うが、その要領で私は『がらくたマーチ』の夢を見ているのだ。多分。
私はバス停のベンチに座って、辺りを見回した。気が付いたら、という言い方は正しいのかどうか分からないけれども、ともかく私はここにいた。生き物がいそうな気配は少しもない。音もしない。こんな場所は、地球のどこを探したって見当たらないだろう。
その時、目の前の道路を灰色の何かが駆け抜けた。走るのが凄く速かったのでそれが何だったのか、私には分からない。何かは、ビルの隙間にするりと入って見えなくなった。あまりに唐突なことだったので、今見たものが実際にあったものか、気のせいなのか、それすら分からないでいると、その後を追うように、男が走ってきた。
その男を見たとき、私はぎょっとした。その男は、間違いなく、がらくた王だったのである。ここが『がらくたマーチ』の夢ならば驚くことではないのかもしれないけれども、何しろマンガの登場人物が自分と同じように立体の体を持って、確かにそこに、人間として存在しているのだ。驚いて当然だろう。
がらくた王は、黒いコートに例のアンドロイドの仮面、そして、なぜか手には虫取り網を持って、おおいに息を切らしながら走ってきた。だが、ちょうど道の真ん中あたりで、立ち止まってしまう。どうやら力尽きたようだった。彼は何かを探すようにあたりを見回す。そのとき、私と目が合った。
彼は、口元だけでそれとわかるくらいの笑みを浮かべ、虫取り網を杖にして、こちらに近づいてきた。
「ちょっと、すみません。伺いたいことがあるのですが」
私が想像していたより低い声だった。それに、近づいてみるとかなり背が高い。私はがらくた王を二十代前半の若い男だと思っていたが、こうして見るともしかしたらもう少し上かもしれなかった。ただ、目元が見えないのでよくは分からない。
「さっき、ここを何か、こう、小さな、小動物みたいなものが通りませんでしたか?」
きっとさっき私が目撃したものだ。私は、頷いた。
「どっちに行ったか分かりますか?」
私は、さっきのものが消えた所を指差した。がらくた王は丁寧にお礼を言って、ビル影へと消えていく。私は呆然として、その背中を見送った。マンガのキャラクターと喋っている夢を見ているなんて、学校のみんなに知れたら死ねると思っていると、また、ビル影から例のすばしっこいものが飛び出した。ただ、やはりあまりに速いので何なのか分からない。そいつは矢のように、また道向こうのビル影に飛び込んだ。
その後ろを、またがらくた王が息を切らしながら追いかけてきた。まるでコントだ。がらくた王はまた、こちらに近づいてきた。
「また、さっきの奴走ってきませんでした?」
私はまた、ビル影を指差した。がらくた王はまた、ビル影に消える。今度は、がらくた王がいなくなった瞬間、灰色のものが走ってきた。今度はよく見ようとしたけれども、がらくた王が言うように、小動物みたいなものだということしか分からなかった。そいつが消えると、やはりがらくた王が現れた。
がらくた王は疲れ果てたようで、ふらふらとした足取りで近づいてきた。そして、肩をすくめる。
「あいつは僕のことが嫌いで、お嬢さんのことが好きなようだね」
がらくた王は、尻から崩れるように私の目の前のベンチに座り込んだ。悔しそうに頭を掻く。
「何を追いかけているんですか?」
私が聞くと、がらくた王は顔を上げ、ベンチにもたれかかった。
「僕はがらくた王という者なのだけれども、今度がらくた四天王というものを結成するんだ。そのうち、三人は集められたんだが、最後の一人が逃げるばっかりでいっこうに捕まらない」
がらくた四天王最後の一人と聞いて、私ははっとした。急に、寝る前の現実的な問題を思い出す。そして、同時に、あの逃げまくる灰色の何かの正体が分かった。
四天王を考えて、と言われたとき、私は何となく、わくわくした。どんな兵器がいいだろうか。どんな兵器を考え出せるだろうか。けれど同時に、それを考えて、芳香に伝えることがいいことなのか、悪いことなのか分からなかった。そんなことにわくわくすることも、恥ずかしいことのように思えた。たとえば、マンガを描くことのように。
それでも、頭の中は自由で制し難い。気づいたときには、これはいいじゃないか、という四天王の四人目ができていた。ただし、そいつは何の形にもなっていない。私の頭の中だけにいる。それを、がらくた王は迎えにきたのだ。
「今度見かけたら捕まえてくださいね」
と言って、がらくた王はまたビルの影に消えた。彼は、四天王ができていることは知っているけど、それを捕まえることができないのだ。私が、その四人目を明らかにすることを迷っているから。
私は、とりあえず道の方に出た。がらくた王が四人目を捕まえられない理由は、考えたのとは違うかもしれない。違っていればいいな、と思う。だから、そいつを捕まえて、確かめてみようと思ったのだ。道の真ん中に出ると、全てのビル影が見渡せる。私の真横のビルとビルの間の小道も見える。けれど、その向こう側はもやでもかかっているかのように暗くなっていて、まったく見通せなかった。この黒い何かの中を、四天王とがらくた王は、多分、ワープか何かしてぐるぐると回っている。もし、私があの中に入ったらどうなるのだろう。私だけは、彼らのように軽快にワープできないような気がする。
と、その時、私が見ていたもやの中から、灰色の四天王が飛び出してきた。さっきと同じ速さなのに、不思議なことに今はそいつの顔が見えた。
「ピータン」
私はつい、呼びかけてしまった。そう、その猫は私が創作した、四天王の四人目だった。
四天王の四人目は、頭にアンテナを生やした灰色のアンドロイド猫だ。『がらくたマーチ』の未来の世界では、動物は不潔なものとして嫌われる。けれどペットというのは子どもにとっては大切な家族になる。だから、ペットロボットというのがあって当然のはずだ。ロボットならいろんな機能もつけられる。護衛機能や、人語を解する機能、端末にアクセスする能力。しかし、兵器の存在を黙殺し、平和な世界を築こうとする世界にとっては、ペットロボットの護衛機能だって兵器になりうる。ペットロボットたちは家族から引き離され、兵器の墓場に捨てられる。そこでがらくた王に拾われるのだ。
この設定の売りは、兵器であるペットロボットたちが、人間に復讐しつつも昔どおり人間と暮らしたいと願っていることだ。そんな設定ができたのは、がらくた王は復讐よりも、兵器の幸せを願っているような気がしたからだ。がらくた王は、人間を愛したい兵器のために何をしてくれる? それを芳香に問えば、がらくた王の魅力がどこから来るのか分かる気がして、私は四天王の四人目にペットロボット集団のボスを創作した。
私に気づくと、ピータンはスピードジェットを止めて立ち止まった。大きくてつぶらな瞳で、私を睨み上げる。その目は、私が頭の中で想像していた、ペットロボットたちが人間を見る目であった。
「僕を捕まえて、がらくた王に引き渡す度胸があるのかい?」
ピータンは笑いを含んだような、舐め腐った口調で問う。私は、彼の問いに答えることができなかった。ただただ、やっぱり私の創作はなかなかセンスがよかった、とだけ思っていた。この灰色の猫はがらくた王によく似合う。それに、いかつい他の四天王と対照的でいい。けれどセンスがいいと思えば思うほど、何だか無駄なことに労力を使ったような、そんな気持ちになってしまう。
私の気持ちがどちらかにたどり着かないうちに、ピータンは私の横をすり抜け、勢いよく走り出した。それと同時に、さっきピータンが出てきた黒いもやの中から、息を切らしたがらくた王が出てくる。
がらくた王は肩で息をしながら、
「なるほど、道理で追いつけないわけだ」
と、少し怒ったような口調で言った。虫取り網を杖に、こちらへ近づいてくる。
「僕は僕の世界、つまり芳香の想像世界にいるつもりだったが、彼を追って君の世界へ踏み込んでいたようだ。世界が違えばルール、つまり支配者が違う。ここで君に歯向かうようなことはできないってわけだね。
けれども、それなら」
がらくた王はそこで言葉を一旦切った。その時、一瞬ではあるが唇を尖らせる、芳香のような表情を浮かべたが、すぐに唇を真一文字に結び私を真正面から見据えた。
「それなら、君はピータンをどうするつもりだい。僕がピータンをどうするか問う前に、君自身の気持ちに問うべきなんじゃないか」
私は、がらくた王から目を逸らした。私はそんなつもりじゃなかったのに。ピータンを宙ぶらりんにするつもりなんかなかった。けれど、ピータンは宙ぶらりんになっている。
ピータンが、宿題の提出物みたいな何でもないものだったら、さっさと芳香に見せて、私はその瞬間にピータンのことを忘れられたのだろう。けれど、ピータン一匹は重いものを背負っている。だから私は彼について悩んでいる。彼が何だったのか、私はすぐに分かった。素直になればすぐに考え付くものだった。
「彼は、仲立ちなの」
言って私は、顔をあげた。少し涙目になった目で、がらくた王を見据えた。
「今から私、ピータンを捕まえに行くわ」
そう言って私は、さっきピータンが消えたビル影に向かった。黒いもや。向こう側は全く見えない。けれど、どこに繋がっているのか、私には見えなくても、分かった。
出来るだけ、背筋をのばして、歩いていく。もやは、向こう側が見えないほど濃かったのに、暗闇の幅は意外と短い。私はあっという間にもやの向こう側にいた。
目の前に広がったのは、見慣れた私の国、私の物語の国だった。心の中で、広げるともなく広げ、物語るともなく物語った世界。それは、私が思ったよりずっと壮大で、ずっと美しい。ここには、千の私がいる。樹木の一つ、水の一滴が全て私を反映している。
いつでも、私は日常を生きながら、同時にこの、私の物語の世界を生きてきた。生活での悩みや苦しみを、ここで解決しようとあがいた。結局解決しなかったことが多かったけれども、こうして見渡せば、あがいた歴史がこの世界に刻まれて、年輪みたいになってこの世界をこんな、壮大なものにしたのだ。
この国を高台から見つめていると、私の側にピータンが擦り寄ってきた。
「来るとは思わなかった。あんた、もっと頑固なんだと思ってた」
「そうでもないわよ。だって、私はここ、好きだもの」
ピータンはふんと鼻で笑った。照れ笑いみたいだった。
私たちが喋っていると、目の前の国から、物語の登場人物たちがやってきた。彼らも、ピータンみたいに照れ笑いを浮かべている。私は、彼らを見て笑った。みんな、やっぱりよくできてる。そう思えるのは、隠し味みたいに、無意識に私を反映させているからだ。
「ピータンを先頭に、行進してがらくた王のところへ行きましょう。凱旋みたいでかっこいいわ」
「まるでお姫様の嫁入り行列みたいだ」
ピータンは笑って、くるりと体を反転させた。私は彼の横に並ぶ。私のすぐ後ろには、私のキャラクターの主人公が続いてくれた。その後ろに、たくさんの仲間たち。そして、この国そのものが続く。
帰りのもやは行きと違って白かった。その中を、行列して通り抜ける。途中でわたしはおや、と思った。これじゃまるで『がらくたマーチ』だ。がらくた王が兵器を率いて人間の前に再来する「がらくたマーチ」と同じだ。私は、不思議な存在であるがらくた王の気持ちが少し分かった気がした。
廃墟に戻ったとき、がらくた王は私の飛び込んだ筋の前に座り込んでいた。なんと、その時仮面をとっていたのだが、私の気配を感じ取るとすぐに仮面をつけてしまった。惜しいなぁ。
がらくた王は私たちを見て、ぽかんと口を開けた。まさか、こんな大行列で帰ってくるとは思わなかったのだろう。しかし、すぐに笑顔になった。
「いいじゃないか。お姫様の嫁入りみたいで」
がらくた王の感想に、ピータンが私を睨み上げた。が、すぐに歯を見せて笑った。
「なんとも、ダメそうな王様だね。作者の力量が知れるよ。瀬莉華の方が十倍マシ」
私はむすっとしているピータンを抱き上げた。
「あんたのことは私が全面プロデュースする。あんたの物語は、私が考えるわ」
ピータンと笑いあったとき、夢が終わった。
目を覚ましたとき、目の前に芳香がいた。芳香は、にやにやしながら私を見ている。
「ねえ、寝言を言ってたよ。ネコロイドのピータン、アンテナ猫って。どうすんの? 学校の友達とかに聞かれてたら」
「その時は芳香みたいに腹を括るわ」
私は冗談めかして言って、ペンを持ち直した。
「四天王の四番目はネコロイドのピータン。紙、貸してくれない?」
「お、急に前向き発言だね」
「考えてあげるわ。だけど、話も考えさせて。あんたやがらくた王は迷惑するかもしれないけどね」
風穴が開いたみたいだ。外へ外へと、私の中身が吸い出されていく。私がピータンに乗って、新しい冒険に行くようだ。そこで、私は何に出会うだろう? 怖い気がする。けれども、楽しいことも多そうだ。宝物も見つかるかもしれない。
なんだが、わくわくしてきた。私の物語の世界が、お祭りでもしているのかもしれない。
※ 作品の無断転載を禁じます。
その時、私ははたと立ち止まった。同じ高校の理沙が、短いスカートの下に短パンを穿いた格好で、犬の散歩をしている。手にはケータイを持って、メールをしているようだった。
私は、学校では彼女と同じような短いスカートで通している。理沙は、学校では一番の友達だ。彼女がメールを打っている相手は私かもしれない。しかし、理沙は夢にも思わないだろう。友達の瀬莉華が、わざわざ制服をぬいでジャージに着替え、顔が見えないようにマフラーを巻いて、帽子まで被って、こそこそとマンガを描きに行こうとしているだなんて。
私は今、忍者みたいだ。毎回、芳香(ほうか)の家に行くたびに誰かに見咎められやしまいかと警戒している。忍者と私に共通していることは、見つかっちゃいけないような秘密を抱えているということ。理沙が行き過ぎても、私はしばらく動かなかった。
理沙は、中学生のころ、私と芳香の家の間くらいの所に引っ越してきた。私と芳香はそれより前から親友だったけれども、理沙が越してきたころには、私は忍者になっていた。だから理沙は、自分が芳香をバカにしているように、私も芳香をバカにしていると思っている。
マンガを描くなんて、ダサい。芳香なんてオタクだ。キモい。そういわれ始めた時から、私は芳香から離れだした。あれは、中学に入るか、入らないかくらいのころだったか。同じように見られて、みんなにバカにされるのが嫌だった。そう思いはじめたら、芳香自身についても友達づきあいするに値しない子のように思えた。
結局、学校では、私と芳香は無視しあうようになった。芳香も、その点で言えば空気を読んでくれていたのだろう。けれど、不思議なことにマンガを描きにいくことだけは、今の今まで続いている。こんな忍者まがいのことをしてでも、芳香の家に行かない、という選択肢は考えられなかった。これはとても、不思議なことだ。
芳香の家は武家屋敷みたいな豪華な家だ。今は普通の家庭なのだが、昔はかなりのお金持ちだったらしい。特に凄いのは玄関で、人の出入りする場所のはずなのに、何となく、人を拒むような雰囲気があった。
そのせいなのか、それとも幼い頃からこの家に出入りしているせいか、私はいつも勝手口からあがっていた。勝手口から入るとすぐに台所だ。私は「おじゃまします」も言わないで上がりこんだ。台所と繋がっているリビングでは、芳香のお母さんがコタツに入って寝ている。私が犯罪者だったらどうするつもりだろう、と思うけれども、私だと分かって寝ている気もする。
私はこの家の人のような顔をして奥へ進み、芳香の部屋のドアをあけた。ストーブのせいで澱んだ空気と、インクの臭いがぶわっと外まで流れ出る。芳香は、勉強机に座って、天上を眺めていた。
芳香は華奢で小さな女の子だ。顔立ちは可愛いのだが、唇を尖らせる変な癖があるので可愛いことはあまり知られていない。今も、尖らせた唇と鼻の間に鉛筆を挟んでいる。彼女の手元には、絵の描かれた紙があった。たぶん、あれは学校でもらったプリントの裏紙だ。
私は何も言わず、部屋の中心に置かれた座机に向かった。勉強机が芳香、この机が私の場所と決まっている。私の場所には、所々背景が描かれていない原稿が置かれていた。この背景を埋め尽くしていくのが、私の仕事というわけだ。
道具は自分の道具がある。それらを広げて、白いところに鉛筆で書かれた指示通りの背景を描く。私は、人物は描けないが、風景は芳香より上手に描けた。
「森」と描かれたところには、すでにがらくた王がいる。芳香が中学生のころから描いている『がらくたマーチ』という物語の悪役で、かつてライバルだったアンドロイドから剥ぎ取った機械の顔を、仮面として自分がつけている、という奇怪な男だ。仮面は目元だけ覆っていて、口元は見えている。不思議なもので、口元しか見えないのに、この男は魅力的に思われた。
私はこのがらくた王が、芳香のキャラクターのなかで一番好きだった。戦争が終わって捨てられた兵器を率いて人間に復讐するという恐ろしいやつなのだが、私はただの悪役ではないと確信している。きっと、この人のバックグラウンドには深い謎があるのだ。ただ、芳香はいくら聞いてもその謎を教えてくれなかった。
しばらく黙って森を描いていると、芳香が立ち上がって、私の机の向こう側に座った。その手には、さっきの裏紙が握られている。
「がらくた王四天王、四人目考えてきてくれた?」
紙には、三つの絵が描かれていた。がらくた王は兵器の王様なので、その四天王も戦車にアンドロイド、ハッキング用プログラムということになっている。私は、曖昧な笑みを浮かべ、首を振った。
「あんたが考えなさいよ。私、そういうの考えられないわ」
芳香は私が背景を描いていた原稿に目を落とした。芳香は人の目を見て話さない。相手の反応を見ないで、自分の言いたいことだけを言う。
「考えられないって、そんなことないでしょ。昔は色々、物語を考えてたじゃん」
「小学生のころでしょ? 大昔のことだわ」
芳香は、唇をとがらせた。どう見たって何か言いたげだったが、何も言わなかった。芳香は破天荒に見られがちだが、意外と気を遣っている。人の目を見ないのも、人の反応を見れば気が引けるからだろう。
「大体、一人だけ他の人が考えたキャラクターが混じっていたら、おかしく思われるんじゃない。どうするの、私がマンガを描いてるってバレたら」
芳香は泣き出しそうな人のように眉をしかめたまま、立ち上がって、勉強机に戻った。私は、机の上に残されていた三人だけの四天王の絵を机の下におろした。
一箇所、背景を埋め終えると次の背景も「森」だった。単純作業を続けていると、段々疲れてくる。芳香のわずかな友達の目にしか触れないマンガなのに、どうして芳香は、こんなに労力をかけるのだろう。あんたはプロじゃないんだよ、と言いたくなる。
それにしたって、空気が悪い。気づけば、二三度、瞬間的に意識がなくなる。要するにこれは眠いんだ、と気づいたときには、私は眠っていた。
夕日を浴びて、長い影を伸ばすビル群。そこに人は一人もいない。きちんと背筋を伸ばして建っているように見えるビルも、よく見ればどれも窓ガラスが吹っ飛んでいて、中にあったものは吹き出された後である。そのとき中にいたはずの人はどうなったのか、それはよく分からないが、今ここに人は私一人っきりだということはよく分かる。
断言していい。私は夢を見ている。なぜなら、この、荒廃したビル群は『がらくたマーチ』の背景なのだ。よく、枕の下に絵を敷いて寝るとその夢を見ると言うが、その要領で私は『がらくたマーチ』の夢を見ているのだ。多分。
私はバス停のベンチに座って、辺りを見回した。気が付いたら、という言い方は正しいのかどうか分からないけれども、ともかく私はここにいた。生き物がいそうな気配は少しもない。音もしない。こんな場所は、地球のどこを探したって見当たらないだろう。
その時、目の前の道路を灰色の何かが駆け抜けた。走るのが凄く速かったのでそれが何だったのか、私には分からない。何かは、ビルの隙間にするりと入って見えなくなった。あまりに唐突なことだったので、今見たものが実際にあったものか、気のせいなのか、それすら分からないでいると、その後を追うように、男が走ってきた。
その男を見たとき、私はぎょっとした。その男は、間違いなく、がらくた王だったのである。ここが『がらくたマーチ』の夢ならば驚くことではないのかもしれないけれども、何しろマンガの登場人物が自分と同じように立体の体を持って、確かにそこに、人間として存在しているのだ。驚いて当然だろう。
がらくた王は、黒いコートに例のアンドロイドの仮面、そして、なぜか手には虫取り網を持って、おおいに息を切らしながら走ってきた。だが、ちょうど道の真ん中あたりで、立ち止まってしまう。どうやら力尽きたようだった。彼は何かを探すようにあたりを見回す。そのとき、私と目が合った。
彼は、口元だけでそれとわかるくらいの笑みを浮かべ、虫取り網を杖にして、こちらに近づいてきた。
「ちょっと、すみません。伺いたいことがあるのですが」
私が想像していたより低い声だった。それに、近づいてみるとかなり背が高い。私はがらくた王を二十代前半の若い男だと思っていたが、こうして見るともしかしたらもう少し上かもしれなかった。ただ、目元が見えないのでよくは分からない。
「さっき、ここを何か、こう、小さな、小動物みたいなものが通りませんでしたか?」
きっとさっき私が目撃したものだ。私は、頷いた。
「どっちに行ったか分かりますか?」
私は、さっきのものが消えた所を指差した。がらくた王は丁寧にお礼を言って、ビル影へと消えていく。私は呆然として、その背中を見送った。マンガのキャラクターと喋っている夢を見ているなんて、学校のみんなに知れたら死ねると思っていると、また、ビル影から例のすばしっこいものが飛び出した。ただ、やはりあまりに速いので何なのか分からない。そいつは矢のように、また道向こうのビル影に飛び込んだ。
その後ろを、またがらくた王が息を切らしながら追いかけてきた。まるでコントだ。がらくた王はまた、こちらに近づいてきた。
「また、さっきの奴走ってきませんでした?」
私はまた、ビル影を指差した。がらくた王はまた、ビル影に消える。今度は、がらくた王がいなくなった瞬間、灰色のものが走ってきた。今度はよく見ようとしたけれども、がらくた王が言うように、小動物みたいなものだということしか分からなかった。そいつが消えると、やはりがらくた王が現れた。
がらくた王は疲れ果てたようで、ふらふらとした足取りで近づいてきた。そして、肩をすくめる。
「あいつは僕のことが嫌いで、お嬢さんのことが好きなようだね」
がらくた王は、尻から崩れるように私の目の前のベンチに座り込んだ。悔しそうに頭を掻く。
「何を追いかけているんですか?」
私が聞くと、がらくた王は顔を上げ、ベンチにもたれかかった。
「僕はがらくた王という者なのだけれども、今度がらくた四天王というものを結成するんだ。そのうち、三人は集められたんだが、最後の一人が逃げるばっかりでいっこうに捕まらない」
がらくた四天王最後の一人と聞いて、私ははっとした。急に、寝る前の現実的な問題を思い出す。そして、同時に、あの逃げまくる灰色の何かの正体が分かった。
四天王を考えて、と言われたとき、私は何となく、わくわくした。どんな兵器がいいだろうか。どんな兵器を考え出せるだろうか。けれど同時に、それを考えて、芳香に伝えることがいいことなのか、悪いことなのか分からなかった。そんなことにわくわくすることも、恥ずかしいことのように思えた。たとえば、マンガを描くことのように。
それでも、頭の中は自由で制し難い。気づいたときには、これはいいじゃないか、という四天王の四人目ができていた。ただし、そいつは何の形にもなっていない。私の頭の中だけにいる。それを、がらくた王は迎えにきたのだ。
「今度見かけたら捕まえてくださいね」
と言って、がらくた王はまたビルの影に消えた。彼は、四天王ができていることは知っているけど、それを捕まえることができないのだ。私が、その四人目を明らかにすることを迷っているから。
私は、とりあえず道の方に出た。がらくた王が四人目を捕まえられない理由は、考えたのとは違うかもしれない。違っていればいいな、と思う。だから、そいつを捕まえて、確かめてみようと思ったのだ。道の真ん中に出ると、全てのビル影が見渡せる。私の真横のビルとビルの間の小道も見える。けれど、その向こう側はもやでもかかっているかのように暗くなっていて、まったく見通せなかった。この黒い何かの中を、四天王とがらくた王は、多分、ワープか何かしてぐるぐると回っている。もし、私があの中に入ったらどうなるのだろう。私だけは、彼らのように軽快にワープできないような気がする。
と、その時、私が見ていたもやの中から、灰色の四天王が飛び出してきた。さっきと同じ速さなのに、不思議なことに今はそいつの顔が見えた。
「ピータン」
私はつい、呼びかけてしまった。そう、その猫は私が創作した、四天王の四人目だった。
四天王の四人目は、頭にアンテナを生やした灰色のアンドロイド猫だ。『がらくたマーチ』の未来の世界では、動物は不潔なものとして嫌われる。けれどペットというのは子どもにとっては大切な家族になる。だから、ペットロボットというのがあって当然のはずだ。ロボットならいろんな機能もつけられる。護衛機能や、人語を解する機能、端末にアクセスする能力。しかし、兵器の存在を黙殺し、平和な世界を築こうとする世界にとっては、ペットロボットの護衛機能だって兵器になりうる。ペットロボットたちは家族から引き離され、兵器の墓場に捨てられる。そこでがらくた王に拾われるのだ。
この設定の売りは、兵器であるペットロボットたちが、人間に復讐しつつも昔どおり人間と暮らしたいと願っていることだ。そんな設定ができたのは、がらくた王は復讐よりも、兵器の幸せを願っているような気がしたからだ。がらくた王は、人間を愛したい兵器のために何をしてくれる? それを芳香に問えば、がらくた王の魅力がどこから来るのか分かる気がして、私は四天王の四人目にペットロボット集団のボスを創作した。
私に気づくと、ピータンはスピードジェットを止めて立ち止まった。大きくてつぶらな瞳で、私を睨み上げる。その目は、私が頭の中で想像していた、ペットロボットたちが人間を見る目であった。
「僕を捕まえて、がらくた王に引き渡す度胸があるのかい?」
ピータンは笑いを含んだような、舐め腐った口調で問う。私は、彼の問いに答えることができなかった。ただただ、やっぱり私の創作はなかなかセンスがよかった、とだけ思っていた。この灰色の猫はがらくた王によく似合う。それに、いかつい他の四天王と対照的でいい。けれどセンスがいいと思えば思うほど、何だか無駄なことに労力を使ったような、そんな気持ちになってしまう。
私の気持ちがどちらかにたどり着かないうちに、ピータンは私の横をすり抜け、勢いよく走り出した。それと同時に、さっきピータンが出てきた黒いもやの中から、息を切らしたがらくた王が出てくる。
がらくた王は肩で息をしながら、
「なるほど、道理で追いつけないわけだ」
と、少し怒ったような口調で言った。虫取り網を杖に、こちらへ近づいてくる。
「僕は僕の世界、つまり芳香の想像世界にいるつもりだったが、彼を追って君の世界へ踏み込んでいたようだ。世界が違えばルール、つまり支配者が違う。ここで君に歯向かうようなことはできないってわけだね。
けれども、それなら」
がらくた王はそこで言葉を一旦切った。その時、一瞬ではあるが唇を尖らせる、芳香のような表情を浮かべたが、すぐに唇を真一文字に結び私を真正面から見据えた。
「それなら、君はピータンをどうするつもりだい。僕がピータンをどうするか問う前に、君自身の気持ちに問うべきなんじゃないか」
私は、がらくた王から目を逸らした。私はそんなつもりじゃなかったのに。ピータンを宙ぶらりんにするつもりなんかなかった。けれど、ピータンは宙ぶらりんになっている。
ピータンが、宿題の提出物みたいな何でもないものだったら、さっさと芳香に見せて、私はその瞬間にピータンのことを忘れられたのだろう。けれど、ピータン一匹は重いものを背負っている。だから私は彼について悩んでいる。彼が何だったのか、私はすぐに分かった。素直になればすぐに考え付くものだった。
「彼は、仲立ちなの」
言って私は、顔をあげた。少し涙目になった目で、がらくた王を見据えた。
「今から私、ピータンを捕まえに行くわ」
そう言って私は、さっきピータンが消えたビル影に向かった。黒いもや。向こう側は全く見えない。けれど、どこに繋がっているのか、私には見えなくても、分かった。
出来るだけ、背筋をのばして、歩いていく。もやは、向こう側が見えないほど濃かったのに、暗闇の幅は意外と短い。私はあっという間にもやの向こう側にいた。
目の前に広がったのは、見慣れた私の国、私の物語の国だった。心の中で、広げるともなく広げ、物語るともなく物語った世界。それは、私が思ったよりずっと壮大で、ずっと美しい。ここには、千の私がいる。樹木の一つ、水の一滴が全て私を反映している。
いつでも、私は日常を生きながら、同時にこの、私の物語の世界を生きてきた。生活での悩みや苦しみを、ここで解決しようとあがいた。結局解決しなかったことが多かったけれども、こうして見渡せば、あがいた歴史がこの世界に刻まれて、年輪みたいになってこの世界をこんな、壮大なものにしたのだ。
この国を高台から見つめていると、私の側にピータンが擦り寄ってきた。
「来るとは思わなかった。あんた、もっと頑固なんだと思ってた」
「そうでもないわよ。だって、私はここ、好きだもの」
ピータンはふんと鼻で笑った。照れ笑いみたいだった。
私たちが喋っていると、目の前の国から、物語の登場人物たちがやってきた。彼らも、ピータンみたいに照れ笑いを浮かべている。私は、彼らを見て笑った。みんな、やっぱりよくできてる。そう思えるのは、隠し味みたいに、無意識に私を反映させているからだ。
「ピータンを先頭に、行進してがらくた王のところへ行きましょう。凱旋みたいでかっこいいわ」
「まるでお姫様の嫁入り行列みたいだ」
ピータンは笑って、くるりと体を反転させた。私は彼の横に並ぶ。私のすぐ後ろには、私のキャラクターの主人公が続いてくれた。その後ろに、たくさんの仲間たち。そして、この国そのものが続く。
帰りのもやは行きと違って白かった。その中を、行列して通り抜ける。途中でわたしはおや、と思った。これじゃまるで『がらくたマーチ』だ。がらくた王が兵器を率いて人間の前に再来する「がらくたマーチ」と同じだ。私は、不思議な存在であるがらくた王の気持ちが少し分かった気がした。
廃墟に戻ったとき、がらくた王は私の飛び込んだ筋の前に座り込んでいた。なんと、その時仮面をとっていたのだが、私の気配を感じ取るとすぐに仮面をつけてしまった。惜しいなぁ。
がらくた王は私たちを見て、ぽかんと口を開けた。まさか、こんな大行列で帰ってくるとは思わなかったのだろう。しかし、すぐに笑顔になった。
「いいじゃないか。お姫様の嫁入りみたいで」
がらくた王の感想に、ピータンが私を睨み上げた。が、すぐに歯を見せて笑った。
「なんとも、ダメそうな王様だね。作者の力量が知れるよ。瀬莉華の方が十倍マシ」
私はむすっとしているピータンを抱き上げた。
「あんたのことは私が全面プロデュースする。あんたの物語は、私が考えるわ」
ピータンと笑いあったとき、夢が終わった。
目を覚ましたとき、目の前に芳香がいた。芳香は、にやにやしながら私を見ている。
「ねえ、寝言を言ってたよ。ネコロイドのピータン、アンテナ猫って。どうすんの? 学校の友達とかに聞かれてたら」
「その時は芳香みたいに腹を括るわ」
私は冗談めかして言って、ペンを持ち直した。
「四天王の四番目はネコロイドのピータン。紙、貸してくれない?」
「お、急に前向き発言だね」
「考えてあげるわ。だけど、話も考えさせて。あんたやがらくた王は迷惑するかもしれないけどね」
風穴が開いたみたいだ。外へ外へと、私の中身が吸い出されていく。私がピータンに乗って、新しい冒険に行くようだ。そこで、私は何に出会うだろう? 怖い気がする。けれども、楽しいことも多そうだ。宝物も見つかるかもしれない。
なんだが、わくわくしてきた。私の物語の世界が、お祭りでもしているのかもしれない。
※ 作品の無断転載を禁じます。