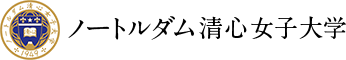2012.04.12
本学科の授業科目「文学創作論」では、履修生が1年をかけて作り上げた作品をまとめて、文集を発
行しています。
ここでは、第7集『望月草』(2009年度)より、1作品をご紹介します。
文集は、オープンキャンパスなどでご希望の方にお頒ちしております。機会がありましたらぜひお手
にとってみてください。
花便り
作・恩部千浪
行しています。
ここでは、第7集『望月草』(2009年度)より、1作品をご紹介します。
文集は、オープンキャンパスなどでご希望の方にお頒ちしております。機会がありましたらぜひお手
にとってみてください。
花便り
作・恩部千浪
届いたばかりの手紙が、ふゆきの膝の上にある。先ほど、家の中でじっと耳を澄ませていたふゆきが、バイクの音を聞きつけてすぐにポストへ向かって取り出したものだ。
もやもやを吐き出すように息をついて、ふゆきは縁側に座った。簡素な白い封筒を手にとる。表には、崩しながらも美しさを損なわない字でふゆきの名前が書いてあり、裏へ向けてみると左下に「植物博士」の字があって、ふゆきは少し笑った。厚みを確認するように封筒を押した。
(二枚かな)
封を開けて手紙を取り出した。やはり二枚の紙がたたんである。
[お久しぶりです。返事が遅れて申し訳ない。]
「いつものことじゃん」
ふゆきは強がるように言った。
[春になって、君も高校生になるんだね。今年は四月初めでも暖かいから、お家にある桜が早めに咲くんじゃないだろうか。]
庭から木の枝や葉のぶつかり合う音がして、ふゆきは手紙から目を放した。春の突風が敷いてあるじゃり石をあちこちに転がし、ふゆきの庭をかき回した。
一際大きな音を立てたのが、ふゆきの目の前にある御(ぎよ)衣(い)黄(こう)桜(ざくら)だった。
特徴的な黄緑色の花びらは、この地域周辺では名物だ。
「文通も、今年で四年目に突入か」
ふゆきは博士宛に送ってきた手紙の数々を思い返して、一人気恥ずかしくなった。
(昔の自分を殴ってやりたいくらい散々だったな)
博士から手紙が来ても、すぐに返さず日にちを置いて返事を出した。自分を苦しめる結果になっても、余裕ぶっていたかったのだ。
「博士は、もうこの桜を見に来る気はないのかな」
言葉にしてから酷く苦い顔をして、ふゆきは目を閉じた。
小学六年生になっても、ふゆきはあまり身長が伸びなかった。御衣黄桜の木の下に立って、満開になった枝に爪先立ちで手を伸ばすが、なかなか届かない。その場でぴょこぴょことジャンプするが、指先に掠る程度だった。
「もぉ」
ふゆきはじゃり石を蹴飛ばした。一度御衣黄桜から離れ、そこから勢い込んで助走をつける。腕を大きく振りかぶると、渾身の力で地面を蹴って飛び上がり、両手でしっかり太い枝につかまった。
「やった」
足をぶらぶらさせながら、達成感で息をはずませた。しかし、身動きができずにただぶら下がることしかできない。
「ああー、桜がとれない」
手を移動させようとすると、頭の上に樹皮がぱらぱらと落ちてきた。
なすすべもないままぶらぶらとしていると、庭の入り口から人がくる足音がして、ぱっとそちらの方へ首を廻らせた。若い青年が、目をまん丸にして木にぶら下がっているふゆきを見ていた。
「こんにちは」
なんとも格好がつかず、ふゆきは目を逸らしながらしらっと挨拶をした。すると、青年は堪えかねたように吹き出して、その笑顔のままふゆきに話しかけた。
「こんにちは。遊んでるの」
「違うよ。花びらに触りたいから」
「でも、それじゃ手が使えないよね」
ふゆきが押し黙ってしまうと、青年はさくさくと近づいてきたかと思うと、ちょっと失礼と一言、人形でも持ち上げるようにふゆきを抱き上げた。突然のことでふゆきはどうすることもできずにただ固まっていると、青年はふゆきの目の前に花がくるようにしてみせた。
「ほら、これで触れるよ」
青年に言われ、ふゆきはやっと花に目がいった。花びらに手を伸ばすと、まず厚みを確かめるようにつまんで、次に指先で撫でてみた。「食べてみたい」
「桜の塩漬けならあるよ。お茶に入れるんだ。でも御衣黄桜を食べるっていうのは聞いたことがない
なぁ」
「甘いのが食べたいの」
「ジャムにしたら、意外とおいしいかもしれないね」
「うんうん」
大きく首を振って嬉しそうに頷いた。
「これ、花びらがいっぱい重なってて、妖精のドレスみたいだなっていっつも思ってた」
「八重咲きっていうんだよ。確かに花びらが裾みたいに広がってるよね。御衣黄っていう名前も、もともとは貴族の衣装の色に似ているところが由来なんだって」
「へぇ~、貴族って外国の?」
「日本の」
「なぁーんだ」
ふゆきは改めて青年をまじまじと見た。
「お兄さん、なんでも知ってるんだね」
「一応植物を研究してるからね。特に桜が好きで」
「この御衣黄を見に来たんだ」
「ここの近くに住んでるんだ。珍しい桜が咲くって聞いたから見せてもらおうと思ってね」
「研究、ってことは博士だ」
「いや、ただの大学生だよ」
「でも研究してるんでしょ」
「うん、まあ」
「じゃあやっぱり博士ね」
困ったな、と博士は笑ったが、ふゆきは譲らなかった。勝ったというようににんまりと口端を上げたが、不意に博士が抱きなおすようにふゆきを揺らすと、途端に顔を真っ赤にさせた。
「もう下ろしていいよ」
羞恥心で焦らないように、精一杯平然と言った。博士は急に様子が変わったふゆきに首をかしげながらゆっくり地面に下ろした。
今度はきゅっと唇を引き結んで仏頂面になったふゆきだが、博士の近くからは離れなかった。
(そんなすぐに下ろさなくてもいいのに)
今さら口に出しては言えず、ふゆきはぷいっと顔を背けてしまった。
ちょっとした間(ま)に沈黙が続き、言葉が出てこずいよいよふゆきがそわそわとし始めた時、博士が腕時計を見て、あっ、と声を上げた。
「まずい、戻らないと」
「え、帰るの」
「うん、ちょっと用事があって。また今度遊びに来てもいいかな」
「来たいならいつでも来ればいいよ」
少々つっけんどんな物言いをしてしまい、言い終わってからふゆきは焦ったが、博士はありがとう、と言葉を置いて、すぐに立ち去ってしまった。
博士は二週間後にまたふゆきの家を訪ねてきた。友達の家にも遊びに行かず、毎日何気なさを装って縁側に座っていたふゆきは思わず駆け寄りそうになった。
「また遊びに来たよ」
にこにことしながらふゆきの隣に座った博士に、たまたま居合わせたように驚いた顔をして、いらっしゃい、と声をかけた。
「残念だったね、御衣黄はもう散っちゃったよ」
「うん、本当はすごく見たかったんだけど時間がなくて」
博士は心底がっかりしたようにため息をついた。ふゆきはじっと様子を窺っていたが、隠すように持っていた栞(しおり)を勢いのまま博士の手にばちんと乗せた。
「これ作ったからあげる」
「え、これって。御衣黄の押し花?」
「赤くなって落ちてきたやつ。全然豪華じゃないけど」
御衣黄桜は、日にちがたつごとに花の色が変わり、最後には紅に近い色で花ごと地面に落ちる。ふゆきは庭いっぱいに落ちている様子を知っているだけに、押し花はとても貧相なものに見えた。しかし、博士はとびきりの笑顔をふゆきに向けた。
「ありがとう、大事に使わせてもらうよ」
ふゆきは博士とは反対側に身体(からだ)が傾いだ。手をついて倒れこまないようにするのに必死だった。
(小学校を卒業するくらいまで、いっつも二人で植物観察をしてたな)
ふゆきの目元がじんわりと熱くなった。
中学校に入っても博士のことが気になって、友達もできず一人で孤立していたとき博士から手紙がきた。
ふゆきはすがるような思いで内容をろくに把握せずに返事を書きなぐった。
(あれも消せるものなら消してしまいたい)
だが、一度ふゆきが捨ててしまってもいい、と手紙に書いたら絶対に嫌だと断られたため、すでになすすべがない。
飛ばないように押さえていた手紙に再び視線を戻した。御衣黄桜が咲く季節になると、ふゆきは博士からの手紙を読むのが億劫になる。
[いつも押し花を送ってくれてありがとう。でもこれからは送ってくれなくてもいいよ。]
え、とふゆきは思わず声をもらした。押し花を作って博士に送ることが、手紙の文面よりもふゆきの想いを真っ直ぐに伝えることができる唯一の手段だった。
(もう文通が嫌になっちゃったの)
手紙を中断されることを恐れて、博士への手紙には必ず、返事はいつでもいいからね、と書いている。やせ我慢でもなんでも、続けられないよりましだと思った。
手紙から目を逸らそうとしたふゆきだが、強引に視線を戻した。ここで避けるわけにはいかない。
[実は、この春から君の高校で教師をすることになったんだ。これからも押し花を作ってくれるなら、直接渡してね]
高速で走り回る衝撃が、ふゆきの心臓を轢(ひ)いて通り過ぎていった。
[成長したふゆきちゃんに会えるのを楽しみにしてるよ]
ふゆきはふっと笑いがもれた。
「とか言って、あたしがチビのままだと思ってるんでしょ」
みてろよ、とふゆきはつぶやいた。
(この想いは本物)
ただの憧れだと友達に言われ迷ったこともあったが、ふゆきは手紙を書き続け、押し花を送り続けた。
「博士への返事は決まりだな」
ふゆきが手紙に絶対に書かなかった言葉があった。どうやら次の手紙には、書いても問題無さそうだ。
今度家に来る時は、御衣黄桜の散り時に間に合わせて下さいね。
※作品の無断転載を禁じます。
もやもやを吐き出すように息をついて、ふゆきは縁側に座った。簡素な白い封筒を手にとる。表には、崩しながらも美しさを損なわない字でふゆきの名前が書いてあり、裏へ向けてみると左下に「植物博士」の字があって、ふゆきは少し笑った。厚みを確認するように封筒を押した。
(二枚かな)
封を開けて手紙を取り出した。やはり二枚の紙がたたんである。
[お久しぶりです。返事が遅れて申し訳ない。]
「いつものことじゃん」
ふゆきは強がるように言った。
[春になって、君も高校生になるんだね。今年は四月初めでも暖かいから、お家にある桜が早めに咲くんじゃないだろうか。]
庭から木の枝や葉のぶつかり合う音がして、ふゆきは手紙から目を放した。春の突風が敷いてあるじゃり石をあちこちに転がし、ふゆきの庭をかき回した。
一際大きな音を立てたのが、ふゆきの目の前にある御(ぎよ)衣(い)黄(こう)桜(ざくら)だった。
特徴的な黄緑色の花びらは、この地域周辺では名物だ。
「文通も、今年で四年目に突入か」
ふゆきは博士宛に送ってきた手紙の数々を思い返して、一人気恥ずかしくなった。
(昔の自分を殴ってやりたいくらい散々だったな)
博士から手紙が来ても、すぐに返さず日にちを置いて返事を出した。自分を苦しめる結果になっても、余裕ぶっていたかったのだ。
「博士は、もうこの桜を見に来る気はないのかな」
言葉にしてから酷く苦い顔をして、ふゆきは目を閉じた。
小学六年生になっても、ふゆきはあまり身長が伸びなかった。御衣黄桜の木の下に立って、満開になった枝に爪先立ちで手を伸ばすが、なかなか届かない。その場でぴょこぴょことジャンプするが、指先に掠る程度だった。
「もぉ」
ふゆきはじゃり石を蹴飛ばした。一度御衣黄桜から離れ、そこから勢い込んで助走をつける。腕を大きく振りかぶると、渾身の力で地面を蹴って飛び上がり、両手でしっかり太い枝につかまった。
「やった」
足をぶらぶらさせながら、達成感で息をはずませた。しかし、身動きができずにただぶら下がることしかできない。
「ああー、桜がとれない」
手を移動させようとすると、頭の上に樹皮がぱらぱらと落ちてきた。
なすすべもないままぶらぶらとしていると、庭の入り口から人がくる足音がして、ぱっとそちらの方へ首を廻らせた。若い青年が、目をまん丸にして木にぶら下がっているふゆきを見ていた。
「こんにちは」
なんとも格好がつかず、ふゆきは目を逸らしながらしらっと挨拶をした。すると、青年は堪えかねたように吹き出して、その笑顔のままふゆきに話しかけた。
「こんにちは。遊んでるの」
「違うよ。花びらに触りたいから」
「でも、それじゃ手が使えないよね」
ふゆきが押し黙ってしまうと、青年はさくさくと近づいてきたかと思うと、ちょっと失礼と一言、人形でも持ち上げるようにふゆきを抱き上げた。突然のことでふゆきはどうすることもできずにただ固まっていると、青年はふゆきの目の前に花がくるようにしてみせた。
「ほら、これで触れるよ」
青年に言われ、ふゆきはやっと花に目がいった。花びらに手を伸ばすと、まず厚みを確かめるようにつまんで、次に指先で撫でてみた。「食べてみたい」
「桜の塩漬けならあるよ。お茶に入れるんだ。でも御衣黄桜を食べるっていうのは聞いたことがない
なぁ」
「甘いのが食べたいの」
「ジャムにしたら、意外とおいしいかもしれないね」
「うんうん」
大きく首を振って嬉しそうに頷いた。
「これ、花びらがいっぱい重なってて、妖精のドレスみたいだなっていっつも思ってた」
「八重咲きっていうんだよ。確かに花びらが裾みたいに広がってるよね。御衣黄っていう名前も、もともとは貴族の衣装の色に似ているところが由来なんだって」
「へぇ~、貴族って外国の?」
「日本の」
「なぁーんだ」
ふゆきは改めて青年をまじまじと見た。
「お兄さん、なんでも知ってるんだね」
「一応植物を研究してるからね。特に桜が好きで」
「この御衣黄を見に来たんだ」
「ここの近くに住んでるんだ。珍しい桜が咲くって聞いたから見せてもらおうと思ってね」
「研究、ってことは博士だ」
「いや、ただの大学生だよ」
「でも研究してるんでしょ」
「うん、まあ」
「じゃあやっぱり博士ね」
困ったな、と博士は笑ったが、ふゆきは譲らなかった。勝ったというようににんまりと口端を上げたが、不意に博士が抱きなおすようにふゆきを揺らすと、途端に顔を真っ赤にさせた。
「もう下ろしていいよ」
羞恥心で焦らないように、精一杯平然と言った。博士は急に様子が変わったふゆきに首をかしげながらゆっくり地面に下ろした。
今度はきゅっと唇を引き結んで仏頂面になったふゆきだが、博士の近くからは離れなかった。
(そんなすぐに下ろさなくてもいいのに)
今さら口に出しては言えず、ふゆきはぷいっと顔を背けてしまった。
ちょっとした間(ま)に沈黙が続き、言葉が出てこずいよいよふゆきがそわそわとし始めた時、博士が腕時計を見て、あっ、と声を上げた。
「まずい、戻らないと」
「え、帰るの」
「うん、ちょっと用事があって。また今度遊びに来てもいいかな」
「来たいならいつでも来ればいいよ」
少々つっけんどんな物言いをしてしまい、言い終わってからふゆきは焦ったが、博士はありがとう、と言葉を置いて、すぐに立ち去ってしまった。
博士は二週間後にまたふゆきの家を訪ねてきた。友達の家にも遊びに行かず、毎日何気なさを装って縁側に座っていたふゆきは思わず駆け寄りそうになった。
「また遊びに来たよ」
にこにことしながらふゆきの隣に座った博士に、たまたま居合わせたように驚いた顔をして、いらっしゃい、と声をかけた。
「残念だったね、御衣黄はもう散っちゃったよ」
「うん、本当はすごく見たかったんだけど時間がなくて」
博士は心底がっかりしたようにため息をついた。ふゆきはじっと様子を窺っていたが、隠すように持っていた栞(しおり)を勢いのまま博士の手にばちんと乗せた。
「これ作ったからあげる」
「え、これって。御衣黄の押し花?」
「赤くなって落ちてきたやつ。全然豪華じゃないけど」
御衣黄桜は、日にちがたつごとに花の色が変わり、最後には紅に近い色で花ごと地面に落ちる。ふゆきは庭いっぱいに落ちている様子を知っているだけに、押し花はとても貧相なものに見えた。しかし、博士はとびきりの笑顔をふゆきに向けた。
「ありがとう、大事に使わせてもらうよ」
ふゆきは博士とは反対側に身体(からだ)が傾いだ。手をついて倒れこまないようにするのに必死だった。
(小学校を卒業するくらいまで、いっつも二人で植物観察をしてたな)
ふゆきの目元がじんわりと熱くなった。
中学校に入っても博士のことが気になって、友達もできず一人で孤立していたとき博士から手紙がきた。
ふゆきはすがるような思いで内容をろくに把握せずに返事を書きなぐった。
(あれも消せるものなら消してしまいたい)
だが、一度ふゆきが捨ててしまってもいい、と手紙に書いたら絶対に嫌だと断られたため、すでになすすべがない。
飛ばないように押さえていた手紙に再び視線を戻した。御衣黄桜が咲く季節になると、ふゆきは博士からの手紙を読むのが億劫になる。
[いつも押し花を送ってくれてありがとう。でもこれからは送ってくれなくてもいいよ。]
え、とふゆきは思わず声をもらした。押し花を作って博士に送ることが、手紙の文面よりもふゆきの想いを真っ直ぐに伝えることができる唯一の手段だった。
(もう文通が嫌になっちゃったの)
手紙を中断されることを恐れて、博士への手紙には必ず、返事はいつでもいいからね、と書いている。やせ我慢でもなんでも、続けられないよりましだと思った。
手紙から目を逸らそうとしたふゆきだが、強引に視線を戻した。ここで避けるわけにはいかない。
[実は、この春から君の高校で教師をすることになったんだ。これからも押し花を作ってくれるなら、直接渡してね]
高速で走り回る衝撃が、ふゆきの心臓を轢(ひ)いて通り過ぎていった。
[成長したふゆきちゃんに会えるのを楽しみにしてるよ]
ふゆきはふっと笑いがもれた。
「とか言って、あたしがチビのままだと思ってるんでしょ」
みてろよ、とふゆきはつぶやいた。
(この想いは本物)
ただの憧れだと友達に言われ迷ったこともあったが、ふゆきは手紙を書き続け、押し花を送り続けた。
「博士への返事は決まりだな」
ふゆきが手紙に絶対に書かなかった言葉があった。どうやら次の手紙には、書いても問題無さそうだ。
今度家に来る時は、御衣黄桜の散り時に間に合わせて下さいね。
※作品の無断転載を禁じます。