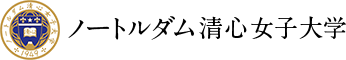2012.04.12
本学科の授業科目「文学創作論」では、履修生が1年をかけて作り上げた作品をまとめて、文集を発
行しています。
ここでは、第6集『汲々』(2008年度)より、1作品をご紹介します。
夕べの鐘
作・由村知子
行しています。
ここでは、第6集『汲々』(2008年度)より、1作品をご紹介します。
夕べの鐘
作・由村知子
【一】
「『老鳥』召喚して、攻撃表示」
将太がモンスターカードを専用シートにセットした。カードは傷んでボロボロで、角がとれて丸くなっている。
けたたましい蝉の声に呼ばれて窓の外を見ると、強い緑色が空の青に映えていた。田んぼの苗は風でゆれる度に葉を裏返して白く光る。
野球用品、教材、ビー玉、ルアー、クレーンゲームで獲った安っぽいヌイグルミ、テレビゲームの説明書、なんでか真っ二つに裂けたコミック本、何もかもが山積みで身動きがとれないほどやっちゃない将太の部屋。それでもクーラー十八度設定でキンキンの部屋は極楽だった。
八月三一日、僕と将太は、小学校生活最後の夏休みを満喫していた。
僕らが熱中しているのは『モンスターズカードバトル』というカードゲーム。それぞれが買い集めて組んだ自分の山札を持っていて、戦略を巡らせながらモンスターを戦わせるというもの。トランプで言うならポーカーが近い・・・・・・かな。
「次、ヒロアキの番(ターン)やぞ」
おー、と僕は一枚一枚保存カバーに入れた自分の手札を見つめる。
攻撃攻撃の将太は、トラップカードにめっぽう弱い。僕は常勝パターンで攻めようと決めた。手札の中で、ラメの入った切り札の希少(レア)カードがきらりと光る。
「ほな、この二枚出して、前にセットしとったトラップカード発動」
・・・・・・同じようにやってるようで、やり込みが全然違う。何回勝負しても将太には負ける気がしなかった。
それから三分と経たないうちに、結果は僕の思った通りになった。
「うわまた負けたし。ヒロアキの攻め方、何かえげつないんやって」
将太はそう言って手札を放り出して見せてくる。降参の合図だ。
僕はふっと口元が緩むのを我慢した。あんまり機嫌損ねて「もうこんなんやらん!」とか言い出されたらかなわんし。
「いや、将太やりゃええやん。強化系の魔法カードとかもっと有効に使うんやって」
「フンフン」
「例えばこの『老鳥』のカード、誰でも持っとる弱小の凡カードやけど特殊召喚出来るやんかぁ。こっちの魔法カード使こて・・・・・・」
僕が戦略の基礎を伝授しようとしたその時、階段の下から声がした。
「将太、将太や。ヒロくんも降りてきぃな」
しゃがれてのっそりした声の主は、将太ん家のバアちゃんだ。将太はカードに目をやったまま面倒くさそうに返事した。
「何ぃ?」
ちょっと下ぶくれの将太の顔は眉間にしわを寄せ、下唇を突き出していた。気ィ悪い時はいっつもコレだ。
同じように日焼けした黒い肌をしていても、少し肉の付きすぎた将太の体はゴボウみたいな僕の体と対称的だった。
バアちゃんの番(ターン)。
「ビワ、取りにおいでぇな」
将太の番(ターン)。
「いらん」
即答。
この上村の家(ウチ)の人間はいつ遊びに来てもこんな感じ。そんで、あまりにそっけない将太になんでか毎回僕が焦る。と言っても、バアちゃんもたいがい引かない人で、将太の言葉なんかまるっきり意に介していない風だった。
バアちゃんは二階に上がってきて、僕らのいる部屋の戸を開けた。
部屋の戸を全開にされて、もあっとした空気が部屋に侵略してくる。廊下へ撤退していく十八度の空気が惜しい。
「おいでぇな」
「いらん言うとるやん」
おいおい、お年寄りにそんなキツい言い方していいんか。そう思いながらも心のどこかでは将太を応援していた。カードバトルを中断するのもヤだし、ビワとか別にどっちでもいーし、わざわざクーラーの効いたこの極楽を離れるのがダルかった。
「いらんのかいや」
深いシワと区別がつかないたれた瞼(まぶた)。その奥に見える目からはイマイチ感情が伝わってこない。
「やから、いらん言うとるやん、戸ぉ閉めてや!」
将太の声が部屋に響く。その口調の厳しいのに僕はいたたまれなくなって、思わずバアちゃんをかばった。
「将太、僕ビワ食べたいし。ビワ食べてから続きやろうで。カードこのまま置いとったらええやん」
将太は、細い目をますます細めて僕を睨んだ。僕は緊張を隠してわざとらしいぐらい笑った。そしてそんな一瞬の沈黙をアッサリ破ったのはバアちゃんだった。
「あーあーあー、そんなんあくかいや。一回離れたら片付けせぇへんやろうな」
えー、あなたの為のフォローじゃないすかぁ。そしてそして、立場をなくした気の毒な僕に、さらに将太からのトドメの一撃。
「ほんだらヒロアキ行ってきぃや。俺ここ居るわ」
将太から送られた軽蔑の眼差しに殺意が芽生える。精一杯の気遣いがアダになって、僕は一人食い意地の張った協調性無いヤツみたいな位置(ポジション)に立った。もういっそ殺していただきたい。
などという表情はおくびにも出さず、わぁ、ほんま? やったぁ、じゃあ行ってくるゥ、なんて一人芝居してバアちゃんと部屋を出た。
外に出ると、コレデモカ! と照りつける太陽に大ダメージ。
「ホレ、こっちじゃがな。早よ来(き)ぃ」
バアちゃんは、まるで家の子に接するみたいに僕に話してくる。どう対応していいのか困るのも毎回の事で、正直言うと僕はほんの少しだけこのバアちゃんが苦手だった。
深い雑草の中をスタスタ進むバアちゃんを追いかけて、家の裏の畑を奥へ進んだ。
「ほら、ヒロくん、これ大きい大きいがな。食べてみぃ」
バアちゃんは、枝からビワを一つちぎって差し出してきた。ほれ、とビワを渡されて一瞬とまどった。傷の入って黒くなったトコのあるビワは、まるで虫がついているように見えた。洗わんの? そのひとことが言えない。
妙に剥きにくい皮を、出来るだけ丁寧にはがして口に放り込んだ。味が悪いわけではない・・・・・・と思うけど、食べにくいと思いながら食べるものなんて、そうおいしくは感じないんだなとこの時初めて知った。
そんな僕を知ってか知らいでか、バアちゃんが呟く。
「最近の子は、ほんま、外に出ぇもせんとクーラーの部屋で」
かっちーん。
バアちゃんだって一階でクーラー付けとるやん! なーんて、口に出せる性格だったらまずこんな状況に陥ってないですね。
僕らが室内でばっかり遊んでるかどうかなんて、この真っ黒な肌を見ればすぐに分かることだ。どうせ、ワイドショーのふてぶてしい司会者の「最近の子供は~」みたいな苦言を鵜呑みにしてるんだと思うと、このオバアサンには救いが無いように思った。
枝の実をちぎりとって、大ざっぱに皮を剥がして口に放り込む。黒い種を舌で転がして畑の端にプッと吐く。それを、三回、四回と黙って繰り返した。苛立ちを表現する僕の精一杯だった。
そんな僕の横で、バアちゃんは、ドコを見ているんだか分からない顔で僕にこう言った。
「やーれよぉ、怖(きょう)とやなぁ。そんな食べたら晩ごはん食べれへんようなるがな」
このクソババァ。
【二】
「♪ユウヤケコヤケデヒガクレテ――
子どものみなさん おうちへ帰る 時刻になりました。早く お家へ帰りましょう――
♪マアルイオオキナオツキサマ――
唄が町に響く。部落の自治会館に設置されたスピーカーから流れてくる《夕べの鐘》のアナウンスだ。その声はひどくエコーがかかるから、細切れに、ゆっくりゆっくり話す。
二学期が始まって二週間ほど過ぎた日の夕方六時。僕と将太は夕べの鐘が鳴り止んでもずっと校庭で遊んでいた。
「夕べの鐘、まだ六時なんや」
自分は子供じゃない、と言わんばかりに将太は呟いた。
それもそのはず。時季々々の日没に合わせて鳴る夕べの鐘は、夏には六時に鳴っていても、毎年いつの間にか五時半に鳴るようになり、気付くと冬には五時に鳴るようになってしまう。そんなもの、陸上の練習やら運動会の準備やら放課後にも用事の残る高学年が守れるものではない。
――夕べの鐘なんてのは、低学年の子のモノ――
それがこの町の子供たちの、暗黙の了解だった。
「ヒロアキ、シロミツ行く?」
近くの駄菓子屋に行かないか、と将太が聞いてきた。
「うん。ええで」
僕は短く応えて、ジャングルジムから真下の砂場に飛び降りた。運動靴が半分うまって、中も外も砂だらけになった。頼りなく揺れるジャングルジム。てのひらを見ると、鉄サビとはがれたペンキがぱらぱらとついていた。ぱんぱん払って、丁寧に落とす。
いったん家に帰ってランドセルを放り出してきている僕らの装備は身軽そのもの。マウンテンバイクのカゴの中に、そのまま財布と門スターズのカードが入っているだけだった。
マウンテンバイクにまたがり、ぺダルを逆向きに一つ回して足に留めた。
「今日モンスターズのカード買う?」
「いや、今週マンガ出るから買わん」
いざ漕ぎ出したその時、校舎から飛び出してくる女の子に気付いた。
「兄ちゃーん」
将太の四つ下の妹、知恵ちゃんが駆け寄ってきた。誰が見ても兄妹だとひとめで分かるほど、顔つきも体つきもよく似た妹だった。将太を二まわり小さくして、髪をちょびっと伸ばせば丁度知恵ちゃんになる。
「なんしょん。お前二年やろが。夕べの鐘鳴ったんやから早よ帰れや」
将太がそっけなく言い放って、知恵ちゃんはむっとした。
「帰るわ言われんでも!」
「じゃあ早よ帰れや」
「帰るわ」
「『帰るわ』言う前に、早よ帰れや」
(なんこれ・・・・・・声が大きい方の勝ちとかそんなん?)
一人っ子の僕には理解不能の論争が始まる。そしてオヤクソク、ぐずり始めた知恵ちゃんに焦って僕が仲裁に入るはめに。
「なぁ知恵ちゃん、どしたん。帰らんの」
僕が割って入って、やっと知恵ちゃんが事情を話してくれた。
「あのな、うちな、マナミちゃんと遊んびょったんやけどな、マナミちゃんがな、それまでな、黒板に絵かいたりしょったんやけどな、それでな、マナミちゃんがな、マナミちゃんがな・・・・・・」
・・・・・・。つまり、こういう話だった。
同級生の子と二人、教室に残って遊んでいた。一緒に帰るつもりだったから遅くなるのを承知で遊んでいたけど、いざ夕べの鐘が鳴るころ、一緒に遊んでいた子は親が車で向かえに来て、自分を残してさっさと帰ってしまった。だから一人で帰るはめになった。お兄ちゃん一緒に家まで帰ってくれ。
話が終わるのを待っていたように、将太が言った。知恵ちゃんの訴えなんか、もとから聞いちゃいないようだった。
「めんどい。嫌じゃ、一人で帰れ」
正直、僕も知恵ちゃんに巻き込まれて遊ぶ時間がなくなるのは嫌だった。何と言っても微妙な時間帯で、今すぐ家に帰る必要はないにしても、いっぺん家に戻ってまた出ようとすれば親に止められてシロミツには行けなくなる。
「帰れ、早よ帰れや」
「やから、帰るって言ようるやん!」
ああ、エンドレス。僕はしばらく黙って、このうっさい兄妹喧嘩をボケっと見ていた。すると、ふと知恵ちゃんが下を向く。口を尖らせて眉間にシワを寄せている顔はさすが兄妹だ。
「だって、のうての池・・・・・・」
僕はそこまで聞いて、初めて知恵ちゃんの意図が理解できた。
学校と上村の家をつなぐ一直線の道沿いに構える《のうての池》――ここに住む妖怪の伝説は、もう何十年も前から子供たちに受け継がれていた。
「河童、食われる・・・・・・怖い・・・・・・」
そう、底なし沼と噂されるこの池にの主は河童。夜行性で、夕べの鐘を境に活動を開始し、小さな女の子を特に好んで池に引きずり込むと言われていた。
強情な妹の決死の告白を聞いても将太は仏ゴコロを起こさなかった。
「知らん。食われろ。一人で帰れ。ヒロアキ行こうで」
マウンテンバイクのペダルに足をかけて進もうとする将太。そのマウンテンバイクのカゴを両手で持って、知恵ちゃんがグズり出した。
「帰る! 一緒に帰る!」
知恵ちゃんの金切り声が校庭に響く。校舎の時計の長針がまた一つ進んだのを見て、この堂々巡りに観念したのは僕だった。
「なぁ、もう今日シロミツええわ。帰ろうや」
僕に言われて、将太が西の空を見た。シロミツ行こうや、と言っていた時よりずっと鮮明なオレンジ色の空だった。
「知恵、お前ほんまうっといわ」
結局そのままマウンテンバイクを押しながら、三人並んで家路についた。
ジージー、ゲコゲコ、グアッグアッグアッ・・・・・・鈴虫と蛙の大合唱。たまに車がブーンと横切るとぴたりと鳴り止んで、様子をうかがうように一匹が鳴いてまた合唱が始まる。
問題ののうての池にさしかかった。
『危険区域 ここで遊ぶな』を示す赤い旗は日に焼けて朱色になっていた。二十五メートルプール三つ分程の池は水が真緑色に濁っていて、水底なんて見えたものじゃあない。かすかに見えるのは、水面に顔を出す鯉の姿。あちこちで浮かび上がっては沈む赤や黄、白の影がその下にまだ何千匹といることを想像させた。
僕と将太に挟まれた知恵ちゃんは、すこぶる機嫌が良かった。小学六年生の護衛(ナイト)を二人も連れているのだ。河童も手出し出来るはずがない、そんな風に思っていたに違いない。
が、彼女は甘かった。
将太はいきなりマウンテンバイクにまたがり、立ち漕ぎで進み出した。僕はびっくりしながら、マウンテンバイクにまたがってその後を追う。
「将太?」
「兄ちゃん、待って!」
後ろから知恵ちゃんの懇願の声。
「将太、ええん?」
僕は将太に追いつくわけでもなく、知恵ちゃんを待つわけでもない微妙な位置でうろたえた。知恵ちゃんが必死になって追いかけてくる。
「兄ちゃん、待って」
金切り声に拍車をかけて、所々声が裏返る。しかし小学二年生の足と小学六年生の自転車、当たり前のようにぐんぐん距離がひらいた。
「将太―」
立ちこぎでグングン進んでいく将太。
「なぁ、将太ー!」
反応のないその後ろ姿に、思わず僕の声も大きくなった。
「にいちゃん、待って、って、言ようる、やんかあァア!」
ふと後ろを振り向くと、そこには物凄い形相の知恵ちゃんがいた。目を真っ赤にして大粒の涙をボロボロこぼし、鼻の穴が全開だった。口も、歯茎が丸出しになるまで開けて泣きじゃくって走ってくる。
「ウワァアアアア、兄ちゃ、アアアァァァアア・・・・・・」
奇声をあげて追いかけてくる知恵ちゃんを見て、ふと思ってしまった。
(――河童や、ここに河童がおる!)
ついおかしくなって、僕もマウンテンバイクのスピードを上げた。
知恵ちゃんの悲鳴はますます高くなり、超音波のようだった。
「なー将太ー、知恵ちゃんに河童伝説教えたん、お前やでなー!」
「そーやでぇー!」
結局、将太の家まで二人で帰ってきてしまった。一本道のずっと向こうをちらっと横目で確認すると、遠くに小さく見える知恵ちゃんが泣きながら歩いてくるのが見えた。自転車ならすぐの距離だけど、小二の子が走りきれる距離じゃあない。のうての池を過ぎてからは歩いているんだろう。
今更ながら我に返って、かわいそうな事をしたかもしれないと心が重くなった。おそるおそる将太の顔をのぞくと、まるっきり平然としていた。ここの兄妹はいっつもこんな。
「ほな帰るわ」
何となく、知恵ちゃんが追いつくより先にここを離れようと急いだ。
僕の家は、将太の家から南に曲がって一軒目の家だった。間に、田んぼや畑があるからお隣さんとは言えないけど。
五十メートル程しかない一人の道、僕は全力でペダルを踏んだ。
【三】
「ご町内の 皆様に お知らせです」
それからまた数日経った頃のことだった。授業中、ノートの端に落書きをしていると町内アナウンスが聞こえてきた。相変わらず、エコーのきつい間延びした声。
「本日 二時より 町内役場で 『高齢者の為の予防注射』 説明会を 行います。六五歳 以上の方は 是非・・・・・・」
担任の橋元(はしもと)先生(ハゲのハシゲン)は教科書を読むのを止めなかった。アナウンスの割れた声が先生の低い声と不協和音を奏でる。
町内放送はしょっちゅうだった。だいたい大した事もない内容で、地区の小学校の運動会や祭りの雨天延期とか町立公園の開催イベントなんかの告知がほとんどだった。あと、死亡(おく)告知(やみ)、それに・・・・・・
「続きまして、行方不明者 捜索協力の お願いです」
そう、たまにこんなのがある。こういうのが流れるのは決まってお年寄りの姿が見えなくなったときだ。
「先日 夕方より 内海町木庄地区 上村誠一郎さん宅 上村フジ子さん 八十歳が 行方不明と なりました。 情報を お持ちの方は 提供を お願い いたします 繰り返します・・・・・・」
(――え、これ・・・・・・)
心臓がキュッと縮こまるのを感じながらナナメ後ろを振り返った。将太を見ると、教科書に書き込みをしている。あの筆運びは完璧に落書きだ。
なんだ、聞き間違いか。そうやなぁ、そんな訳ない。あそこのバアちゃんはあれで気ィはシャンとしとるもんなぁ。そんな風に胸をなでおろすのと同時に、クラスメートの一人が叫んだ。
「将太! これお前ん家(チ)ちゃうん!」
授業中だというのに、皆が一斉にざわめき出した。
「何、将太、あんたんとこのおばあちゃん行方不明なん」
「え、どして」
「こら、授業中やぞ、静かにせんか」
「いつから?」
「こら、授業中やぞ、静かにせんか」
先生の静止もむなしく、質問はひっきりなしに将太に浴びせられた。
「なんで?」
「前にはこんな事あったん?」
将太は怒るでもなく、悲しむでもなく淡々と応えた。少し声を張り上げて、誰とも目を合わさずに。
「昨日の昼、母ちゃんが見てから行方が知れん。畑とか親戚んトコとか、家のモンでバアちゃんの行きそうなトコあたったケド見つからんかった。から、今日の朝、役場に捜索願の頼みに行くって言よった。以上!」
休み時間に入ると一瞬で将太は取り囲まれた。
「なぁ、今日も探すんけ」
「なぁ、昨日どこどこ探したん」
なぁなぁなぁなぁ。そんな言葉ばかりが矢のように降り注ぐ。
「今日から大人の人集めてその辺探すんやってさ」
僕はその人だかりに参加せずに、冷めた目でただ見ていた。アニメの話みたいに応える将太は注目の的で、興奮する一団の真ん中でけらけら笑っている。何とも思っていないような顔をしているのがクールだと思っているみたいに見えて、それが妙に頭にきた。
僕の視線なんか気付きもしてなかった将太が、急にこっちをふりむいた。逃げ出したい気持ちになる。
「なぁヒロアキー、今日遊ぶやろ? こないだ借りたゲーム返すわー」
将太を取り巻く皆が僕のほうを見る。なんだ、なんで僕がこんなに惨めなんだ。
「ええわ」
「は? なんで」
「今日遊ぶ気ぃない」
「習い事の日ィやったっけ?」
「ちゃうけど」
そのまま僕がそっぽを向くと、待ってましたと言わんばかりにまた騒ぎが起こった。僕はただそれを背中に感じていた。
結局その後は一言も話さないまま、一人家路に着いた。通学路がほとんど一緒で、約束しなくても毎日一緒に登校して下校する将太。その将太が今さら分からない。
今までにも、知恵ちゃんやバアちゃんや僕に思いやりのない言い方してなのは何度も見てきた。でも、表現がブキッチョなだけで根心では優しいヤツだと信じていた。信じたかった。
(――結局、カラッポなヤツなんだ)
照り付ける日差しをうなじに感じながら、ただ一心に右が出ては左が出る自分の運動靴ばかり見て歩いた。
パシャン
途中、鯉の跳ねる音に呼ばれてのうての池をのぞいた。何の事はない、ただの汚いため池だった。
【四】
家に帰ると、まだ四時すぎだというのにお父さんが帰ってきていた。仕事の背広を脱ぎ、のら仕事の時の
格好に着替えている。
「どしたん父さん、仕事終わったん」
「昨日から、将太君とこの婆さんがおらんようなったやろうがな」
「ウン」
自分だけが今日の今日まで知らなかったのだと思うと気に入らなくて、まるでもっと前から知ってるよう
な顔で応えた。
「今日から地区の組合でこの近所探すゆうんでなぁ。今日仕事早引きしてな。今から手伝い行くんじゃ」
「近所って?」
「田んぼやら、川やら、溝やら。消防団やら自治会なんぞでもう今日の朝から探っしょるがな」
「え」
「まぁ、河童に連れて行かれでもしたんじゃろうて話やからな」
「あ・・・・・・」
石化呪文でもかけられたみたいに体の内側がずしりと重くなった。
僕が小学校に上がる前、向かいの家のおじいさんが河童に連れて行かれた。台風の日に木庄川の様子を見に行ったためだった。隣の部落の漁師さんも今年河童に連れて行かれた。波の高い日に無理に船を出し、帰ってこなかったのだという。母さんが小学生の頃の水害なんか、何十人も河童に連れて行かれたと言っていた。
つまり、この地域一帯は、水難で亡くなる事を『河童に連れて行かれる』という。
「同じ部落やし、世話なっとる家やからしょうが無いけど、まぁ一銭にもならんのに大儀(たいぎ)ぃこっちゃで」
父さんは、村八分(むらはちぶ)なっても困るしのぉ、と笑えない冗談を言いながらさっさと出ていった。僕は二階にかけ上がり、窓を開け外を眺めた。田んぼ と畑があって、その向こうに将太の家。見ると、確かに首にタオルを巻いた大人があちこちで草をかき分けたり、溝さらいを始めていた。いつも畑仕事のおじいさんとかが歩いてるから区別がつかなかったのか、怒りで何も見えていなかったのか、下校中に気付かなかったのが不思議なぐらいだった。
道路わきの草むらで、三、四人のオジサンと話す父さんの姿を見つけた。話はすぐ終わって、オジサンの一人が指差した方へ父さんが歩き出す。どうやら、僕の家と将太の家の間にある雑草だらけのひと区間が父さんの担当らしかった。父さんは、電動草刈機で草を刈り取っていく。
ギイイイイイイン
電動草刈機の音が夕(ゆう)雅山(がさん)にこだまする。
電動草刈機の鋭い刃は、一メートル近くもあるような雑草をどんどんなぎ倒していく。僕は、そんな様子をイライラしながら見ていた。(・・・・・・もしバアちゃんが倒れてるのに当たったりしたら危ないじゃないか)
大人たちは、バアちゃんがもう死んでると思ってるんだ。万に一つも生きて帰らないと思ってるんだ。
「♪ユウヤケコヤケデヒガクレテ――
子どものみなさん おうちへ帰る 時刻になりました――」
一時間、二時間と経ったころ、夕べの鐘が鳴り始めた。
大人たちは、夕べの鐘なんか聞こえていないみたいに黙々と作業を続ける。
「そっちお願いします」
「あっちもう済んだんけ」
ときどきそんな声が飛び交うその光景を、一人ぼんやりと眺めた。もしかして夕べの鐘は大人になると聞こえなくなるのかな。なんて考えながら。
だんだん日が落ちて、じきに道路の電灯が危うげに灯った。電灯の弱い光がはっきり見えてくるころ、大人たちがのそのそと引き上げだした。
大人たちの思惑通りにはならなかった。
「やあい・・・・・・」
誰もいない薄暗い部屋でポツリと言った。
道路のわきに二十人ばかり集まって、その中の一人が、帽子を取って頭を下げた。――将太の父ちゃんだ。僅かに家の二階まで声が届く。
「どうもありがとうございました。ご苦労さんでした」
他の大人たちも、次々に首のタオルを外して汗をぬぐい、ほなまた、まあ頑張りましょ、などと言い合っていた。
解散しようとしたそこに、三人の人影が走りよった。知恵ちゃんと、将太の母ちゃんと、将太だ。将太の母ちゃんは何回も頭を下げて、持っていたスーパーの袋から缶ジュースか何かを出して配っているようだった。将太と知恵ちゃんもそれに倣う。
僕のお父さんに渡したのは将太だった。もらった人から順に、すんませんなぁとペコっと頭を下げて散って行く。
将太は、空き地や田んぼをきょろきょろ見回しているように見えた。僕はとっさに窓を閉めた。障子も閉めた。膝を抱えてうずくまる。閉めきると、むし暑くて額に汗がにじみ始めた。
玄関の開く音がして、父さんと母さんの声が入ってきた。バアちゃんの捜索を終えた父さんと、仕事帰りの母さん、すぐそこで鉢合わせたらしかった。僕は、一階に駆け下りていった。
「おったんかいや。電気もつけんと」
「自分の部屋で寝よった」
咄嗟にウソが出た。
父さんは、ふうん、ほれと僕に缶ジュースを差し出してきた。
「ヒロアキにやるわ」
受け取ると、コーラだった。母さんが冷やかすように言う。
「ハハ、それが今日の収穫け」
長靴を脱ぎ捨て、軍手を脱いだ父さんがこたえた。
「ほうよ、それが今日の駄賃じゃ」
家族三人、台所に移っても話題は変らなかった。
「今日も見つからんのけ」
「あかんなぁ」
「明日も仕事早引きすん」
「せんせん。一回顔出しとったら面(めん)目(ぼく)も立つがな。ほんま言ったらのぉ、定年した人らぁの動けるモンで探してくれりゃえんやけどな」
「ほんまにな・・・・・・」
母さんは、仕事帰りに寄ったスーパーの食材を取り出しテキパキと晩ごはんの準備にとりかかっていた。
さっきの小一時間、あんなに一生懸命探しているように見えた大人たちは、みんなこんな風に、面倒くさい、面倒くさいで探してたんだろうか。
(――大人も将太も、みんな冷たい)
僕がおかしいのかな。そうも思えてきて、気分が滅入る。
「どしたんなぁ、ヒロアキえらいムクレとんやん。あ、氷出して」
母さんが、ゆがいた素麺(そうめん)を水にさらしながら言った。
「氷、自分で入れてな」
僕は言われたとおり、手渡された自分の素麺とめんつゆの小皿に氷を放りこんだ。父さんはもうさっさと素麺(そうめん)をすすっていた。風呂の湯がたまるまでに食べきろうとしているようだった。
「はいはいはい、ヒロアキちょっとどいて」
母さんがあげたての唐揚げを、大皿にどんと盛って真ん中においた。僕は唐揚げを小皿にとってマヨネーズをかけた。
「さっき、将太君のお母さんと話したんよぉ」
名前を聞くだけでいらっとして、そっけなく応える。
「ふーん」
「アタシも上村のおばあさんの事、きょう会社で知ったんやけどなぁ。ほらビックリしたわ。近所にも尋ねて周ったりしよったらしいんやけど、ウチは昼誰もおらんからなぁ」
母さんは話すのがやたら好きだ。相づちも打たない父さんの横で、会社のグチを延々話してる、なんてのはよく見る光景だった。だから今日もやっぱり僕の返事なんかお構いなしに話しはじめた。
「ほら大変らしいわな。ぎょうさん人集めとんやって、後から一件一件に礼言うて周らなあかんしなぁ、それに警察にやって役場にやって届けが要るし、見つかるまで葬式の準備やってしたらええもんかも分からんし」
ふーん、あー、へー、そうなんやー。神経の半分をテレビアニメにあてて適当に聞いていた。
それが何分続いただろう。丁度テレビがCMに入ったときだった。
「ほんで子供もなぁ」
聞きたくない。あんな情なしの事。そう思っているのに、反応してしまった。
「将太とかのこと?」
その頃になって、やっと母さんは夕飯の段取りを全部済ませて椅子に腰掛けた。僕ももうほとんど食べ終わっていたけど、父さんはもうとっとと席をたって風呂に向かってしまっていた。
「ほうよ」
母さんは少しだけ目を赤くして、鼻をすすった。自分で話して、感傷に浸っているらしかった。
「上の子、そう、将太君がなぁ。バアさんがおらんようなった日の夜に『僕、何出来る?』って聞いてきたんやと」
そのころ僕はもうおなか一杯だった。だけど、もう一つ唐揚げを小皿に移した。
「ほんで?」
「お父さんに、『お前やこう手伝どうたら余計手ぇかかる。出来るだけ母さんの手ぇかけんよういつも通りにしとれ』って言われたて」
唐揚げが喉を通るのが、やけに苦しく感じた。僕はさっきまでの何気ない顔を崩さないよう続きを聞いた。
「ふーん?」
「ほんでなぁ、その晩自分の部屋こもってワァワァ泣いて寝たか思うと、朝起きてきたらケロっと『いつも通り』しとったって」
僕は、巨人の手に押しつぶされたような気になった。
いじらしいこっちゃ、と涙を一粒こぼす母さんの顔はドラマを観てるときと同じ顔だった。
「まぁ、子にそんな事されたら親にしたって辛いとこあるわなぁ」
母さんはいつも、『○○チャンの親は仕事してないんで』とか『××クンは家に上がっても挨拶もせんから親がちゃんと躾けてないな』とか僕の友達の裏事情をおおっぴらに僕に聞かせてくる。
にしても今日のはダメージがでかすぎる。罠(トラップ)カードが発動して立場逆転。この十五分足らずで、カラッポなのは僕の方になった。なんでそんな極端な態度とるんぞと将太を恨んだ。
教室での将太を一つ一つ思い返し、どうしても将太に謝らなきゃいけないと思った。でも、面と向かってケンカしたわけでもないのに何を?
僕が将太の事をどう思ったかなんて将太の知った事じゃない。それどころか、今日僕に避けられた事だって知らないかもしれない。
(――そうだ)
僕は冷蔵庫の野菜室を開けた。食後のコーヒーを淹れ始めていた母さんが怪訝(けげん)そうな顔をする。
「どしたんヒロアキ」
「なぁ母さん、冷蔵庫のキュウリもろてええ?」
「食べるん? 今?」
「いや、ちゃうけど」
「何するんな」
ほんとの事を言うと説明が長くなる、そう思ってウソをついた。
「学校の飼育小屋のウサギにあげるん」
「ウサギ、キュウリやこう食べるん? キャベツの、外の葉あげら。捨てるとこ」
「いや、キュウリがええ」
攻防が続いた。
「キュウリはアカン」
「なんで」
「買うたやつやもん」
「それやったら、そのキュウリの分こづかいから出す」
うちの息子は何をそんなキュウリにこだわっとんや。という顔をされたけど、やっと僕は勝利した。
「なんや知らんけど、ほんだら持っていきぃな」
「なんぼするん?」
「お金はええわ、もう。そんかわり一番形の悪いん持って行きぃや」
それは困るな、と思ったけど、そこで僕も妥協した。母さんの取り出してくれたキュウリは、形が悪いと言ってもやっぱり売り物らしいナリだったからだ。将太のバアちゃんが畑で育てたヤツみたいに、ぐにゃりと曲がったり、表面にカチカチの白い割れ目があったりというモノじゃあない。
ありがと、そう行って二階に駆け上がり、机の引き出しを勢い良く開けて、専用ケースの中に入ったカードを漁った。
「あった・・・・・・」
一枚取り出して、握りしめる。
【五】
八時を過ぎて、洗い物を終えた母さんと、風呂から出た父さんが居間で落ち着いた頃、僕は勝手口から家を抜け出した。
僕はキュウリとカードを大切に抱えて走り出した。
最初の目的地には一分もかからなかった。そう、将太の家だ。足をとめて呼吸を整え、外灯にカードを照らした。
出来る事なら、今すぐインターフォン鳴らして「一緒にバアちゃん探そうや!」って言ってやりたかった。
けど、それは将太がやらないと決めてるんだから、やらない。
――弱小で、誰でも持っているような凡カード『老鳥』。
将太は絶対分かる。そう確信して、カードをポストに放り込んだ。
ことりとカードがポストの中に落ちて行く。・・・・・・もしかして、小さすぎて気付かれなかったり、知恵ちゃんが先に取ってしまったりしないだろうか。そんな不安をよぎらせながらキュウリを握り締めてまた走った。
雲に隠れながら月が弱く輝いていた。
もう一つの目的地、のうての池に着いた。ハァ、ハ、ハ、カエルの声さえまばらになった池に、僕の息遣いだけがひどく目立つ。
怖い。普段見ることのない、しんとした夜ののうての池。道を挟んだ民家の灯りと月、それだけが頼りなく水面を照らしていた。いつもは濃緑の水も、ただただ真っ黒だった。向こう岸は闇に溶けて全然見えない。
オーン
山の方から犬の遠吠えがした。一匹がオーンと鳴いたのに続き、二、三匹の別の犬がアオーン、キャンキャンと応えるように鳴いた。
(――河童がいたらどうしよう)
元も子もない不安がよぎる。だって、ここに河童が住んでいないのなら、今夜ここまで来た意味がないんだから。
僕のもう一つの計画は、河童に願掛けすることだった。効果は無いかもしれない。いや、効果なんてないだろう。でもやると決めてここまで来た。
僕は、缶ジュースを配る将太の姿を頭に描いた。大人も将太も、口や態度でどうしてたって、出来る事をやっている。
(どんな事でもいい。僕も何か、バアちゃんが見つかる手伝いを、出来る事を・・・・・・)
僕はキュウリを握り締め、目をつむって心の中で必死に願った。
(――将太のバアちゃんが、河童に連れて行かれたんじゃありませんように。今もどこかで生きていますように。無事見つかりますように。また会えますように。河童、もしお前が池に連れ込んだんなら、返して。お願い――)
すっと目をあけた。真っ暗な水面と、その上に僅かににゆれる灯り、犬の遠吠え、目を閉じる前と何一つ変わらなかった。
フゥ、大一番のピッチャーのように深呼吸を一つついて、キュウリを思い切り池に放り投げた。
「そ、れッ!」
キュウリはくるくると回転しながら池の真ん中ぐらいに落ちていった。真っ暗闇に、ぽちゃんと小さな水しぶきが白く光る。
その次の瞬間だった。
バシャバシャバシャバシャ!
池の中央、キュウリの落ちたあたりで、ものすごいしぶきが立ち始めた。僕は息をのみ、思わず池に背を向けてダッシュでそこから離れた。
(――何アレ、何アレ今のん!)
ここは危ない! ここは危ない! ここは危ない!
早く離れろ! 早く離れろ! 早く早く早く!
全身の細胞がそう叫んで、心臓が爆発しそうだった。
「ウウッ」
漏らした嗚咽(おえつ)をまた飲み込む。
声を出したら河童に気(け)取られる! いや、もしかしたらもう、すぐ後ろに迫ってきているのかもしれない。声を押さえ込むと涙が溢れる。
(――殺(や)られる!)
とにかく必死で走った。・・・・・・将太、僕らが知恵ちゃんにやってのけた仕打ちは、僕らが思っていたよりヒドいのかもしれない。
段々大きくなる我が家とその灯りを見つめながら涙と鼻水をTシャツの袖になすりつけ、今度知恵ちゃんにあったら優しくしようと思った。
【六】
将太に会ったのは、翌日の登校中だった。
「よ、よぉ」
つい顔が引きつる。自然に、自然にと心で自分に言い聞かす。我がの巻いた種や、と思うと恥ずかしいやらなんやら・・・・・・もしタイムスリップして昨日の自分に会えるなら、はっ倒してやるのに。
「おぉ。なぁ、昨日の『ワイルドソルジャーズ』観たぁ?」
いきなり、昨晩七時放送のアニメの話だった。カラッとした将太の態度に戸惑わざるをえない僕は、なんて小物なんだろう。それでも必死で話を合わせる。
「あの敵キャラないやろ! って思たよなぁ」
「うん。ない。『キミのハートにロックオン!』って、どんだけクサいんかって話」
「『ロックオン』て! なぁ!」
いつもの他愛ないやりとり。それでも一言口から出て、一言返ってくるたび心が軽くなるのを感じた。もしかして、将太は僕がわざとそっけなくしたのに気付いていないのかな。悩んだのは自分だけか、とまた少しムカついて、ムカついたのの百倍救われた気がした。
「そや、ヒロアキ、これ」
将太が一枚のカードを差し出してきた。渡してきたのは、僕の期待したとおりのカードだった。パワーアップ系の装備カード。これも、『老鳥』と同じぐらいの、希少価値ゼロの凡カードだ。
『燃えたぎる生命の炎』――老鳥専用装備カード。これを装備した老鳥は、不死鳥(フェニックス)として再度その姿を見せる――
「おお、ほんでな、今回味方キャラ増えたやん」
僕はなんだか照れくさくて、わざとカードをぞんざいにポケットの中に突っ込んでアニメの話に戻した。
将太も、あっけらかんとそれに応じた。
「あーあいつな。なんかまた裏切るっぽい感じがめっちゃする!」
「確かに露骨よなぁ。てかマンガの方じゃもう裏切っとるけど」
将太はきっと、僕がこのカードに込めたごめんの意味には気付かなかったんだと思う。それでも、お互いバアちゃんの生還を信じる仲間になった。それで十分だった。たったそれだけのことが、レベル九十九の勇者を味方にするより心強く思えた。
それから、学校で授業を受けて、休み時間にキックベースやって、給食で焼きプリンタルトの争奪戦やって、昼休みにキックベースやって、掃除の時間にキックベースやって叱られて。本当に、何もかもがいつも通りだった。
何も変らない日常に戻った僕は、バアちゃんの無事を確信した。その根拠のない自信に自分がおかしくて笑ける。それでも理屈じゃない。気持ちは晴れていた。
そしてその日の、帰りの会のときだった。
「ご町内の みなさまに 行方不明者 発見の お知らせです」
町内アナウンスに、教室中がしんとした。橋元(ハシ)先生(ゲン)までもが聞き入った。
「先日 行方不明となった 内海町木庄地区 上村誠一郎さん宅 上村フジ子さんが さきほど 発見されました。 みなさまのご協力 ありがとうございました 繰り返します・・・・・・」
アナウンスは、死亡(おく)告知(やみ)じゃない。
「やったァ!」
教室中がわいた。
「将太、よかったな」
「おばあちゃん、結局どこおったんやろ」
クラスの皆が興奮していた。収拾のつかない騒ぎように、橋元(ハシ)先生(ゲン)だけが不機嫌そうだった。
「オイ、座れ。静かに、静かに!」
なかなか興奮の収まらない教室に教頭先生が入ってきて、橋元(ハシ)先生(ゲン)と二言(ふたこと)三言(みこと)会話を交わし、やがて将太を職員室に連行していった。
役者がいなくなってもクラスの浮かれた空気は納まらなかった。僕もやっぱりその一人だった。
「なあヒロアキ、よう将太ん家行くんやろ? 今度行ったらバアちゃんにドコ行っとったんか聞いてみィや」
「おお、分かった」
和やかなムードが教室を包む。そんな空気を払いのけたのは橋元(ハシ)先生(ゲン)だった。
「ちょっと、一つ、聞いてくれ!」
普段聞かない担任の先生の大きな声に、教室中が黙りこくった。
「さっきの放送、何て言うたか・・・・・・ほうやな、ヒロアキ、言うてみてくれ」
いきなり当てられてドキッとしたけど、朗報に変わりない。背筋を伸ばし、どこか誇らしげな気持ちで答えた。
「えっと、行方不明者発見のお知らせです。上村フジ子さんが発見されました。ありがとうございました・・・・・・」
大方言い切ったつもりなのに、橋元(ハシ)先生(ゲン)は浮かない顔をしたままだった。一体何を言い漏らしたっけと周りの席のヤツらに目で助けを求める。皆、首をかしげるばかりだった。先生はそうやな、と言って黒板の方を向き、白いチョークで僕の言った通りを横書きで大きく書いた。
なにがなんだか、という顔をした皆を尻目に、橋元(ハシ)先生(ゲン)は赤いチョークを持ち直して『発見されました』の文字の上に『無事』と付け加えた。
そして、僕らのほうを向きなおして言った。
「皆、知らいでも無理ないけどな。ええ機会やから今日覚えェ。こういう放送ん時、生きて見つかった場合は『発見されました』やのうて『無事発見されました』て言うんや」
ついさっきとは一転して、誰もが言葉を失った。僕は怖くて誰の顔も見れず、ただ赤いチョークで書かれた『無事』の二文字を見ていた。
皆、似たような顔をしていたんだろう。その後は橋元(ハシ)先生(ゲン)もかける言葉が無かったようで、帰りの会が終わると早足に教室を出て行ってしまった。
クラスメイトもぽつりぽつりと席を立ち始め、やがて何事も無かったようにいつもの喧騒を起こし一人また一人と教室を飛び出して行った。
一人になった教室で、ぼんやり黒板の文字を眺めた。金魚の水槽の、ろ過装置の音だけが低く振動する。
どこで死んでいたのか、誰が見つけたのか。将太は職員室で教頭先生に聞かされたのか、泣かなかっただろうか、バアちゃんのことを心から心配出来ていたのは誰か。
とりとめもない事が頭に浮かんでは消えていった。
「♪ユウヤケコヤケデヒガクレテ――
子どものみなさん おうちへ帰る 時刻になりました 早く お家へ帰りましょう―
♪マアルイオオキナオツキサマ―」
随分長く座っていたらしかった。夕べの鐘が聞こえてきて、はっと時計を見ると五時三十分。いつのまにか三十分早くなっていた。僕はランドセルを引っつかみ教室を飛び出し夢中で走った。いちいち上下に暴れるランドセルがうっとくさい。
(なんだ、河童のヤツ! キュウリのお供え持ってったくせに!
のうての池に着くと、立ち入り禁止の土手から握りこぶし程の石を一つ拾い上げ、怒りにまかせ力いっぱい水面にほうりなげた。
バシャバシャバシャ!
石の落ちたところに、昨日の夜とおなじ飛沫(しぶき)が上がる。
(――ああ、これか・・・・・・)
河童の正体は、落ちた石を餌と間違えた鯉の何百と群がる姿だった。
※作品の無断転載を禁じます。
「『老鳥』召喚して、攻撃表示」
将太がモンスターカードを専用シートにセットした。カードは傷んでボロボロで、角がとれて丸くなっている。
けたたましい蝉の声に呼ばれて窓の外を見ると、強い緑色が空の青に映えていた。田んぼの苗は風でゆれる度に葉を裏返して白く光る。
野球用品、教材、ビー玉、ルアー、クレーンゲームで獲った安っぽいヌイグルミ、テレビゲームの説明書、なんでか真っ二つに裂けたコミック本、何もかもが山積みで身動きがとれないほどやっちゃない将太の部屋。それでもクーラー十八度設定でキンキンの部屋は極楽だった。
八月三一日、僕と将太は、小学校生活最後の夏休みを満喫していた。
僕らが熱中しているのは『モンスターズカードバトル』というカードゲーム。それぞれが買い集めて組んだ自分の山札を持っていて、戦略を巡らせながらモンスターを戦わせるというもの。トランプで言うならポーカーが近い・・・・・・かな。
「次、ヒロアキの番(ターン)やぞ」
おー、と僕は一枚一枚保存カバーに入れた自分の手札を見つめる。
攻撃攻撃の将太は、トラップカードにめっぽう弱い。僕は常勝パターンで攻めようと決めた。手札の中で、ラメの入った切り札の希少(レア)カードがきらりと光る。
「ほな、この二枚出して、前にセットしとったトラップカード発動」
・・・・・・同じようにやってるようで、やり込みが全然違う。何回勝負しても将太には負ける気がしなかった。
それから三分と経たないうちに、結果は僕の思った通りになった。
「うわまた負けたし。ヒロアキの攻め方、何かえげつないんやって」
将太はそう言って手札を放り出して見せてくる。降参の合図だ。
僕はふっと口元が緩むのを我慢した。あんまり機嫌損ねて「もうこんなんやらん!」とか言い出されたらかなわんし。
「いや、将太やりゃええやん。強化系の魔法カードとかもっと有効に使うんやって」
「フンフン」
「例えばこの『老鳥』のカード、誰でも持っとる弱小の凡カードやけど特殊召喚出来るやんかぁ。こっちの魔法カード使こて・・・・・・」
僕が戦略の基礎を伝授しようとしたその時、階段の下から声がした。
「将太、将太や。ヒロくんも降りてきぃな」
しゃがれてのっそりした声の主は、将太ん家のバアちゃんだ。将太はカードに目をやったまま面倒くさそうに返事した。
「何ぃ?」
ちょっと下ぶくれの将太の顔は眉間にしわを寄せ、下唇を突き出していた。気ィ悪い時はいっつもコレだ。
同じように日焼けした黒い肌をしていても、少し肉の付きすぎた将太の体はゴボウみたいな僕の体と対称的だった。
バアちゃんの番(ターン)。
「ビワ、取りにおいでぇな」
将太の番(ターン)。
「いらん」
即答。
この上村の家(ウチ)の人間はいつ遊びに来てもこんな感じ。そんで、あまりにそっけない将太になんでか毎回僕が焦る。と言っても、バアちゃんもたいがい引かない人で、将太の言葉なんかまるっきり意に介していない風だった。
バアちゃんは二階に上がってきて、僕らのいる部屋の戸を開けた。
部屋の戸を全開にされて、もあっとした空気が部屋に侵略してくる。廊下へ撤退していく十八度の空気が惜しい。
「おいでぇな」
「いらん言うとるやん」
おいおい、お年寄りにそんなキツい言い方していいんか。そう思いながらも心のどこかでは将太を応援していた。カードバトルを中断するのもヤだし、ビワとか別にどっちでもいーし、わざわざクーラーの効いたこの極楽を離れるのがダルかった。
「いらんのかいや」
深いシワと区別がつかないたれた瞼(まぶた)。その奥に見える目からはイマイチ感情が伝わってこない。
「やから、いらん言うとるやん、戸ぉ閉めてや!」
将太の声が部屋に響く。その口調の厳しいのに僕はいたたまれなくなって、思わずバアちゃんをかばった。
「将太、僕ビワ食べたいし。ビワ食べてから続きやろうで。カードこのまま置いとったらええやん」
将太は、細い目をますます細めて僕を睨んだ。僕は緊張を隠してわざとらしいぐらい笑った。そしてそんな一瞬の沈黙をアッサリ破ったのはバアちゃんだった。
「あーあーあー、そんなんあくかいや。一回離れたら片付けせぇへんやろうな」
えー、あなたの為のフォローじゃないすかぁ。そしてそして、立場をなくした気の毒な僕に、さらに将太からのトドメの一撃。
「ほんだらヒロアキ行ってきぃや。俺ここ居るわ」
将太から送られた軽蔑の眼差しに殺意が芽生える。精一杯の気遣いがアダになって、僕は一人食い意地の張った協調性無いヤツみたいな位置(ポジション)に立った。もういっそ殺していただきたい。
などという表情はおくびにも出さず、わぁ、ほんま? やったぁ、じゃあ行ってくるゥ、なんて一人芝居してバアちゃんと部屋を出た。
外に出ると、コレデモカ! と照りつける太陽に大ダメージ。
「ホレ、こっちじゃがな。早よ来(き)ぃ」
バアちゃんは、まるで家の子に接するみたいに僕に話してくる。どう対応していいのか困るのも毎回の事で、正直言うと僕はほんの少しだけこのバアちゃんが苦手だった。
深い雑草の中をスタスタ進むバアちゃんを追いかけて、家の裏の畑を奥へ進んだ。
「ほら、ヒロくん、これ大きい大きいがな。食べてみぃ」
バアちゃんは、枝からビワを一つちぎって差し出してきた。ほれ、とビワを渡されて一瞬とまどった。傷の入って黒くなったトコのあるビワは、まるで虫がついているように見えた。洗わんの? そのひとことが言えない。
妙に剥きにくい皮を、出来るだけ丁寧にはがして口に放り込んだ。味が悪いわけではない・・・・・・と思うけど、食べにくいと思いながら食べるものなんて、そうおいしくは感じないんだなとこの時初めて知った。
そんな僕を知ってか知らいでか、バアちゃんが呟く。
「最近の子は、ほんま、外に出ぇもせんとクーラーの部屋で」
かっちーん。
バアちゃんだって一階でクーラー付けとるやん! なーんて、口に出せる性格だったらまずこんな状況に陥ってないですね。
僕らが室内でばっかり遊んでるかどうかなんて、この真っ黒な肌を見ればすぐに分かることだ。どうせ、ワイドショーのふてぶてしい司会者の「最近の子供は~」みたいな苦言を鵜呑みにしてるんだと思うと、このオバアサンには救いが無いように思った。
枝の実をちぎりとって、大ざっぱに皮を剥がして口に放り込む。黒い種を舌で転がして畑の端にプッと吐く。それを、三回、四回と黙って繰り返した。苛立ちを表現する僕の精一杯だった。
そんな僕の横で、バアちゃんは、ドコを見ているんだか分からない顔で僕にこう言った。
「やーれよぉ、怖(きょう)とやなぁ。そんな食べたら晩ごはん食べれへんようなるがな」
このクソババァ。
【二】
「♪ユウヤケコヤケデヒガクレテ――
子どものみなさん おうちへ帰る 時刻になりました。早く お家へ帰りましょう――
♪マアルイオオキナオツキサマ――
唄が町に響く。部落の自治会館に設置されたスピーカーから流れてくる《夕べの鐘》のアナウンスだ。その声はひどくエコーがかかるから、細切れに、ゆっくりゆっくり話す。
二学期が始まって二週間ほど過ぎた日の夕方六時。僕と将太は夕べの鐘が鳴り止んでもずっと校庭で遊んでいた。
「夕べの鐘、まだ六時なんや」
自分は子供じゃない、と言わんばかりに将太は呟いた。
それもそのはず。時季々々の日没に合わせて鳴る夕べの鐘は、夏には六時に鳴っていても、毎年いつの間にか五時半に鳴るようになり、気付くと冬には五時に鳴るようになってしまう。そんなもの、陸上の練習やら運動会の準備やら放課後にも用事の残る高学年が守れるものではない。
――夕べの鐘なんてのは、低学年の子のモノ――
それがこの町の子供たちの、暗黙の了解だった。
「ヒロアキ、シロミツ行く?」
近くの駄菓子屋に行かないか、と将太が聞いてきた。
「うん。ええで」
僕は短く応えて、ジャングルジムから真下の砂場に飛び降りた。運動靴が半分うまって、中も外も砂だらけになった。頼りなく揺れるジャングルジム。てのひらを見ると、鉄サビとはがれたペンキがぱらぱらとついていた。ぱんぱん払って、丁寧に落とす。
いったん家に帰ってランドセルを放り出してきている僕らの装備は身軽そのもの。マウンテンバイクのカゴの中に、そのまま財布と門スターズのカードが入っているだけだった。
マウンテンバイクにまたがり、ぺダルを逆向きに一つ回して足に留めた。
「今日モンスターズのカード買う?」
「いや、今週マンガ出るから買わん」
いざ漕ぎ出したその時、校舎から飛び出してくる女の子に気付いた。
「兄ちゃーん」
将太の四つ下の妹、知恵ちゃんが駆け寄ってきた。誰が見ても兄妹だとひとめで分かるほど、顔つきも体つきもよく似た妹だった。将太を二まわり小さくして、髪をちょびっと伸ばせば丁度知恵ちゃんになる。
「なんしょん。お前二年やろが。夕べの鐘鳴ったんやから早よ帰れや」
将太がそっけなく言い放って、知恵ちゃんはむっとした。
「帰るわ言われんでも!」
「じゃあ早よ帰れや」
「帰るわ」
「『帰るわ』言う前に、早よ帰れや」
(なんこれ・・・・・・声が大きい方の勝ちとかそんなん?)
一人っ子の僕には理解不能の論争が始まる。そしてオヤクソク、ぐずり始めた知恵ちゃんに焦って僕が仲裁に入るはめに。
「なぁ知恵ちゃん、どしたん。帰らんの」
僕が割って入って、やっと知恵ちゃんが事情を話してくれた。
「あのな、うちな、マナミちゃんと遊んびょったんやけどな、マナミちゃんがな、それまでな、黒板に絵かいたりしょったんやけどな、それでな、マナミちゃんがな、マナミちゃんがな・・・・・・」
・・・・・・。つまり、こういう話だった。
同級生の子と二人、教室に残って遊んでいた。一緒に帰るつもりだったから遅くなるのを承知で遊んでいたけど、いざ夕べの鐘が鳴るころ、一緒に遊んでいた子は親が車で向かえに来て、自分を残してさっさと帰ってしまった。だから一人で帰るはめになった。お兄ちゃん一緒に家まで帰ってくれ。
話が終わるのを待っていたように、将太が言った。知恵ちゃんの訴えなんか、もとから聞いちゃいないようだった。
「めんどい。嫌じゃ、一人で帰れ」
正直、僕も知恵ちゃんに巻き込まれて遊ぶ時間がなくなるのは嫌だった。何と言っても微妙な時間帯で、今すぐ家に帰る必要はないにしても、いっぺん家に戻ってまた出ようとすれば親に止められてシロミツには行けなくなる。
「帰れ、早よ帰れや」
「やから、帰るって言ようるやん!」
ああ、エンドレス。僕はしばらく黙って、このうっさい兄妹喧嘩をボケっと見ていた。すると、ふと知恵ちゃんが下を向く。口を尖らせて眉間にシワを寄せている顔はさすが兄妹だ。
「だって、のうての池・・・・・・」
僕はそこまで聞いて、初めて知恵ちゃんの意図が理解できた。
学校と上村の家をつなぐ一直線の道沿いに構える《のうての池》――ここに住む妖怪の伝説は、もう何十年も前から子供たちに受け継がれていた。
「河童、食われる・・・・・・怖い・・・・・・」
そう、底なし沼と噂されるこの池にの主は河童。夜行性で、夕べの鐘を境に活動を開始し、小さな女の子を特に好んで池に引きずり込むと言われていた。
強情な妹の決死の告白を聞いても将太は仏ゴコロを起こさなかった。
「知らん。食われろ。一人で帰れ。ヒロアキ行こうで」
マウンテンバイクのペダルに足をかけて進もうとする将太。そのマウンテンバイクのカゴを両手で持って、知恵ちゃんがグズり出した。
「帰る! 一緒に帰る!」
知恵ちゃんの金切り声が校庭に響く。校舎の時計の長針がまた一つ進んだのを見て、この堂々巡りに観念したのは僕だった。
「なぁ、もう今日シロミツええわ。帰ろうや」
僕に言われて、将太が西の空を見た。シロミツ行こうや、と言っていた時よりずっと鮮明なオレンジ色の空だった。
「知恵、お前ほんまうっといわ」
結局そのままマウンテンバイクを押しながら、三人並んで家路についた。
ジージー、ゲコゲコ、グアッグアッグアッ・・・・・・鈴虫と蛙の大合唱。たまに車がブーンと横切るとぴたりと鳴り止んで、様子をうかがうように一匹が鳴いてまた合唱が始まる。
問題ののうての池にさしかかった。
『危険区域 ここで遊ぶな』を示す赤い旗は日に焼けて朱色になっていた。二十五メートルプール三つ分程の池は水が真緑色に濁っていて、水底なんて見えたものじゃあない。かすかに見えるのは、水面に顔を出す鯉の姿。あちこちで浮かび上がっては沈む赤や黄、白の影がその下にまだ何千匹といることを想像させた。
僕と将太に挟まれた知恵ちゃんは、すこぶる機嫌が良かった。小学六年生の護衛(ナイト)を二人も連れているのだ。河童も手出し出来るはずがない、そんな風に思っていたに違いない。
が、彼女は甘かった。
将太はいきなりマウンテンバイクにまたがり、立ち漕ぎで進み出した。僕はびっくりしながら、マウンテンバイクにまたがってその後を追う。
「将太?」
「兄ちゃん、待って!」
後ろから知恵ちゃんの懇願の声。
「将太、ええん?」
僕は将太に追いつくわけでもなく、知恵ちゃんを待つわけでもない微妙な位置でうろたえた。知恵ちゃんが必死になって追いかけてくる。
「兄ちゃん、待って」
金切り声に拍車をかけて、所々声が裏返る。しかし小学二年生の足と小学六年生の自転車、当たり前のようにぐんぐん距離がひらいた。
「将太―」
立ちこぎでグングン進んでいく将太。
「なぁ、将太ー!」
反応のないその後ろ姿に、思わず僕の声も大きくなった。
「にいちゃん、待って、って、言ようる、やんかあァア!」
ふと後ろを振り向くと、そこには物凄い形相の知恵ちゃんがいた。目を真っ赤にして大粒の涙をボロボロこぼし、鼻の穴が全開だった。口も、歯茎が丸出しになるまで開けて泣きじゃくって走ってくる。
「ウワァアアアア、兄ちゃ、アアアァァァアア・・・・・・」
奇声をあげて追いかけてくる知恵ちゃんを見て、ふと思ってしまった。
(――河童や、ここに河童がおる!)
ついおかしくなって、僕もマウンテンバイクのスピードを上げた。
知恵ちゃんの悲鳴はますます高くなり、超音波のようだった。
「なー将太ー、知恵ちゃんに河童伝説教えたん、お前やでなー!」
「そーやでぇー!」
結局、将太の家まで二人で帰ってきてしまった。一本道のずっと向こうをちらっと横目で確認すると、遠くに小さく見える知恵ちゃんが泣きながら歩いてくるのが見えた。自転車ならすぐの距離だけど、小二の子が走りきれる距離じゃあない。のうての池を過ぎてからは歩いているんだろう。
今更ながら我に返って、かわいそうな事をしたかもしれないと心が重くなった。おそるおそる将太の顔をのぞくと、まるっきり平然としていた。ここの兄妹はいっつもこんな。
「ほな帰るわ」
何となく、知恵ちゃんが追いつくより先にここを離れようと急いだ。
僕の家は、将太の家から南に曲がって一軒目の家だった。間に、田んぼや畑があるからお隣さんとは言えないけど。
五十メートル程しかない一人の道、僕は全力でペダルを踏んだ。
【三】
「ご町内の 皆様に お知らせです」
それからまた数日経った頃のことだった。授業中、ノートの端に落書きをしていると町内アナウンスが聞こえてきた。相変わらず、エコーのきつい間延びした声。
「本日 二時より 町内役場で 『高齢者の為の予防注射』 説明会を 行います。六五歳 以上の方は 是非・・・・・・」
担任の橋元(はしもと)先生(ハゲのハシゲン)は教科書を読むのを止めなかった。アナウンスの割れた声が先生の低い声と不協和音を奏でる。
町内放送はしょっちゅうだった。だいたい大した事もない内容で、地区の小学校の運動会や祭りの雨天延期とか町立公園の開催イベントなんかの告知がほとんどだった。あと、死亡(おく)告知(やみ)、それに・・・・・・
「続きまして、行方不明者 捜索協力の お願いです」
そう、たまにこんなのがある。こういうのが流れるのは決まってお年寄りの姿が見えなくなったときだ。
「先日 夕方より 内海町木庄地区 上村誠一郎さん宅 上村フジ子さん 八十歳が 行方不明と なりました。 情報を お持ちの方は 提供を お願い いたします 繰り返します・・・・・・」
(――え、これ・・・・・・)
心臓がキュッと縮こまるのを感じながらナナメ後ろを振り返った。将太を見ると、教科書に書き込みをしている。あの筆運びは完璧に落書きだ。
なんだ、聞き間違いか。そうやなぁ、そんな訳ない。あそこのバアちゃんはあれで気ィはシャンとしとるもんなぁ。そんな風に胸をなでおろすのと同時に、クラスメートの一人が叫んだ。
「将太! これお前ん家(チ)ちゃうん!」
授業中だというのに、皆が一斉にざわめき出した。
「何、将太、あんたんとこのおばあちゃん行方不明なん」
「え、どして」
「こら、授業中やぞ、静かにせんか」
「いつから?」
「こら、授業中やぞ、静かにせんか」
先生の静止もむなしく、質問はひっきりなしに将太に浴びせられた。
「なんで?」
「前にはこんな事あったん?」
将太は怒るでもなく、悲しむでもなく淡々と応えた。少し声を張り上げて、誰とも目を合わさずに。
「昨日の昼、母ちゃんが見てから行方が知れん。畑とか親戚んトコとか、家のモンでバアちゃんの行きそうなトコあたったケド見つからんかった。から、今日の朝、役場に捜索願の頼みに行くって言よった。以上!」
休み時間に入ると一瞬で将太は取り囲まれた。
「なぁ、今日も探すんけ」
「なぁ、昨日どこどこ探したん」
なぁなぁなぁなぁ。そんな言葉ばかりが矢のように降り注ぐ。
「今日から大人の人集めてその辺探すんやってさ」
僕はその人だかりに参加せずに、冷めた目でただ見ていた。アニメの話みたいに応える将太は注目の的で、興奮する一団の真ん中でけらけら笑っている。何とも思っていないような顔をしているのがクールだと思っているみたいに見えて、それが妙に頭にきた。
僕の視線なんか気付きもしてなかった将太が、急にこっちをふりむいた。逃げ出したい気持ちになる。
「なぁヒロアキー、今日遊ぶやろ? こないだ借りたゲーム返すわー」
将太を取り巻く皆が僕のほうを見る。なんだ、なんで僕がこんなに惨めなんだ。
「ええわ」
「は? なんで」
「今日遊ぶ気ぃない」
「習い事の日ィやったっけ?」
「ちゃうけど」
そのまま僕がそっぽを向くと、待ってましたと言わんばかりにまた騒ぎが起こった。僕はただそれを背中に感じていた。
結局その後は一言も話さないまま、一人家路に着いた。通学路がほとんど一緒で、約束しなくても毎日一緒に登校して下校する将太。その将太が今さら分からない。
今までにも、知恵ちゃんやバアちゃんや僕に思いやりのない言い方してなのは何度も見てきた。でも、表現がブキッチョなだけで根心では優しいヤツだと信じていた。信じたかった。
(――結局、カラッポなヤツなんだ)
照り付ける日差しをうなじに感じながら、ただ一心に右が出ては左が出る自分の運動靴ばかり見て歩いた。
パシャン
途中、鯉の跳ねる音に呼ばれてのうての池をのぞいた。何の事はない、ただの汚いため池だった。
【四】
家に帰ると、まだ四時すぎだというのにお父さんが帰ってきていた。仕事の背広を脱ぎ、のら仕事の時の
格好に着替えている。
「どしたん父さん、仕事終わったん」
「昨日から、将太君とこの婆さんがおらんようなったやろうがな」
「ウン」
自分だけが今日の今日まで知らなかったのだと思うと気に入らなくて、まるでもっと前から知ってるよう
な顔で応えた。
「今日から地区の組合でこの近所探すゆうんでなぁ。今日仕事早引きしてな。今から手伝い行くんじゃ」
「近所って?」
「田んぼやら、川やら、溝やら。消防団やら自治会なんぞでもう今日の朝から探っしょるがな」
「え」
「まぁ、河童に連れて行かれでもしたんじゃろうて話やからな」
「あ・・・・・・」
石化呪文でもかけられたみたいに体の内側がずしりと重くなった。
僕が小学校に上がる前、向かいの家のおじいさんが河童に連れて行かれた。台風の日に木庄川の様子を見に行ったためだった。隣の部落の漁師さんも今年河童に連れて行かれた。波の高い日に無理に船を出し、帰ってこなかったのだという。母さんが小学生の頃の水害なんか、何十人も河童に連れて行かれたと言っていた。
つまり、この地域一帯は、水難で亡くなる事を『河童に連れて行かれる』という。
「同じ部落やし、世話なっとる家やからしょうが無いけど、まぁ一銭にもならんのに大儀(たいぎ)ぃこっちゃで」
父さんは、村八分(むらはちぶ)なっても困るしのぉ、と笑えない冗談を言いながらさっさと出ていった。僕は二階にかけ上がり、窓を開け外を眺めた。田んぼ と畑があって、その向こうに将太の家。見ると、確かに首にタオルを巻いた大人があちこちで草をかき分けたり、溝さらいを始めていた。いつも畑仕事のおじいさんとかが歩いてるから区別がつかなかったのか、怒りで何も見えていなかったのか、下校中に気付かなかったのが不思議なぐらいだった。
道路わきの草むらで、三、四人のオジサンと話す父さんの姿を見つけた。話はすぐ終わって、オジサンの一人が指差した方へ父さんが歩き出す。どうやら、僕の家と将太の家の間にある雑草だらけのひと区間が父さんの担当らしかった。父さんは、電動草刈機で草を刈り取っていく。
ギイイイイイイン
電動草刈機の音が夕(ゆう)雅山(がさん)にこだまする。
電動草刈機の鋭い刃は、一メートル近くもあるような雑草をどんどんなぎ倒していく。僕は、そんな様子をイライラしながら見ていた。(・・・・・・もしバアちゃんが倒れてるのに当たったりしたら危ないじゃないか)
大人たちは、バアちゃんがもう死んでると思ってるんだ。万に一つも生きて帰らないと思ってるんだ。
「♪ユウヤケコヤケデヒガクレテ――
子どものみなさん おうちへ帰る 時刻になりました――」
一時間、二時間と経ったころ、夕べの鐘が鳴り始めた。
大人たちは、夕べの鐘なんか聞こえていないみたいに黙々と作業を続ける。
「そっちお願いします」
「あっちもう済んだんけ」
ときどきそんな声が飛び交うその光景を、一人ぼんやりと眺めた。もしかして夕べの鐘は大人になると聞こえなくなるのかな。なんて考えながら。
だんだん日が落ちて、じきに道路の電灯が危うげに灯った。電灯の弱い光がはっきり見えてくるころ、大人たちがのそのそと引き上げだした。
大人たちの思惑通りにはならなかった。
「やあい・・・・・・」
誰もいない薄暗い部屋でポツリと言った。
道路のわきに二十人ばかり集まって、その中の一人が、帽子を取って頭を下げた。――将太の父ちゃんだ。僅かに家の二階まで声が届く。
「どうもありがとうございました。ご苦労さんでした」
他の大人たちも、次々に首のタオルを外して汗をぬぐい、ほなまた、まあ頑張りましょ、などと言い合っていた。
解散しようとしたそこに、三人の人影が走りよった。知恵ちゃんと、将太の母ちゃんと、将太だ。将太の母ちゃんは何回も頭を下げて、持っていたスーパーの袋から缶ジュースか何かを出して配っているようだった。将太と知恵ちゃんもそれに倣う。
僕のお父さんに渡したのは将太だった。もらった人から順に、すんませんなぁとペコっと頭を下げて散って行く。
将太は、空き地や田んぼをきょろきょろ見回しているように見えた。僕はとっさに窓を閉めた。障子も閉めた。膝を抱えてうずくまる。閉めきると、むし暑くて額に汗がにじみ始めた。
玄関の開く音がして、父さんと母さんの声が入ってきた。バアちゃんの捜索を終えた父さんと、仕事帰りの母さん、すぐそこで鉢合わせたらしかった。僕は、一階に駆け下りていった。
「おったんかいや。電気もつけんと」
「自分の部屋で寝よった」
咄嗟にウソが出た。
父さんは、ふうん、ほれと僕に缶ジュースを差し出してきた。
「ヒロアキにやるわ」
受け取ると、コーラだった。母さんが冷やかすように言う。
「ハハ、それが今日の収穫け」
長靴を脱ぎ捨て、軍手を脱いだ父さんがこたえた。
「ほうよ、それが今日の駄賃じゃ」
家族三人、台所に移っても話題は変らなかった。
「今日も見つからんのけ」
「あかんなぁ」
「明日も仕事早引きすん」
「せんせん。一回顔出しとったら面(めん)目(ぼく)も立つがな。ほんま言ったらのぉ、定年した人らぁの動けるモンで探してくれりゃえんやけどな」
「ほんまにな・・・・・・」
母さんは、仕事帰りに寄ったスーパーの食材を取り出しテキパキと晩ごはんの準備にとりかかっていた。
さっきの小一時間、あんなに一生懸命探しているように見えた大人たちは、みんなこんな風に、面倒くさい、面倒くさいで探してたんだろうか。
(――大人も将太も、みんな冷たい)
僕がおかしいのかな。そうも思えてきて、気分が滅入る。
「どしたんなぁ、ヒロアキえらいムクレとんやん。あ、氷出して」
母さんが、ゆがいた素麺(そうめん)を水にさらしながら言った。
「氷、自分で入れてな」
僕は言われたとおり、手渡された自分の素麺とめんつゆの小皿に氷を放りこんだ。父さんはもうさっさと素麺(そうめん)をすすっていた。風呂の湯がたまるまでに食べきろうとしているようだった。
「はいはいはい、ヒロアキちょっとどいて」
母さんがあげたての唐揚げを、大皿にどんと盛って真ん中においた。僕は唐揚げを小皿にとってマヨネーズをかけた。
「さっき、将太君のお母さんと話したんよぉ」
名前を聞くだけでいらっとして、そっけなく応える。
「ふーん」
「アタシも上村のおばあさんの事、きょう会社で知ったんやけどなぁ。ほらビックリしたわ。近所にも尋ねて周ったりしよったらしいんやけど、ウチは昼誰もおらんからなぁ」
母さんは話すのがやたら好きだ。相づちも打たない父さんの横で、会社のグチを延々話してる、なんてのはよく見る光景だった。だから今日もやっぱり僕の返事なんかお構いなしに話しはじめた。
「ほら大変らしいわな。ぎょうさん人集めとんやって、後から一件一件に礼言うて周らなあかんしなぁ、それに警察にやって役場にやって届けが要るし、見つかるまで葬式の準備やってしたらええもんかも分からんし」
ふーん、あー、へー、そうなんやー。神経の半分をテレビアニメにあてて適当に聞いていた。
それが何分続いただろう。丁度テレビがCMに入ったときだった。
「ほんで子供もなぁ」
聞きたくない。あんな情なしの事。そう思っているのに、反応してしまった。
「将太とかのこと?」
その頃になって、やっと母さんは夕飯の段取りを全部済ませて椅子に腰掛けた。僕ももうほとんど食べ終わっていたけど、父さんはもうとっとと席をたって風呂に向かってしまっていた。
「ほうよ」
母さんは少しだけ目を赤くして、鼻をすすった。自分で話して、感傷に浸っているらしかった。
「上の子、そう、将太君がなぁ。バアさんがおらんようなった日の夜に『僕、何出来る?』って聞いてきたんやと」
そのころ僕はもうおなか一杯だった。だけど、もう一つ唐揚げを小皿に移した。
「ほんで?」
「お父さんに、『お前やこう手伝どうたら余計手ぇかかる。出来るだけ母さんの手ぇかけんよういつも通りにしとれ』って言われたて」
唐揚げが喉を通るのが、やけに苦しく感じた。僕はさっきまでの何気ない顔を崩さないよう続きを聞いた。
「ふーん?」
「ほんでなぁ、その晩自分の部屋こもってワァワァ泣いて寝たか思うと、朝起きてきたらケロっと『いつも通り』しとったって」
僕は、巨人の手に押しつぶされたような気になった。
いじらしいこっちゃ、と涙を一粒こぼす母さんの顔はドラマを観てるときと同じ顔だった。
「まぁ、子にそんな事されたら親にしたって辛いとこあるわなぁ」
母さんはいつも、『○○チャンの親は仕事してないんで』とか『××クンは家に上がっても挨拶もせんから親がちゃんと躾けてないな』とか僕の友達の裏事情をおおっぴらに僕に聞かせてくる。
にしても今日のはダメージがでかすぎる。罠(トラップ)カードが発動して立場逆転。この十五分足らずで、カラッポなのは僕の方になった。なんでそんな極端な態度とるんぞと将太を恨んだ。
教室での将太を一つ一つ思い返し、どうしても将太に謝らなきゃいけないと思った。でも、面と向かってケンカしたわけでもないのに何を?
僕が将太の事をどう思ったかなんて将太の知った事じゃない。それどころか、今日僕に避けられた事だって知らないかもしれない。
(――そうだ)
僕は冷蔵庫の野菜室を開けた。食後のコーヒーを淹れ始めていた母さんが怪訝(けげん)そうな顔をする。
「どしたんヒロアキ」
「なぁ母さん、冷蔵庫のキュウリもろてええ?」
「食べるん? 今?」
「いや、ちゃうけど」
「何するんな」
ほんとの事を言うと説明が長くなる、そう思ってウソをついた。
「学校の飼育小屋のウサギにあげるん」
「ウサギ、キュウリやこう食べるん? キャベツの、外の葉あげら。捨てるとこ」
「いや、キュウリがええ」
攻防が続いた。
「キュウリはアカン」
「なんで」
「買うたやつやもん」
「それやったら、そのキュウリの分こづかいから出す」
うちの息子は何をそんなキュウリにこだわっとんや。という顔をされたけど、やっと僕は勝利した。
「なんや知らんけど、ほんだら持っていきぃな」
「なんぼするん?」
「お金はええわ、もう。そんかわり一番形の悪いん持って行きぃや」
それは困るな、と思ったけど、そこで僕も妥協した。母さんの取り出してくれたキュウリは、形が悪いと言ってもやっぱり売り物らしいナリだったからだ。将太のバアちゃんが畑で育てたヤツみたいに、ぐにゃりと曲がったり、表面にカチカチの白い割れ目があったりというモノじゃあない。
ありがと、そう行って二階に駆け上がり、机の引き出しを勢い良く開けて、専用ケースの中に入ったカードを漁った。
「あった・・・・・・」
一枚取り出して、握りしめる。
【五】
八時を過ぎて、洗い物を終えた母さんと、風呂から出た父さんが居間で落ち着いた頃、僕は勝手口から家を抜け出した。
僕はキュウリとカードを大切に抱えて走り出した。
最初の目的地には一分もかからなかった。そう、将太の家だ。足をとめて呼吸を整え、外灯にカードを照らした。
出来る事なら、今すぐインターフォン鳴らして「一緒にバアちゃん探そうや!」って言ってやりたかった。
けど、それは将太がやらないと決めてるんだから、やらない。
――弱小で、誰でも持っているような凡カード『老鳥』。
将太は絶対分かる。そう確信して、カードをポストに放り込んだ。
ことりとカードがポストの中に落ちて行く。・・・・・・もしかして、小さすぎて気付かれなかったり、知恵ちゃんが先に取ってしまったりしないだろうか。そんな不安をよぎらせながらキュウリを握り締めてまた走った。
雲に隠れながら月が弱く輝いていた。
もう一つの目的地、のうての池に着いた。ハァ、ハ、ハ、カエルの声さえまばらになった池に、僕の息遣いだけがひどく目立つ。
怖い。普段見ることのない、しんとした夜ののうての池。道を挟んだ民家の灯りと月、それだけが頼りなく水面を照らしていた。いつもは濃緑の水も、ただただ真っ黒だった。向こう岸は闇に溶けて全然見えない。
オーン
山の方から犬の遠吠えがした。一匹がオーンと鳴いたのに続き、二、三匹の別の犬がアオーン、キャンキャンと応えるように鳴いた。
(――河童がいたらどうしよう)
元も子もない不安がよぎる。だって、ここに河童が住んでいないのなら、今夜ここまで来た意味がないんだから。
僕のもう一つの計画は、河童に願掛けすることだった。効果は無いかもしれない。いや、効果なんてないだろう。でもやると決めてここまで来た。
僕は、缶ジュースを配る将太の姿を頭に描いた。大人も将太も、口や態度でどうしてたって、出来る事をやっている。
(どんな事でもいい。僕も何か、バアちゃんが見つかる手伝いを、出来る事を・・・・・・)
僕はキュウリを握り締め、目をつむって心の中で必死に願った。
(――将太のバアちゃんが、河童に連れて行かれたんじゃありませんように。今もどこかで生きていますように。無事見つかりますように。また会えますように。河童、もしお前が池に連れ込んだんなら、返して。お願い――)
すっと目をあけた。真っ暗な水面と、その上に僅かににゆれる灯り、犬の遠吠え、目を閉じる前と何一つ変わらなかった。
フゥ、大一番のピッチャーのように深呼吸を一つついて、キュウリを思い切り池に放り投げた。
「そ、れッ!」
キュウリはくるくると回転しながら池の真ん中ぐらいに落ちていった。真っ暗闇に、ぽちゃんと小さな水しぶきが白く光る。
その次の瞬間だった。
バシャバシャバシャバシャ!
池の中央、キュウリの落ちたあたりで、ものすごいしぶきが立ち始めた。僕は息をのみ、思わず池に背を向けてダッシュでそこから離れた。
(――何アレ、何アレ今のん!)
ここは危ない! ここは危ない! ここは危ない!
早く離れろ! 早く離れろ! 早く早く早く!
全身の細胞がそう叫んで、心臓が爆発しそうだった。
「ウウッ」
漏らした嗚咽(おえつ)をまた飲み込む。
声を出したら河童に気(け)取られる! いや、もしかしたらもう、すぐ後ろに迫ってきているのかもしれない。声を押さえ込むと涙が溢れる。
(――殺(や)られる!)
とにかく必死で走った。・・・・・・将太、僕らが知恵ちゃんにやってのけた仕打ちは、僕らが思っていたよりヒドいのかもしれない。
段々大きくなる我が家とその灯りを見つめながら涙と鼻水をTシャツの袖になすりつけ、今度知恵ちゃんにあったら優しくしようと思った。
【六】
将太に会ったのは、翌日の登校中だった。
「よ、よぉ」
つい顔が引きつる。自然に、自然にと心で自分に言い聞かす。我がの巻いた種や、と思うと恥ずかしいやらなんやら・・・・・・もしタイムスリップして昨日の自分に会えるなら、はっ倒してやるのに。
「おぉ。なぁ、昨日の『ワイルドソルジャーズ』観たぁ?」
いきなり、昨晩七時放送のアニメの話だった。カラッとした将太の態度に戸惑わざるをえない僕は、なんて小物なんだろう。それでも必死で話を合わせる。
「あの敵キャラないやろ! って思たよなぁ」
「うん。ない。『キミのハートにロックオン!』って、どんだけクサいんかって話」
「『ロックオン』て! なぁ!」
いつもの他愛ないやりとり。それでも一言口から出て、一言返ってくるたび心が軽くなるのを感じた。もしかして、将太は僕がわざとそっけなくしたのに気付いていないのかな。悩んだのは自分だけか、とまた少しムカついて、ムカついたのの百倍救われた気がした。
「そや、ヒロアキ、これ」
将太が一枚のカードを差し出してきた。渡してきたのは、僕の期待したとおりのカードだった。パワーアップ系の装備カード。これも、『老鳥』と同じぐらいの、希少価値ゼロの凡カードだ。
『燃えたぎる生命の炎』――老鳥専用装備カード。これを装備した老鳥は、不死鳥(フェニックス)として再度その姿を見せる――
「おお、ほんでな、今回味方キャラ増えたやん」
僕はなんだか照れくさくて、わざとカードをぞんざいにポケットの中に突っ込んでアニメの話に戻した。
将太も、あっけらかんとそれに応じた。
「あーあいつな。なんかまた裏切るっぽい感じがめっちゃする!」
「確かに露骨よなぁ。てかマンガの方じゃもう裏切っとるけど」
将太はきっと、僕がこのカードに込めたごめんの意味には気付かなかったんだと思う。それでも、お互いバアちゃんの生還を信じる仲間になった。それで十分だった。たったそれだけのことが、レベル九十九の勇者を味方にするより心強く思えた。
それから、学校で授業を受けて、休み時間にキックベースやって、給食で焼きプリンタルトの争奪戦やって、昼休みにキックベースやって、掃除の時間にキックベースやって叱られて。本当に、何もかもがいつも通りだった。
何も変らない日常に戻った僕は、バアちゃんの無事を確信した。その根拠のない自信に自分がおかしくて笑ける。それでも理屈じゃない。気持ちは晴れていた。
そしてその日の、帰りの会のときだった。
「ご町内の みなさまに 行方不明者 発見の お知らせです」
町内アナウンスに、教室中がしんとした。橋元(ハシ)先生(ゲン)までもが聞き入った。
「先日 行方不明となった 内海町木庄地区 上村誠一郎さん宅 上村フジ子さんが さきほど 発見されました。 みなさまのご協力 ありがとうございました 繰り返します・・・・・・」
アナウンスは、死亡(おく)告知(やみ)じゃない。
「やったァ!」
教室中がわいた。
「将太、よかったな」
「おばあちゃん、結局どこおったんやろ」
クラスの皆が興奮していた。収拾のつかない騒ぎように、橋元(ハシ)先生(ゲン)だけが不機嫌そうだった。
「オイ、座れ。静かに、静かに!」
なかなか興奮の収まらない教室に教頭先生が入ってきて、橋元(ハシ)先生(ゲン)と二言(ふたこと)三言(みこと)会話を交わし、やがて将太を職員室に連行していった。
役者がいなくなってもクラスの浮かれた空気は納まらなかった。僕もやっぱりその一人だった。
「なあヒロアキ、よう将太ん家行くんやろ? 今度行ったらバアちゃんにドコ行っとったんか聞いてみィや」
「おお、分かった」
和やかなムードが教室を包む。そんな空気を払いのけたのは橋元(ハシ)先生(ゲン)だった。
「ちょっと、一つ、聞いてくれ!」
普段聞かない担任の先生の大きな声に、教室中が黙りこくった。
「さっきの放送、何て言うたか・・・・・・ほうやな、ヒロアキ、言うてみてくれ」
いきなり当てられてドキッとしたけど、朗報に変わりない。背筋を伸ばし、どこか誇らしげな気持ちで答えた。
「えっと、行方不明者発見のお知らせです。上村フジ子さんが発見されました。ありがとうございました・・・・・・」
大方言い切ったつもりなのに、橋元(ハシ)先生(ゲン)は浮かない顔をしたままだった。一体何を言い漏らしたっけと周りの席のヤツらに目で助けを求める。皆、首をかしげるばかりだった。先生はそうやな、と言って黒板の方を向き、白いチョークで僕の言った通りを横書きで大きく書いた。
なにがなんだか、という顔をした皆を尻目に、橋元(ハシ)先生(ゲン)は赤いチョークを持ち直して『発見されました』の文字の上に『無事』と付け加えた。
そして、僕らのほうを向きなおして言った。
「皆、知らいでも無理ないけどな。ええ機会やから今日覚えェ。こういう放送ん時、生きて見つかった場合は『発見されました』やのうて『無事発見されました』て言うんや」
ついさっきとは一転して、誰もが言葉を失った。僕は怖くて誰の顔も見れず、ただ赤いチョークで書かれた『無事』の二文字を見ていた。
皆、似たような顔をしていたんだろう。その後は橋元(ハシ)先生(ゲン)もかける言葉が無かったようで、帰りの会が終わると早足に教室を出て行ってしまった。
クラスメイトもぽつりぽつりと席を立ち始め、やがて何事も無かったようにいつもの喧騒を起こし一人また一人と教室を飛び出して行った。
一人になった教室で、ぼんやり黒板の文字を眺めた。金魚の水槽の、ろ過装置の音だけが低く振動する。
どこで死んでいたのか、誰が見つけたのか。将太は職員室で教頭先生に聞かされたのか、泣かなかっただろうか、バアちゃんのことを心から心配出来ていたのは誰か。
とりとめもない事が頭に浮かんでは消えていった。
「♪ユウヤケコヤケデヒガクレテ――
子どものみなさん おうちへ帰る 時刻になりました 早く お家へ帰りましょう―
♪マアルイオオキナオツキサマ―」
随分長く座っていたらしかった。夕べの鐘が聞こえてきて、はっと時計を見ると五時三十分。いつのまにか三十分早くなっていた。僕はランドセルを引っつかみ教室を飛び出し夢中で走った。いちいち上下に暴れるランドセルがうっとくさい。
(なんだ、河童のヤツ! キュウリのお供え持ってったくせに!
のうての池に着くと、立ち入り禁止の土手から握りこぶし程の石を一つ拾い上げ、怒りにまかせ力いっぱい水面にほうりなげた。
バシャバシャバシャ!
石の落ちたところに、昨日の夜とおなじ飛沫(しぶき)が上がる。
(――ああ、これか・・・・・・)
河童の正体は、落ちた石を餌と間違えた鯉の何百と群がる姿だった。
※作品の無断転載を禁じます。