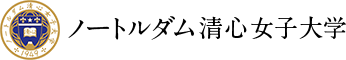2014.04.01
本学科の授業科目「文学創作論」では、履修生が1年をかけて作り上げた作品をまとめて、文集を発
行しています。
文集第11集『あい』(2013年度)より、1作をここにご紹介します。
神様に一番近い少女の話
作・疋田早紀
「未歩ちゃん、遅いな」
みなみが白い息とともに吐いた言葉は、夜の街ひっそりと消えた。辺りは、仕事帰りの会社員や学生、親子連れなどであふれ返っている。彼らは、煌々と光るイルミネーションをしばらく眺め、ビル街に消えていく。雑踏の中には、時折電車の停止する音が聞こえ、その度にみなみは改札に目を向ける。
「未歩ちゃん、早く来て。そろそろ私の寂しさもお腹も限界です」
一時間前に連絡が来て以来、鳴る気配のない携帯を見る。画面には未読メール二件の文字が浮かんでいた。素早く画面をタッチし、詳細を確認する。受信画面には、『ゼミ課題の連絡』と『就活対策講座のお知らせ』と表示されていた。
慣れた手つきで胃の辺りをさする。一、二と指を立てていき、指が足りなくなったところでため息をついた。
(やらなきゃいけないこと、たくさん)
腹部をさすっていた手は、切りそろえられていた前髪を乱暴に掻きあげる。みなみは携帯をポケットに突っ込んだ。
(これから未歩ちゃんに会うのに、何でこんなやなことばっかり)
みなみを照らすのは、桃太郎像に施されている桃の電飾だけだった。薄色の光は夜に溶けてしまいそうなほど弱弱しい。再びついたため息は、誰に聞かれることもなく、電車の音にかき消された。
「みーなみ、お待たせっ。凍えてない?」
声の主は、みなみの両肩を掴む。みなみは声をあげ、思わず前につんのめった。
ごめんごめん、と軽く謝る声に、記憶の中の幼なじみのいたずらっぽい笑みが浮かぶ。うるさい心臓を抑え込み、恨みがましそうな表情で声の主のほうへ顔を向ける。
待ち人を目にした時、みなみは二の句が告げなかった。
「未歩ちゃん、髪......」
言葉になったのは二単語だけだった。二十年来の付き合いのある幼なじみに、あるはずのものが消失していた。未歩は、仕事で邪魔になるから切っちゃった、と笑った。
「ごめん。髪、短くなってたから、一瞬、人違いかと」
「そっか、みなみと最後に会ったのは、髪切る前か」
じゃあ、もう一年くらい前になるのかなあ、と続ける。幼なじみの見慣れない姿に、みなみの目は自然と向いてしまう。
(なんかまた、大人びたな、未歩ちゃん)
一年前には、緩く巻かれていたロングヘアは、今では肩で切り揃えられている。ネイルで彩られていた爪は、短くなっていた。すべすべだった手は、今では荒れて皮が剥けている。「もしかして似合わない? 職場ではわりと好評だったんだけど」
「い、いや、そんなことないよ。かわいいよ」
未歩にぐっと手を握られ、距離を詰められる。みなみは視線を反らせ、たじろぐ。
「目を見て話せないってことは、嘘だね」
「......ごめん」
慣れなくて、とみなみが漏らすと、未歩はあっさりと手を離した。それはそうか、と未歩は一人で納得した。
「ところで未歩ちゃん、今日はどうしたの?」
未歩ちゃんのとこの保育園、七時退勤じゃなかったっけ、と続けると、あー、と視線をそらされる。
「本来はそうなんだけど......なかなか最後の子のお母さんが迎えにきてくれなくて」
「クリスマス前なのに? いつの時代になっても薄情な親はいるんだね」
「まあ、社会人にはいろいろあるんだよ。なってみないとわからないことばっかだし」
社会人という言葉を聞き、就活サイトのメールが頭をよぎった。同時にみなみの表情は曇る。
「言い訳ばっかりしてごめんね。こんな寒い中待たせちゃったし、なんか奢るわ」
「いやいや、いいよ。待つの嫌いじゃないし。それより早く、お店行こう」
みなみは、笑顔を作り、お腹が空いたよ、と未歩を急かした。
みなみと未歩が向かい合って席に着く。同時に、ウェイターが食事に必要な道具を置き、お料理すぐお持ちいたしますね、と厨房に消えていった。
「みなみとご飯食べるの久しぶりだね」
「前の時は、買い物だけだったから......二年ぶりぐらい?」
「小さい頃は、家が近かったから毎日のように一緒に食べてたのにね」
小学校の頃は未歩ちゃんがいつも家に来て、晩御飯食べてたよね、とみなみは昔を懐かしむ。未歩も同調した。
「うちの親は帰りが遅いから寂しくて。悪いとは思ってたんだけど」
「そんなこと気にしなくてもよかったのに。母さんが、未歩ちゃんは娘みたいなものだから、遠慮なんてしなくていいって言ってたよ」
みなみは母が、ひっそりと口角を上げていたことを思い出す。記憶にある母は、未歩が欲しい料理を、静かに差し出していた。次第にみなみの家には、みなみ、母、未歩という三人の晩御飯の習慣が形成されていった。
「本当、おばさんには感謝してる。おばさん料理上手だから、ご飯食べれなくなるの、嫌だったなあ」
「私は、未歩ちゃんともうご飯が食べれないってわかった後は、絶望のあまり食欲失せたからね」
みなみは未歩のいる席で、父親に転校を告げられた日のことを思い出す。中学二年生の夏休みの補習帰り。未歩と一緒に自転車に乗り、切なく鳴る腹の虫に耐え、みなみの家を目指していた。
「私、父さんの言ってることの意味がわからなくて。今じゃこんだけ冷静に話せるけど、最初はあの日のことを思い出す度に、泣きまくってたから」
「知ってるよ。あの日はみなみが先に泣き出しちゃったから、私、泣けなかった」
未歩や自分の父親と食べた昼食は、サイダーとチャーハンだった。みなみは、好物だったにもかかわらず、未だにその味を思い出せないでいる。
「しょうがないじゃん、生まれて初めての大きな別れだったんだから」
「私もそうだったよ」
「しかも、長崎なんて遠いとこだし」
「みなみ、毎日のように電話かけてくれたよね」
みなみは、自分のカバンに目をやる。突然、カバンの中に入っているものが熱を帯びたような感覚に包まれた。未歩は言葉を続ける。
「それがだんだん、一週間に一回になって、二週間に一回になって、月一回になって、高校上がる頃には、半年に一回ぐらいになって。こっちで就職してからは、一年に一回」
「でも、間隔空くのに未歩ちゃんとは気まずさとか全くないよ」
そういえばそうだね、と返した未歩の前にコーンスープが置かれる。みなみの前には、ミネストローネが置かれた。二人は会話を一旦やめ、暖かいスープを前に顔を見合わせる。
「とりあえず、スープが冷めちゃうから」
二人は手を合わせ、互いにいただきます、と感謝の言葉を述べた。
行しています。
文集第11集『あい』(2013年度)より、1作をここにご紹介します。
神様に一番近い少女の話
作・疋田早紀
「未歩ちゃん、遅いな」
みなみが白い息とともに吐いた言葉は、夜の街ひっそりと消えた。辺りは、仕事帰りの会社員や学生、親子連れなどであふれ返っている。彼らは、煌々と光るイルミネーションをしばらく眺め、ビル街に消えていく。雑踏の中には、時折電車の停止する音が聞こえ、その度にみなみは改札に目を向ける。
「未歩ちゃん、早く来て。そろそろ私の寂しさもお腹も限界です」
一時間前に連絡が来て以来、鳴る気配のない携帯を見る。画面には未読メール二件の文字が浮かんでいた。素早く画面をタッチし、詳細を確認する。受信画面には、『ゼミ課題の連絡』と『就活対策講座のお知らせ』と表示されていた。
慣れた手つきで胃の辺りをさする。一、二と指を立てていき、指が足りなくなったところでため息をついた。
(やらなきゃいけないこと、たくさん)
腹部をさすっていた手は、切りそろえられていた前髪を乱暴に掻きあげる。みなみは携帯をポケットに突っ込んだ。
(これから未歩ちゃんに会うのに、何でこんなやなことばっかり)
みなみを照らすのは、桃太郎像に施されている桃の電飾だけだった。薄色の光は夜に溶けてしまいそうなほど弱弱しい。再びついたため息は、誰に聞かれることもなく、電車の音にかき消された。
「みーなみ、お待たせっ。凍えてない?」
声の主は、みなみの両肩を掴む。みなみは声をあげ、思わず前につんのめった。
ごめんごめん、と軽く謝る声に、記憶の中の幼なじみのいたずらっぽい笑みが浮かぶ。うるさい心臓を抑え込み、恨みがましそうな表情で声の主のほうへ顔を向ける。
待ち人を目にした時、みなみは二の句が告げなかった。
「未歩ちゃん、髪......」
言葉になったのは二単語だけだった。二十年来の付き合いのある幼なじみに、あるはずのものが消失していた。未歩は、仕事で邪魔になるから切っちゃった、と笑った。
「ごめん。髪、短くなってたから、一瞬、人違いかと」
「そっか、みなみと最後に会ったのは、髪切る前か」
じゃあ、もう一年くらい前になるのかなあ、と続ける。幼なじみの見慣れない姿に、みなみの目は自然と向いてしまう。
(なんかまた、大人びたな、未歩ちゃん)
一年前には、緩く巻かれていたロングヘアは、今では肩で切り揃えられている。ネイルで彩られていた爪は、短くなっていた。すべすべだった手は、今では荒れて皮が剥けている。「もしかして似合わない? 職場ではわりと好評だったんだけど」
「い、いや、そんなことないよ。かわいいよ」
未歩にぐっと手を握られ、距離を詰められる。みなみは視線を反らせ、たじろぐ。
「目を見て話せないってことは、嘘だね」
「......ごめん」
慣れなくて、とみなみが漏らすと、未歩はあっさりと手を離した。それはそうか、と未歩は一人で納得した。
「ところで未歩ちゃん、今日はどうしたの?」
未歩ちゃんのとこの保育園、七時退勤じゃなかったっけ、と続けると、あー、と視線をそらされる。
「本来はそうなんだけど......なかなか最後の子のお母さんが迎えにきてくれなくて」
「クリスマス前なのに? いつの時代になっても薄情な親はいるんだね」
「まあ、社会人にはいろいろあるんだよ。なってみないとわからないことばっかだし」
社会人という言葉を聞き、就活サイトのメールが頭をよぎった。同時にみなみの表情は曇る。
「言い訳ばっかりしてごめんね。こんな寒い中待たせちゃったし、なんか奢るわ」
「いやいや、いいよ。待つの嫌いじゃないし。それより早く、お店行こう」
みなみは、笑顔を作り、お腹が空いたよ、と未歩を急かした。
みなみと未歩が向かい合って席に着く。同時に、ウェイターが食事に必要な道具を置き、お料理すぐお持ちいたしますね、と厨房に消えていった。
「みなみとご飯食べるの久しぶりだね」
「前の時は、買い物だけだったから......二年ぶりぐらい?」
「小さい頃は、家が近かったから毎日のように一緒に食べてたのにね」
小学校の頃は未歩ちゃんがいつも家に来て、晩御飯食べてたよね、とみなみは昔を懐かしむ。未歩も同調した。
「うちの親は帰りが遅いから寂しくて。悪いとは思ってたんだけど」
「そんなこと気にしなくてもよかったのに。母さんが、未歩ちゃんは娘みたいなものだから、遠慮なんてしなくていいって言ってたよ」
みなみは母が、ひっそりと口角を上げていたことを思い出す。記憶にある母は、未歩が欲しい料理を、静かに差し出していた。次第にみなみの家には、みなみ、母、未歩という三人の晩御飯の習慣が形成されていった。
「本当、おばさんには感謝してる。おばさん料理上手だから、ご飯食べれなくなるの、嫌だったなあ」
「私は、未歩ちゃんともうご飯が食べれないってわかった後は、絶望のあまり食欲失せたからね」
みなみは未歩のいる席で、父親に転校を告げられた日のことを思い出す。中学二年生の夏休みの補習帰り。未歩と一緒に自転車に乗り、切なく鳴る腹の虫に耐え、みなみの家を目指していた。
「私、父さんの言ってることの意味がわからなくて。今じゃこんだけ冷静に話せるけど、最初はあの日のことを思い出す度に、泣きまくってたから」
「知ってるよ。あの日はみなみが先に泣き出しちゃったから、私、泣けなかった」
未歩や自分の父親と食べた昼食は、サイダーとチャーハンだった。みなみは、好物だったにもかかわらず、未だにその味を思い出せないでいる。
「しょうがないじゃん、生まれて初めての大きな別れだったんだから」
「私もそうだったよ」
「しかも、長崎なんて遠いとこだし」
「みなみ、毎日のように電話かけてくれたよね」
みなみは、自分のカバンに目をやる。突然、カバンの中に入っているものが熱を帯びたような感覚に包まれた。未歩は言葉を続ける。
「それがだんだん、一週間に一回になって、二週間に一回になって、月一回になって、高校上がる頃には、半年に一回ぐらいになって。こっちで就職してからは、一年に一回」
「でも、間隔空くのに未歩ちゃんとは気まずさとか全くないよ」
そういえばそうだね、と返した未歩の前にコーンスープが置かれる。みなみの前には、ミネストローネが置かれた。二人は会話を一旦やめ、暖かいスープを前に顔を見合わせる。
「とりあえず、スープが冷めちゃうから」
二人は手を合わせ、互いにいただきます、と感謝の言葉を述べた。
「おいしかったー」
「未歩ちゃんって昔から謎だよね。その細い体のどこに膨大な量の食べ物いれてるの」
二人の目の前にはデザートのケーキが並べられている。満たされた胃と相まって、みなみは生クリームの甘い匂いに少し吐き気を催した。
「ん? みなみ食べないの。そっか生クリーム、苦手だったもんね」
みなみが肯定する間もなく、ショートケーキは未歩の口の中に消えた。小さい頃と変わらない光景に、自然と口角が上がった。
「で、なんで私を食事に誘ったの。重い腰のみなみがまた」未歩は食後の紅茶を飲みながら尋ねる。
「あー、あのね、私今、授業で文章書いてて、リアリズム書いてて」
口から出たのは、何ともまとまりのない言葉だった。
「みなみ、小さい頃からお話書くの好きで、よく私に見せてくれたよね」
「今回は昔と違ってまだ書きかけなんだけど......とにかく、未歩ちゃんに読んでほしい」
みなみはカバンから味気のない原稿を取り出す。未歩は、気押されたのか、う、うん、とだけ返事をして、黙って原稿を読み始めた。
「未歩ちゃんって昔から謎だよね。その細い体のどこに膨大な量の食べ物いれてるの」
二人の目の前にはデザートのケーキが並べられている。満たされた胃と相まって、みなみは生クリームの甘い匂いに少し吐き気を催した。
「ん? みなみ食べないの。そっか生クリーム、苦手だったもんね」
みなみが肯定する間もなく、ショートケーキは未歩の口の中に消えた。小さい頃と変わらない光景に、自然と口角が上がった。
「で、なんで私を食事に誘ったの。重い腰のみなみがまた」未歩は食後の紅茶を飲みながら尋ねる。
「あー、あのね、私今、授業で文章書いてて、リアリズム書いてて」
口から出たのは、何ともまとまりのない言葉だった。
「みなみ、小さい頃からお話書くの好きで、よく私に見せてくれたよね」
「今回は昔と違ってまだ書きかけなんだけど......とにかく、未歩ちゃんに読んでほしい」
みなみはカバンから味気のない原稿を取り出す。未歩は、気押されたのか、う、うん、とだけ返事をして、黙って原稿を読み始めた。
*
中学校の校庭には冷たい木枯らしが吹きつけている。枯れ葉は音をたて、行くあてを知る由もなく、彷徨い、何時の間にか消えている。校庭に生徒の姿はない。生徒たちはみな、各々の教室で次のテストに備え、勉強している。そんな中、何をするでもなく、椅子に座ってうつむいている少女がいた。机に無造作に置かれたノートには、『二年一組 山本さつき』と丁寧に書かれている。
さつきは、他の生徒に比べて大きな身体を、机と椅子という小さな空間に押し込め、動かない。生徒たちも、まるでさつきが存在しないようかのようにふるまう。
(だから、転校なんて、やだったんだよ)
さつきの瞳はみるみる水気を帯びてゆく。たまらず椅子から立ち上がると、一瞬教室の空気が止まる。
さつきが動き出すと、教室では他人の声門がわずかにこすれる音がさつきの聴覚をわずかに刺激した。それは、さつきの小さな心に、ちくり、ちくりと確実に痛みを残す。毎晩、自分の記憶に墨液を垂らしても、いくつかの記憶は墨がすぐには染みこまず、時には完全に染み込んだ後でも、墨をはじいて再び心を苛むトゲとなる。
勉強机に押し込めていた足までもが軋むように痛む。それでも、トイレへ向かう足は止めない。
(わたしがなにをしたって、いうの)
熱い液体がさつきの瞳の中でゆらめく。歯を食いしばり、眉間にしわをよせて、自分の目の中でくすぶる想いを決して外界と触れ合わさぬように、うつむいて歩く。誰もいないトイレの一番奥に閉じこもり、ハンカチを目に押し当てる。嗚咽も涙もみな、ハンカチの柔らかさに吸い込まれていった。
(ちょっと人より、体が大きいだけなのに)
怖がらないで、そんな目で見ないで、さつきの心は常にその思いでいっぱいだった。しかし、自分の思いを口にすることを恐れ、ただ身を縮こまらせて、自分に向かってくる悪意をやりすごすので精一杯だった。
(ミホちゃん、たすけて)
さつきは、人目を忍んで泣く時に、引っ込み思案で臆病な自分の前に立って、力強く手を引っ張ってくれた幼なじみのことを思い出す。
「さっちゃんはいいなあ。おっきいから」
――なんで。
「だって、空の上にいるかみさまに私よりもずっとずっと近いんだもん」
――かみさま?
「そう、かみさま。誰よりも私たちを見てくれていて、誰よりも私たちをあいしてくれている方なんだよ。
さっちゃんは大きいから、かみさまに一番に見てもらえるね」
過去のさつきは、ミホが褒めてくれたのが嬉しくて、笑っていた。
さつきの願いはただ一つ、ミホのいる場所に帰ることだけだった。
(かみさまなんかじゃなくて、ミホちゃんがいいよ)
記憶の中のミホは、十字架のペンダントを手で包みながら、聖歌を歌っていた。さつきの伸ばした手をつかんでくれることはない。次第に、ミホの歌にさつきの鼻をすする音が交じる。聖歌は雑音によって神聖な響きを失い、記憶の中のミホの顔もぼやけていった。
六限後のホームルームを終え、生徒たちは下校していく。さつきに声をかける者はおらず、仲の良い者同士で手を取り合い帰りの道を急ぐ。さつきは、足を机の中にしまいこみ、微動だにしない。あの雑音の中を帰るのはひどく不快だった。ひんやりとした空気が、産毛の生えた頬に突き刺さる。
下校の波が切れると、スクールバックから宿題を取り出し、帰る前に済ませてしまう。どんよりとした夕日が去って、暗闇が押し寄せようとする頃に帰っても、誰にも文句は言われない。
「今日の宿題終わった。帰ろう」
校庭に目をやると、夕日は沈みかけ、校庭には既に誰もいなかった。見てくる人がいなければうつむく必要もない。一度伸びをして、身体をほぐしてから学校を出た。
学校近くの住宅地を抜け、公園が目に入る。普段は子供でにぎわっているが、カラスの鳴き声が響くだけで、人の姿はない。わずかに揺れるブランコと、乗り手を失い、動きを止めたシーソー。その中でジャングルジムはひときわ夕日の赤に染まり、さつきの目に強烈に焼きついた。
(空に近い場所。かみさまに一番近い場所)
さつきはジャングルジムに登った。地上の雑音から逃げるように。まるで頂上に自分の求めるものが存在するかのように登っていった。冷たい金属は、容赦なくさつきの手を刺した。それでも登ることをやめなかった。さつきの視界から、ジャングルジムの金属が消え、夕日の完全に消えた空が目に入る。辺り一帯をゆっくり見渡す。さつきの知らない建物がたくさんある。明かりの暖色が、寒さを緩和させているようだった。
中学校の校庭には冷たい木枯らしが吹きつけている。枯れ葉は音をたて、行くあてを知る由もなく、彷徨い、何時の間にか消えている。校庭に生徒の姿はない。生徒たちはみな、各々の教室で次のテストに備え、勉強している。そんな中、何をするでもなく、椅子に座ってうつむいている少女がいた。机に無造作に置かれたノートには、『二年一組 山本さつき』と丁寧に書かれている。
さつきは、他の生徒に比べて大きな身体を、机と椅子という小さな空間に押し込め、動かない。生徒たちも、まるでさつきが存在しないようかのようにふるまう。
(だから、転校なんて、やだったんだよ)
さつきの瞳はみるみる水気を帯びてゆく。たまらず椅子から立ち上がると、一瞬教室の空気が止まる。
さつきが動き出すと、教室では他人の声門がわずかにこすれる音がさつきの聴覚をわずかに刺激した。それは、さつきの小さな心に、ちくり、ちくりと確実に痛みを残す。毎晩、自分の記憶に墨液を垂らしても、いくつかの記憶は墨がすぐには染みこまず、時には完全に染み込んだ後でも、墨をはじいて再び心を苛むトゲとなる。
勉強机に押し込めていた足までもが軋むように痛む。それでも、トイレへ向かう足は止めない。
(わたしがなにをしたって、いうの)
熱い液体がさつきの瞳の中でゆらめく。歯を食いしばり、眉間にしわをよせて、自分の目の中でくすぶる想いを決して外界と触れ合わさぬように、うつむいて歩く。誰もいないトイレの一番奥に閉じこもり、ハンカチを目に押し当てる。嗚咽も涙もみな、ハンカチの柔らかさに吸い込まれていった。
(ちょっと人より、体が大きいだけなのに)
怖がらないで、そんな目で見ないで、さつきの心は常にその思いでいっぱいだった。しかし、自分の思いを口にすることを恐れ、ただ身を縮こまらせて、自分に向かってくる悪意をやりすごすので精一杯だった。
(ミホちゃん、たすけて)
さつきは、人目を忍んで泣く時に、引っ込み思案で臆病な自分の前に立って、力強く手を引っ張ってくれた幼なじみのことを思い出す。
「さっちゃんはいいなあ。おっきいから」
――なんで。
「だって、空の上にいるかみさまに私よりもずっとずっと近いんだもん」
――かみさま?
「そう、かみさま。誰よりも私たちを見てくれていて、誰よりも私たちをあいしてくれている方なんだよ。
さっちゃんは大きいから、かみさまに一番に見てもらえるね」
過去のさつきは、ミホが褒めてくれたのが嬉しくて、笑っていた。
さつきの願いはただ一つ、ミホのいる場所に帰ることだけだった。
(かみさまなんかじゃなくて、ミホちゃんがいいよ)
記憶の中のミホは、十字架のペンダントを手で包みながら、聖歌を歌っていた。さつきの伸ばした手をつかんでくれることはない。次第に、ミホの歌にさつきの鼻をすする音が交じる。聖歌は雑音によって神聖な響きを失い、記憶の中のミホの顔もぼやけていった。
六限後のホームルームを終え、生徒たちは下校していく。さつきに声をかける者はおらず、仲の良い者同士で手を取り合い帰りの道を急ぐ。さつきは、足を机の中にしまいこみ、微動だにしない。あの雑音の中を帰るのはひどく不快だった。ひんやりとした空気が、産毛の生えた頬に突き刺さる。
下校の波が切れると、スクールバックから宿題を取り出し、帰る前に済ませてしまう。どんよりとした夕日が去って、暗闇が押し寄せようとする頃に帰っても、誰にも文句は言われない。
「今日の宿題終わった。帰ろう」
校庭に目をやると、夕日は沈みかけ、校庭には既に誰もいなかった。見てくる人がいなければうつむく必要もない。一度伸びをして、身体をほぐしてから学校を出た。
学校近くの住宅地を抜け、公園が目に入る。普段は子供でにぎわっているが、カラスの鳴き声が響くだけで、人の姿はない。わずかに揺れるブランコと、乗り手を失い、動きを止めたシーソー。その中でジャングルジムはひときわ夕日の赤に染まり、さつきの目に強烈に焼きついた。
(空に近い場所。かみさまに一番近い場所)
さつきはジャングルジムに登った。地上の雑音から逃げるように。まるで頂上に自分の求めるものが存在するかのように登っていった。冷たい金属は、容赦なくさつきの手を刺した。それでも登ることをやめなかった。さつきの視界から、ジャングルジムの金属が消え、夕日の完全に消えた空が目に入る。辺り一帯をゆっくり見渡す。さつきの知らない建物がたくさんある。明かりの暖色が、寒さを緩和させているようだった。
「あれ、なんだろう」
街の風景を一周分堪能した後、さつきの目に入ったのは、町のどの建物よりも高い位置にある十字架だった。屋根の上に、十字架を掲げ、屋根の中央部には鐘が見える。十字架は白く張りつめた光に照らされ、独特の雰囲気を纏っていた。さつきは思わず息を詰める。
(もしかして、あれ、教会かな)
ミホに連れられて一度だけいったことのある、赦しの場。白く、重い扉を開けるのには勇気がいるが、一度入ってしまうと、空気の流れがさらさらと、全身をなで、優しく包んでくれる。教会にいる人は、みな平等で、雑音を発さない。とても心地の良い場所。寂しさも苦しさも悲しみも、全て祭壇の十字架が吸い取ってくれるような気さえしていた。
「かみさま」
さつきは、自身の心のトゲを抜き、傷を撫でさすってくれるものを求めていた。血が吹き出るとわかっていながらも、何の見返りもなく傷の治療をしてくれる人を求めていた。自分の力では、傷から目を反らし、痛みに震えていることしかできなかった。さつきの心は孤独だった。
教会につく頃には、夕日は夜の闇にさらわれていた。頬は寒さでぴりぴりと痛む。金色の取っ手をつかんだ両のてのひらは既に感覚がない。教会に来るまでは、何も考えていなかったけれども、取っ手をつかんでから急に、心臓が存在を主張してきた。本当に自分が来ていい場所なのか、そもそも来て何をするつもりなのか、ここは本当に教会なのか。疑問が浮かんでは消える。その間、煌々と光る十字架だけがさつきを見ていた。
(どうしよう、どうしよう)
肝心の一歩が出ない。少し力を入れるだけで、ドアは簡単に開くはずなのに、さつきの身体は心臓だけがうるさく打つのみで、身体は凍ったように動かない。ここまで来たのに、結局何も変わらない。さつきは唇を噛んだ。すると、
「きゃあ」
いきなりドアが反対側から押され、不意をつかれたさつきの身体はお尻から後ろに倒れてしまう。じんじんと尻から伝わる痛みに、鼻の奥がつんとした。
「申し訳ありません。大丈夫ですか」
ドアを開けたであろう人物が、さつきをそっと助け起こす。近づいた時に祖母の家に似た匂いに交じって、ほんの少し煙草が香った。さつきが手を借りて立ちあがると、どこもけがはないですか、としゃがんで聞いてきた。さつきは、蚊のなくような声で、はい、と返すのが精一杯だった。
「そこにいては寒いでしょうから、どうぞ中に」
男はさつきが開けられないでいた教会の扉をいとも簡単に開け、さつきを招き入れた。足を踏み入れると、かつん、かつんという靴音がやけに耳につく。教会の中は、昔ミホと共にいった時と変わらず、柔らかな空気が頬を撫でる。鼓動の音は安定を取り戻し、男の茶色いパーマのかかった頭から、白く光る髪の毛を見つけるほどに余裕ができていた。祭壇の近くの椅子の前で男は止まり、さつきに、どうぞ、と椅子に座るように促した。
「先ほどはすみません。こんなに小さくて愛らしいお嬢さんがいるとは思っていませんでしたので」
小さい、愛らしい、という聞き慣れぬ言葉にどう反応してよいかわからず、さつきは首を横に振るだけだった。男は、ちょっと待っててくださいね、と祭壇の奥の部屋に消えた。さつきは辺りを見渡す。昔ミホと行った教会もこんな感じだっただろうか、あの空間に流れる空気は鮮明に覚えているのに、それ以外は靄がかかったようにはっきりしない。
靄の中で少しだけ記憶にあるのは、神父の姿だった。白い服を着て、黒髪に少し日に焼けた肌を持ち、周りの空気まで清廉さを纏った神父。朗々と式を進める神父は、さつきにとっては神そのもののように思えた。この教会であった男とは正反対の雰囲気を持っていた。
(茶色の髪と、髪よりも薄い、茶色の瞳。煙草の匂いがする黒いスーツみたいな服に、わたしより白い肌、に、紫色のアザ)
それに、暖かい手。さつきは、そっと彼の掴んでくれた手を頬に当てた。頬は既に熱を持っており、あまり暖かさを感じられなかった。
「お待たせしました」
男の声が部屋に反響する。同時に、甘い香りが漂ってきた。すると、途端に胃が空腹を訴え始めた。音がならないように、お腹を押さえてこらえる。ココアはお好きですか、という言葉に、一度だけうなずき、手を伸ばす。一口飲むと、甘さが舌から喉を通って、胃にじんわりと広がる感覚がした。思わず笑みがこぼれる。
「口に合ったようでよかったです。女の子を泣かせてしまっては、男として最低ですからね」
ウインクをすると目尻のしわが、左目に集中する。左手が、さつきの頭の上に優しく添えられ、髪の一筋一筋をいたわるようになでた。右手の数珠が音を立てる。久しぶりに頭をなでられ、一瞬びくりとふるえたが、気持ちがいいのでそのままにしておいた。
「今日は、どうしていらしてくださったんですか、小さなお嬢さん」
目を覗きこまれる。決していやらしさを感じさせない、人懐っこい目だった。さつきは、震える唇から、ちいさい、という言葉だけを紡ぎだした。自分を形容する時には決して使われない、憧れの言葉。さつきが欲しい言葉を、さも当たり前であるかのように、男は言った。けれどもさつきは、その言葉をすぐ信用できるほど子供ではなかった。唇をぐっと噛み、ゆらゆらと熱く揺れはじめる視界の中、真実か嘘かを必死に見極めようとしていた。
「うそ」
こぼれでた言葉は、男の言葉を否定するものだった。言葉を発すると同時に息が漏れ、はずみで、涙がこぼれた。脳裏には、足を窮屈に折りたたんで座っている自分を、のけものにする同級生の顔が浮かぶ。
同級生たちは、山本さんって大きいから怖い、いつもうつむいてて、何考えてるかわかんないし、時々私たちのこと睨んでるし、と記憶の中でさつきを苛んだ。
(ちがうよ。そんなことしてない。もうやめて、いわないで)
いそいで記憶に墨液を垂らすも間に合わない。ついに、小さな心は限界を迎えてしまった。
「もういやだよぉ......。わたしのがっこの、ひとたちは、み、みんな、うっ、わたしのっ、からだがおおきい、おおきい、からぁ、こわい、って」
喉の奥に何かが詰まっているように息が苦しかった。さつきの、喉にかかった嗚咽は、教会の空気を波立たせた。天井に吸い込まれては、また新たな音の波が生まれた。男は、黙ってさつきの言葉を待った。
「おおきく、なりたくてっ......うう、っふ、なったわけじゃ、ない、のに。わたしだって、わたしだって、......みんなといっしょがよかったっ。みんなと」
仲良くしたいだけなのに、という思いは喉にひっかかって消えた。あとはただ、両の手で、自分の目を覆うだけだった。つぶらな瞳からは、まばたきをするたびに、熱い塊がちぎれて落ちていった。さつきの心の傷すべてから、血が噴き出したかのように、悲しみは教会中を埋め尽くそうとしていた。さつきは涙を止める術を持たず、喉の奥でひいひいと音を鳴らして、熱い濁流を目から流し続けた。
男は、目の前で泣き続けるさつきをそっと抱きしめた。嗚咽はやまず、肩の辺りに濃いしみが広がっていく。ゆっくり左手で、さつきの頭を撫でる。まるで幼子に眠りを促すように、鼓動のリズムで、右手で背中を叩く。次第に、鼻を鳴らす回数が減っていく。ほっと息をついて、さつきの耳元にそっと囁いた。
「ねえ、知ってますか。身体の大きい人は、神様に近いんですよ」
かみさま、という言葉を聞いて、さつきの身体がぴくりと反応する。鼻をすする音が教会に響く。
「神様とは全ての生物を見守り、愛してくれる方のことですね。その方は空のずっと上におられます」
さつきは、男の腕の中で相槌を打った。男は話を続ける。
「体の大きなあなたは、空に誰よりも近いから、神様にも一番近いんです。だから、神の愛が一番最初に届きます」
さつきが顔を上げて、顔を見ると、ねっ、と微笑みかけられる。昔、自分に同じ言葉をかけてくれた幼なじみの顔が男に重なって見える。
「きっとあなたの周りの子たちは、まだ神様の愛が届いてないんです。だから、自分たちより、少しだけ個性的なあなたと仲良くすることができなかった。愛をもらった人は、全ての人を平等に捉え、受け入れられるようになるんです」「わたし、かみさまの愛、本当に届いてるの? こんなに、さびしいのに」
男は、届いていますよ、と返事をし、さつきの髪を優しく梳いた。さつきの目からは、残っていた涙がぽろりと零れ落ちた。
「あなたが怒っているのは周りに対してではなく、あなた自身に対してですよね。寂しいのも、悲しいのも全部自分の責任だと思っています。周りの子をせめないで、赦そうとしている。間違いなく、あなたは神様の愛を一番に受けた、優しい子です」
男の目尻に刻まれたしわは、笑うと一層際立った。それが、彼の優しさを象徴しているようで、さつきはまた視界のゆらめきを味わった。喉がぐっと狭まるような感覚に、息が苦しくなる。まるで深海に潜っているようで、もう一人の力では耐えられなかった。さつきは長い腕を男の首の後ろに回し、顔を胸に押しつけた。男の胸元に新たな染みが広がっていく。男は何も言わず、静かに泣くさつきの身体を抱きしめた。
「ごめんなさい、服、汚しちゃって」
涙で腫れてしまった目をこすりながら謝る。気分はとてもすっきりしたが、今度は恥ずかしさがこみ上げて来て、男の顔をまっすぐに見られなかった。
「いえいえ、お気になさらず。あなたのきれいな涙なら、いくらでも大歓迎です」
あ、でも笑顔はもっと大歓迎ですね、と笑う彼の顔は本当にあたたかった。
「私、信者さんじゃないんですけど、これからもここに来ていいですか」
「もちろんです。神様の教えの通り、教会は全ての人のための場ですから」
さつきは帰る場所を見つけた子どものように喜んだ。たとえ傷ついても、教会は自分の傷を、優しく愛撫し癒やしてくれる。そう確信したからだ。
「ええと、あの、すごく遅くなってしまったんですけど、わたし、山本さつきって言います。この町に引っ越してきたばかりで。教会に来たのは、前住んでたところにいた友達が、信者さんで、教会は、迷い苦しむ人を受け入れてくれる場所だって、教えてくれたからで、それで」
言葉に詰まりながらも、なんとか話を進める。彼は決してさつきを急かすことなく、真剣に耳を傾けた。
「お友達のおっしゃる通りです。だから、さつきさんが来たいと思った時に来てください。ああ、私のほうこそ申し遅れましたね。私は、森崎真澄アルフレットと申します。友人には、アルと呼ばれたり、真澄と呼ばれたり、でもここに来る方は、神父さまと呼んでくださいますね」
さつきは神父の名前を聞き、自分とは大きく異なる容姿に納得した。しかし、神父が何者であろうとも、さつきの中の気持ちは揺るがなかった。
「ありがとうございます、神父さま」
*
みなみは、未歩が原稿を読み終わるのを待っていた。時折、眉間にしわが寄ったり、目を見開いたりといった、一挙一動を見逃さないようにしていた。
やがて、未歩は原稿を机に置き、深呼吸をした。何と言っていいかわからない、という表情だった。二人の間に沈黙が流れる。何も言わないみなみを見かねて、未歩が口火を切った。
「この話に出てくる、『ミホ』って私のこと? もしかして、みなみが転校してからの話をもとにしてるの?」
みなみは首を縦に振る。未歩は、原稿に目を落とし、言葉を続ける。
「電話してくるたびに、泣いてた時よね」
受話器を涙で濡らしては、電話代いくらかかると思ってるの、と母に怒られていた日が甦る。未歩ちゃんはいつも、大丈夫だから、そんなに泣かないの、と繰り返していた。
「でも、いつの間にか泣かなくなって、友達ができて......。電話の回数も減って。こうゆうことだったんだね」
うん、と一言だけ返す。未歩の目が、うるんでいるようにみなみには映った。
「いつも後ろに隠れてたみなみが、私のいないとこで、こんなこと経験してたんだね。でも、なんで今まで教えてくれなかったの」
未歩の声は震えていた。思いがけず深刻な雰囲気になってしまったことに、みなみは身を固くした。
えっと、あの、と意味のない言葉しか口にしないでいると、未歩に突然手をひかれた。
「教会行こうか」
未歩の手は、みなみの手を力強く引っ張っていった。その手の感触の懐かしさに、みなみは黙って身を預けた。
「神様の前だから、嘘はだめ」
しんと冷える室内に、未歩の声が反響する。二人の目の前には祭壇と十字架にかけられたキリストがいた。未歩の胸には、転校前と変わらず、十字架のネックレスがあった。隣に座るみなみと目が合う。みなみは、小さくうなずいた。
「あのお話にもあったよね。教会は赦しの場だって。私、みなみにどんなこと言われても赦すから」
だから、教えて、と言った未歩の目は頑なだった。大きな黒眼にみなみの姿だけが映っている。みなみの呼吸が、僅かに教会の空気を揺らした。
「何で今まで言わなかったというと、その、未歩ちゃんの知らないとこで、自分がきちんとやってけるっていうのが嬉しかったのと......」
未歩は急かすことはせず、静かにみなみの言葉の続きを待った。
(今日はすべて話すと決めていたのに)
口に出そうとすればするほど、言葉同士がもつれてしまうようで、みなみは何もしゃべることができなくなってしまった。
苦し紛れに、十字架にかけられたキリストを見る。愛によって人々を救ってくれた救世主は、ただそこに在るだけで、みなみには何も与えなかった。居心地悪く、手をもじもじと動かす。そこに、いつもみなみを引っぱっていた手が重なった。
「みなみ、目をそらさないで。ゆっくりでいいから、本当のこと、話して」
未歩は、まるで子供を相手にするかのように優しく話しかけた。みなみの中で、もつれた言葉同士が、自分の居場所を見つけたかのように、解けていく。言葉を紡ごうとして、出した声はかすれていた。
「......未歩ちゃんに、神父さまのこと、知られたくなかった」
みなみの手に重ねられていた手が、ぴくりと反応した。みなみは恐る恐る未歩の目を覗くと、複雑な色を宿し、揺れていた。
「あ、ちがうの! 未歩ちゃんにだけじゃなくて、誰にも知られたくなかった」
未歩は、なんで、と小さく漏らした。みなみの頬は、赤に染まっていく。頬の熱が、口から溢れ出るように、白い息が出る。白い息に紛れ、小さく言葉が紡がれる。
「私、自分のことを受け入れてくれた神父さまのことが好きだった。でも、未歩ちゃんに話してしまったら、絶対にすぐばれちゃうから、恥ずかしかった」
「じゃあ、なんでその話、読んでほしい、って言ってきたの」
未歩は、胸につかえているものを吐き出すように言った。みなみは、手の中からそっと抜け出し、未歩の荒れた手に自分の傷一つない手を重ねた。未歩の目に、きちんと自分が映っていることを確認し、消えないように、ゆっくりと応える。
「大事な人には、ちゃんと大事だって言葉で伝えないといけないって思ったから」
その言葉とともに、みなみの脳裏に半年前のことが甦る。自分のことを、抱きしめ、暖めてくれた手が、自分の手の中で力をなくしていく感覚。紫色のアザは視界の中でにじんでいき、像を崩してゆくこと。次第に、神父の声門をこじ開けて出てきたような呼気が鼓膜を刺激するだけになった。最後には、完全にこの世から姿を消してしまった。
「実は、未歩ちゃんに見せた原稿の、さつきの最後のセリフは、私が言えなかったことなんだ。私は、神父さまに、最期まで感謝の気持ちが伝えられなかった」
そこまで言いかけて、ぐっと下唇を噛んだ。みなみの手の中の未歩の手が、堅く縮こまる。みなみは、消えることを恐れるかのように、荒れた手を強く握った。手の中にある確かな温もりは、みなみの頬を濡らしていく。
「毎日会ってたから、いつの間にかすべてが当たり前になってて。いつか、いつかって先延ばしにして。その、曖昧だった気持ちのせいで、私今、すごく後悔してる」
みなみの声は嗚咽で不明瞭になっていく。未歩の目は、水気を帯びていた。
「みなみ......」
「私と未歩ちゃんは、小さい時からずっと一緒で、離れる日なんて考えてもなかった。そしたら、別れは早くやってきて。あの時も、私は未歩ちゃんに、感謝の気持ちを伝えられなかった。いつも私を引っ張って、守ってくれてたのに」
みなみが思い返すのは、自分よりいつも低い位置にある後ろ頭だった。かわいらしいツインテールが凛々しいポニーテールになっても、みなみの一歩前に強く在る。大人になって、立場が変わっても、昔と同じように笑いあえる幸せを、みなみは噛みしめていた。
「未歩ちゃん、ありがとう。未歩ちゃんがいたから、未歩ちゃんの言葉があったから、私、転校前もその後も、何とか潰れずに生きてこれた。本当にありがとう」
教会の空気が大きく揺れる。みなみは思いの丈をぶつけ、盛大にむせ込んだ。未歩は労わるようにそっとみなみの背中に腕を回し、さすった。みなみは、堰が切れたように、声を上げて泣いた。
「みなみ、昔から本当に泣き虫だね。変わらないね」
未歩は、大きいから子供みたいに抱きしめられないし、と続けた。みなみの肩は濡れていた。教会には、二人分の嗚咽だけが響いていた。
「みなみの話読んだら、すっごい自分が美化されてて戸惑った」
未歩はまだ赤い目をしながら、鼻をすすった。みなみと目を合わせようとしない。未歩は、小さな声で、私はいつも思ったままを言ってるだけ、と言った。
「今だから懺悔するけど、みなみが自分の知らないところで立ち直って笑ってるのが、なんか嫌で、何回か電話無視した。ごめん」
未歩はすまなそうに謝った。みなみは、未歩の下がった眉尻に、笑いが漏らした。未歩は、人が真面目に謝ってるのに、と背中を向ける。
(やっぱり未歩ちゃんは、このくらい勢いがあったほうがいい)
「ごめんごめん。そのことはいいよもう。これでお互い腹の中あらいざらいだしたかな」
そうだね、と小さな返事が返ってきた。怒らせてしまったかと不安になっていると、未歩がみなみのほうに向く。
「ではここで、神様に一番近い元少女さんに質問です」
何それ、とみなみが笑うと未歩も笑った。
「今、神様の愛は届いてますか」
みなみは一拍置いて、答える。
「もちろん。だって」
それを聞いたら神父さま、喜ぶと思うよと未歩は呟く。みなみは、記憶の中の神父にそっと、ありがとう、と告げた。
※ 作品の無断転載を禁じます。
さつきは神父の名前を聞き、自分とは大きく異なる容姿に納得した。しかし、神父が何者であろうとも、さつきの中の気持ちは揺るがなかった。
「ありがとうございます、神父さま」
*
みなみは、未歩が原稿を読み終わるのを待っていた。時折、眉間にしわが寄ったり、目を見開いたりといった、一挙一動を見逃さないようにしていた。
やがて、未歩は原稿を机に置き、深呼吸をした。何と言っていいかわからない、という表情だった。二人の間に沈黙が流れる。何も言わないみなみを見かねて、未歩が口火を切った。
「この話に出てくる、『ミホ』って私のこと? もしかして、みなみが転校してからの話をもとにしてるの?」
みなみは首を縦に振る。未歩は、原稿に目を落とし、言葉を続ける。
「電話してくるたびに、泣いてた時よね」
受話器を涙で濡らしては、電話代いくらかかると思ってるの、と母に怒られていた日が甦る。未歩ちゃんはいつも、大丈夫だから、そんなに泣かないの、と繰り返していた。
「でも、いつの間にか泣かなくなって、友達ができて......。電話の回数も減って。こうゆうことだったんだね」
うん、と一言だけ返す。未歩の目が、うるんでいるようにみなみには映った。
「いつも後ろに隠れてたみなみが、私のいないとこで、こんなこと経験してたんだね。でも、なんで今まで教えてくれなかったの」
未歩の声は震えていた。思いがけず深刻な雰囲気になってしまったことに、みなみは身を固くした。
えっと、あの、と意味のない言葉しか口にしないでいると、未歩に突然手をひかれた。
「教会行こうか」
未歩の手は、みなみの手を力強く引っ張っていった。その手の感触の懐かしさに、みなみは黙って身を預けた。
「神様の前だから、嘘はだめ」
しんと冷える室内に、未歩の声が反響する。二人の目の前には祭壇と十字架にかけられたキリストがいた。未歩の胸には、転校前と変わらず、十字架のネックレスがあった。隣に座るみなみと目が合う。みなみは、小さくうなずいた。
「あのお話にもあったよね。教会は赦しの場だって。私、みなみにどんなこと言われても赦すから」
だから、教えて、と言った未歩の目は頑なだった。大きな黒眼にみなみの姿だけが映っている。みなみの呼吸が、僅かに教会の空気を揺らした。
「何で今まで言わなかったというと、その、未歩ちゃんの知らないとこで、自分がきちんとやってけるっていうのが嬉しかったのと......」
未歩は急かすことはせず、静かにみなみの言葉の続きを待った。
(今日はすべて話すと決めていたのに)
口に出そうとすればするほど、言葉同士がもつれてしまうようで、みなみは何もしゃべることができなくなってしまった。
苦し紛れに、十字架にかけられたキリストを見る。愛によって人々を救ってくれた救世主は、ただそこに在るだけで、みなみには何も与えなかった。居心地悪く、手をもじもじと動かす。そこに、いつもみなみを引っぱっていた手が重なった。
「みなみ、目をそらさないで。ゆっくりでいいから、本当のこと、話して」
未歩は、まるで子供を相手にするかのように優しく話しかけた。みなみの中で、もつれた言葉同士が、自分の居場所を見つけたかのように、解けていく。言葉を紡ごうとして、出した声はかすれていた。
「......未歩ちゃんに、神父さまのこと、知られたくなかった」
みなみの手に重ねられていた手が、ぴくりと反応した。みなみは恐る恐る未歩の目を覗くと、複雑な色を宿し、揺れていた。
「あ、ちがうの! 未歩ちゃんにだけじゃなくて、誰にも知られたくなかった」
未歩は、なんで、と小さく漏らした。みなみの頬は、赤に染まっていく。頬の熱が、口から溢れ出るように、白い息が出る。白い息に紛れ、小さく言葉が紡がれる。
「私、自分のことを受け入れてくれた神父さまのことが好きだった。でも、未歩ちゃんに話してしまったら、絶対にすぐばれちゃうから、恥ずかしかった」
「じゃあ、なんでその話、読んでほしい、って言ってきたの」
未歩は、胸につかえているものを吐き出すように言った。みなみは、手の中からそっと抜け出し、未歩の荒れた手に自分の傷一つない手を重ねた。未歩の目に、きちんと自分が映っていることを確認し、消えないように、ゆっくりと応える。
「大事な人には、ちゃんと大事だって言葉で伝えないといけないって思ったから」
その言葉とともに、みなみの脳裏に半年前のことが甦る。自分のことを、抱きしめ、暖めてくれた手が、自分の手の中で力をなくしていく感覚。紫色のアザは視界の中でにじんでいき、像を崩してゆくこと。次第に、神父の声門をこじ開けて出てきたような呼気が鼓膜を刺激するだけになった。最後には、完全にこの世から姿を消してしまった。
「実は、未歩ちゃんに見せた原稿の、さつきの最後のセリフは、私が言えなかったことなんだ。私は、神父さまに、最期まで感謝の気持ちが伝えられなかった」
そこまで言いかけて、ぐっと下唇を噛んだ。みなみの手の中の未歩の手が、堅く縮こまる。みなみは、消えることを恐れるかのように、荒れた手を強く握った。手の中にある確かな温もりは、みなみの頬を濡らしていく。
「毎日会ってたから、いつの間にかすべてが当たり前になってて。いつか、いつかって先延ばしにして。その、曖昧だった気持ちのせいで、私今、すごく後悔してる」
みなみの声は嗚咽で不明瞭になっていく。未歩の目は、水気を帯びていた。
「みなみ......」
「私と未歩ちゃんは、小さい時からずっと一緒で、離れる日なんて考えてもなかった。そしたら、別れは早くやってきて。あの時も、私は未歩ちゃんに、感謝の気持ちを伝えられなかった。いつも私を引っ張って、守ってくれてたのに」
みなみが思い返すのは、自分よりいつも低い位置にある後ろ頭だった。かわいらしいツインテールが凛々しいポニーテールになっても、みなみの一歩前に強く在る。大人になって、立場が変わっても、昔と同じように笑いあえる幸せを、みなみは噛みしめていた。
「未歩ちゃん、ありがとう。未歩ちゃんがいたから、未歩ちゃんの言葉があったから、私、転校前もその後も、何とか潰れずに生きてこれた。本当にありがとう」
教会の空気が大きく揺れる。みなみは思いの丈をぶつけ、盛大にむせ込んだ。未歩は労わるようにそっとみなみの背中に腕を回し、さすった。みなみは、堰が切れたように、声を上げて泣いた。
「みなみ、昔から本当に泣き虫だね。変わらないね」
未歩は、大きいから子供みたいに抱きしめられないし、と続けた。みなみの肩は濡れていた。教会には、二人分の嗚咽だけが響いていた。
「みなみの話読んだら、すっごい自分が美化されてて戸惑った」
未歩はまだ赤い目をしながら、鼻をすすった。みなみと目を合わせようとしない。未歩は、小さな声で、私はいつも思ったままを言ってるだけ、と言った。
「今だから懺悔するけど、みなみが自分の知らないところで立ち直って笑ってるのが、なんか嫌で、何回か電話無視した。ごめん」
未歩はすまなそうに謝った。みなみは、未歩の下がった眉尻に、笑いが漏らした。未歩は、人が真面目に謝ってるのに、と背中を向ける。
(やっぱり未歩ちゃんは、このくらい勢いがあったほうがいい)
「ごめんごめん。そのことはいいよもう。これでお互い腹の中あらいざらいだしたかな」
そうだね、と小さな返事が返ってきた。怒らせてしまったかと不安になっていると、未歩がみなみのほうに向く。
「ではここで、神様に一番近い元少女さんに質問です」
何それ、とみなみが笑うと未歩も笑った。
「今、神様の愛は届いてますか」
みなみは一拍置いて、答える。
「もちろん。だって」
それを聞いたら神父さま、喜ぶと思うよと未歩は呟く。みなみは、記憶の中の神父にそっと、ありがとう、と告げた。
※ 作品の無断転載を禁じます。