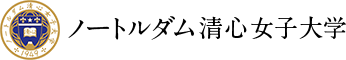2016.10.25
本学科生の創作作品が、活水文学賞受賞作品(女子大学生部門・ジャンルA<優秀賞>)を受賞しま
した。
ここにその作品を紹介致します。
蝸牛
作・宮阪理夏子
八月下旬。夏はまだここに居るのだろう。熱を持った日の光がおんぼろで穴だらけのよもぎ色のカーテンから漏れ出し、カビの湿っぽい臭いを嫌に生暖かくさせている。締め切った窓が風で軋む音と一緒に、どんよりとした朝を迎える。四階建てアパートの今にも崩れそうな四畳半の一室で、私は蝸牛になっていた。
外は静かだ。時々犬が鳴いている。今は何時だろうか。人の声はしない。ニスの剥がれ落ちたちゃぶ台にのろのろと向かう。私の後ろには銀の道が出来た。動いてみるとやはりのろまで、蜻蛉ならいくらかよかったのに、と思う。不思議と蝸牛になった事に困惑する事はなかった。人間は非日常な事件に巻き込まれた時、意外にも冷静な生き物なのだと思う。
ちゃぶ台の上には見慣れた水色の置時計が見慣れない大きさとなって座っていた。秒針の音がうるさい。今は十時十二分。一限目の講義がもうすぐ終わる。私は二か月前から大学へ行かなくなっていた。特にこれといった原因があるわけではないが、いつの間にか行かなくなっていた。だからといって不規則な生活をしているわけでもなく、朝は八時半に起き、夜も日が変わる頃には布団に潜る。自炊をし、三食きっちり食事もしているし、健康なほうだと思う。それでも、大学へは行かなかった。
便利なもので、蝸牛は壁を登るのは造作ない。もっとも、人間であれば壁を登らなくとも簡単に窓の外を眺められるのだが。湿ったのろまな体を動かして、汚れたクリーム色の壁を這う。壁は所々剥がれ落ちている。外は風が強いのだろうか、窓が怒ったようにがたがたと揺れている。やっとの思いでカビ臭いカーテンをくぐると、眼が潰れるような真っ白の日差しが容赦なく私を取り囲んだ。溶けそうだ。あるいは、溶け始めているのかもしれない。体が少し軽くなっているように感じた。
カーテンの外を覗いたのはいつぶりだろうか。そういえば、大学へ行かなくなって一度もカーテンを開けていなかったかもしれない。小さく、のろまになった体が溶けていく感覚を覚えながら、私はぼうっと、人間であった頃の私を思い出していた。
カーテンを開けていないからといって、ドアまで閉じきっているわけではない。むしろ散歩は好きなほうで、欠けた茶碗で昼食を済ませた後、近所の公園へ出かけては、夕日が傾くまでベンチに寝転がっていた。公園は静かだ。もう子供は外で遊ばない時代になったのだろうか。公園の入り口には注意書きとして、ボール遊び禁止とまで書いてある。私は子供が好きなほうではないので、静かな公園はありがたい物だったが、公園でボールを追いかけて走り回っていた子供は今、どこで、何を追いかけて笑っているのか、少し変な気持ちになったりした。もしかすると、薄暗い、鍵のかかった部屋で、夕飯を待っているのかもしれない。夕焼けのオレンジの代わりに、液晶のカラフルな電磁波が彼の目には映っているのかもしれない。どうであれ、幸せに生きているのだろう。子供は幸せな生き物だ。どこであれ、自分なりの幸せを見つけて笑っている。私はいつから子供でなくなってしまったのだろう。子供のいなくなった公園で、私は子供に戻りたいと願いながら、大人になってしまった体を寝転がせているのだ。時々退屈になると起き上がって、蟻の巣を土で埋めたりした。
なんてことはない、退屈ではあるが不自由のない生活をしていたのだと気づく。不自由な体をのろりと動かし、私は公園へ向かう事を決めた。どのくらいの時間がかかるのだろう。途中で烏に食われて死んでしまうかもしれない。それでも、ここでじいっと、死ぬのを待つよりずっといいと思った。
やはり、外は静かだ。のろのろと壁を這い、なんとか地面に降り立つ。アスファルトはとんでもなく熱かった。少し進めば日陰の道になっている。蝸牛の焦げる臭いを感じながら私は日陰へと急いだ。十八分の時がながれ、ようやく日陰へとたどり着いた。人間であればおそらく大股一歩でたどり着ける距離である。私は小さなため息をついて、また足を進めた。しかし、這っても這っても同じ景色だ。気のせいか、気温も上がっているようだ。何もかもがどうでもよくなるような暑さの中、部屋から這い出して三十分、私は早くも公園へ行くのを諦めた。
した。
ここにその作品を紹介致します。
蝸牛
作・宮阪理夏子
八月下旬。夏はまだここに居るのだろう。熱を持った日の光がおんぼろで穴だらけのよもぎ色のカーテンから漏れ出し、カビの湿っぽい臭いを嫌に生暖かくさせている。締め切った窓が風で軋む音と一緒に、どんよりとした朝を迎える。四階建てアパートの今にも崩れそうな四畳半の一室で、私は蝸牛になっていた。
外は静かだ。時々犬が鳴いている。今は何時だろうか。人の声はしない。ニスの剥がれ落ちたちゃぶ台にのろのろと向かう。私の後ろには銀の道が出来た。動いてみるとやはりのろまで、蜻蛉ならいくらかよかったのに、と思う。不思議と蝸牛になった事に困惑する事はなかった。人間は非日常な事件に巻き込まれた時、意外にも冷静な生き物なのだと思う。
ちゃぶ台の上には見慣れた水色の置時計が見慣れない大きさとなって座っていた。秒針の音がうるさい。今は十時十二分。一限目の講義がもうすぐ終わる。私は二か月前から大学へ行かなくなっていた。特にこれといった原因があるわけではないが、いつの間にか行かなくなっていた。だからといって不規則な生活をしているわけでもなく、朝は八時半に起き、夜も日が変わる頃には布団に潜る。自炊をし、三食きっちり食事もしているし、健康なほうだと思う。それでも、大学へは行かなかった。
便利なもので、蝸牛は壁を登るのは造作ない。もっとも、人間であれば壁を登らなくとも簡単に窓の外を眺められるのだが。湿ったのろまな体を動かして、汚れたクリーム色の壁を這う。壁は所々剥がれ落ちている。外は風が強いのだろうか、窓が怒ったようにがたがたと揺れている。やっとの思いでカビ臭いカーテンをくぐると、眼が潰れるような真っ白の日差しが容赦なく私を取り囲んだ。溶けそうだ。あるいは、溶け始めているのかもしれない。体が少し軽くなっているように感じた。
カーテンの外を覗いたのはいつぶりだろうか。そういえば、大学へ行かなくなって一度もカーテンを開けていなかったかもしれない。小さく、のろまになった体が溶けていく感覚を覚えながら、私はぼうっと、人間であった頃の私を思い出していた。
カーテンを開けていないからといって、ドアまで閉じきっているわけではない。むしろ散歩は好きなほうで、欠けた茶碗で昼食を済ませた後、近所の公園へ出かけては、夕日が傾くまでベンチに寝転がっていた。公園は静かだ。もう子供は外で遊ばない時代になったのだろうか。公園の入り口には注意書きとして、ボール遊び禁止とまで書いてある。私は子供が好きなほうではないので、静かな公園はありがたい物だったが、公園でボールを追いかけて走り回っていた子供は今、どこで、何を追いかけて笑っているのか、少し変な気持ちになったりした。もしかすると、薄暗い、鍵のかかった部屋で、夕飯を待っているのかもしれない。夕焼けのオレンジの代わりに、液晶のカラフルな電磁波が彼の目には映っているのかもしれない。どうであれ、幸せに生きているのだろう。子供は幸せな生き物だ。どこであれ、自分なりの幸せを見つけて笑っている。私はいつから子供でなくなってしまったのだろう。子供のいなくなった公園で、私は子供に戻りたいと願いながら、大人になってしまった体を寝転がせているのだ。時々退屈になると起き上がって、蟻の巣を土で埋めたりした。
なんてことはない、退屈ではあるが不自由のない生活をしていたのだと気づく。不自由な体をのろりと動かし、私は公園へ向かう事を決めた。どのくらいの時間がかかるのだろう。途中で烏に食われて死んでしまうかもしれない。それでも、ここでじいっと、死ぬのを待つよりずっといいと思った。
やはり、外は静かだ。のろのろと壁を這い、なんとか地面に降り立つ。アスファルトはとんでもなく熱かった。少し進めば日陰の道になっている。蝸牛の焦げる臭いを感じながら私は日陰へと急いだ。十八分の時がながれ、ようやく日陰へとたどり着いた。人間であればおそらく大股一歩でたどり着ける距離である。私は小さなため息をついて、また足を進めた。しかし、這っても這っても同じ景色だ。気のせいか、気温も上がっているようだ。何もかもがどうでもよくなるような暑さの中、部屋から這い出して三十分、私は早くも公園へ行くのを諦めた。
部屋に戻る力もない。私はアパートとアパートの間にある細い路地へ置いてある鉄パイプへ向かった。古いアパートに面する路地は湿った空気がうろうろしていて不気味だが、今の私には丁度よかった。鉄パイプの上はひんやりしている。このままここでじいっとしているのが一番良いのかもしれない。部屋でぼうっとしている事と変わりはない。私はとにかく何もしたくなかった。夏の暑さから逃げる事だけを考えた。遠くで犬が鳴いている。私が蝸牛になっても、世界はいつも通り静かに進んでいる。
やけに弾んだ雨音がする。私はいつの間にか眠っていたようだ。トタン屋根の下は雨音がいつもより騒がしい。それでいて、煩わしくはない。静かすぎる世界の音を隠してくれているようで、落ち着く。雨音以外何も聞こえないほどに、雨は強く強く降っていた。雨は好きなほうだ。特に、夏の雨は良い。夏の、どこまでも汚れのない、瑠璃を透明な水で伸ばしたような空が、低い低いねずみ色に無理やり泣かされているようで、好きだった。夏の空はいつまでも眩しくて、馬鹿にされているようで嫌いだ。
激しい雨音に包まれながら、心地よい眠気が再びやってくるのを感じていた。時折吹く横風に乗せられた雨が私の体を濡らす。寒いほどに涼しくて、夏の面影が見えなくなった。もう夏は終わったのかもしれない。雨音に交じって遠くから鈍い足音が聞こえてくるのを知らないふりをして、目を閉じた。
足音は近づいてくる。雨の中の足音は湿っていて、気持ちが悪い。閉じた瞼の向こう側を、出来る事ならこのまま知らないふりをして、何者かが過ぎ去るのを待っていたかったのだが、泥をつま先でえぐるような音を立てながら、ゆっくりと、私の前でそれは立ち止まった。
赤い靴。下を向いていた私がうっすらと目を開けると、艶やかな赤色が飛び込んできた。てかてかと光る底の低いパンプスのつま先は泥で汚れていた。フリルのついた真っ白な靴下にも、泥が跳ねていた。無頓着な奴なのか。それにしては靴も、靴下も、上品な物を履いている。私は目線を動かし、目の前に立つ女を見た。病人のような青白い肌をした、若い女が立っていた。丸襟の黒いワンピースと同じ色をした、深く黒い三つ編みのおさげを風になびかせて、切れ長の鋭い目で私をじいっと睨んでいた。私に用でもあるのかと思ったが、そういえば私は蝸牛としてここに居るので、そんなはずはなかった。女はまだ私を睨んでいる。
「湯原耕介」
たしかに女はそう言った。蚊の鳴くような声で私に向かって言ったのだ。しかし、そんなはずはなかった。第一、私はこの女を知らない。
「湯原耕介君ね」
再び女は私の名前を呟いた。間違いなく、湯原耕介は私であるが、それがこの女に分かるはずはなく、今私は大きく戸惑っている。私は声を出せない姿になっているし、そもそも何と言い返してよいかも分からず、必然的に黙って下を向いた。
女は私を強引にひっつかんで、自らの肩に乗せた。素手で蝸牛をつかむ事に抵抗は無いのだろうか。女は初めから表情一つ変えずに静かに歩き出した。直後、気持ち悪い、と吐き捨てるように呟いたが、それでも表情は変わらなかった。
女は真っ直ぐに私の部屋へと向かった。アパートにはそれなりの部屋数があるのだが、私の住んでいる204号室めがけて迷いなく歩いた。女は細身というよりも痩せすぎなほどで、手足は長く、猫背で、不気味であるのに、その中に美しさがあった。消えかけの蛍光灯のようだと思った。女の細い指が204号室のドアノブを回す。生ぬるいカビの臭いがした。「汚い部屋ね」
女は丁寧に靴を脱ぎ揃え、勝手に私の部屋へ上がった。陰鬱な空気の玄関に、赤色が浮いて見える。
「カーテンくらい、開けたら。どうせ、一日中閉めきったままなんでしょう」
大きなお世話だと思った。女はちゃぶ台に私を投げるように置き、勢いよくカーテンを開けた。埃が舞う。いつの間にか夏のぎらぎらと光る青い青い空が、さっきまでのねずみ色を嘘のように、晴れ晴れと広がっていた。目を刺すような日差しが部屋に溶け込む。窓際で光に当てられた女は透明で、今にも消え入りそうだった。少し笑っているように見えた。
「夏が終わるよ、湯原君」
女は私を冷たい左手で握り潰した。左手首に茶色い傷跡が見えた。私はこの女を知っている。何故気付かなかったのか。この女は死んだ私の恋人だ。何も見えない。女の手の中で、蝸牛は死んだ。
八月二十九日、午前十時過ぎ。四畳半の一室で目を覚ました。汗で湿った寝間着が気持ち悪い。重い体を起こす。昨日の事は夢だったのだろうか。自分では開ける事のないカーテンが開けられていた。朝日が眩しい。蝉が最期の鳴き声を上げている。洗面台の前に立ち、鏡に顔を映す。人相の悪い顔が伸び切った前髪で隠れている。頬には汗なのか涙なのか、蝸牛の這ったような透明な跡があった。顔を洗い、適当に歯を磨いたら少しスッキリした。
冷蔵庫を開けると賞味期限の切れた牛乳と、腐りかけのトマトがあったので、朝食を取ることにした。ガラスのコップに牛乳を注ぐ。目の覚めるような真っ白だ。隣に置いたトマトとの対比が綺麗だった。
横目で見たカレンダーは六月十八日から進んでいない。そういえば、その日は私の二十二回目の誕生日だった。
やけに弾んだ雨音がする。私はいつの間にか眠っていたようだ。トタン屋根の下は雨音がいつもより騒がしい。それでいて、煩わしくはない。静かすぎる世界の音を隠してくれているようで、落ち着く。雨音以外何も聞こえないほどに、雨は強く強く降っていた。雨は好きなほうだ。特に、夏の雨は良い。夏の、どこまでも汚れのない、瑠璃を透明な水で伸ばしたような空が、低い低いねずみ色に無理やり泣かされているようで、好きだった。夏の空はいつまでも眩しくて、馬鹿にされているようで嫌いだ。
激しい雨音に包まれながら、心地よい眠気が再びやってくるのを感じていた。時折吹く横風に乗せられた雨が私の体を濡らす。寒いほどに涼しくて、夏の面影が見えなくなった。もう夏は終わったのかもしれない。雨音に交じって遠くから鈍い足音が聞こえてくるのを知らないふりをして、目を閉じた。
足音は近づいてくる。雨の中の足音は湿っていて、気持ちが悪い。閉じた瞼の向こう側を、出来る事ならこのまま知らないふりをして、何者かが過ぎ去るのを待っていたかったのだが、泥をつま先でえぐるような音を立てながら、ゆっくりと、私の前でそれは立ち止まった。
赤い靴。下を向いていた私がうっすらと目を開けると、艶やかな赤色が飛び込んできた。てかてかと光る底の低いパンプスのつま先は泥で汚れていた。フリルのついた真っ白な靴下にも、泥が跳ねていた。無頓着な奴なのか。それにしては靴も、靴下も、上品な物を履いている。私は目線を動かし、目の前に立つ女を見た。病人のような青白い肌をした、若い女が立っていた。丸襟の黒いワンピースと同じ色をした、深く黒い三つ編みのおさげを風になびかせて、切れ長の鋭い目で私をじいっと睨んでいた。私に用でもあるのかと思ったが、そういえば私は蝸牛としてここに居るので、そんなはずはなかった。女はまだ私を睨んでいる。
「湯原耕介」
たしかに女はそう言った。蚊の鳴くような声で私に向かって言ったのだ。しかし、そんなはずはなかった。第一、私はこの女を知らない。
「湯原耕介君ね」
再び女は私の名前を呟いた。間違いなく、湯原耕介は私であるが、それがこの女に分かるはずはなく、今私は大きく戸惑っている。私は声を出せない姿になっているし、そもそも何と言い返してよいかも分からず、必然的に黙って下を向いた。
女は私を強引にひっつかんで、自らの肩に乗せた。素手で蝸牛をつかむ事に抵抗は無いのだろうか。女は初めから表情一つ変えずに静かに歩き出した。直後、気持ち悪い、と吐き捨てるように呟いたが、それでも表情は変わらなかった。
女は真っ直ぐに私の部屋へと向かった。アパートにはそれなりの部屋数があるのだが、私の住んでいる204号室めがけて迷いなく歩いた。女は細身というよりも痩せすぎなほどで、手足は長く、猫背で、不気味であるのに、その中に美しさがあった。消えかけの蛍光灯のようだと思った。女の細い指が204号室のドアノブを回す。生ぬるいカビの臭いがした。「汚い部屋ね」
女は丁寧に靴を脱ぎ揃え、勝手に私の部屋へ上がった。陰鬱な空気の玄関に、赤色が浮いて見える。
「カーテンくらい、開けたら。どうせ、一日中閉めきったままなんでしょう」
大きなお世話だと思った。女はちゃぶ台に私を投げるように置き、勢いよくカーテンを開けた。埃が舞う。いつの間にか夏のぎらぎらと光る青い青い空が、さっきまでのねずみ色を嘘のように、晴れ晴れと広がっていた。目を刺すような日差しが部屋に溶け込む。窓際で光に当てられた女は透明で、今にも消え入りそうだった。少し笑っているように見えた。
「夏が終わるよ、湯原君」
女は私を冷たい左手で握り潰した。左手首に茶色い傷跡が見えた。私はこの女を知っている。何故気付かなかったのか。この女は死んだ私の恋人だ。何も見えない。女の手の中で、蝸牛は死んだ。
八月二十九日、午前十時過ぎ。四畳半の一室で目を覚ました。汗で湿った寝間着が気持ち悪い。重い体を起こす。昨日の事は夢だったのだろうか。自分では開ける事のないカーテンが開けられていた。朝日が眩しい。蝉が最期の鳴き声を上げている。洗面台の前に立ち、鏡に顔を映す。人相の悪い顔が伸び切った前髪で隠れている。頬には汗なのか涙なのか、蝸牛の這ったような透明な跡があった。顔を洗い、適当に歯を磨いたら少しスッキリした。
冷蔵庫を開けると賞味期限の切れた牛乳と、腐りかけのトマトがあったので、朝食を取ることにした。ガラスのコップに牛乳を注ぐ。目の覚めるような真っ白だ。隣に置いたトマトとの対比が綺麗だった。
横目で見たカレンダーは六月十八日から進んでいない。そういえば、その日は私の二十二回目の誕生日だった。
私の恋人は猪名寺雪という名前の、一つ年下で背の低い女だった。名前と同じように、本当に雪のように白い肌をしていた。時折桃色に染まるのが、とても可愛らしかった。私と彼女が付き合い始めてすぐの六月、彼女はレイプに遭った。それっきり、人が変わったようになってしまって、彼女は部屋から出てこなくなってしまった。毎日様子を見に彼女の部屋へ訪ねたが、何度インターホンを押しても部屋の中は静まり返っていた。毎回ドアノブに差し入れのゼリーや果物を買い物袋にいれて引っ提げておいたのが、次の日にはいつも無くなっていたので、とりあえず生きている事に安心した。今思えば、アパートの管理人か誰かが処分していたのかもしれないが。そんな毎日だったが、一度だけ彼女が部屋の鍵を開けた事があった。三回インターホンを鳴らし、返答がないのでいつものように買い物袋をぶら下げ、帰ろうとした時、紺色に塗られた扉が勢いよく開き、涙と鼻水でとてつもなく汚い顔になった彼女が出て来た。真っ赤な目をしてたすけて、と言った彼女はうさぎのようだった。よく見ると彼女の左手首は血まみれで、透き通るような白い肌にてかてかと光る赤色が少し美しく感じた。
彼女の部屋は怖いほど何も無かった。台所には割れたコップが一つと、ゼリーのカップが沢山積み重なっていただけで、他の食器は見当たらない。タンスにも少しの下着と、寝間着があるだけだった。バイト代をはたいて買った、と嬉しそうに言っていた、良く似合う水色のワンピースも無かった。後で聞くと、全部捨てちゃった、と彼女は笑うように言っていた。
殺風景な部屋で彼女は散々泣いて、泣き疲れて眠ってしまった。窓際の白いベッドに寝かせて、薄い毛布をかけてやった。ぐっすりと眠っている彼女は綺麗で、死人のようにも見えた。手をにぎると温かかっ
た。
次の日の朝、私の携帯電話に彼女から一通メールが届いていた。
「湯原君へ。昨日はごめんなさい。私、あまり覚えてないの。だけど、湯原君が来てくれて嬉しかったな。いつも来てくれてた事、知ってた。ありがとう。すこし元気になったよ。そういえばもうすぐ湯原君の誕生日だよね。私、湯原君にプレゼントを渡そうと思うんだ。だから、外に出るの、頑張るね。楽しみにしててね。それじゃあ」
絵文字一つない白黒の文章だが、とても嬉しかった事を覚えている。彼女が外出する時に困らないよう、ワンピースを買ってやった。彼女が大切にしていた水色のワンピースによく似た形の、黒いワンピース。本当は可愛らしい色の洋服をプレゼントしたかったが、買うのがどうも気恥ずかしかった。それに、黒いワンピースは彼女の白い肌が映えて、よく似合うと思ったからだ。彼女は喜んで、
「このワンピースに似合う靴を選ばなくちゃ」
と張り切っていた。
六月十八日の午前十時過ぎ。私は近所のおばさんの叫び声で目を覚ました。彼女は、私の住むアパートの階段で足を滑らせて、頭から血を流して死んだ。私の好きな手作りのチーズケーキとサンドイッチを大切に抱えていた。よく似合う黒いワンピースに、上品な赤いパンプスと真っ白な靴下を履いて、頭から真っ赤な血を流していた。その日は雨だったのを覚えている。急いで来たのだろうか、せっかくの綺麗な靴や靴下に泥が跳ねていた。それさえも可愛くて、私は彼女を起こして、
「あわてんぼうだなあ、雨の日は滑りやすいんだから、気を付けなくちゃ。さあ、行こう」
と言って彼女を抱きかかえ、部屋に入っていったらしい。それからの事は、覚えていない。私の時間は六月十八日のまま止まっていた。彼女の事も、忘れていた。
彼女は夏を終わらせに来たのだ。そういえば、彼女の誕生日は九月だったような気がする。何もかも忘れて、六月のまま立ち止まっている私に拗ねていたのかもしれない。
※ 作品の無断転載を禁じます。
彼女の部屋は怖いほど何も無かった。台所には割れたコップが一つと、ゼリーのカップが沢山積み重なっていただけで、他の食器は見当たらない。タンスにも少しの下着と、寝間着があるだけだった。バイト代をはたいて買った、と嬉しそうに言っていた、良く似合う水色のワンピースも無かった。後で聞くと、全部捨てちゃった、と彼女は笑うように言っていた。
殺風景な部屋で彼女は散々泣いて、泣き疲れて眠ってしまった。窓際の白いベッドに寝かせて、薄い毛布をかけてやった。ぐっすりと眠っている彼女は綺麗で、死人のようにも見えた。手をにぎると温かかっ
た。
次の日の朝、私の携帯電話に彼女から一通メールが届いていた。
「湯原君へ。昨日はごめんなさい。私、あまり覚えてないの。だけど、湯原君が来てくれて嬉しかったな。いつも来てくれてた事、知ってた。ありがとう。すこし元気になったよ。そういえばもうすぐ湯原君の誕生日だよね。私、湯原君にプレゼントを渡そうと思うんだ。だから、外に出るの、頑張るね。楽しみにしててね。それじゃあ」
絵文字一つない白黒の文章だが、とても嬉しかった事を覚えている。彼女が外出する時に困らないよう、ワンピースを買ってやった。彼女が大切にしていた水色のワンピースによく似た形の、黒いワンピース。本当は可愛らしい色の洋服をプレゼントしたかったが、買うのがどうも気恥ずかしかった。それに、黒いワンピースは彼女の白い肌が映えて、よく似合うと思ったからだ。彼女は喜んで、
「このワンピースに似合う靴を選ばなくちゃ」
と張り切っていた。
六月十八日の午前十時過ぎ。私は近所のおばさんの叫び声で目を覚ました。彼女は、私の住むアパートの階段で足を滑らせて、頭から血を流して死んだ。私の好きな手作りのチーズケーキとサンドイッチを大切に抱えていた。よく似合う黒いワンピースに、上品な赤いパンプスと真っ白な靴下を履いて、頭から真っ赤な血を流していた。その日は雨だったのを覚えている。急いで来たのだろうか、せっかくの綺麗な靴や靴下に泥が跳ねていた。それさえも可愛くて、私は彼女を起こして、
「あわてんぼうだなあ、雨の日は滑りやすいんだから、気を付けなくちゃ。さあ、行こう」
と言って彼女を抱きかかえ、部屋に入っていったらしい。それからの事は、覚えていない。私の時間は六月十八日のまま止まっていた。彼女の事も、忘れていた。
彼女は夏を終わらせに来たのだ。そういえば、彼女の誕生日は九月だったような気がする。何もかも忘れて、六月のまま立ち止まっている私に拗ねていたのかもしれない。
※ 作品の無断転載を禁じます。