オンラインとオフラインで考える特別支援教育(共著)
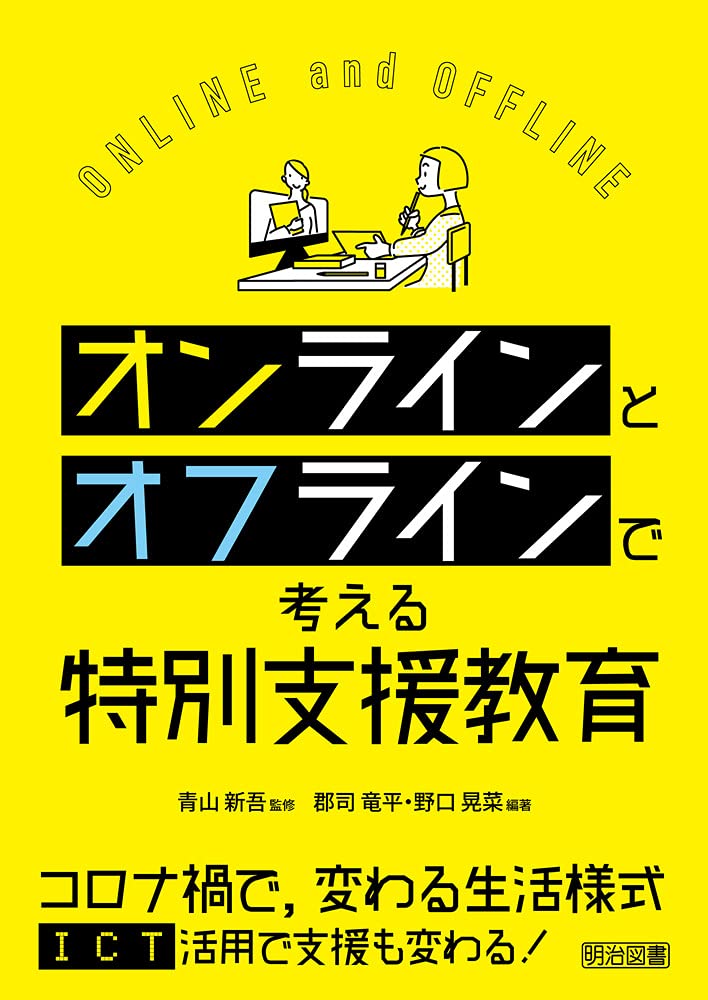
| 学科・機関 | 人間生活学部 児童学科/インクルーシブ教育研究センター |
|---|---|
| 教員名 | 青山新吾 准教授 |
| 著者情報 | 青山新吾 監修、郡司竜平・野口 晃菜 編著 |
| 出版社 | 明治図書 |
| 発行日 | 2021年7月 |
| サイズ・頁数 | A5判 202頁 |
| 金額 | 2,160円+税 |
- 内容紹介
-
本書は、特別支援教育の最前線の現場にいる16名の方々が、コロナ禍において、子どもたちの生活を支え、学びを止めないように取り組み続けた記録です。華々しい実践記録ばかりではありませんが、子どもたちと共に歩いた試行錯誤の様子がリアルな筆致で記述されている1冊です。青山は本書を監修すると同時に、コラム及び第7章3節の執筆と、第8章の座談会で発言しています。
はじめに
第1章 臨時休業中の取り組み―そこから見えてきた課題とヒント―
1 中学校特別支援学級での工夫
・顔を合わせず学習保障?
2 知的障害特別支援学校の取り組み
・手探りの学習支援から見えてきた「つながる」ヒント
3 ポジティブな行動支援に基づいた親子支援
・どんなときでもポジティブに!
コラム 著作権を考慮して,教材を自作しよう!
―家庭学習用の「九九チャンツ」CDを作成・配布
第2章 学校再開後の学習の様子と指導・支援の実際
1 日常生活の指導―着替え,給食,掃除,朝の会・帰りの会
・探そう! 今できること,今だからできること
・スタンダードが変わる? 日常生活の指導の見直し
2 生活単元学習
・ちょっとした工夫が功を奏した生活単元学習
・Zoomで小中交流会
3 作業学習
・とにかく場所がない
・新しい生活様式を考慮した作業学習の工夫
4 各教科の学習での工夫
・新しい生活様式を考慮した国語授業の工夫
・距離をとって,一緒に学べますか?
5 通級による指導
・特別支援教室の個別学習課題からのスタート
・限りなく減った通級指導の時数の中で,我々は何ができるのか
第3章 オンラインを活用した取り組み
1 オンラインの有効性
・オンライン活用の準備と工夫
2 メンターとしてのオンラインの活用
・「とりあえず,やってみよう!」から全ては,はじまる!
3 Teams活用の取り組み
・学ぶ場所は,学校だけじゃない
第4章 コロナ禍の保護者や地域とのつながり
1 保護者懇談と授業参観
・直接? オンライン? 選べる懇談会と授業参観
2 進路指導
・必要な情報をどう伝える?
3 地域での学習の様子の変化
・ウリが仇となる!?
第5章 コロナ禍のメンタルヘルスケア
1 子どもと教師に起こったこと
・「未知との遭遇」―暗がりの中,共に歩く仲間たちへ
2 子どものメンタルヘルスケア
・こころの拠り所をつなぐには?
3 教師のメンタルヘルスケア
・コロナ禍を乗り越える教師のメンタル
4 コロナ禍のメンタルヘルス対応事例
・困難な状況だからこそ心がけたいこと
第6章 学校の現在地
1 学校と私の変化
・「行事が生み出す学びの場」「今の自分にできること」
2 学校があること
・学校の「変わっていくよさ」と「変わらないよさ」
コラム 緩やかにつながっている実感を
第7章 コロナ禍で露呈した特別支援教育の課題
1 つながりのある指導・支援のための仕組みの課題
・場の連携と教育内容のつながりを
2 指導内容や指導方法の固定化―ICTやオンラインの活用
・ICTは必須ツールの一つ
3 特別支援教育については後回し?
・後回しにしない実際的な仕組みをつくる
第8章 今後の特別支援教育[座談会]
・二分化してきている現場
・メンタリティ
〈座談会のまとめ〉
・オンラインとオフラインのハイブリッドの維持
・特別支援を後回しにしない
・燃え尽き症候群になるタイミング
・行政が動くということ
・コロナ禍でも春の人事異動を行う世界
・笑い飛ばして進むメンタリティ―最後に
おわりに
・青山新吾准教授(教員紹介)
・児童学科(学科紹介)
・インクルーシブ教育研究センター


