社会学史入門――黎明期から現代的展開まで(共著)
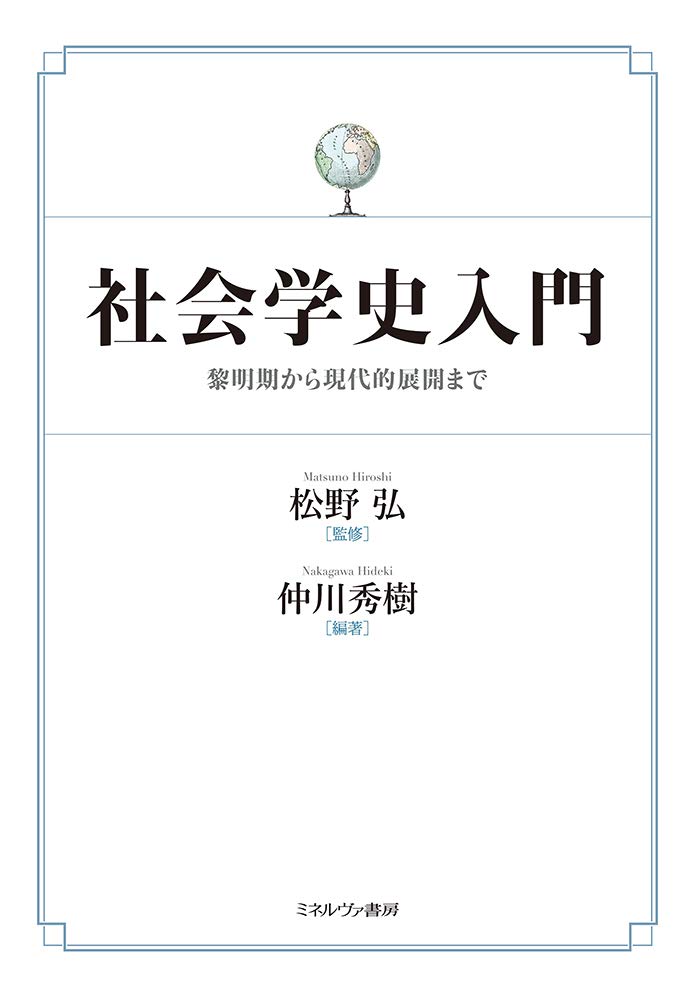
| 学科・機関 | 文学部 現代社会学科/地域連携・SDGs推進センター |
|---|---|
| 教員名 | 濱西栄司 准教授 |
| 著者情報 | 仲川秀樹 編 |
| 出版社 | ミネルヴァ書房 |
| 発行日 | 2020年4月20日 |
| サイズ・頁数 | A5版 344頁 |
| 金額 | 3,500円+税 |
- 内容紹介
-
本書は、国家・地方公務員試験の「社会学」分野に対応した教科書です。「社会学」分野は、公務員試験では「専門科目」(行政系及び人間科学系)に入っており、社会学者名・学説に関する問題がたくさん出ます。そのため、本書でも代表的な社会学者・学説についてわかりやすく説明がなされています。執筆者はおもに日本社会学史学会会員で、本書は社会学史に関する書籍としても信頼性が高く、評価されています。濱西は第17章「A・トゥレーヌ」を担当しています。
はじめに なぜ,社会学史を学ぶのか──「社会学」の誕生と歴史への理解(松野 弘)
第Ⅰ部 初期社会学思想とは何か──視点・考え方・方法
序 章 C.H. ド・サン=シモン──科学と産業に基づく社会の再組織(池田祥英)
第1章 A. コント──「社会学」の誕生(池田祥英)
第2章 H. スペンサー──進化論思想と社会学(挾本佳代)
第Ⅱ部 中期社会学思想とは何か──視点・考え方・方法
第3章 G. タルド──模倣の社会学理論(池田祥英)
第4章 G・ジンメル──2は1より古い(早川洋行)
第5章 デュルケム──実証的科学としての社会学の確立(清水強志)
第6章 M・ヴェーバー──行為と歴史の理解社会学(井腰圭介)
第7章 K・マンハイム──動的で綜合的な社会学 飯島祐介
第Ⅲ部 後期社会学思想とは何か──視点・考え方・方法
第8章 T・パーソンズ──主意主義と行為体系論(鈴木健之)
第9章 R・K・マートン──理論と実証の往還(小谷 敏)
第10章 G・H・ミード──コミュニケーションと自己(小谷 敏)
第11章 C・ライト・ミルズ──視点を編み直す「社会学的創造力」(伊奈正人)
第12章 H・ブルーマー──ジェネリックな社会学方法論(仲川秀樹)
第Ⅳ部 現代社会学思想とは何か──視点・考え方・方法
第13章 アルヴィン・W・グールドナー──ラディカル社会学のレジェンド(大黒正伸)
第14章 ピーター・バーガー/トマス・ルックマン/ハロルド・ガーフィンケル──日常生活の探検者たち(大黒正伸)
第15章 A・ギデンズ──構造化と自己(鈴木健之)
第16章 J・アレクサンダー──行為体系論の再構成(鈴木健之)
第17章 A・トゥレーヌ──運動・紛争を中心とした社会学(濱西栄司)
第18章 日本の社会学思想と理論──輸入学問からの脱皮と自立(井腰圭介)
終 章 これからの社会学史のゆくえ──ネオ社会学知の歴史形成(松野 弘)
[特別研究編]公務員試験社会学分野の研究(渕元 哲)
1 公務員試験における社会学の出題数・難易度
2 公務員試験における「社会学」問題への対策
3 公務員試験で出題される「社会学」の学習戦略
◆過去の問題にチャレンジしよう


