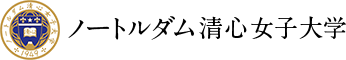2008.11.04
日本語日本文学科 リレーエッセイ
【第61回】2008年11月4日
失われる言葉
著者紹介
星野 佳之(ほしの よしゆき)
日本語学担当
古代語の意味・文法的分野を研究しています。
※教員情報は、掲載時のものです。
授業中に、私と学生達とが持つ言葉の違いに気づくことは珍しくない。多くの場合は方言差によるものだが、少し前にあった次の話は、どちらかといえば世代差が要因であろう。
日本語のさまざまな「音」の中で、「清音・濁音」の説明をしていた回だった。「清む音・濁る音」と言われたりもする、「か」と「が」のような、音のペアについてである。全ての音が清濁のペアを持つのではなく、例えば「な」に「゛」(濁点)をふれないのは、ナ行が濁音を持たないからである。
しかし、その本来濁音を持たないはずのナ行が濁音を(臨時に)持ったのが「のら猫」に対する「どら猫」ではないか、という面白い説があるので、それを紹介しようと思ったのだが、関連語として「どら息子」に触れたところ、学生のほとんどがこの語を知らなかったのである。
【第61回】2008年11月4日
失われる言葉
著者紹介
星野 佳之(ほしの よしゆき)
日本語学担当
古代語の意味・文法的分野を研究しています。
※教員情報は、掲載時のものです。
授業中に、私と学生達とが持つ言葉の違いに気づくことは珍しくない。多くの場合は方言差によるものだが、少し前にあった次の話は、どちらかといえば世代差が要因であろう。
日本語のさまざまな「音」の中で、「清音・濁音」の説明をしていた回だった。「清む音・濁る音」と言われたりもする、「か」と「が」のような、音のペアについてである。全ての音が清濁のペアを持つのではなく、例えば「な」に「゛」(濁点)をふれないのは、ナ行が濁音を持たないからである。
しかし、その本来濁音を持たないはずのナ行が濁音を(臨時に)持ったのが「のら猫」に対する「どら猫」ではないか、という面白い説があるので、それを紹介しようと思ったのだが、関連語として「どら息子」に触れたところ、学生のほとんどがこの語を知らなかったのである。

こちらの期待する言葉を学生が知らないのはたまにあることだが、よくよく考えてみれば、「どら息子」にせよ「どら猫」にせよ、私もその実態をよく知っている訳ではない。学生達がまだ知っていた方の「どら猫」にしても、通りで猫を見て「あ、どら猫だ」という場面は、実は実生活に於いては想像しづらいのではないだろうか。
一体「どら猫」とはどのような猫かというに、具体的な性質は規定しにくい。恐らくはたちの悪い猫なのであろう、ということくらいだ。もとより、「あ、どら猫だ」が言いづらいのは、見かけただけでは「たちが悪い=どら猫だ」と性質の指定までしにくい、という事情によるのかも知れない。しかし、見かけるだけでなくて、のら猫に引っかかれてその悪さに触れ得た学生なら、「このどら猫!」と呼ばわるものだろうか。
その場面もなかなか想像しにくいのだが、実態はどうなのであろう。実験を試みる訳にもいかず、「どら猫」なるものの姿が、随分と朧ろになってしまった。
更に「どら息子」は霧の中である。「たちの悪い息子」というのは今でも必ずや世の中にいるはずで、自分のことを言って恐縮であるが、家業も継がず言葉について考えるような職業を選択して顧みなかった私などは相当悪い方であろう。また私の親というのも上品な方の人たちではないから、「どら息子!」と認定される要素は十分にあったように思うのだが、この言葉で怒鳴られた記憶だけはない。他の多彩な表現に埋もれて覚えていないだけであろうか。
「どら猫」も「どら息子」も、イメージ先行の語といった印象がどうも拭えない。「どら猫」が実際の道ばたを歩いていたり、私たちの隣人が「どら息子」に手を焼いていたりするよりも、漫画やドラマの中でそういうことが起こっていそうな気がするのである。
とすると、学生世代が「どら息子」を知らないのは、言葉が失われたというよりも、そういう存在が虚構の世界で描かれなくなったから、ということかも知れないのである。確かに、親子のいさかいをドラマで描くにしても、昔と今とでは事情も異なろう。極端な状況を描写しがちな作品が多くなると、多少の問題くらいでは取り上げてもらえない。包丁を持って自分に襲いかかる息子に対しては、いくら親でも「このどら息子!」と言っている場合ではない。ならば「このどら息子!」と怒鳴ったドラマの親に、我が子への情はまだあったのかも知れない。
「どら息子」はまさに忘れられつつある存在である。別にこれを絶滅の危機から救おうというつもりはないが、このたちは悪くても人を殺める程ではない困り者が起こす「事件」では物語に採用され得ない、というのが現代だとすれば、私たちは随分と余裕を失った時代に生きているというべきではないか。先日行ってきた東京の池袋演芸場という寄席は立ち見の満席であったが、これがその余裕を回復するような方向の文化の動きと見ていいのなら、少しは頼もしいのだが。
もちろん、「どら息子」の語感が古臭くなって用いられなくなったというのなら話は全く別である。その場合は代わりを務める今風に言い換えた表現というのを、是非聞いてみたいと思う。
結局「どら息子」のことに拘りすぎて、授業では当初紹介しようとした説には触れずじまいになってしまったのだが、これは『日本語の世界7 日本語の音韻』(小松英雄、中央公論社、1981)の第四章で述べられている。上記の説を含め全巻とてもユニークで面白い説が書かれ、それでいて分かりやい本なので、この際是非一読をお薦めしたい。
・日本語日本文学科
・日本語日本文学科(ブログ)
一体「どら猫」とはどのような猫かというに、具体的な性質は規定しにくい。恐らくはたちの悪い猫なのであろう、ということくらいだ。もとより、「あ、どら猫だ」が言いづらいのは、見かけただけでは「たちが悪い=どら猫だ」と性質の指定までしにくい、という事情によるのかも知れない。しかし、見かけるだけでなくて、のら猫に引っかかれてその悪さに触れ得た学生なら、「このどら猫!」と呼ばわるものだろうか。
その場面もなかなか想像しにくいのだが、実態はどうなのであろう。実験を試みる訳にもいかず、「どら猫」なるものの姿が、随分と朧ろになってしまった。
更に「どら息子」は霧の中である。「たちの悪い息子」というのは今でも必ずや世の中にいるはずで、自分のことを言って恐縮であるが、家業も継がず言葉について考えるような職業を選択して顧みなかった私などは相当悪い方であろう。また私の親というのも上品な方の人たちではないから、「どら息子!」と認定される要素は十分にあったように思うのだが、この言葉で怒鳴られた記憶だけはない。他の多彩な表現に埋もれて覚えていないだけであろうか。
「どら猫」も「どら息子」も、イメージ先行の語といった印象がどうも拭えない。「どら猫」が実際の道ばたを歩いていたり、私たちの隣人が「どら息子」に手を焼いていたりするよりも、漫画やドラマの中でそういうことが起こっていそうな気がするのである。
とすると、学生世代が「どら息子」を知らないのは、言葉が失われたというよりも、そういう存在が虚構の世界で描かれなくなったから、ということかも知れないのである。確かに、親子のいさかいをドラマで描くにしても、昔と今とでは事情も異なろう。極端な状況を描写しがちな作品が多くなると、多少の問題くらいでは取り上げてもらえない。包丁を持って自分に襲いかかる息子に対しては、いくら親でも「このどら息子!」と言っている場合ではない。ならば「このどら息子!」と怒鳴ったドラマの親に、我が子への情はまだあったのかも知れない。
「どら息子」はまさに忘れられつつある存在である。別にこれを絶滅の危機から救おうというつもりはないが、このたちは悪くても人を殺める程ではない困り者が起こす「事件」では物語に採用され得ない、というのが現代だとすれば、私たちは随分と余裕を失った時代に生きているというべきではないか。先日行ってきた東京の池袋演芸場という寄席は立ち見の満席であったが、これがその余裕を回復するような方向の文化の動きと見ていいのなら、少しは頼もしいのだが。
もちろん、「どら息子」の語感が古臭くなって用いられなくなったというのなら話は全く別である。その場合は代わりを務める今風に言い換えた表現というのを、是非聞いてみたいと思う。
結局「どら息子」のことに拘りすぎて、授業では当初紹介しようとした説には触れずじまいになってしまったのだが、これは『日本語の世界7 日本語の音韻』(小松英雄、中央公論社、1981)の第四章で述べられている。上記の説を含め全巻とてもユニークで面白い説が書かれ、それでいて分かりやい本なので、この際是非一読をお薦めしたい。
・日本語日本文学科
・日本語日本文学科(ブログ)