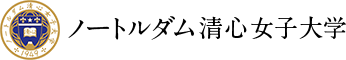2014.11.27
破天荒なイタリア・ルネサンスの芸術家
轟木広太郎准教授
イタリア・ルネサンスの華といえば、それは当然フィレンツェである。この町を東西に横切って流れるアルノ河には、金細工品や宝飾品を扱う商店があることで有名な「ヴェッキオ橋」という橋が架かっている。なんと橋の上の両脇に店舗がびっしりと軒を連ねて並んでいるのだが、近世ヨーロッパの大きな都市ではこれは見慣れた光景だった。ただ、橋の中央部は吹き抜けになっていて、横を振り向けばゆったりした河の流れを再び見ることができる。
轟木広太郎准教授
「教員紹介」ページへ
イタリア・ルネサンスの華といえば、それは当然フィレンツェである。この町を東西に横切って流れるアルノ河には、金細工品や宝飾品を扱う商店があることで有名な「ヴェッキオ橋」という橋が架かっている。なんと橋の上の両脇に店舗がびっしりと軒を連ねて並んでいるのだが、近世ヨーロッパの大きな都市ではこれは見慣れた光景だった。ただ、橋の中央部は吹き抜けになっていて、横を振り向けばゆったりした河の流れを再び見ることができる。

写真1 ヴェッキオ橋
さて、今夏フィレンツェを訪れた時に、その地点に16世紀の彫金師ベンヴェヌート・チェッリーニ(1500-71)の胸像が置かれているのを見つけて、「おおっ」と思わず小さく声をあげた。この人物、ダ・ヴィンチやミケランジェロよりも一・二世代若いフィレンツェ人で、いわゆる「超有名どころ」には入らないものの、ローマ教皇やフランス王をパトロンに持った、それなりの名声に恵まれた芸術家であった。ところで、この芸術家は歴史学の領域では、その作品よりも自伝で著名なのだ(本人には少し申し訳ないが)。
日本語でも二種類の翻訳が存在するが、この自伝、ゼミや「史料講読」という授業でも取り上げたことがあり、また卒論で扱ったゼミ生もいたが、なんといってもすこぶる面白いのだ。喧嘩や刃傷沙汰は数知れず、険悪な仲の同業者たちと乱闘になったり、殺された弟の仇討に行ったり、自分を侮辱した知り合いと情婦に切りつけたり、喧嘩になったパトロンの差し向けた兵士たちを向こうに剣を振りかざして啖呵を切ったりする。そうかと思えば、1527年の神聖ローマ帝国軍によるローマ略奪の際には、請われて教皇軍に加わり、サン・タンジェロ城から敵軍に向かってズドン・ズドンと大砲を打ち込んで、自分こそ並ぶものなき名手だと自慢する。こうした荒っぽい話だけでなく、シチリア出身の黒魔術師に弟子にならないかとも持ちかけられて、コロッセウムで大掛かりな降霊術を体験したり、窃盗の嫌疑で2年間も地下牢に幽閉されたり、笛吹きとして教皇の楽団に加わったり、あるいは女性との色恋話にも事欠かない。
日本語でも二種類の翻訳が存在するが、この自伝、ゼミや「史料講読」という授業でも取り上げたことがあり、また卒論で扱ったゼミ生もいたが、なんといってもすこぶる面白いのだ。喧嘩や刃傷沙汰は数知れず、険悪な仲の同業者たちと乱闘になったり、殺された弟の仇討に行ったり、自分を侮辱した知り合いと情婦に切りつけたり、喧嘩になったパトロンの差し向けた兵士たちを向こうに剣を振りかざして啖呵を切ったりする。そうかと思えば、1527年の神聖ローマ帝国軍によるローマ略奪の際には、請われて教皇軍に加わり、サン・タンジェロ城から敵軍に向かってズドン・ズドンと大砲を打ち込んで、自分こそ並ぶものなき名手だと自慢する。こうした荒っぽい話だけでなく、シチリア出身の黒魔術師に弟子にならないかとも持ちかけられて、コロッセウムで大掛かりな降霊術を体験したり、窃盗の嫌疑で2年間も地下牢に幽閉されたり、笛吹きとして教皇の楽団に加わったり、あるいは女性との色恋話にも事欠かない。

写真2 チェッリーニの胸像
もちろんこれは老齢になってから著した自伝で、誇張や歪曲も多いことが察せられる。ゼミ生たちはこの人物の強烈すぎる個性と生き方に、「もし身近にいたとしたらとても付き合いきれない」といった感想を持ったようだ。しかし私は、社会史の史料としてこれほど魅力的な材料に溢れているものは少ないのではないかと思う。いくたの暴力沙汰の原因はなにもチェッリーニの激しい気性だけに帰せられるものではなく、侮辱に端を発した刃傷沙汰は汚名を雪ぐ「あっぱれな」行為として周りから称賛されているし、身内の復讐は自分に限らず当然のこととして語られている。それから、芸術家同士の抗争が起こるのは、同業組合の秩序が揺らぎかけていたこの頃、パトロンの恩顧をめぐって彼らのライバル関係がそれだけ熾烈になっていたことを物語るだろう。またチェッリーニは、彫金師という生業を持ちながらも、そこから笛吹き、あるいはことによると軍人に転身していてもおかしくなかった。つまり、この時代、芸術家という職業選択は、あるいは一つ一つの芸術分野の選択は、当人にとってそれほど永続的で固定的なものではなかったのだ(かのダ・ヴィンチもミラノ公の宮廷では晩餐会の演出をしたり、楽器演奏をしたりしていた。じつはルネサンスの万能人というのはおそらくこういうことなのだろう)。また、この自伝は当時の刑罰や裁判のありかたや男女関係、魔術信仰を知る一助としても活用することができるであろう。
もちろん、一人の芸術家の創作活動と、パトロンなど彼を取り巻く人間関係こそがこの自伝の本来的にもっとも重要な部分であり、そうした記述こそもっとも密で充実した内容となっている。しかもその部分の語りも、上に紹介したようなルネサンス時代の一市民としての生きざまに劣らない精彩を放っている。そこには、われわれ現代人の知っているのとはおよそ異なるルネサンス芸術家の世界が開けているのを目にすることができるだろう。
だが、この話は稿を改める必要がありそうである。いやそれとも、興味を惹かれた人のために、自分で文献を味読する機会を残しておくべきか...
もちろん、一人の芸術家の創作活動と、パトロンなど彼を取り巻く人間関係こそがこの自伝の本来的にもっとも重要な部分であり、そうした記述こそもっとも密で充実した内容となっている。しかもその部分の語りも、上に紹介したようなルネサンス時代の一市民としての生きざまに劣らない精彩を放っている。そこには、われわれ現代人の知っているのとはおよそ異なるルネサンス芸術家の世界が開けているのを目にすることができるだろう。
だが、この話は稿を改める必要がありそうである。いやそれとも、興味を惹かれた人のために、自分で文献を味読する機会を残しておくべきか...